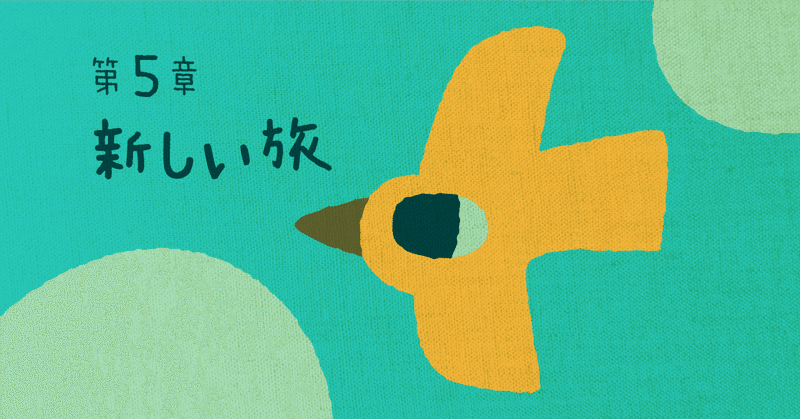
『モリリュウのモリーが消えた』 第5話(最終回)
第5章 新しい旅
[1]モリーの木
クオじいは、ぼんやり目をあけた。
枝葉の間から外の光がちらちらまぶしい。
「おじいちゃん、おはよう」
「おはよう、キトリ」
「きずの具合はどう?」
けさはずいぶんいいよ。
ヤマモリにはじめて雪がふったのが、ついきのうのようだ。
モリリュウたちが植えてくれた木のおかげで、鳥たちはこごえずにすんだ。フークさんは仲間といっしょに北の森へ、クオじいはひとりで西の森へ。海辺からにげてきた何万羽もの鳥たちも、ヤマモリの四つの森で冬を乗りきった。
池のほとりにモリーが植えた木は、キトリが使うことになった。アオイノがそう望んで、みんなもそれが良いと思った。
「キトリ、木のようすを毎日調べてほしい。モリーを見つける手がかりが見つかるかもしれないから」
冬の間じゅう、キトリは木のすみずみまで見てまわった。枝葉が多く冬でもあたたかい木。青い実はとてもあまくて、食べると元気が出た。でも、それ以外はふつうの木。変わったようすは見られない。
おだやかに晴れた冬の日には、鳥たちはおたがいの木をたずね合った。
ねぇ、クオじいのうわさを聞いた?
火事を思い出してねむれないらしい。
ちかごろはもう何も食べないって。
キトリは急いで西の森へ飛んだ。
クオじいはやつれていた。
「わはは。年寄りあつかいするな。だいじょうぶだ」
だからキトリはこう言ってみた。
クオじい、聞いて。わたし、さばくではぐれた弟が気がかりで夜もねむれない。ひとりで冬を越せるか心細い。モリーの木でわたしと暮らしてくれませんか。
次の日、クオじいはモリーの木にひっこしてきた。クオじいは、火事でなくした子どもや孫や仲間たちの思い出を少しずつキトリに話してくれた。キトリも弟がどんな子だったかをクオじいに話した。キトリはクオじいをおじいちゃんと呼び、毎日いっしょに青い実を食べた。
アオイノは何度かモリーの木をたずねて来たけれど、やがて来なくなった。こうもりはほら穴の奥でひと冬ねむって過ごすのだ。
小さなほら穴だったから風の強い日は雪が奥までふきこんでくる。このままでは冬が終わる前にみんなこごえてしまう。
「何だこれ」だれかが天井に小さな小さな穴を見つけた。いつだったかモリーが頭の角をぶつけたあたりだ。こうもりたちが体をすぼめて穴の奥へ進むと、そこには別の広間があった。ここなら風もふせげるし、あたたかい。安心したこうもりたちは、なんだかねむくなってきた。
鳥やこうもりとちがって、気の毒だったのは草原に住むけものたちだ。雪がふるとわかっていたら冬じたくできただろうに、キツネも野ねずみもあわてて巣穴へにげこんだのだ。雪にとざされたねぐらでおなかをすかせて死んだウサギがいた。うっかり外に出てそのままこおったヘビもいた。
[2]雪しずく
冬の間クオじいはずっと考えていた。
考えても考えても答は出なかった。
モリリュウたちはなぜ、わしらのようなちっぽけな生き物のためにいのちをかけて木を植えてくれたのだろう。モリリュウは千年生きるという。リュウから見ればわしらの一生など、まばたき一回分にすぎないのに。
クオじいのつぶやきに、キトリはなぜかあの夏の日を思い出していた。空色のモリーが気持ちよさそうに川をぷかぷか流れてくる。おなかを上に向け、しっぽでじょうずにかじを取り、太陽がまぶしくて目をつむったままモリーは言ったっけ。
みんな同じだよ。
大きくても、小さくても。
いのちの重さは同じ。
「おじいちゃん、見て」枝の先からキトリが呼んだ。緑の葉の間からクオじいとキトリは顔だけ外に出した。
「いい天気だ」
すっかり春だ。
池のほとりには新しい草が生え、花が咲いている。若木の森から聞こえてくるのは葉ずれの音、羽ばたき、木をつつく音、さえずり。
「おじいちゃん、水を飲みに行かない?」
「行っておいで。気をつけなさい。けものたちがうろついとる」
かつてヤマモリの地面をおおっていたトゲトゲカユカユは、山火事でみな燃えてしまった。そのかわり黒こげの地面には新しい草花が根をおろしていた。ヤマモリを歩いても痛くもかゆくもない。むしろふかふかと気持ちいいのだ。草原のけものたちがおなかをすかせてヤマモリにのぼってきた。ヤマモリはもう、飛ぶものだけの楽園ではない。
「キトリ、アオイノに会っておいで」
冬が終わったのに暗がりにひきこもっていてはいかん。
キトリは笑ってうなずいた。
ぽたっ、ぽたぽた。
暗いほら穴でアオイノは、雪どけの森の音に耳をすませていた。おもては春だ。でもヤマモリにモリーはいない。
長い冬の間、アオイノは何度も同じ夢を見た。モリーが緑のほのおをはきながら飛んでいく。やめろとさけびながらアオイノもあとを追う。モリーはほのおの枝葉をくわえたまま、空中でくるりと向きをかえてつぶやく。
おぁ、ふぁ、うぇ。
いつもそこで目がさめるのだ。おぁ、ふぁ、うぇ。何を言おうとしたんだろう。モリリュウの国の言葉かな。いや、待てよ。モリーは緑のほのおのかたまりをくわえていたっけ。ということは‥‥
あっ。
そのころキトリは池の中島で水を飲んでいた。冷たくておいしい。水面の青空に小さな雲がひとつ流れてきた。水に映る雲をぼんやりながめながら、キトリはこの一年を思った。
春、さばくと草原を越えて池にたどり着いたこと。夏、アオイノたちと川で遊んだこと。秋、山火事を消すためにモリーが雨雲を呼んできたこと。木を植える魔法のせいでモリーが消えたこと。おおぜいのモリリュウたちが新しい森を作ってくれたこと。まっ白な冬がはじまったこと。
思いがあふれそうになってキトリは顔を上げた。さっきの小さな雲がまだヤマモリの真上にうかんでいる。雲はその場所を動こうとしない。まるでだれかを待っているみたいに。
キトリはなぜか、胸がどきどきした。
[3]雲の声
おぁ、ふぁ、うぇ。
アオイノは左右の前足を天井にひっかけて、ぶらさがったまま後ろ足を口にくわえてみた。
おぁ、ほぁ、うぇ。
もぁ、ほぁ、うぇ。
もぁ、ほぁ、ね‥‥
ま、た、ね。
モリーはまたねと言ったんだ。
また会おうね。モリーは帰ってくる!
アオイノはほら穴の入り口のまぶしい光へ飛び出そうとして、きゃっ、だれかとぶつかりそうになった。
「キトリ!」
「アオイノ!」
「キトリ?」
「モリーが!」
えっ。
「来て!」
黄色い小鳥と青いこうもりが空高くまいあがってゆく。アオイノは「どこ?」と聞いた。キトリがくちばしで示した先に、小さな雲がひとつうかんでいる。
アオイノたちが雲の前まで来ると、雲の中からふわっと声がした。
「アオイノ」
モリーの声だ!
「ただいま」ふたたび雲から声がした。
アオイノは顔がくしゃくしゃになりそうなのをこらえながら、わざとぶっきらぼうに返事した。
どこ行ってたんだよ。
「ごめん」
「出てこいよ」
雲はだまっている。
「モリー、出てこいったら」
「アオイノ‥‥」
アオイノはついにどなった。
「出てこい!」
「アオイノ、ぼくは」モリーの言葉を最後まで聞かず、アオイノは雲の中へ飛びこんだ。そしてすぽっと向こうに出た。アオイノはきょろきょろ見まわして、もう一度雲に飛びこんだ。
雲の中にはだれもいない。
でもこのにおい、ぬくもり。まちがいなくモリーだ!
「あの日、目をあけると」雲の中で声がひびいた。「ぼくは雲になっていた」
あの日というのは、モリーが魔法で木を植えた日だ。
[4]おはよう
緑のほのおの木をくわえてさかだちしたまま、ぼくはねむくてねむくてしかたなかった。まぶたをとじて、それから目をあけると、ぼくは空からヤマモリを見おろしていたんだ。木のまわりにみんなが豆つぶのように集まって泣いている。アオイノもキトリもいる。降りて行きたいけれど、カラダがふわふわして進めない。
すると頭の上から歌声が聞こえてきたんだ。
トゥララ、ラルリ。
「おはよう」
小さな雲がひとつうかんでいた。
ぼくは何か言おうとしたけれど、こまったぞ、自分の口がどこにあるのかもわからない。
ゆっくりでいいよ。
めざめたばかりだから。
雲はまるで歌うように楽しそうに言った。
「新しい仲間がのぼってきたのはひさしぶり。わたしも昔、モリリュウだった」
雲は鼻歌を歌いながら、北風に乗って空をすべりはじめた。ぼくも風に押されて動きはじめた。
「モリリュウはね、木を植えると空にのぼって《くもリュウ》になるの。見た目は雲でもリュウなんだ。わたしはきみのマモリノリュウに選ばれた。これから少しずつおしえるよ。きみ、魔法はあの子からおそわったの」
あの子?
「今はもうおじいさんかな。わたしがあの子に魔法をおしえたのは何千年も前だから」
「あの、ぼく」ようやく自分の口の場所がわかったので、一番聞きたかったことを聞いた。「ぼくは死んだのですか」
「いいえ」マモリノリュウははっきり言った。
わたしたちには二通りの生き方がある。
モリリュウのまま地上で生きて、老いていのちを終えるか。
それともくもリュウになって空をかけめぐりながら、この星のいとなみに長く深くかかわっていくか。
ぼくはマモリノリュウからいろいろな話を聞かされた。くもリュウのいのち。くもリュウの仕事。どれもむずかしすぎて、ぼくにはまだよくわからない。
「では、くもリュウは死なないのですか」
「そうね、まず無口になるの。何万年もかけて。やがて自分の名前もわすれて最後はふつうの雲になる。そういえば、きみの名前をまだ聞いてなかった」
「モリーです」
「モリリュウにはめずらしい名前だね」
「ぼくのたからものです」
ひゅうっ。
北風がぼくらの間をふきぬけた。
するとマモリノリュウが風に向かって「あら、そう」と言ったんだ。
ひゅうっ。
「わかった、ありがとう」どうやら、くもリュウは風と話せるらしい。
「引き返しましょう」マモリノリュウは向きを変えた。「きみのご両親がヤマモリに来た」
[5]雲の輪
モリーの話は長い夢のようだった。でも夢じゃない。ぼくは今、モリーの中にいるのだ。雲の外から鳥たちの声が聞こえてくる。そろそろ行かなくちゃ。
アオイノはつぶやいた。「おかえり」
モリーもほほえんだ。「ただいま」
フークさんとキトリが羽ばたきながら話している。
「この雲がモリーなの?」
雲からぽそっとアオイノが出てきた。
「ただの雲にしか見えないよ」フークさんは顔をしかめている。
「モリーは」アオイノが答えた。「くもリュウになったんだ」
って言われてもねぇ。
雲がふわふわ笑った。
「フークさん、ぼくだよ」
うわさを聞きつけた鳥たちとこうもりたちがのぼってきて、空の上はおどろいたり、とまどったり、よろこんだり、泣いたり大さわぎ。
「ねえ、モリー」キトリが聞いた。「お父さんとお母さんに会えた?」
「うん。ほら、上に」
見上げると雲の群れが大きな輪になってヤマモリを見おろしている。新しい森を作って消えたモリリュウたちもみな、くもリュウになったのだ。
雲がひとつ近づいてきて「行こうか」と言った。
「待って、兄さん」
キトリははっとした。「行くって、どこへ」
やっと会えたのに、行ってしまうの?
ヤマモリの空にずっとうかんでいられないの?
「ごめん」
「いやよ!」
「また会いに来るから」
「キトリ」アオイノがなだめた。「モリーは世界中を旅してまた帰ってくる。これからも会えるよ」
キトリは泣きそうな顔でうつむいて、向こうへぷいと飛んで行ってしまった。
「キトリ、聞いて」
くもリュウのモリーは、背を向けたキトリにふわっと追いついて、何か一言ささやいた。すると、キトリがおどろいてふり向いたのだ。「どうして」
どうしてわたしの名前を知ってるの。
モリーがふわふわ笑った。
「きみの弟がおしえてくれた」
[6]塔のてっぺん
モリーは冬にあったことを話した。
ヤマモリに初雪がふったあの日、くもリュウになったモリーと数千びきのモリリュウたちはマモリノリュウとともに世界の空へ旅に出た。地上から見上げるとくもリュウたちは小さな小さなうろこ雲の群れにしか見えない。
世界で起こるあらゆることを見て、聞いて、風に伝えるのがくもリュウの仕事。集めた話を風たちがどこへ運ぶのかわからないけれど、くもリュウたちはこの仕事が好きだった。くもリュウは目と耳がとてもいい。あんな高い空の上から、草の葉をすべるしずくひとつも見のがさないし、羽虫のあくびも聞きのがさない。
冬も終わりに近づいたある月の夜、雲の旅団は海をこえ、さばくをこえ、かつてキトリが暮らしていたヒツカイたちの町の上を飛んでいた。ヒツカイというけものはよほど高いものが好きと見えて、町のあちこちに塔がそびえている。家々のあかりがぽつぽつ消えはじめていた。
「いい歌ね」マモリノリュウがつぶやいた。
どこかの塔からかすかに歌声が聞こえてくる。
この歌、知ってる!
モリーが目をこらすと、塔のてっぺんに一羽の黄色い小鳥がとまっていた。
キトリの弟は砂あらしのあと、半分砂にうもれていたところをヒツカイに拾われたのだ。ヒツカイは町にもどり、小鳥をかごに入れて朝市に出した。「姉さん、姉さん!」泣きさけぶ声はヒツカイたちには美しい歌声にしか聞こえなかったので、小鳥は高い値で売れた。買われた家の子はやさしい子だったけれど、小鳥は何度も鳥かごからにげようとして体じゅう傷だらけになった。
ある日、小鳥は窓辺でスズメたちのうわさ話を耳にした。
「楽園が山火事で燃えたって」
「みんな焼け死んだらしい」
黄色い小鳥は歌わなくなった。何も食べなくなった。ぼくはここで死ぬのだ。夜の窓辺をヒツカイたちのいくさの火が赤く照らした。
ある朝、ヒツカイの子どもが小鳥に何か話しかけた。子どもは鳥かごのとびらをあけ、かべの後ろにそっとかくれた。小鳥がおずおずとかごを出て、窓から出ていくのを見届けてから、子どもはぼんやり空を見上げた。
せっかく自由になったのに小鳥は悲しくてたまらない。ヤマモリはもうないし、
姉さんもいないのだから。町の鳥たちは小鳥の身の上話に同情してくれた。気の合う仲間もできたけれど、さびしさはうめられなかった。小鳥は毎夜、塔にのぼってなつかしい歌を歌っては、姉さんを思い出して泣いた。すると向こうからうろこ雲の群れが近づいてきたのだ。
[7]あの歌
「キトリ、きみの弟はさばくの南の町にいる。冬が終わったら仲間たちと町を出ると言ってたよ」
「ホゥオ、あたしが言った通りだろ」フークさんがとくいげに笑った。「やっぱりモリーが見つけてくれた」
雲たちの輪がゆっくりヤマモリに降りてくる。モリーはアオイノとキトリとヤマモリの仲間たちに囲まれて、歌うように言った。
またね。
池のほとりの木のこずえでは、クオじいが空を見上げていた。おおぜいの鳥とこうもりたちが小さな雲のまわりで楽しそうに羽ばたいている。みんな何をしているんだろう。ヒバリがひゅるひゅる降りてきて、クオじいに話して聞かせた。
モリーが生きていただと?
雲になって帰ってきただと?
わははは、長生きはしてみるもんだ。
クオじいも飛んで行きたかったけれど、つばさが痛くてあきらめた。おや、雲の群れが南へ動きはじめたぞ。
「行ってしまうのか」
クオじいはしんみりつぶやいた。
くもリュウの群れはみるみる遠ざかってゆく。
「約束だぞー。帰ってこいよー」
見送る鳥たちの群れにキトリがいない。

いた。あんな空高くに。
ぐんぐんのぼって、空気がうすく冷たいところまで来ると、くもリュウの旅団がよく見える。はるか岩山まで見えそう。キトリは歌を歌いはじめた。
モリーとならんで先頭を飛んでいるマモリノリュウはとても耳がいい。ふわっと後ろを向いてほほえんだ。「あの歌だね」
花咲く草原のまん中でウサギが立ち上がった。影の群れが草をすべって来る。雲たちは音もなく草原とウサギを青くそめ、さっと通りすぎた。きょうはぽかぽか良い天気。ねぼけまなこのヘビの頭に小さなチョウがとまった。
「あら」マモリノリュウが今度は前を見てつぶやいた。「向こうからも」
同じ歌だ。
草原とさばくをへだてるぶあつい岩山の向こうから、一羽の黄色い小鳥がおどり出た。その後ろから五羽、百羽、いやもっと、千羽以上の色とりどりの鳥たちが山を越えて来る。みんな、いくさの町からにげてきたのだ。歌っているのはもちろん先頭をゆく黄色い小鳥だ。
鳥の大群の中でひときわ目立つ黒いひとかたまりはカラスたち。群れから一羽がはみ出して、もう一羽があわてて連れもどしに行くようすが空の上からよく見える。くもリュウたちは見下ろしながらくすくす笑った。
「まっすぐ飛びなさいったら」
「母ちゃん母ちゃん母ちゃん、オレさぁ」
ぼさぼさ頭の子ガラスが、あはあは笑っている。
「オレ、ヤマモリってとこで暮らすの?」
「そうよ、だまって飛びなさい」
「母ちゃん母ちゃん、ヤマモリっていいとこ?」
「いいとこらしいよ」
「ねぇ母ちゃん、ヤマモリってさぁ」
「ほら、よそ見しないの」
「ヤマモリって、カラスいるかな」
そうねぇ。
母ちゃんカラスは草原のかなたを見つめてほほえんだ。
いるといいね。
[おわり]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
