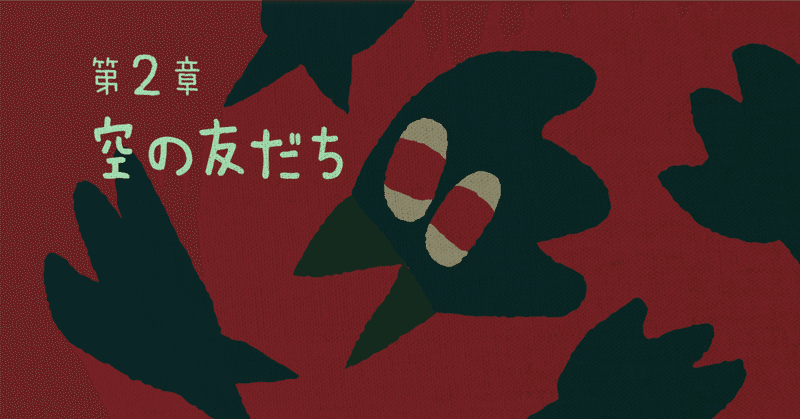
『モリリュウのモリーが消えた』 第2話
第2章 空の友だち
[1]秋風
さりさり、さら。
草の実を鳴らして風が草原をかけてゆく。
ぽつんと見える小さな山はヤマモリ。
山の四つの森に何千羽もの鳥と数百羽のこうもり、そして一ぴきのモリリュウが暮らしている。
森の木々の多くは一年を通じて緑だけれど、秋に葉の色が赤や黄色にそまる木もところどころにあった。
「見ぃつけた」
色づきはじめた枝のあいだを、鳥たちが飛びまわっている。きょうはみんなでかくれんぼ遊びをする日だ。
「あとはキトリだけだ」
「どこにかくれたかな」
みんな首をかしげながら向こうへ飛んでゆく。黄色い木の葉の奥からくすくす笑い声が聞こえてきた。
キトリはもともと町の小鳥だった。さばくをこえ、岩山をこえ、草原をこえてヤマモリにやってきたのだ。砂あらしではぐれた弟はまだゆくえがわからない。
「わけがあって来られないんだよ」
「どこかで元気に暮らしてるさ」
ヤマモリの仲間たちはキトリをなぐさめてくれる。それでもどうしようもなくさびしくなると、キトリはひとりで夜空へのぼり、思い出の歌を口ずさむ。今夜も雲ひとつない星空。西風がひんやりと気持ちいい。深く息をすって歌おうとした、その時。
こほっ、こほっ。
キトリはせきこんだ。何だろう。こげくさい。
ヤマモリを見おろすと四つの森はいつものように静かだ。南のちょろちょろ森、東のきらきら森、北のまっくら森。西のざわざわ森‥‥あっ。
ざわざわ森の西の野原がめらめら赤く光っている。光は夜風にあおられてふくらむと、ざわざわ森をぺろりとなめた。
[2]火の色
火だ。あれは火事だ。
町で暮らしていたころ、ヒツカイたちが争いごとに火を使うのを何度も見た。ヒツカイは二本足で歩く大きなけものだ。火をおこして大きな町を作り、せっかく作った町を火でこわす。キトリと弟はヒツカイたちのいくさにまきこまれ、やっとの思いで町からにげ出したのだ。
みんなにげて、にげて。
ヤマモリが燃えている。
キトリは力のかぎりさけびながらヤマモリをぐるぐる飛びまわった。声は東のほら穴のくらやみにまで届いた。
ヤマモリの北から、南から、東から鳥たちが空へのぼってくる。カラスたちの住む西のざわざわ森はすでにまっ赤な光のかたまりだ。ごうごうと風の音。ぱちぱちはじけてくずれる音。アオイノとモリーはヤマモリのてっぺんまでまいあがり、ぐるりと見おろした。このままだと夜明けまでに四つの森が燃えてしまう。
「みんなを東の草原へ」
東には川がある。ひとまず安心だ。
「わかった。モリーは?」
「雲を呼んでくる。雨をふらせてもらう」
えっ、そんなことできるの。
「わからない」
モリーは南の空をにらんでいる。草原のかなたを何かが流れてゆく。
「雲だ」アオイノがそう言い終わる前にモリーはぽーんと飛び立っていた。ほら、もうあんな遠くまで。
[3]古い歌
雲を呼べるのかモリーにも本当はわからなかった。古い歌を思い出したのだ。モリーがまだ小さかったころ、兄さんリュウたちからおそわった歌を。
雲は 友だち
雲は やさしい
雲は 無口だ
けれど たのもしい
世界の 悲しみと
世界の 苦しみを
全部 見てきたから
雲は やさしい
そして たのもしい
モリーは歌をつぶやきながら、南の空へ矢のように飛んでいった。
アオイノはけむりと火の粉の中をにげまどう鳥たちに呼びかけている。
「東へ、東の草原へ!」
けむりの向こうからキトリがあらわれた。息が苦しそう。
「わたしはだいじょうぶ。早くみんなを」
アオイノとキトリはけむりをすいこまないように気をつけながら、ほかの鳥たちに声をかけつづけた。夜のにがてな鳥たちは声をたよりにくらやみへ羽ばたいた。
南の空を小さなうろこ雲の群れが流れてゆく。雲たちに追いついたモリーは「おーい」とさけんで、それから急に不安になった。雲に言葉がわかるだろうか。雲に聞く耳はあるのだろうか。モリーは雲の群れにつっこんだ。
[4]無口な友だち
東の草原の川辺では焼け出された鳥とこうもりが身を寄せ合い、燃えさかるヤマモリを見上げていた。
キトリが知らせてくれなかったら、もっとおおぜいがにげおくれていた。ありがとう、ありがとう。けれどもキトリはつらそうだ。けむりにまかれて落ちていった鳥たちのすがたが目に焼きついてはなれない。西の森は火のいきおいがはげしすぎて、近づくことすらできなかった。
後ろでだれかがさわぎはじめた。南の野原で暮らすヒバリだ。
「いないの、子どもたちが」
五羽いるはずの子ヒバリが三羽しか。
「さがしてくる」
アオイノが飛び立ち、キトリも追いかけた。
そのころモリーは雲の群れのまわりを飛びながら、声がかれるほどさけびつづけていた。
山が燃えているんです!
雨をふらせてください!
雲たちがゆっくり止まった。
「おねがいです。雨を」
雲はだまっている。
「ぼくたち、友だちでしょう」
モリーがそう言うと、雲のどこかが「ふ」とつぶやいた。
ふ?
雨をふらせるの「ふ」。
ふらせないの「ふ」。
それとも今のは笑い声?
答えはすぐにわかった。雲の奥から風がわき起こり、動きはじめたのだ。北へ、北へ向かって。
「ありがとう」
モリーは雲たちの先頭へ回りこみ、これ以上飛べないくらいの早さで、くらやみに赤くともるヤマモリへ急いだ。
[5]雲の色
南の野原の草かげから泣き声が聞こえてくる。二羽の子ヒバリたちだ。一羽は飛べるけれど、もう一羽は羽に力が入らない。飛べる一羽が寄りそいながら星空へさけんだ。「お母さん、お母さん!」
その声がアオイノとキトリに届いた。
さて、こまったぞ。
アオイノとキトリは草原に降りて顔を見合わせた。飛べない子ヒバリをどうやって連れて行こう。歩いていたら火に追いつかれる。
さりさり、さら。
草の奥から何かが近づいて来る。
まず目と舌があらわれて、てらてら光る長い体があらわれた。ヘビだ。燃えさかる西の野原からにげてきたヘビは、目の前にごちそうが四羽もならんでいたのでおどろいた。いやいや、今はにげるのが先。ヘビは小鳥たちを横目でにらみながら向こうの草むらへ消えていった。
そして、すぐにもどってきた。一、二羽食べるくらいの時間はあるだろう。鳥たちをかばってアオイノがつばさを広げると、ヘビはしゃーっと飛びかかった。そしてそのまま高く高くまいあがった。
草原がはるか下に見えている。ヘビのうろこにだれかの爪がくいこんでくる。だれだ、はなせ、はなせ。頭上から声がした。ほぅお。
ひゃーっ。ヘビはまっさかさまに落ちていった。
ヘビのかわりに降りてきたのはフクロウだ。
「フークさん!」
子ヒバリが飛べないことをキトリは伝えた。
「あはは、腰がぬけたのね」
そう言うとフークさんは、つばさを広げたまま地面に腹ばいになった。
「あたしの背中に乗りな」
アオイノはさっきから東の草原を見つめている。
「ヘビもキツネも、きっと東へ向かってる」
「安心しな。あたしの一族が輪になってみんなを守ってる」
「フークさぁん」ふかふかの背中で子ヒバリがそわそわつぶやいた。「あそこで光ってるの何?」
おちびちゃん、あれは火よ。
熱くて、痛くて、こわいの。
近づいたらだめ。
「そうじゃなくて、あっち」
みんないっせいに、南の空を見た。
モリーの後ろを黒雲の群れが飛んでくる。
ごろぐろごろぐろ、ぴかっ!
かみなりだ。雲が雨雲になったのだ。
「モリーが雲を連れてきた!」
「ホゥオ、やるねぇ、あの子」
四羽の鳥と一羽のこうもりがぽかんと見上げるその真上を、黒い雲たちが通りすぎてゆく。すると‥‥
ざばざばざばざばざばざば!
目をあけていられないほど大つぶの雨だ。子ヒバリたちはおどろいてフクロウの背中からすべり落ちた。雲がはなれていくと雨はすぐにやんだけれど、そこらじゅう水たまりができている。あははは、こりゃすごい。
「さぁ乗りな。お母さんが待ってるよ」
雲の群れはヤマモリの上を何度も回りながら、雨をおしみなくふらせている。あっ、あれは。燃えさかる火の上を一羽のカラスがさけびながら飛んでいる。クオじいだ。雲たちはクオじいに向かって雨を浴びせた。黒けむりを上げていた地面から白い湯気がしゅうしゅうのぼってくる。クオじいの姿はたちまち湯気にかくれて見えなくなった。

[6]木の数
ヤマモリから赤い色が消えた。
今夜は一面の星空。ヤマモリの上だけが黒けむりにぼんやりおおわれている。
火が消えたぞ!
東の草原から鳥たちのよろこぶ声が上がった。
フークさんがとくいげに話している。「みんな同時にふり向いたのさ。そしたらモリーと雨雲がぐんぐん近づいてくるじゃないか。あたしゃ鳥はだが立ったね」
雨であふれそうな川を鳥たちが流れてくる。ほとんど死んでいたけれど、まだ息のある者もいた。キトリとアオイノは鳥たちを川から助け出した。
ヤマモリはどこもかしこも、まっ黒こげのびしょぬれだ。モリーは雲たちに近寄ってありがとうと伝えた。けれども雲たちは雨のいきおいを弱めない。火が消えたように見えても安心できない。それが山火事のおそろしさだと雲たちは知っているようだった。
西の森から弱々しい声が聞こえてきた。どこだー、みんなー、じいちゃんが助けるぞー。声は今にも消えそうだ。たちのぼる湯気の中にモリーは飛びこみ、それからふたたび夜空へまいあがった。クオじいのぼろぼろの体をだいて。
東の草原のかたすみで、こうもりたちは輪になってだまりこんでいた。いや、だまっていたのではない。こうもりにしか聞こえないこうもりだけの声で話し合っていたのだ。輪のまん中にいるのはアオイノだ。
「で、西のざわざわ森は?」
「ダメだ。一本残らず燃えてしまった」
「北のまっくら森は」
「あっちもひどい。燃えなかったのは七本」
「南のちょろちょろ森は十二本。だが、そのうち二本は冬に葉が落ちる木だ」
こうもりがまた一羽もどってきた。
「東もかなりやられたぞ。きらきら森は十八本だ」
何千本もあったヤマモリの木の、ほとんどが燃えてしまった。地面をおおっていたトゲトゲカユカユが燃えやすい草だったせいで、草から草へ、森から森へあっというまに広がったのだ。雨がふらなければ草原まで焼いていただろう。
ヤマモリに残った木はたった三十七本。そのうち冬でも緑なのは三十五本。鳥たちは冬の間どこで寒さをしのげばいい。
こうもりたちの後ろでどよめきが起きた。モリーがもどってきたのだ。鳥たちはわぁっと羽ばたいてモリーのまわりに集まったけれど、すぐにしずまりかえった。そのしずけさのまん中にモリーはクオじいの体を横たえた。
「だいじょうぶ。生きてる」
キトリは川のほとりへ飛び、ありったけの水を口にふくんで、クオじいのところへもどった。かすかな息づかいの合間にクオじいが何かつぶやいている。口うつしでクオじいに飲ませようとしたキトリにだけ、その言葉が聞きとれた。
ゆるさんぞ。ヒツカイめ。
[7]夜明け
モリーの耳元にアオイノが飛んできた。
残った木の数をそっと伝えるために。
冬が来る。木がたりない。
鳥たちにとって緑の木の枝は屋根つきのねぐらだ。木の幹はけものから身を守る塔。木の実や皮は冬の間の食料庫。
冬の草原には食べ物があまりないし、けものにおそわれる心配もある。どこか木の多い場所をさがさなければ。だけど、やけどをおって飛べない仲間たちをどうしよう。おさない小鳥たちをどうしよう。
ううう。
クオじいが目をさました。立ち上がろうとしてすぐにころんだ。
「目が見えん」
けむりと火の粉にやられたのだ。川の水で目を洗ってあげよう。キトリとアオイノがクオじいに寄りそった時、後ろでちりちりと鈴のような音がした。モリーの空色の羽が逆立ち、ふるえている。
ぼく、行ってくる。
どこへ、とアオイノが言いかけた時モリーはもう地面をけっていた。あっというまに高くまいあがって、空の上できらりとピンク色に光った。東の地平線から朝日がのぼってきたのだ。
朝やけ色の雲の群れが南へ帰ってゆくのが見える。雨をふらせたせいでずいぶんちぢんでしまった。古い歌のとおり、雲はぼくらの友だちだった。
モリーは深く息をすって、風を切った。
モリーのやつ、どこ行った。
「どっちの方角だ」目の見えないクオじいが聞いた。川にそって飛んでいったから、まっすぐ北だ。「北か」
わしがまだ若いころ、ワタリガラスたちから聞いたことがある。北の海をいくつもこえると、北の果ての果てにあるらしい。
あるって何が?
「モリリュウの国だ」
空が明るくなってきた。ごうごうと風を切って飛ぶモリーのまなざしのかなたに海が見えてきた。
(第3章『一度きりの魔法』へつづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
