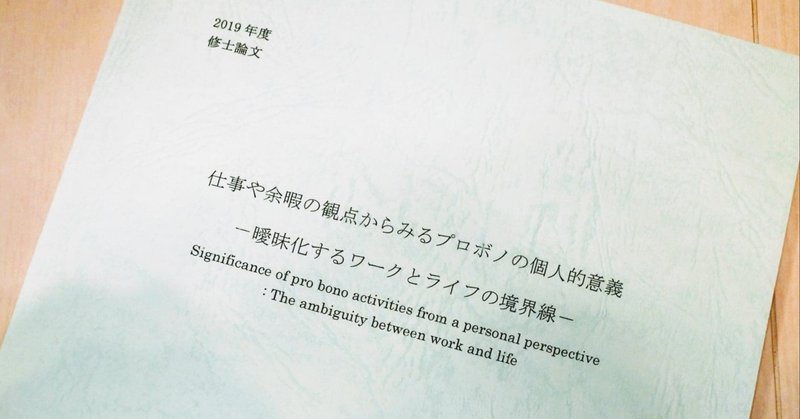
社会人大学院生だった話。~第1章~
論文を書きたい、という衝動。
私の社会人大学院生話をこの先何回かに分けて書いていきますが、前回(~はじめに~)に書いたように私は「論文が書きたくて大学院に入った」という人です。日々普通に仕事したり暮らしていて論文が書きたくなる状況いうのも稀かもしれませんが、言葉を換えると「ある事柄に関して、じっくり腰を据えて探求してみたい、そしてそれを形にしたい」ということだと思います。
そう、「形」にしたかったんです。
英語でも「figure out」という表現があるように、分かることとは、つまり物事に輪郭をつけることなんだと思うんですね。生活するなかできっとこうだろうと思っていることは、まだ輪郭をもたないことが多い。だけど、それでも日々の大抵の物事は進められるもんです。用語の定義だの、ここは私の取扱い範囲外だの、いちいち線引きしていたら、仕事でも生活でも弊害だらけ。一方で、なんとなく分かっていることを他の人に示すとき、雲のようなものを言葉を連ねて説明しても、大まかな内容は伝えられるものの、クリアに受け取ってもらうことは難しい。そりゃそうです、自分の中でクリアではないのだから。(ただし、誰かに話すことでクリアになったり、相手が自分の話を整理してくれてクリアになったりすることはある)
ということで、私には雲のような自分の中では何となく分かっていることがあって、それをちょっと他の人にも説明したくて、そのためにはもう少し深く掘り下げる必要があると感じていたから、論文を書こうと思い、大学院に入ったということになります。
もう少し細かいことを書くと、大学院進学は以前から希望していて、社会人になってからずっと、いつ行こうか?と時期を見計らっていました。大学で研究の面白さを知ってしまい、そのまま大学院に進むつもりだったものの、肝心の研究テーマが定まらず、一旦社会に出ることになった私(突然大学院進学を取り止め、就活をスタート、終わりかけとはいえ就職氷河期、大学4年時はまさに紆余曲折!)。そこから15年ほどしてようやく論文として取り組みたいテーマが見つかり、満を辞して大学院へ。
まぁそんな経緯はどうでもいいんですが・・そんな私が大学院に求めたものは、論文を書くための環境です。そしてここがちょっと普通じゃないかもしれませんが、教えてもらうこと自体はあまり重視してなかったんです。
論文を書くのは私。
お金を払って学校に行くんだから、授業とか論文指導とか教えてもらうことを期待するのが一般的なのかもしれません。ですが私の場合、「論文を書きたいのは自分、伴走支援してくれるのが学校や先生」という認識だったので、研究にはうってつけの環境を得ることを学校に求めました(大学とは元々そういう場所ですね)。多分これは自分が小さいながらも事業をする立場であることが影響しているのかもしれません。「個人事業主というのは自分で事業を作らないと仕事がない!」ということに独立してからはたと気づき(遅い)、自分でやらなければお金が入ってこない、誰もお膳立てしてくれないという状況が身に染みています。一方で、自分でやりたいことの場合、下手に他人に口出しされるのも嫌。だからこそ、伴走支援が最もありがたい。方向性に迷ったら相談に乗ってもらう、情報が欲しかったたら文献を紹介してもらう、関係者に繋いでもらう。それで十分ありがたかったんです。
このあたりの感覚は、社会人大学院に通う人や目指す人のなかでも、それぞれ違うだろうと思います。ただ、こういう期待の度合いだと、大学という場に対して不満は無くなります。スペシャリストは揃っているし、図書館や院生室など書く環境は整っているし、完璧です!(当然すぎるけど)。加えて、授業が面白くて、論文指導を丁寧にしてくださる先生がいたりすると、期待を大いに上回り、感動の域になります(笑)
自分の解明したいことに、とことん向き合う。
そして、これが仕事との大きな違いだと思っているんですが、「私の解明したいこと」にとことん付き合ってくれる先生や同期がいることへの感謝と感動(論文提出間際にしみじみ感じた)。仕事で「私はこれがしたい」「私はこう思う」を出すこと自体はNGではないけれど、あまりにそれに固執してしまうと方向性を見失うものです。やはり組織に属するひとりの人間としての考えと判断を求められるわけですから。極端なことをいえば、会社は自分のやりたいことを実現してくれるところではない(あ、でも会社で自分のやりたいことを実現することは可能。微妙な違いだけど)。一方、大学では徹底的に「自分は何を解明したいのか」そこに意識を向けることが許され、組織にとってどうなの?とか、社会にとって意味ある?とか多少言われようと、最終的には「私はこれを解明したい」を尊重できるわけです。(結果的に組織にとってや、社会にとって意味のある論文にはなるんですけどね)
ちなみに、そもそも論文を書くだけなら大学院は必須ではないのですが、やはり「場」と「締切」は超重要。大学に行くとスイッチが入って論文が書ける。仕事柄在宅ワークをしますが、やはり特定の場に行くことでやる気スイッチが入るということを経験上分かっているので、むしろ「学校行く、すなわち、論文書く」にモードを設定。実際自宅で論文書いたことなかったです(相当珍しいと思う)。今も研究を続けたいなと思っているのに、家ではダメ、スイッチ入りません。
そして、締切があると、人は否が応でも書きます。あえて留年や休学を選択するのも社会人大学院生ならではだけど、もう今年で卒業だ!と決めた時に、人は火事場の馬鹿力を発揮します。年末年始のまさに最終コーナーを回ったあたり、いま思えばあれは何だったのかと思うほど(遠い目)。もうできる気がしない。
じっくり向き合って書いたものは、覚えている。
先日、実家の片付けをしていた時に見つけたものがあります。中学3年時に書いた小論文と、大学4年時の卒業論文。そのほかにもノート類はごっそり出てきて目を通したんですが、さっぱり中身を覚えてない(笑)真面目にノート取ってるなぁとか、当時はなんて字が綺麗なんだとか、感想は出てくるけど、「そうそう、こんなこと習ったよね!」みたいなのが出てこない・・記憶が薄い。だけど、小論文と卒業論文は、書いていた時のことも内容もありありと思い出せる。なんなんだ、この濃度の差はと思いました。やはりじっくり深く掘り下げて向き合ったからなのでしょう。自分で探求したものは、残る。
以上、論文書きたくて大学院に入ったというお話でした。でも多分、別の動機で大学院に入る人も多いと思ってます。そのあたり、私が観察したこと、感じたことを次回以降書いていきます。長文お付き合いいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
