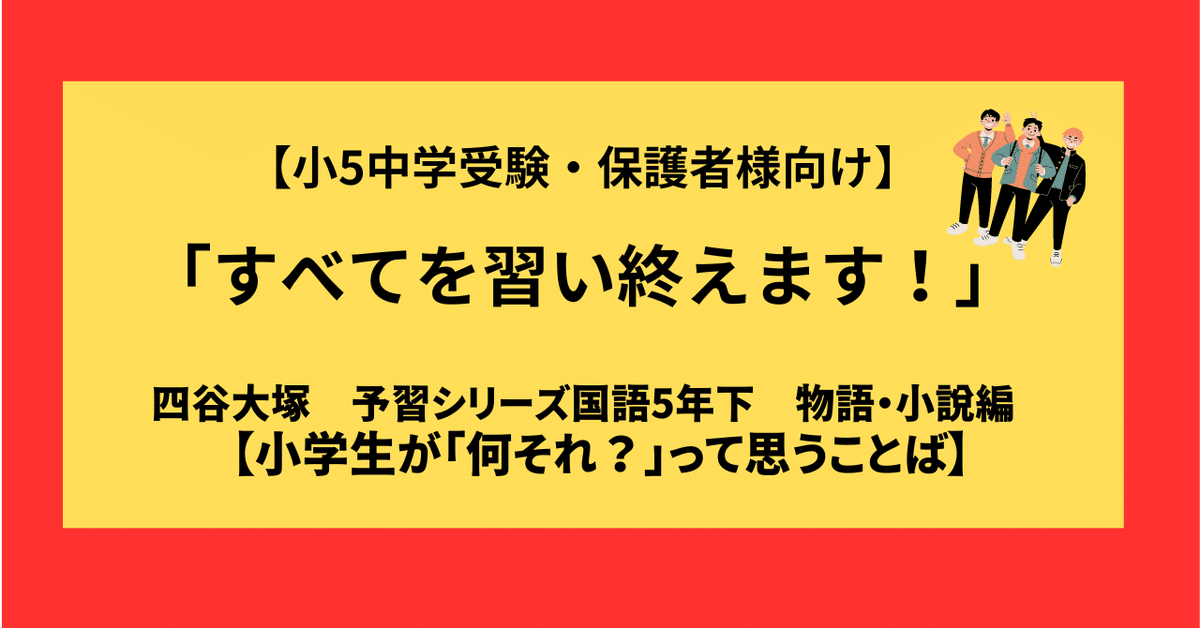
【小学生が「何それ?」って思うことば】四谷大塚予習シリーズ国語5年下から集めました。
小5のお子様がいらっしゃる保護者の皆様こんにちは!夏期講習もお疲れ様でした。予習シリーズも下に入り、間もなくひと月が過ぎます。お子様の様子はいかがでしょうか。
後期の日曜特訓にも通い出したお子様もいらっしゃると思います。
自由な時間が少なくなり、余裕がなくなってきたと感じるご家庭もあるのでは。これまで以上に自己管理力が必要になりますね。中学受験の経験を通して子ども達が成長してくれることを願うばかりです。
さて、ついに予習シリーズ下を学習し始めました。物語・小説・論説文だけでなく、随筆・詩・短歌・俳句、そして助詞・助動詞と盛りだくさんの内容で、もはや受験に必要な項目を全て終了すると言っても過言ではありません。以前の版と比較すると、ボリューム減にはなっていますが、助詞・助動詞なんかは中2、中3で学習する範囲です。
国語に関しては、5年生終了時点で入試問題演習ができる状態になりますよ!!
今回は保護者の方々、そして塾、家庭で頑張る子ども達に向けて、予習シリーズ国語5年下の「物語・小説」に出てくる【小学生が「何それ?」って思うことば】をピックアップしました。(演習問題集国語5年下も含めます)
予習シリーズ下及び演習問題集下には計21作品の物語・小説がありますが、そのうち10作品は実際の入試問題に使用されたものとして確認できました。森絵都さんやまはら三桃さんなど中学入試問題では常連作家さん達の作品。また、灘中、桜蔭中など最難関中で出題歴のある作品が並んでいます。
また、予習シリーズ5年上では最高70字の自由記述問題であったのが、5年下では第5回の総合問題で80字の自由記述問題があります。さらに「気持ちはどのように変化していますか」という心情読解もあります。主観で答えず、文章中から解答の要素を拾えるように取り組んでほしいところです。特に国語が苦手なお子様にはしんどい作業なはずですが、焦らずに客観的な読解方法を定着していってくださいね。
お子様は「どんどん成長しています!」
今回ピックアップした言葉は読解中にわからなくても、問題を解く上ではさほど影響はありません。(そもそも難しいと思われることばには注釈が付いています)
どうしても世代や時代の違いが要因の小学生が知らないことばが登場しますので、「お母さんが子どものときにやってたよ」とか「試しに今度これ食べてみようか」という感じで、お子様との会話が増えればいいなあと思っています。
ではではさっそく。
第1回基本問題(「カンフー&チキン」小嶋陽太郎)より
袋小路:行き止まりになっている路地。物事が行き詰って先に進めない状況のこと。
類語に八方ふさがりがあります。
額面どおり:言葉や物事の表面的な意味そのまま。文字通り。
会話のやりとりの中で額面どおりにしかことばを受け取れない生徒さんが増えてきたなと感じていました。例えば僕が「姿勢悪いよー」と呼びかけると、「はい」と返事だけしてくれます。(姿勢はそのまま)こちらの「姿勢を正しくしようね」というメッセージを察することができないようなんですね。皆さんの周りの子ども達はどうでしょうか。
第3回基本問題(「四万十川」笹山久三)より
たんすながもちどの子がほしい:わらべ歌「はないちもんめ」の歌詞。
集団で行う遊びです。小学生のころ教室でやってました。いじめにつながるので禁止されている学校もあるそうです。また「はないちもんめ」は「口減らし」の歌だということで好ましくないという意見もあるとか。
僕は奈良市なので関西バージョンの歌詞です。「たんすながもちどの子がほしい~♪」から始まります。全国でいろいろな歌詞があって興味深いですね。ちなみに「だるまさんがころんだ」は僕の地域では「坊さんが屁をこいた」です。(関西の方は共感していただけるかな)

第6回発展問題(「よろこびの歌」宮下奈都)より
蚊帳の外:集団から無視や仲間外れをされること。
そもそも「蚊帳」が「何それ?」となるので「トトロで出てきたやつやん」と言うと通じるのですが、なんと現在の予習シリーズには画像が掲載されています!第9回「俳句」における季語紹介のページをご覧ください。
蚊帳以外にも「土筆・こたつ」なんかも掲載されていて良いですよ。
第10回総合問題(「いちょうの実」宮沢賢治)より
はっか水:シソ科植物のハッカを原材料とする。スーッとする香味があり医薬品・お菓子・歯磨きなどに用いられる。
にっき水やひやしあめなんかも賞味したことがないんですが、チャレンジしてみようかなと思っております。

第16回発展問題(「美晴さんランナウェイ」山本幸久)より
八つ橋:京都のおみやげの定番。八つ橋の原料を焼かずにそのまま切り出した皮だけのものを生八つ橋という。
株式会社美十のつぶあん入り生八つ橋が「おたべ」です。
僕は若い頃、聖護院御殿荘という旅館の住み込みバイトをやってまして、旅館の向かいに聖護院八つ橋総本店がありました。そこの商品名は「聖」です。「聖」は毎日いただいてました。
※関東の方は聖護院御殿荘に修学旅行で宿泊された方もいらっしゃるのでは。夜食はモスバーガーでしたよ。覚えてますかー。
演習問題集 第1回(「クラスメイツ」森絵都)より
ハイテク:ハイテクノロジーの略。高度な先端技術をさすことば。
死語扱いされることも。90年代のハイテクスニーカー、懐かしい!
演習問題集 第10回(「タンポポのわたげみたいだね」豊島ミホ)より
学ラン:詰襟学生服のこと。江戸時代に洋服を蘭服(蘭はオランダ)と呼び、学生が着る蘭服なので「学ラン」となった。
学ランの原形を最初に導入したのは1886年帝国大学(現 東京大学)だそうです。
学生服を製造しているトンボさんの2019年の調査によれば、高校生男子の制服タイプは学ラン41.0%、ブレザー49.6%だったそうです。現在はさらにブレザーが伸びているはず。
母校の中学校は、僕が通っていた当時学ランでしたが、今は私服になってしましました。詰襟の学ランは絶滅危惧です。個人的には残念……。

演習問題集 第16回(「真夜中の自転車」村田喜代子)より
三角乗り:子どもが大人用の自転車に乗るために編み出した乗り方。サドルに座ると、ちゃんとペダルを踏めないので、フレームの三角部分に片足を突っ込みペダルを漕ぐ。不安定な乗り方なので転びやすい。
何台も自転車を買ってもらえない時代を象徴することばです。子ども用自転車を買うコストを省くため、いきなり大人用の自転車を買うんですね。
現在のように、ストライダー→子ども用自転車→大人用自転車と順番に買ってもらえるのは、めぐまれているなぁと感じます。
サドルにお腹を乗せる「スーパーマン乗り」なんていうのもありました。
最近見てないですね。
子ども達がテキストや入試問題で読む作品には、上記のように今では「死語」として扱われるようなことばも出てきます。小学生にとっては本当に「何それ?」ですよね。ときには親子の会話のネタにしてくださいね。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
いつもはnoteで中学入試問題頻出作家さんの作品から小学生になじみのない言葉をピックアップした記事を書いています。よろしければ前回の記事です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
