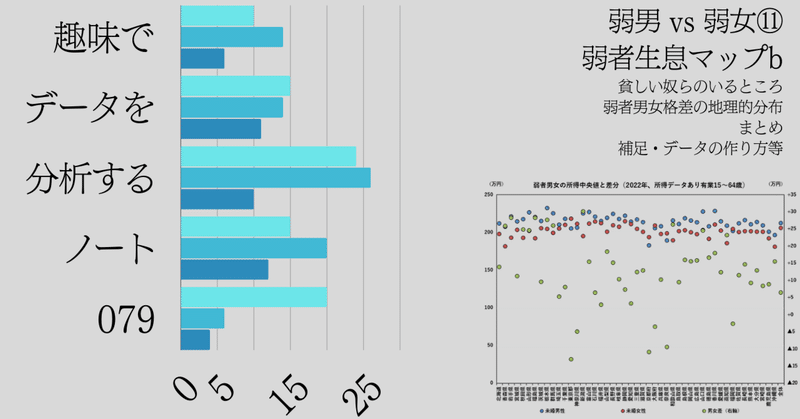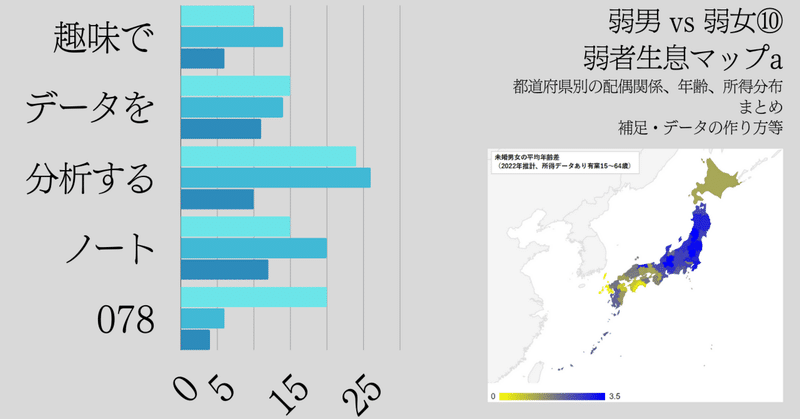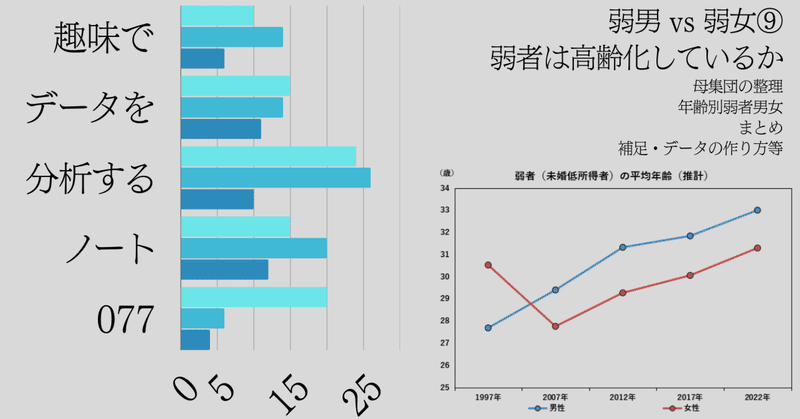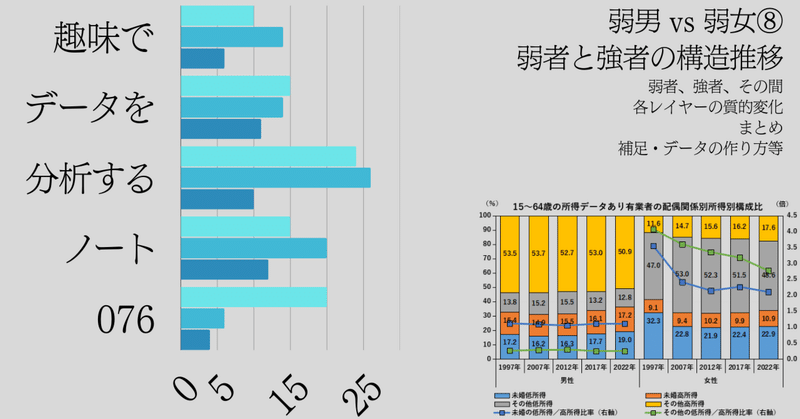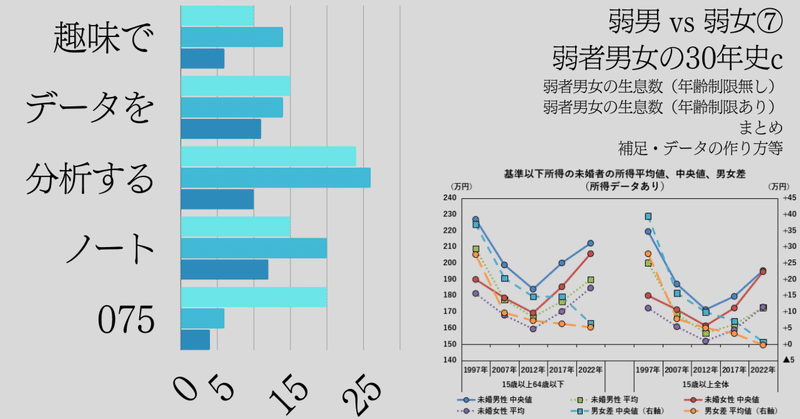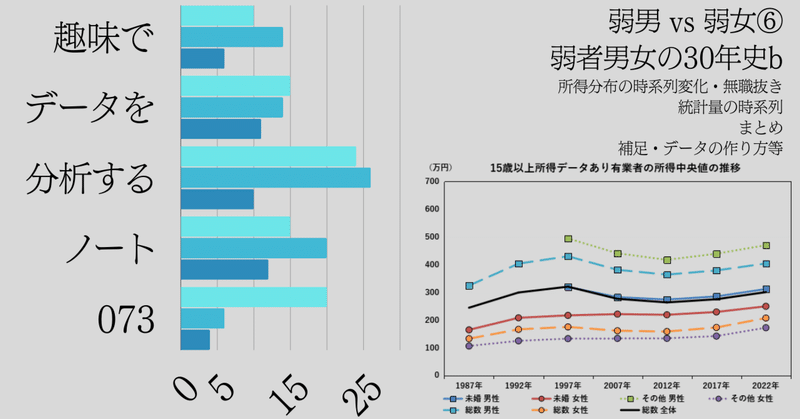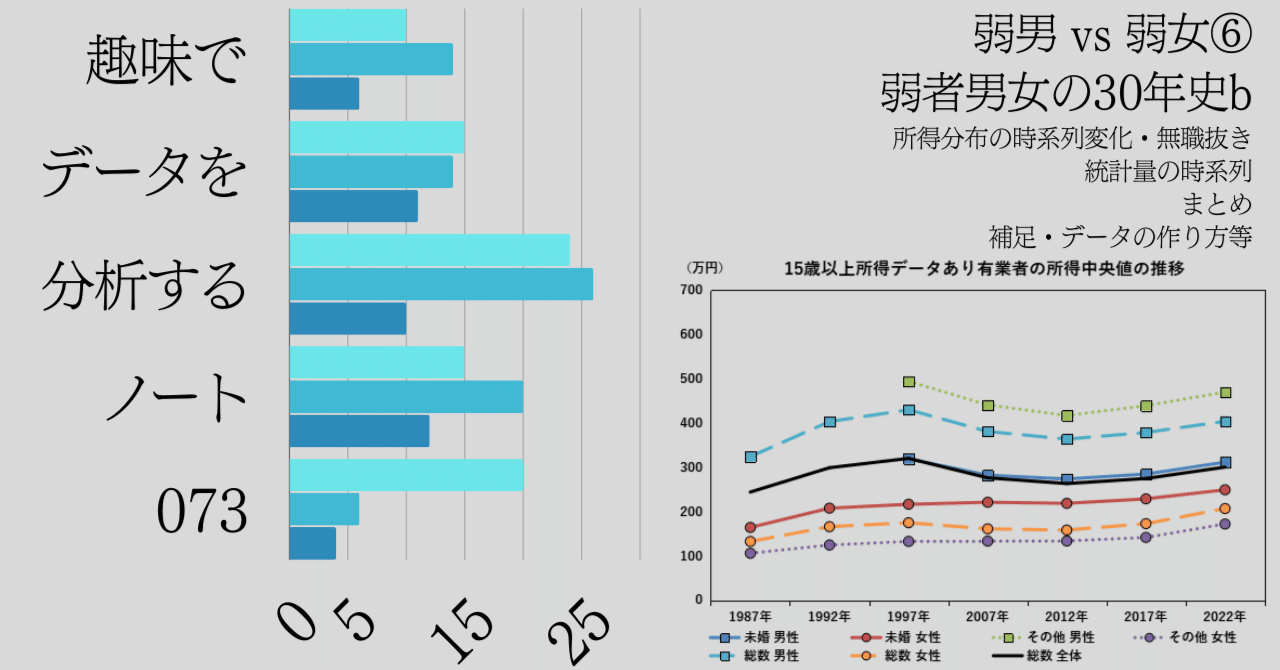最近の記事

趣味の読書003_あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠(キャシー・オニール)と測りすぎ(ジェリー・Z・ミュラー)
同じテーマを似たような感じで斬っている本を、2冊連チャンで読んだので、2つ一緒に読書感想文を書いてみよう。前者(以下、Math Destruction)は元の"Weapon of Math Destruction"という名前のほうがカッコいい。日本語訳では「数学破壊兵器」という直訳になっていて、"Mass"のニュアンスが落ちているのが、ちょっと残念。 両方とも主にアメリカの、データ計測が社会にもたらした歪みを、具体例を交えつつ描いている。Math Destructionのほ