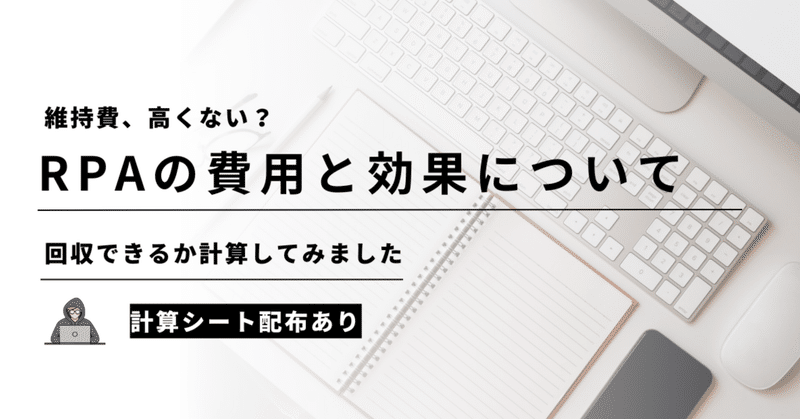
RPAの費用対効果は〇年!投資回収をリアル計算してみた
はじめに
皆様の仕事の助けになるため、いつも考えを巡らせているアカマツです。
何らかのITツールの導入をするにあたって、どうしても気になるのが【コスト】ですよね。
どんなに便利で魅力的な製品でも、「この製品のコストパフォーマンスはどうなの?」「投資回収はできるの?」という検討は、皆様されていると思います。
今回はその投資回収・コスパの面から、RPA(Robotic Process Automation)に切り込んでみたいと思います。
RPAは、業務プロセスを自動化するためのツールであり、業務効率の向上やコスト削減に貢献できる便利なツールです。しかし多くの製品が、導入時の初期費用に加え、継続的なランニングコストを必要とします。
というのも、RPAツールには買い切りタイプの製品がなく、利用するためのライセンスを購入するサブスクリプション型が主流です。「一括ご購入で300万円です!」などとは言われないものの、ツールを使い続ける限り発生する費用は、決して安いものではありません。
主なRPAツールは、ランニングコストが月額5万円~10万円となっており、年間に換算すると60万円~120万円にのぼります。そのため、「本当にコストに見合う効果が得られるの?」と導入に慎重になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事ではRPAツール本体のみならず、導入・維持に必要なその他のコストにも言及し、どれくらいの業務を自動化できれば元が取れるのか?ということを一緒に確認していきたいと思います。文末には計算に使ったスプレッドシートへのリンクをご用意しております。お急ぎの方はそちらだけでもご覧ください。
(補足1)今回の計算は「RPAにかかる費用はRPAで元を取る!」という発想に基づいております。「RPAのおかげでコア業務に集中して業績が上がった!」「RPAのおかげで残業が減った!」という効果は加味しておりません。
(補足2)すべての金額は2024年4月に調査しており、表示金額はすべて税抜にしています。あくまで参考値であることをご理解いただき、実際にRPAの導入を検討される際は、ご自身で各社ツールの利用金額等をお調べいただくよう、お願い申し上げます。
イニシャルコストは196,000円
RPA専用PC 80,000円
見落としがちかもしれませんが、RPAを導入するにあたっては、専用のPCを準備することをお勧めいたします。理由としては、RPAが稼働している間は、そのPCを手動で操作することはできないためです。
RPAは人がPCを操作するときと同じように、ディスプレイ上にExcel・Webブラウザなどのアプリケーションを起動し、操作を進めていきます。また1つ1つの操作は、どのアプリケーション・ウィンドウに対して、クリック操作をする・キー入力をするなどが細かく指示されています。
もしもここに手動の操作が混ざってしまうと、操作対象にするアプリやウィンドウが変わり、想定と違う結果になるか、エラーが発生してロボットが止まってしまうことが考えられます。
導入当初は担当者のPCを使って、ロボットの開発・テスト実行を行って問題ありません。将来的にロボットの稼働時間が1時間を超えたり、平日・土日などを問わず毎日動かすロボットが完成するなど、状況に応じて専用PCを準備してもいいでしょう。
もしも会社でお持ちのPCに余剰がありましたら、それを使って初期費用を抑えることができます。RPA提供企業が示す推奨動作環境を満たしているか、確認をしてください。
ここでは専用PCを新規に準備する前提で進めます。なお、金額80,000円については、価格.comのオススメPCランキングから、メモリ8GB以上のPC上位10件の平均額を切り上げて算出しています。
初期費用 100,000円
RPAツールの提供企業と契約する際、初期費用が発生する場合と、月額費用のみの場合があります。今回は検索で上位にヒットする主要なRPAツールを参考にしましたが、うち4社が初期費用ありの契約形態でした。
ここでは初期費用ありを想定し、金額は最も低価格であった10万円を参考金額として採用いたします。
RPAツールの操作方法を習得するまでにかかる人件費 16,000円
RPAによる業務の自動化は、企業の業務改革やDX推進にとって非常に有効な手段です。ただし、RPAツールを導入したところがゴールではなく、スタートだということを間違えないでください。
PCを自動操作するロボットを作っていく業務は、人の手で行う必要があります。ツールの操作難易度は様々ですが、今回は担当者がプログラミング未経験者であることを想定します。
ちなみに私自身も、プログラミング未経験でRPAを使い始めました。その際はツール提供企業からのサポートは受けず、Webで公開されていたマニュアルや練習事例をもとに操作練習を重ねていきました。本格的な稼働までに、1か月程度を要したと記憶しています(ただし他の業務と兼任していました)。
今回は初期費用の発生を想定しているため、初期段階でまとまった操作説明のサポートを受けることとします。その場合、RPA提供企業のツール紹介に例示されている習得時間、および私自身の経験等から、8時間で基本操作を習得できるものと仮定します。担当される方の時給相当額を2,000円とした場合、8時間で16,000円です。
なお、ここで習得するものは、あくまで基本操作であることに注意してください。イメージとしては、画面の見方・簡単なロボットの作成手順・スケジュール実行をする手順の確認、などです。実際に日々の業務を実行するロボットを作成する時間は、ランニングコストとして別に必要となります。
初年度のランニングコストは月額211,236円(細かい)
RPAツールの月額利用料 50,000円
日本国内で提供されているRPAツールは、私が把握している限り、すべてが月額または年額のサブスクリプション型となっています。(無料のものを除く)
今回調べたRPAツール10個については、最安が月額30,000円、高いもので270,000円ほど、平均額は90,000円程度でした。スモールスタートのため平均額より安い製品にすること・初期費用が設定されているツールに絞ることなどを加味した結果、設定金額として最も多かった50,000円を採用します。
契約期間については、最低〇か月と決まっているもの・1か月ごとに更新の有無が選べるもの・年額制のものと様々ですが、ここはあまり深く考えないものとします。
Microsoft365のライセンス料 月額1,236円
細かい数字が出てきてしまいました。
RPA専用PCを準備したため、そこにインストールするOffice製品が必要となります。バージョンも様々ありますが、最新バージョンとして月額1,236円とします。
ロボットの開発・保守にかかる人件費 1年目は160,000円
イニシャルコストのところでも述べましたが、ロボットの開発は人の手で行う必要があります。基本操作の習得とは別に、自動化する業務を選定する時間や、実際に業務を実行してくれるロボットの開発時間を確保する必要があります。そのため、人件費を無視して費用対効果を計算することはできません。しっかり計算に含めていきましょう。
また、特に初期段階においては、稼働し始めたロボットがエラーを起こすことが想定されます。RPAは正確にPCを操作します、と言われることがありますが、これはエラーを起こさないという意味ではありません。Web操作であれば通信環境が、Excel操作であればデータ量などが、外部要因としてかかわってきます。また、ロボットを作っていく中で、エラーが起きる可能性に気づかされることも多々あり、最初の半年程度はエラー対応を繰り返しながらRPAに慣れていくため、思ったほど自動化が進まないという事態が想定されます。
RPA専任の従業員を新たに雇ったり、今ある業務を差し置いてRPA担当者になるというのは、なかなかに難しいと思います。そのため今回の算出では、RPAを扱う担当者は別業務との兼任とします。業務の自動化を早期実現する重要性も考え、1日の勤務時間8時間のうち、半分の4時間をRPAに関する業務に充てるものとします。時給は2000円相当、週の稼働日数は平日相当の5日間、週数は4週として、2,000円×4時間×5日間×4週=160,000円です。2年目以降はRPAに慣れてきてエラー回数も減少するため、1年目の半額にあたる月額80,000円とします。
元を取れるか計算してみる
2年間の費用合計:4,305,664円
1年目の費用:2,730,832円
イニシャルコスト:196,000円
ランニングコスト:211,236円×12か月
2年目の費用:1,574,832円
イニシャルコスト:0円
ランニングコスト:人件費が減るため、131,236円×12か月
2年間の費用を参考に、元がとれる体制を算出します
上記のコストを単純に日割りしていくと、以下のようになります。(端数は都度切り上げ)
4,305,664円÷2年=2,152,832円/年間
2,151,832円÷365日=5,980円/日
この計算は、2年間の費用を均等に日割り計算したものです。ロボットが1日につき人件費6,000円相当の仕事をすることが、最低限達成すべき目標であると考えられます。
元が取れるのは、運用3年目以降
ここまでの計算を、もう少し掘り下げて考えてみましょう。
前項で人件費6,000円相当の仕事をすることが目標と述べましたが、RPAが1年目の初日から6,000円/日相当の仕事をすることは、現実的ではありません。ロボットを開発する時間が、絶対的に足りていないからです。そこで、次のように仮定します。
RPA担当者は半年以内に十分なスキルを習得し、ロボットの開発が可能になる
RPA導入から満1年の時点で、RPAが6,000円/日相当の業務を行う
1年目の単日効果は平均して3,000円/日とする(目標に対して50%)
2年目の単日効果は6,000円/日とする(目標に対して100%)
3年目以降、RPAの効果は10%ずつ増加するものとする
ランニングコストは増加しないものとする
この仮定と、先に計算した費用を掛け合わせると、次のようなグラフになります。

棒グラフの濃い紫色が年間コスト、オレンジが効果を示しています。棒グラフは【効果-コスト】を累計したものです。
1年目はイニシャルコストが発生し、RPAを使い慣れるまで人件費も高く設定されているため、コストが跳ね上がっています。そして先に述べた通り、1年目の効果は低く設定されているため、費用対効果としては大きくマイナスのスタートです。
2年目以降はランニングコストは一定額ですが、RPAが担当する業務は徐々に増加するため、効果が少しずつ高まりを見せます。
費用対効果の折れ線グラフが0のラインを上回った時点で、イニシャルコストまでの回収ができたことになります。このグラフでは「3年目=36か月経過」となりますので、運用開始から満3年~4年目が投資回収の目安になるといえるでしょう。
6,000円/日のロボットってどれくらい?
RPAの担当者と同様に人件費を時給2,000円として考えると、6,000÷2,000=3時間となりますので、人が手動で行っている業務3時間分を、RPAで自動化するということになります。さて、ロボットに任せる業務を1日3時間分、月間で約90時間分、考え出せそうですか?
月間90時間相当の業務量は、決して1人が行う仕事から捻出する必要はありません。主な業務がデスクワークの方が9人いれば、9人で90時間の業務自動化を実現すればよいことになります。1人あたりは10時間=600分ですが、月間の勤務日数が20日である場合、600分÷20日=30分です。「あなたの仕事のうち、1日30分の業務をロボットで自動化するので、アイディアを出してください!」と言われたら、何とかなる気がしてきませんか?
どんな業務の自動化を目指すか
弊社で自動化した業務の一部実例
弊社で実際に自動化した業務として、簡単なものを例示します。
店舗の前営業日の売上データをWebからダウンロードし、ファイル名を「日付+営業日報」に変えて、指定のフォルダに保管する(経理、毎日5分)
店舗で入金機に投入された現金のデータをWebからダウンロードし、ファイル名を「日付+入金データ」に変えて、指定のフォルダに保管する(経理、毎日5分)
約20店舗の前営業日の売上データをダウンロードし、売上と粗利の金額を抽出し、管理会計用の資料に転記する(営業、毎日60分)
最新の入荷予定データをWebからダウンロードし、Excelで不要な列を削除し、指定のフォルダに保管する(営業、毎日20分)
この4件で約90分の業務が自動化されました。
毎日行う業務には、自動化のチャンスあり!
1番や2番のように、Webからデータをダウンロードして保管する、という手動で5分くらいの業務は、最初に自動化を試みるものとしてオススメです。開発するロボットが複雑ではないため、業務を自動化しつつ、RPAに慣れていくことができます。
また、Webサイトにアクセスする際にブックマークを探す、抽出条件を間違えていたのでやり直す、ファイル名のルールをど忘れしたので確認する、保管先のフォルダを探す…など、意外に時間がかかっていたり、やり直しのストレスが発生していたりする側面があります。
毎日行っている業務を手間に思っている方もいると思いますので、積極的に自動化することを検討してみてください。
新しい業務をロボットで行う
現在は行っていないけど、本当はやりたいと思っていた仕事をロボットに任せる、という選択肢もあります。例に挙げたものでいうと、3番がこれにあたります。
弊社には、特定の商品の売上・粗利をしっかり分析したいというニーズがありましたが、人手不足の関係で、資料の元になるデータを抽出・転記することができていませんでした。私がRPA開発のスキルを習得したことを機に、このデータ抽出・転記を自動化できると聞いた営業担当者から、ぜひ協力してほしいとオファーを受け、自動化しました。
業務の自動化はRPA担当者だけでなく、全社で取り組みたい
既存の業務を自動化するにしても、未実施の業務をロボットで実現するにしても、大事なのはアイディアをたくさん出すことです。
私は店舗勤務をしたこともあれば、新店舗や改装にかかわる開発部・財務経理部・総務部と多彩な業務にかかわることができました。この経験から多くの従業員に顔と名前を覚えてもらっていましたし、とりあえず困ったらあいつに声かけよう、というポジションになっていました。
そのような経緯が功を奏して、業務自動化のネタに困ることはありませんが、これを一人で考えていたら、今と同じような成果は出せていなかったと思います。皆さんもぜひ、RPAを担当者一人で悩んだり、抱えこんだりせず、「こんなに便利なロボットを一緒に作りましょう!」と会社を挙げて取り組んでいってください。
補足
1契約で操作できるPCの台数に注意
RPAツールの契約によっては、月額50,000円で自動操作できるPCの時間・台数に制限がある場合があります。例えば、以下のようなものです。
1ライセンスで動かせるPCは1台まで、2台目以降は別途費用がかかる
1ライセンスで複数のPCが動かせる。ただし、同時に2台以上のPCを動かすことができないので、稼働時間をずらす必要がある
ロボットを作って動かすライセンスと、ロボットを動かすだけのライセンスが分かれている など
先に計算した費用対効果は、1ライセンス50,000円を想定しています。そのため、ツールによっては動かせるPCが1台だけという制限がかかる場合があります。
弊社の経験上、RPA専用のPCが1台あれば、十分に投資回収ラインに到達できると考えます。一方で、「前営業日の実績を午前中に集計して、午後の業務で使う」など、午前中にRPAの稼働が集中する場合は、1ライセンスでは自動化が実現できないことも考えられます。
RPAのライセンスが増えると、自然とランニングコストが増加し、投資回収のハードルも高まってしまいます。そのため、契約に際しては1ライセンスでどんなことができるのか、よく確認しておきましょう。
RPAだけで投資回収をする必要はない
ここまで計算しておきながら何を言う!とお思いかもしれません。
別の記事でもお伝えしておりますが、RPAは人件費削減のためのツールではありません。RPAによって手作業が減ることで、次のような効果も期待されます。
細かい手作業が減り、コア業務に集中できる→業績アップ
時間のかかる手作業が減り、残業が解消される→コストダウン
ミスなどが減り、業務上のストレスが軽減される→従業員の定着率アップ
事務作業が減り、退職・異動の引継ぎ量が減る→効率アップ、求人コストダウン
このような効果は数値にしづらいため、今回の投資回収計算に含めておりません。もちろん、RPAに多くの業務を任せることで、投資回収が実現するに越したことはありません。ただ、その考えにとらわれすぎず、従業員の皆様にとっていろんなメリットがあるのだな、ということもお考えいただけると幸いです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。やや計算が荒い面もあったかと思いますが、RPAにかかるリアルなコストに対して、どの程度の業務が自動化されればペイできるのか、具体的にご検討いただくきっかけになれたら、嬉しいです。
今回の計算内容をまとめたスプレッドシートを、以下に公開しております。数字を変更や改造をご希望の場合、コピーしてご利用ください。
では、今回の話を簡単にまとめます。
RPAのコストには、ツール本体のライセンス料だけでなく、様々なイニシャルコストや、人件費等のランニングコストがかかる
1ライセンスが月額50,000円の場合、月間90時間の業務を自動化することで、満3年程度で投資回収効果が得られる
大きな業務で90時間の業務自動化を達成するのではなく、多くの従業員からアイディアを募り、ちょっとした業務の自動化を積み上げていく方法がおすすめ
なお、弊社が運用サポートを実施しているRPAツール「マクロマン」は、ライセンス料が無料という驚きの製品です。この製品を使った場合の投資回収再計算については、改めて記事を用意したいと考えております。ご興味のある方は、ぜひ下記よりお問い合わせください。
【宣伝】RPAツール「マクロマン」公式パートナー企業として活動しています
アカマツの所属するニューコ・ワン株式会社は、株式会社コクー様の公式パートナー企業として、RPAツール「マクロマン」の運用サポート・ロボット開発受託を行っております。
マクロマン最大の魅力は、ツール本体の利用料が無料!いつまでも、何台でも、何度でも!RPAを無料でご利用いただけます。
事業規模を問わず、あらゆる企業・個人がRPAを活用することで、継続的な成長が可能となる未来に向けて、お手伝いをさせていただきたく、様々なサービスをご用意しております。
RPAでどんな業務が自動化できるの?
ロボットを作る様子や、動いているところを見てみたい!
ロボットの使い方を教えてほしい
自社で使うロボットを作ってほしい など
RPAに関するお悩み・ご相談など、お問い合わせいただけると幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
