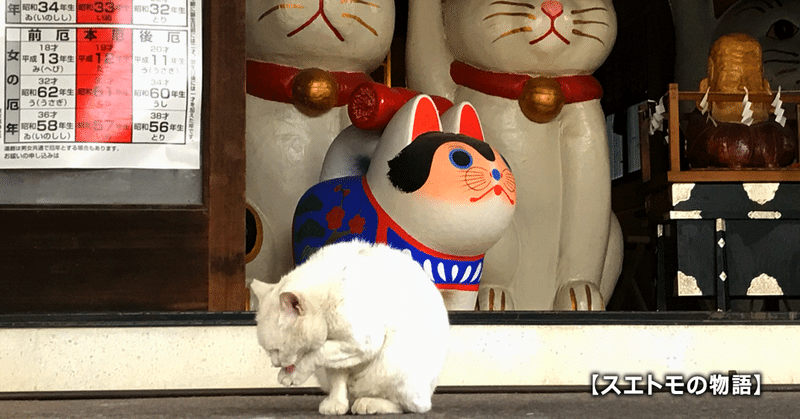
短編:【木の上の猫】
昨夜の雨も上がり、久々に日向であれば薄手のコートでも充分暖かく感じる、ある冬の昼下がり。たまたま入ったお店の、本日のランチが大正解で、満腹感プラスアルファーの満足感の中、公園の木々の間を歩いていた。
「あの~、あの、すいません…」
どこからともなく、中年男性の声がする。
自分の右手の方から聞こえた気もするし、後方からの気もする。
気のせいか?誰もいない。
「ちょっと、そこの旦那さん…」
やっぱり聞こえる。周りには人影はない。気味が悪い。それに私はまだまだヤングで、旦那と呼ばれる歳ではない。
「や、あの、向かって右手の木の上です」
向かって…右手の…木の上?言われるままに視線を動かした、その先にいたのは、一匹の黒い猫である。
「猫?」
舌なめずりをしながら、こちらをじっと見ている。力無く尻尾を揺らしながら、2メートルを超える高さから様子を伺っている。
「…どうも」
しゃべった。いや、舌なめずりで口もとが動いただけのような気もするが、しゃべった気もする。
「あのですね…」
「やっぱりしゃべった!」
こちらのビクッとした動きに合わせるように、猫も少しだけ腰を浮かしかける。
「や、さっきっからしゃべってますし…」
猫の狭い額がハの字に動いたような気がした。以前洋画で観たような、アリスワンダーランドに出てくるようなそんな印象か。
「あのですね、実は足を挫きまして。それと二日ほど前から何も食べられず、上手に飛び降りることが難しそうでして…」
やはりしゃべっている。中年親父のような声でしゃべる猫。
「ね、猫はしゃべらないでしょ…?」
「あら、旦那さん初めてですか?」
「初めて?」
「猫がしゃべるのを見たのは…」
それは、映画だとか漫画なら年中見ているし、何とかというパソコンの動画サイトでも、「ごはん」とか「おかえり」とか、ぼそぼそ一言二言、しゃべっている映像が出ていたこともあるが、それとはワケが違う。
「猫はしゃべるんですよ」
何も答えない私に、猫は続ける。
「家猫も野良猫も。ただね、馬鹿にしてるんですよ、人間を」
目を閉じ、たまにひげを撫でながら、ため息混じりに語る猫。
「それはさておき、降りれないので、肩をお借りしたいんですよ」
「ちょっと待ってよ!猫がしゃべるって…」
「ですからね、それはもうイイじゃないですか。空腹と昨日の雨でカラダが冷えてしまって、一刻も早く降りたいんですよ!」
猫はイライラしていた。前足を突っ張り腰を浮かせ、戦闘態勢で鳴くときの、フーッと言う唸り声にも似た高い声である。
「猫は全部しゃべるんですか?」
「旦那さんもしつこいな…全部しゃべりますよ!だけど、心を許した人間や、自分の切羽詰まった時にしか、声を出したくないんですよ。
ほら人間って、猫がしゃべると『バケネコ』とか言って、信じないじゃないですか。猫もね、馬鹿じゃない。いや、どちらかというと賢いんですよ、猫は。だから、人間を馬鹿にしてるんです」
木の上からしゃべられていることもあり、何だか侮辱されているような気分になる。猫がたまに見せる、呆れたようなあの顔は、本当に馬鹿にしていたのだろうか。
「そんな賢い猫が、なんでそんな木の上で降りれなくなるんだい」
グッと、痛いところを突かれた、という表情でそっぽを向き、ゆっくりと語り出す。
「騙されたんですよ、飼い猫の彼女に…」
ちょっと興味が出てくる。思わず口もとが緩くなる。
「なんだい、飼い猫の彼女って」
「だから、もうイイじゃないですか、カゼひきそうなんですよ、僕は!」
またしてもイライラしている。小さい体ながらに、生意気な態度でいる猫に対し、ちょっと意地悪をしたくなる。
「理由を言わないなら、肩は貸せないよ」
しばらく先程と同じように、狭い額をハの字に動かし、睨んでいる。
「…ですから、あの、この先のお宅で飼われている、メスの猫がですね、僕を騙しまして、で、そこら中の野良犬の怒りを買ってしまいましてね」
「恋のいざこざかあ?」
そんな、人間臭いことじゃないよ、と言いたげな表情で目線を逸らす。
「わかったよ、イイよ。ほら、肩を使って」
私は組み体操の時の馬のように両手で股を掴み、広めの背中を彼の方へ向けてやった。と同時に、猫は素早くタタッと飛び降りる。
思ったよりも軽かったが、バランスが悪かったのか、ブレるような印象があった。地面に降りたような気がしたので振り返る。
猫は軽く足をかばうように、素早く道の先の方へと一目散に逃げていた。お礼の一言もないのかと憮然と思った時、猫は静かに止まり、一度だけ
振り向いた。言葉には出さないが、一度お辞儀をしたような気がした。
が、すぐに草むらの中へと消えていった。
「何だったんだろう…」
そんな夢のような出来事は気のせいだと思い、仕事に戻る。
会社の受付には、今年の夏から派遣できている女性が座っている。以前から気になってはいるのだが、彼女はいつも無表情で、中々話し掛けにくい、高嶺の花だと感じていた。今日も硬い表情で会釈される。
その前を通り過ぎると、
「背中…」と声を掛けられる。
「ん?」とキョロキョロしていると
「動物の足跡みたいな泥が付いてますけど」
指さしながら指摘をされる。
「芝生かどこかで寝てたんですか?猫に踏まれたとか?」
ほんの少し、面白いモノを見た時のような笑みを見せる。思わず、私も笑ってしまう。珍しく会話が出来たことに満足をし去ろうとしたのだが、せっかくなので聞いてみる。
「あの、さ。もしかして、君んち、犬とか猫とか、飼ってる?」
きっかけは、どんな些細なことでも良いのだ。
「ええ、犬を…」口もとに笑みを残したまま、じっとこちらを見て答える。
「君んちの犬もしゃべるの?」
受付の彼女は、一瞬考えるような表情を見せる。
「ウチのペルちゃんはしゃべりますよ。私の言うことも良く聞くし」
「そっか…」
たぶん僕の知っている猫のようなしゃべり方ではないだろう。それでも、彼女には充分に飼い犬の声が聞こえていることだろう。
「今度、そのしゃべる犬を見に、君のウチに行ってもイイ?」
受付の彼女は軽く笑ってこう言った。
「新しい社内ナンパですか?…ウチには入れられないですけど…」
一瞬明るく、花が咲くような輝いた表情を見せる。
「今度、外で食事くらいでしたらイイですよ」
こんなに明るい彼女の笑顔は、初めて見たような気がする。笑いながら答えてくれた。
誰にも聞こえないような声で、私はつぶやいた。
「猫の恩返し…かな…」
「つづく」 作:スエナガ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
