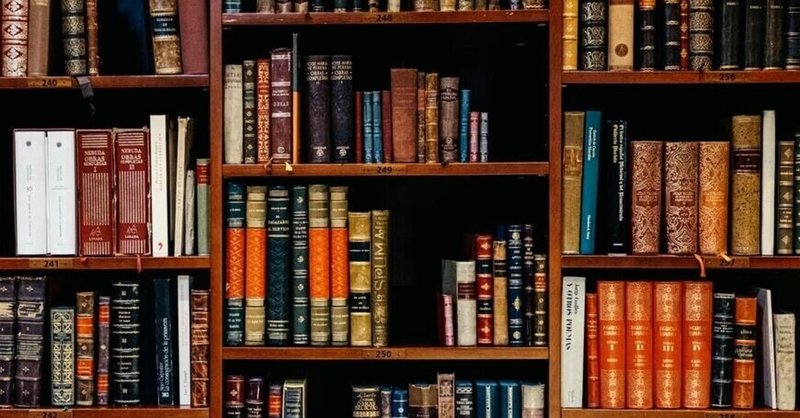
【感想4】もし僕らのことばがウイスキーであったなら
村上春樹(2002)、『もし僕らのことばがウイスキーであったなら』新潮文庫を読了しました。
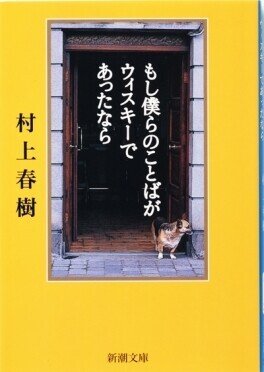
確か年が明けて少し経ったころに、近くのショッピングモールに入っている本屋さんで入手した本でした。本当はクリスマスに関するキャンペーンで売り出していた本だったらしく、そういった趣旨の期間限定の帯が付いたままになっていたのを覚えています。
新潮文庫ですが、本作は小説ではなく写真付きの紀行文で、村上がアイラ島やアイルランドで蒸留所や地元のパブを訪ねて、その土地その土地のウイスキーを現地の雰囲気とともにじっくりと味わうさまを描く作品です。いつもながらの文体でほっとします。奥さまが撮影したと云う、うつくしい写真が文章の合間にたくさん掲載されています。
ウイスキーそのものは不勉強で「へええ…」と思うような記述が多かったのですが、私が読んでいて、いちばん印象に残っているのは裏表紙にもある、一杯のタラモア・デューを味わう老人の話です。
村上が入ったパブに、古めかしいスーツをきちんと着た老人が入ってきて、なにも云わずにカウンターに腰掛けますが、バーテンダーもなにも云わずちょっと微笑したぎり、タラモア・デューを大ぶりなグラスに入れて彼の前に置いていきます。老人はストレートでそのウイスキーをゆっくりと飲んでいく。その、恐らくは毎日繰り返されている風景を、村上は「潮の満ち干」と形容しました。
しかしやがてグラスは飲み干された。しかるべき時刻が到来し、入り江に満ちた潮が引いていくのと同じように確実に。それがすっかり飲み干されたことを確認すると、彼は『不思議の国のアリス』に出てくる兎のようにちらりと腕時計に目をやり、再び僕の顔を見て、にっこりとした。僕もしょうがないからにっこりとした。彼の顔には満足の色が浮かんでいた。ちょうど良いだけの量の酒が、ちょうど良いだけの時間で飲み干されたことを、その微笑みは示していた。なによりのことだ。それから彼はカウンターの上に置かれていた左腕をおもむろに回収し、人々のあいだを縫って、足早に店を出て行った。(pp.108-109)
最高の飲み方ではないでしょうか。
ぐちぐちと口汚くだれかのことを罵りながら自棄酒をするでもなく、いつまでも意地汚く自然と意識が遠のくまで延々と飲みつづけるのでもない。「ちょうど良いだけの量の酒が、ちょうど良いだけの時間で飲み干された」と感じて、すっと酒場を去って行く。こういうおとなになるには、私もまだまだ樽での熟成が足りないように思われます。最高に恰好良い。
夜な夜な文字の海に漕ぎ出すための船賃に活用させていただきます。そしてきっと船旅で得たものを、またここにご披露いたしましょう。
