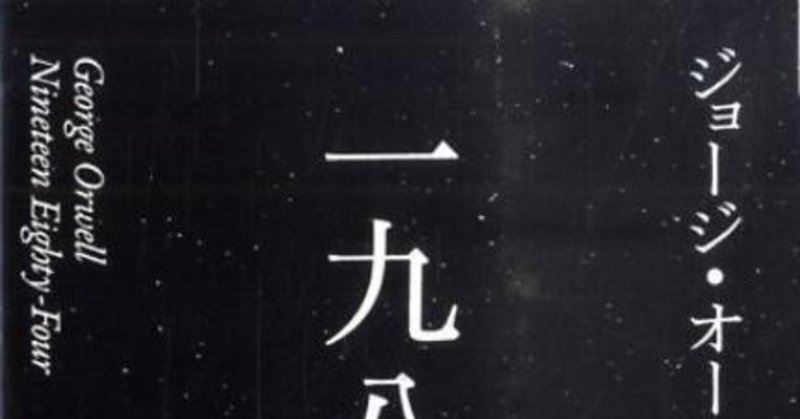
「一九八四年」(ジョージ・オーウェル)感想
党は真実を、現実を支配する。また言語を支配する。敵への憎悪を掻き立てて、党への忠誠を約束させる。人々は誰かを見下すことでアイデンティティを獲得し、強大な力を持つはずのプロールは、愚かで無関心に生きている。それらは全て、我々の生きる現実と、同じ姿をしているように私は思う。
多数派は常に正義であり、常識外れは断罪される。言語は文法によって人工的に支配され、煽動的な政治家は、次から次へと現れる。そして衆愚は、最も惜しむべき力を抱きつつ、世界への無関心とともに生きているのだ。
本書が描こうとしているのは、他ならぬ我々が生きる社会である。程度こそ違え、周囲を少し見渡せば、一九八四年のオセアニアの片鱗が、あちこちに見いだせることだろう。……執筆された一九四九年から、七十年近く経っているにも関わらず。
ディストピアは、劇的な技術革命や未知との遭遇によってもたらされるばかりではない。本書は文字通り「暗黒近未来小説」であり、ディストピアが現実の延長線上にあるのだという原点を、偉大な文学性とともに示す傑作なのだ。
しかし最後に疑問が残る。ウィンストン・スミスの結末は、果たして幸福だったのだろうか? そして附録「ニュースピークの諸原理」の著者は、一体何者なのだろうか?
いただいたサポートは書籍購入費に使わせていただきます。
