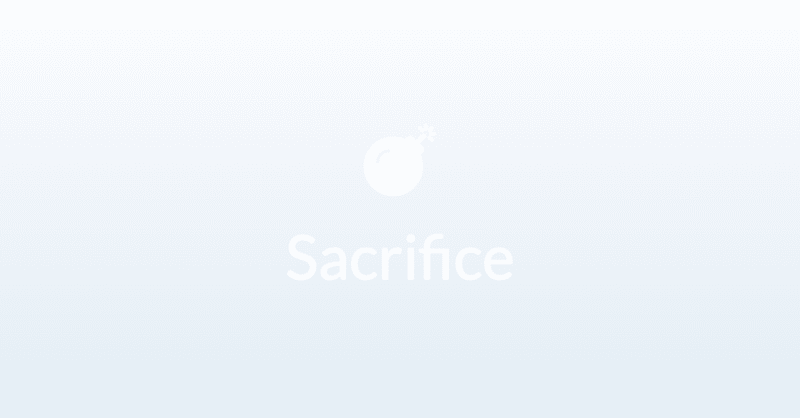
知れば知るほど面白いマーケティングの世界
三軍暴骨(さんぐんばくこつ)
→ 三軍は大軍の意で、戦いに敗れて多くの兵士が死ぬこと。
多くの犠牲の上で成り立っていることは世の中には結構ある。
犠牲はできるだけ回避したいのは誰もが思うことだろう。
そのために必要なものは戦略だ。
現代の専門用語を使うのであれば、マーケティングやブランディングといったところだろう。
若者という概念との向き合い方
若者と一言でいってもどの世代を若者というのか、その定義は実は結構難しい。
stak, Inc. は最近大きく体制を変えて、スタッフも大幅に入れ替えて若返りを図った。
1月で決算を迎えるのだが、2月は社名変更する前から数えると私が起業してから、ちょうど10年となる。
そう、ありがたいことに起業してから10年目を迎えることができそうなのだが、このタイミングで大きく舵を切ることを決めたのである。
その理由は1つではないが、10年を迎えるに当たって、自分自身がなにができたのだろうかと考えたときに、なに1つできていないと感じたからである。
10年という月日は決して短くない。
人生において10年という期間はとても重要で、ましてや40歳を超えた私からすると、今からの10年はその何倍、何十倍、何百倍も重要なものになる。
そう考えたときに、私自身が可能性に蓋をしていたように思ったのである。
確かに、いろいろとチャレンジはしてきたし、未だにチャレンジし続けている。
けれども、その一方でつい付き合いの長い人を自分の仕事仲間として選んでいる自分がいたということに気がついたのである。
昔から知っている人は自分のことをよく理解してくれているという思い込みが、私自身を縛っていたことに気がついたのである。
付き合いの長い人とのやり取りは楽だし、なんか上手くいっている気がする。
ただ、その一方でどこか思考停止していて、身内だけでしか拡がりがなくなっているという事実を見落としていた。
それがどこか古臭く革新的でないところに繋がっていることが明らかになった2022年だった。
そこで私は、自分よりも圧倒的に年が下の世代の人たちと組むことにしたのである。
具体的には、自分よりも10歳前後年下の世代、15歳前後下の世代、二回り以上下の世代といったところだろうか。
ジェネレーションギャップの実態
そういった若者たちと触れ合っていると、正直疲れるところもある。
まあ、少しでも長い人生を生きているだけでもそれなりの経験をしているわけで、そうなると自分が中心となってトップダウンで進めていかないといけない場面が増えるからである。
事業を大きくさせるため、自分の時間を少しでも多く確保するために若者たちを集めたつもりだが、返って自分の時間を奪われることはザラにある。
これが個人事業主や1人社長企業との大きな違いなのだが、成果が出るかわからないことへの時間とお金の出費が多くなる。
そこにジェネレーションギャップが加わる。
そんなことも知らないのかという単純なことも多いが、それ以上に自分自身が歳を重ねたことの実感の方が大きいかもしれない。
そうか、知らないのかといった気づきを与えてくれるのである。
同世代や近場の人たちだけとの触れ合いだと、そんなところにも気づくことがなく、そんな中で気持ちよくなっている自分がいたのかもしれない。
一方で、自分よりも年上の人たちとの触れ合いも持つようにしている。
そういった場では私が若者として扱われる場面もしばしばある。
そして、私が自分よりも年下の人たちに感じるのと同様に年上の人たちが私に対して同じような感情を抱いているのもわかるときがある。
まさに中間層だというところで、上の人たちに対してのジェネレーションギャップ、下の人たちに対してのジェネレーションギャップも理解できるということだ。
マーケティングやブランディングへの対応
それから、2022年も年の瀬を迎えている中で、私の中でマーケティングやブランディングに対して変化があった。
ありがたいことに、stak, Inc. ではデジタルマーケティング、広報、PRの案件をビジネスとしていただけるようになっている。
そこでは私がトップに立って指示を出すという場面がほとんどだったのだが、その構図が変わっていっている実感がある。
自分よりも年下のスタッフたちに、どんどん任せていくというスタンスに変更しているのである。
なぜそうしているのかというと、私の感覚や経験に基づいたマーケティングやブランディングの基本というか、どうすれば構築していくことができるかに関しては自信がある。
つまり、自分に任せてもらえれば成果を出すことができるという自負はある。
けれども、それだけでは拡がりが少なくなっているということに気がついたのである。
それがジェネレーションギャップによるものなのかは不明だが、10歳以上離れている人たち、15歳以上離れている人たち、二回り以上離れている人たちとのギャップを利用すべきなのだ。
というのも、10歳以上離れている人たちにはなんとなく自分の感覚は伝わるのだが、15歳以上、二回り以上の離れているギャップは想像している以上に大きい。
自分の子どもでもいいくらいの歳なので当たり前といえば当たり前なのだが、ここが利用できるのは大きな強みになる。
私から見て二回り以上離れているということは、私よりも10歳以上、年上の人たちとの付き合いもあるので、そうなるとその人たちからすると三回り以上離れていることになる。
要するに、36歳以上離れているということになるので、このギャップはなかなか大きいことは理解できるだろう。
ここがマーケティングやブランディングで使えるということは、強みでしかないのである。
戦略は若者にも通じる概念
冒頭にも書いたが、なにかを始めるに当たって犠牲はつきものだ。
物事はその犠牲の上で成り立っているといっても過言ではないだろう。
犠牲を失敗という言葉に置き換えるとわかりやすいかもしれないが、失敗は成功のもとというのは、まさにそういった状況を言語化したものだろう。
そして、犠牲が多ければ犠牲を出さないように戦略を考えるようになるということだ。
歳を重ねていくと、この戦略を考えることは自分たちの仕事だと思い込んでしまうという傾向があるように思う。
なにが言いたいのかというと、経験が豊富な人の方が戦略を立てなければいけないという思い込みだ。
これが最近の若い者はという定番の言葉に繋がるような気がしているのだ。
つまり、戦略を立てることは若者にも十分に伝わることで、若者でもいくらでも戦略を考えることはできるということを主張している。
このことは若者と接していかないとわからない。
若者たちとの融合
ということで、stak, Inc. の体制の整理が2022年の年の瀬に向けてしっかりとできた。
これは私にとって、とても大きなことで2023年に向けて蒔いてきた種が少しずつ芽を出し始めている。
事業については随時公開していくので乞うご期待ということで、どの事業にもテーマの1つとして若者との融合というものがあるということを伝えておきたい。
若者にはやはりエネルギーがあるし、フレッシュさは驚異になる。
そんな若者たちと一緒に見に行きたい世界が明確にある。
起業して10年目、stak, Inc. という企業は大きく生まれ変わるだろう。
まとめ
マーケティング、ブランディングという言葉は考えれば考えるほど奥が深いものだ。
そのことは多くの若者と触れ合い、多くの年上の人たちと触れ合うとよくわかる。
そのギャップが大きければ大きいほど不協和音が生まれるのだが、その不協和音がときとしてキレイな和音として聞こえたときにブランディングの完成となるような気もしている。
そんなブランディングをしていくためのマーケティングの方法、つまり犠牲の上での戦略を考えれば考えるほど奥が深くて面白いということだ。
【Twitterのフォローをお願いします】
株式会社stakは機能拡張・モジュール型IoTデバイス「stak(すたっく)」の企画開発・販売・運営をしている会社。 そのCEOである植田 振一郎のハッタリと嘘の狭間にある本音を届けます。
