
小説『水蜜桃の涙』
※はじめに
このたび柄にもなく、小説の執筆という自分でもおこがましいものに足を踏み入れてしまいました。
このnoteで交流させていただいている「夕陽が海に沈む時さん」からお誘いを受け、恥ずかしながら小説を書こうと思ってしまったのです。
初心者ですので、いろいろと不足している部分が大いにあるかと思われますがどうぞ温かい目でもって読んでいただければ幸いです。
第1章 「美しき村」
この章の登場人物:
成沢 清之助・・・高等師範学校の最終学年に通う都会育ちの20歳の青年
谷口 倖造・・・・高等師範学校の教授
その土地は初めて足を踏み入れたはずだが、どこか懐かしさを覚えるような感覚があり不思議でしょうがない。きっと里山の原風景がそのままで、東京で生まれ育った僕にもあるのだろう、精神の奥底に潜んでいるなじみの風景だからなのか。
高等師範学校の教授に誘われ、教授の故郷だというこの場所を訪れたのは卒業前の年の夏の初めであった。
駅を降りてずいぶん歩いたが、ひとつ峠を越えなければいけないらしい。さすがに汗が噴き出してきた。
「先生、まだ歩くんですよね。先生のふるさとはあの峠の先ですか?」
「成沢君、もう音を上げたのかね?やはり都会育ちの坊ちゃんには、これくらいの山歩きも苦痛と見えるな」
この谷口教授は何かというと“都会育ち”と言っては、僕をそんじょそこらの生っ白い奴らと一緒にして馬鹿にする。それならばと、こちらも意地になって歩を速めてみる。
「ははは…安心したまえ。その力強い歩みならばもうすぐ着くだろう。この林を抜けると、ちょっとした大きな池があるから、そこでひと休みとしよう」
教授の話によると、この林を抜ける道は教授が子どものころ駆け回ったという村への近道らしい。どうりで公道をはずれているなと思った。
おかげでブナやナラなどの木々が陰を作ってくれているから、陽の光をまともに受けることが少なく、暑さも和らぐというものだ。
心の中だけで教授には感謝の弁を述べつつ、少し行くと、眼下に教授が言った池の水面が光っているのが見えてきた。
癪だが休めると思って、ややほっとする。
教授とともに、やや大きめの池全体が眺められる土手に腰を下ろす。
よくよく見渡せば、美しいところである。
遠くまで続く山々は青く煌めいている。木々が豊かに生い茂り、時折吹くそよ風に葉がちらりちらりと見た目にも心地よい。
池の水面を生まれたばかりの風がひゅるりと小さな波を作りながら、離れた向こう岸まで小走りしていく様は、可愛い童子を想像してしまい思わず口元が緩んでしまった。
きっと村の中も、美しいに違いない。
「物心ついた幼いころからこれまで確信しているが、我が故郷ながらこんなに美しい場所はないとね。ここに帰るたびにそれを実感するのだよ。どうかね?出発前に私が君に言ったとおりの場所だろう?」
谷口教授は僕をここに引っ張ってくるために、自分の住んでいた故郷がいかに美しいかを力説したのだった。
一度見てみないかと、僕に興味を持たせるために。
「成沢君、ちょっと君に話があるのだが」
そう谷口教授に呼び止められたのは、授業が終わった夕方の学校の廊下にてである。
そして教授の部屋に一緒についてくるよう言われた時は、まさか僕の試験の点数が悪いとか、日頃の素行が悪いなどと責められるのではないかと、そのような自分の悪い部分がもしかしたらあるのかもしれないとしか頭には浮かばなかった。
下手すると、教授たちの間にとんでもない評判が立っていて、最悪学校を辞めさせられるのではないかとまで想像してしまったのである。
いやいや、自分が思う分には成績はさほど悪くはない、むしろ上位成績を常に維持しているではないかと自負しているくらいなのだが。
しかし根っからの心配性である。
まさかという場合もあるということを考えておかなくてはいけない。
祖父に教えられたではないか。人間、驕り高ぶるのは恥ずべきことだと。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」と先人も言っている。
「和光同塵」である。南無…。
などと、いらぬことを頭の中で巡らせているうちに教授の部屋の前に着いていた。
額に冷や汗をじわりと流しながら教官室に入ると、椅子に座るよう勧められた。
「いや、帰るところをすまないね。実は折り入って君に頼みがあるのだ。来週の休みを利用して、私は帰郷しようと考えている。一泊だけの慌ただしい宿泊にはなるのだが、ちょっと君についてきてもらえないかと思ってね」
「は?先生の故郷へ、ですか?」
嫌な想像しかしていなかった私は、面食らって、やや素っ頓狂な声を出してしまった。
「急なことで驚くのも無理はない。私の故郷というのが、山の多い田舎でね。いや、なに、田舎ではあるがとても風光明媚でいいところなのだよ。
ただ、当たり前と言っては何だが教育が遅れていて、高等小学校はあるが官制の中学校が未だ存在していないのだ。
才能ある者がわざわざ、故郷を出て隣町の中学校に通わなくてはならないのだ。状況は私の学生時代とほとんど変わっていないじゃないか、君!
それで、私が村長に掛け合って、村の有力者で昔は名主だったという家督の人物に民間の中学校創設の資金を出してもらえないかと頼んでもらったのだよ」
「それが、僕とどういう…」
教授の田舎の話で少し退屈し始めたが、なぜ帰郷同行に自分が付き合わなければならないのかが気になって、話の腰を折る。
しかし教授は意にも介さず、話を続ける。
「いやあ、無理な頼みだし実現しないだろうと思っていたのだがね。
その有力者という人物が、なんと金を出してくれるという返事が村長から届いたのだ。青天の霹靂だよ、全く。頼んではみるものだな。
村長によるとその人物、名誉欲は人一倍あるらしく、何か自分の名を残したいと思っていたらしいのだ。
そこへ運よくというかだな、私の陳情が舞い込んできたものだから、上手く利用したというあんばいだ。
まあ、こちらとしては中学校を快く作ってくれるのなら、名誉とかそんなもの、どうぞ差し上げますよ、ってなもんでね。はははは」
まだ僕との関連が全く見えてこない。ちょっとばかり、椅子から尻が浮きかける。なんならもう、お暇しようかと思った矢先、こちらの様子を見て慌てた教授は僕の腕を抑えつつ、
「そこでだ。名誉はもちろんだがね、それと同時に中学校の教師を一人こちらで推薦するように条件を出されたのだよ。
それも都会の学校に匹敵するような優秀な教師を連れてくるよう命じられたのだ。それが何を隠そう、君だ!」
第2章へつづく
※注・・・学制については、明治時代改変が繰り返されていました。
高等小学校は明治後期、約14歳くらいまでの就学。中学校は今の
高校くらいだと思われます。
高等師範学校は男子が16歳から20歳までの就学だったようです。
参考:文部科学省 学校系統図より
※ この物語に登場する人物・場所は完全なるフィクションであり実在しません。実際に存在した高等師範学校とも無関係です。尚、時代も明治後期の某年とだけあらかじめ書き添えておきます。
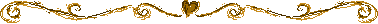
「はじめに」で紹介させていただいた「夕陽が海に沈む時さん」の作品はコチラです。
海外を拠点にされている方ならではの、グローバルな作品を執筆されています。ぜひ訪れてみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

