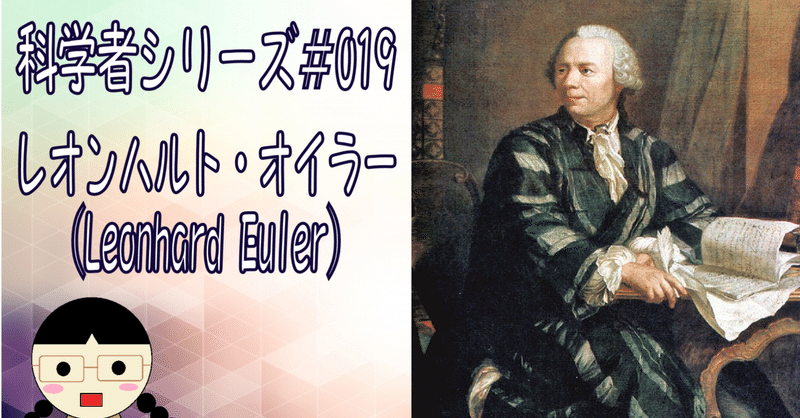
【科学者#019】人類史上最多と言われる膨大な量の論文を残した科学者【レオンハルト・オイラー】
一生のうちに書くことができる論文というのは、何本なのかはよく分からないのですが、例えば年間5本書いて、それを50年間続けのであれば合計で250本になります。
しかし科学者の中には、死んだ後も半世紀にわたって論文が刊行された科学者います。
今回は、人類史上最多と言われる膨大な量の論文を残した科学者レオンハルト・オイラーについてです。
レオンハルト・オイラー

名前:レオンハルト・オイラー(Leonhard Euler)
出身:スイス
職業:数学者・天文学者
生誕:1707年4月15日
没年:1783年9月18日(76歳)
業績
オイラーの名前がついている定理など、たくさん残っていて、今回は一部紹介します。
【オイラーの公式】
まずは解析学から、複素指数関数(ふくそしすうかんすう)と三角関数の間に成り立つのがオイラーの公式です。

【オイラーの多面体定理】
オイラーは幾何学の分野でも数多く業績を残していて、オイラーの名前がついているものではオイラーの多面体定理があります。

穴の開いていない多面体では、頂点、辺、面の数について、
(頂点の数)+(面の数)-辺の数=2
が成り立ちます。
【オイラーの運動方程式】
さらに、オイラーは物理学でも業績を残しており、オイラーの運動方程式という剛体の回転運動を表す式を発見しています。

この他にも、オイラーの微分方程式、オイラーの定数、オイラー関数、オイラー積、オイラーの角など、オイラーの名前がついているものだけでも数多くあります。
オイラーの論文は900以上あり、これを超える科学者は出ないのではないかと言われています。
生涯について
オイラーの父親はプロテスタントの牧師をしていました。
バーゼル大学学部生時代、父親とヨハン・ベルヌーイはヨハンの兄であるヤコブ・ベルヌーイの家に一緒に住んでいました。

ベルヌーイ一族からは、有名な数学者が何人も誕生しています。
大学生時代にオイラーの父親は数学に触れ、のちに息子のレオンハルト・オイラーに数学を教えます。
1720年、14歳のときにバーゼル大学に入学します。
そこで、ヨハン・ベルヌーイの個人授業を受け、さらに数学に対して興味を持ちます。
1723年、牧師である父親の希望に従って神学の研究をはじめます。
しかし、オイラーは神学、ギリシア語、ヘブライ語の研究には興味がありませんでした。
ヨハン・ベルヌーイがオイラーの父親を説得したこともあり、最終的にはオイラーは数学者になる道に変更します。
1727年からは、現在のロシアにあるサンクトペテルブルクの科学学士院で働きます。
そこで、ヨハン・ベルヌーイの息子であるダニエル・ベルヌーイと同僚になります。

ダニエル・ベルヌーイも、有名な数学者・物理学者でベルヌーイの定理などを発見しています。

1734年、画家の娘のカタリーナと結婚します。
カタリーナとは、13人の子どもができるのですが、大人になることができたのは5人だけでした。
1735年には、オイラーは右目を失明してします。
そして、この頃にはロシアの情勢が不安定になります。

1741年、プロイセン王国のフリードリッヒ2世の依頼で、ベルリンの科学アカデミーの会員となったためドイツへ移住します。
しかし、このフリードリッヒ2世からは、のちに疎まれるようになり、ドイツに居づらくなります。
1766年に、ロシアのエカテリーナ2世が帝位についてたことで情勢が安定したことで、オイラーはサンクトペテルブルクに戻ります。
しかし同じ年の1766年に、病気でほぼ全盲になってしまいます。

1771年には白内障の手術をして、数日視力が回復するのですが、その後再び全盲になります。
オイラーは、脳内で執筆した論文を口述記述してもらう形で、両目を失明した後も論文を書き続けます。

1776には、サンクトペテルブルクのアカデミーの物理学部長に任命されます。
そして、1783年に突然発作に襲われて、そのまま息を引きとります。
オイラーという科学者
オイラーは亡くなる1783年までに数多くの論文を発表しました。
これは、人類史上最多と言われる膨大な量の論文や著書で、生前発表した論文数は500余になると言われています。
さらにすごいのは、オイラーの死後半世紀にわたってオイラーの論文は刊行されます。
死後に刊行されたものを含めると論文の数はおよそ900と言われています。
ニュートンの運動方程式を微分形式で表したのもオイラーがはじめてで、本当に数学や物理学で多くの業績を残しています。
オイラー以上に研究への熱意が死ぬ直前まで冷めずに、数多くの論文を書き上げた科学者は、今後現れないのかもしれません。
そんな、オイラーのことを少しでも知るきっかけになることができれば嬉しいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
