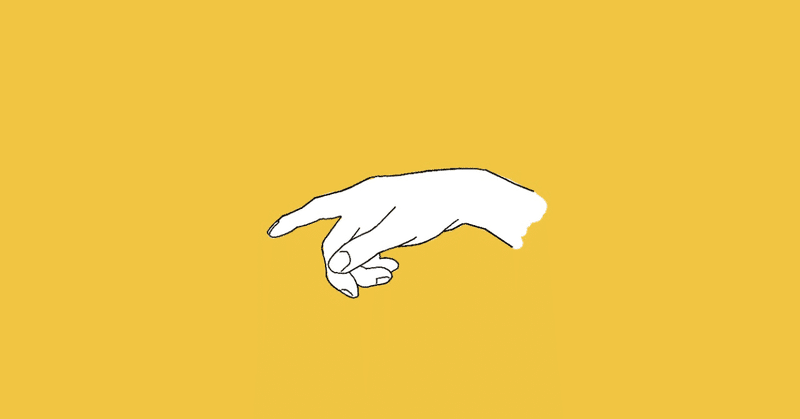
【文章作成の基本】指示語のはたらき
逆説的な言い方になりますが、文章展開(文をつなぐ)で重要なのは、接続詞ではなく、実は指示語の方です。やたらと接続詞で強引につないでいくよりも、指示語をうまく使った方が、自然な文章展開となり読み手に伝わりやすい文章になります。
接続詞と同様に、中高生のみなさんの文章を見ていると、指示語の使い方が恣意的なケースが多いです。中には、指し示すもの(指示内容)が明確でなかったり、存在しなかったりするため、内容が伝わらない文章もあります。指示語を使う以上、それが文章の何を指し示しているのか、その指示内容を明確にするのは、まさに文章作成の基本です。
しかし、「基本」は、「簡単」、「イージー」ということではありません。いわゆる「うまい文章」は、指示語の使い方がとても巧みです。指示語によって「前の内容を受けながら後ろにつなげていき、内容をまとめていくこと」を適切に行っており、読み手が途中で内容がわからなくなって置いて行かれたり脱落したりすることがないようにしているからです。指示語自体は小学校の国語で学習する簡単なものですが、指示語をうまく使うのにはある程度の訓練が必要であると、私は思います。
では、どんな訓練が必要なのか。まずは「文章を読むときに、指示語がその文章中でどう機能しているのかについて自覚的になること」だと思います。指示語がどのように前の内容を受けてその内容を後ろにつないでいるのか、またそれによって、どのように内容がまとまっていくのかを、意識的に追うことが大切です。その上で、その指示語のはたらきを意識して、自分の文章でそれを真似てみるとよいでしょう。それによって、読み手に自分の言いたいことをしっかり伝えて、(書いている自分と同じ精度で)内容を理解させることが可能になります。
とはいえ、具体例がないとわかりにくいですよね。少し長いですが例文を用意しましたので、その文章を使って実際に説明しましょう。
一つ目は、ご存じ「日本国憲法」の前文です。これを例文としたことに、特に政治的な意図はないです。指示語のはたらきを確認するのには、使いやすいサンプルだからです。後、長く引用するため著作権侵害の心配がないテキストを選ばないといけないので、まずはこれを選びました。
例文の内容を読んでみてください。その際、指示語が何を指しているか十分に意識しながら、読んでくださいね。そして、その指示語には一つひとつに番号が付いています。例文の後では、その番号ごとに、その指示語が何を指しているのか、指示内容をまとめていますので、その番号に従って、各指示内容を確認してみてください。
では、どうぞ。
〈例文1〉
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、1「ここ」に主権が国民に存することを宣言し、2「この」憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、3「その」権威は国民に由来し、4「その」権力は国民の代表者が5「これ」を行使し、6「その」福利は国民が7「これ」を享受する。8「これ」は人類普遍の原理であり、9「この」憲法は、10「かかる」原理に基くものである。われらは、11「これ」に反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
※ 番号は〆野による。
※ 一部現代仮名遣いに変えた。
1「ここ」:「この文章(日本国憲法)」を指す。
2「この」憲法:「日本国憲法」を指す。
3「その」権威:「国政の権威」を指す。
4「その」権力:「国政の権力」を指す。
5「これ」:「国政の権力」を指す。なお、ここの文節は「国民の代表者が」が主語。「その権力は」は「その権力について言うと」という、「文の主題」を意味する。
6「その」福利:「国政の福利」を指す。
7「これ」:「国政の福利」を指す。なお、ここの文節は「国民が」が主語。「その福利は」は「その福利について言うと」という、「文の主題」を意味する。
8「これ」:「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威(国民の権威)は国民に由来し、その権力(国民の権力)は国民の代表者がこれ(国民の権力)を行使し、その福利(国民の福利)は国民がこれ(国民の福利)を享受する」までを指している。こういうことが「人類普遍の原理」である、ということ。
9「この」憲法:「日本国憲法」を指す。
10「かかる(このような)」原理:「人類普遍の原理」を指す。したがって8の指示内容「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」原理を包括的に指している。
11「これ」:10の「かかる原理」を指す。したがって10の指示内容「『国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する』という人類普遍の原理」を包括的に指している。
どうでしょうか。大人の方は、「何か『現代文』の授業でこんなのあったなぁ」という感じでしょうか。「この指示語は何を指していますか。」という問題、国語でありましたよね。
ここで注目していただきたいのは、指示語1から11に向けて見てわかるように、前の内容を受けながら、内容が後ろに行くにつれて「集約」されている点です。憲法を確定する上で、そもそも国政がどういうものであるかを説明し、そうしたことが人類普遍の原理であると言っています。そしてその原理に基づいて憲法を確定するのだ、ということを、指示語を使って段階を踏んでまとめていっていることがわかります。
これは少しお堅い公文書なので、次は別の例文で見てみましょう。もう少しやわらかいエッセイで、同じように指示語のはたらきを確認してみます。
それでは、どうぞ。
〈例文2〉
関東大震災の前数年の間、先輩たちにまじって露伴先生から俳諧の指導をうけたことがある。1「その」時の印象では、先生は実によく物の味のわかる人であり、また2「その」味を人に伝えることの上手な人であった。俳句の味ばかりでなく、釣りでも、将棋でも、その他人生のいろいろな面について3「そう」であった。4「そういう」味は説明したところで他の人にわかるものではない。味わうのはそれぞれの当人なのであるから、当人が味わうはたらきをしない限り、ほかからはなんともいたし方がない。先生は自分で味わってみせて、5「その」味わい方をほかの人にも伝染させるのであった。たとえばわかりにくい俳句などを「舌の上でころがしている」やり方などが6「それ」である。わかろうとあせったり、意味を考えめぐらしたりなどしても、味は出てくるものではない。だから早く飲み込もうとせずに、ゆっくりと舌の上でころがしていればよいのである。7「その」うちに、おのずから湧然として味がわかってくる。8「そういう」やり方が、先生と一座していると、自然にうつってくるのであった。
※ 番号は〆野による。
1「その」時:「先輩たちにまじって露伴先生から俳諧の指導をうけた」時を指す。
2「その」味:「物の味」を指す。
3「そう」:露伴先生が「その味を人に伝えることの上手な人」であった、ということを指す。当然2の「その味」を内包しているので、「『物の味』=『俳句の味ばかりでなく、釣りでも、将棋でも、その他人生のいろいろな面について』の味を人に伝えることが上手」であった、ということが指示内容になる。
4「そういう」味:「『物の味』=『俳句の味ばかりでなく、釣りでも、将棋でも、その他人生のいろいろな面について』の味」を指す。
5「その」味わい方:「『物の味』=『俳句の味ばかりでなく、釣りでも、将棋でも、その他人生のいろいろな面について』の味」の味わい方を指す。
6「それ」:5の「その味わい方」を指す。したがってそれは「『物の味』=『俳句の味ばかりでなく、釣りでも、将棋でも、その他人生のいろいろな面について』の味の味わい方」を指している。
7「その」うちに:「早く飲み込もうとせずに、ゆっくりと舌の上でころがして」いるうちに、を指す。なお、これは5、6が指す「味わい方」の詳細である。
8「そういう」やり方:「そのうちに、おのずから湧然として味がわかってくる」やり方を指す。当然7の「そのうちに」を内包しているので、それは「『早く飲み込もうとせずに、ゆっくりと舌の上でころがして』いるうちに、おのずから湧然として味がわかってくる」やり方(露伴先生の「物の味」の「味わい方」)を指している。
こちらはどうでしょうか。
評論家、文筆家の和辻哲郎氏のエッセイです。こちらも、著作権切れした文章の中で、指示語がうまく機能している文章であるため、選びました。文豪である幸田露伴との思い出についてまとめた文章の一部です。「露伴先生は『物の味』の味わい方を人に伝えるのが上手かった」ということを説明しています。その「物の味」とは何のことで、露伴先生がそれをどのように味わい、そしてその味わい方をどのように人に伝えたのか、指示語をうまく使いながらまとめています。ここでも、指示語1から8に向かって、内容が徐々に「集約」しているのがわかるでしょう。
指示語の本当の機能とは、単に「前に述べたことを指す」ということではありません。このように、前の内容を受けて後ろの内容にうまく接続することで展開させ、同時に文章をまとめていくものが指示語なのです。ですから、接続詞ではなく指示語こそが文をつなげる、と言い換えることもできます。
指示語が内容をどうつなげてまとめているのか、意識して文章を展開させ、より伝わりやすい文章を書いていきましょう。
付記:例文引用に関しては、青空文庫さんを活用しました。
「記事が参考になった!」と思われる方がいましたら、サポートしていただけると幸いです。いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
