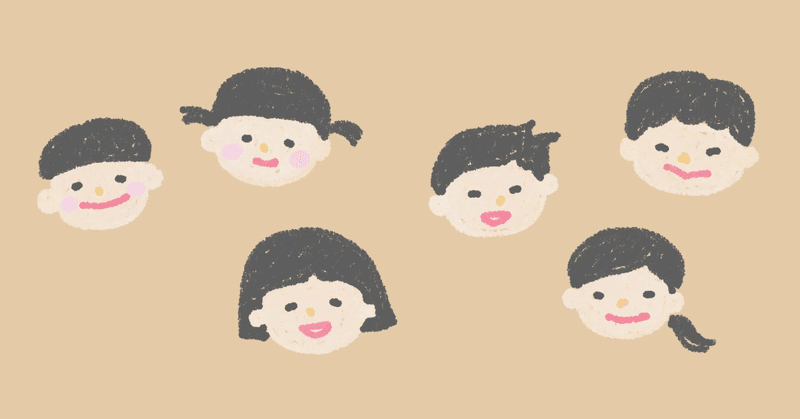
意見が違うから、良い決断ができる~「協調学習」「建設的相互作用」の視点から~
組織のコミュニケーションや意思決定の視点から、
最近考えていることを言語化してみました。
「意見が違うから、良い決断ができる」のメカニズム(論文引用&個人的な考察)について。
意見が違うから、良い決断ができる
題材:ミシンの実験
三宅なほみさん(元東大教授・認知科学)の「協調学習」「建設的相互作用」に関する実験↓
実験は、「ミシンの縫い目はどうやってできるか」について考えてもらいました。ミシンの縫い目は、上糸と下糸が絡み合ってできています。しかし縫っている途中は上糸の片方の端は糸巻きにあり、もう一方の端は布につながっています。一方下糸の端はボビンにあり、もう一方の端は布につながっています。このとき端のない2本の糸が実際にどのように絡み合うか、この問題について2人で一緒に考えてもらいました。
その過程を分析すると、「分かる」ことがさらに「分からない」ことを生み出していくことが分かりました。例えば「針によって上糸の輪ができ、その輪がボビンで下糸を通し、針を輪が引き上げることで縫い目ができる」と考えたとする。すると「ボビンが上糸の輪と下糸を通す働きはどのような機構になっているか」という問題が残るので、それを分かろうとします。そしてこのようなことが繰り返し起こることで、理解が深くなっていくことが分かりました。
また2人いることで、あまり分かっていない人がよく分かっている人の考えをチェックしたり批判することで、それがよく分かっている人に「わからない」を生むきっかけとなることが分かりました。例えば、少しわかっている人が「ボビンには隙間があってそこに輪が通る」と発話したとき、少しわかっていない人が「ボビンは宙に浮いた構造になっているの」と相手を批判する。ここで相手に説明できないとき、それを問題として説明を探ろうとする。このように2人いることで、相手に説明をしなければならない状況を作るため、効果的に理解を深める仕組みとなることが分かりました。
補足:理解の過程
上記の実験が記載された論文を元に、
freeeさんのエンジニアの方が、書かれた記事から抜粋↓
1. Level nの機構の機能の特定(Identified)
2. 機能がどのようにして実現されるのか疑問を抱く(Questioned)
3. Level n+1の機構の探索(Searched)
4. 暫定的な解決策としての機構の提案(Proposed)
4-1. 提案の批判(Criticized)
5. 提案された機構の確定(Confirmed)
具体イメージ:営業MTG
実際の職場での会話に当てはめると、
こんな感じかな?↓
【Identified】
光一さん・剛さん
「今月の目標を達成するためには、A社を攻めていくべきだ!」
↓
【Questioned & Searched】
光一さん
「でも具体的には、どうしよう?」
↓
【Proposed & Criticized】
剛さん
「A社の○○さんを巻き込んで、XXの提案すべきじゃ?」
光一さん
「でも過去に○○さんは~~と言っていたんだよね。それよりもいい方法があるはず。△△さんにアプローチするのはどう?」
剛さん
「そういえば、A社の@@さんが他社事例を求めていた。@@さんは管掌役員とも近い。B社の担当者の◇◇さんにヒアリングして、A社向けのB社の事例を使った提案をするのが良いのでは?」
光一さん
「A社の@@さんと、B社の$$さんって、前職が一緒で仲が良かったはず。$$さんは◇◇さんの上司でもあるので、うまく巻き込むのが良いかも」
↓
【Identified】
光一さん・剛さん
「B社の$$さん・◇◇さんから事例ヒアリングしつつ…(中略)…を実行しよう!」
でも実際には、こんな風にスムーズに議論は進みません。
簡単に、整理してみたいと思います。
結論:異なる視点から「提案を批判」し、客観的に良し悪しを判断する過程を通して、最終的な決断の質が上がる
松田なりの前提条件:決断の質が上がるための議論
関係性:
相手の意見を受け入れることができる
視点の差異
価値観・前提知識が異なるほど、異なる意見や批判は出やすい
話し手のマインド:
否定ではなく、批判する
受け手の判断:
批判の内容の良し悪しを客観的に判断できる
受け手のマインド:
自分の意見に固執しない
議論が良い決断を導くための前提条件
ここからは、個人的な考察です。
(この辺りも、理論や実験でソースを探したい)
関係性:相手の意見を受け入れることができる
お互いの関係性の問題。
そもそも、お互いを忌み嫌っていて、
「あいつのいうことは一つも聞けない!」と言うマインドであれば、
批判・異なる意見を建設的に用い、
良い決断を導くことはできないはず。
視点の差異:価値観・前提知識が異なるほど、異なる意見や批判は出やすい
同質な人間同士、長年の付き合いのある人間同士だと、視点が近いため、異なる意見が出にくいはず。
(意見を戦わせなくていいので、決断に至る速度が上がるというメリットはある)
話し手のマインド:否定ではなく、批判する
話し手のマインドの問題。
客観的な視点無しに、「それは違う」と言わない。
攻撃的な口調は避ける。
人ではなく、コトに向かうという意識。
相手の意見を批判することはどうしてもネガティブに聞こえがちなので、「より良い結果を導くために」という前提を共有し、話し相手ではなく「議論の対象物」に発言を向ける
受け手の判断:批判の内容の良し悪しを客観的に判断できる
受け手の能力的な問題。
複数の選択肢が並んだ時に、メリデメを整理して、適切と思われる選択肢を選択できるか?
認知バイアスに左右されない。
受け手のマインド:自分の意見に固執しない
受け手のマインドな問題。
「良い決断を導く」という目的よりも、
「自分の意見を通したい」という、別の目的を優先してしまうなど。
「自分の意見が通らないと負け」「自分の意見が採用されない=自分の否定された」等、無意識的に考えている人は、一定数いる。
議論が良い決断を導くためにはどうすればいいか?
「前提条件」を打ち消すようなジャブがあれば良い。
例えばこんな感じ↓
人間関係を修復する
前提をシェアする
「この議論は、○○をより良くするためのものである」
「そのために、忌憚なき意見を言おう」
主語を「私は~と思う」にする
判断をしやすいように整理しながら議論する
意見のうち、かぶる部分と異なる部分はどこか?
意見の異なる部分に着目した時、メリデメはそれぞれ何か?
まとめ
異なる視点から「提案を批判」し、客観的に良し悪しを判断する過程を通して、最終的な決断の質が上がる(建設的相互作用)
そのためには前提条件を満たす必要がありそう。
過去の学問の蓄積は偉大。
みんなちがってみんないい。違いをたのしもう
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
