
書籍からみる、「社会起業家」と「政策起業家」
「社会課題の解決」という共通目標に向け、アクションする「社会起業家」と「政策起業家」。それぞれの主体に係る書籍から、理解を深めていこうと思います。
*「社会起業家」は「東北」に絞って見ていきます。
1. 書籍からみる、「社会起業家」
1-1. 社会起業家 #01 | 東北圏社会経済白書
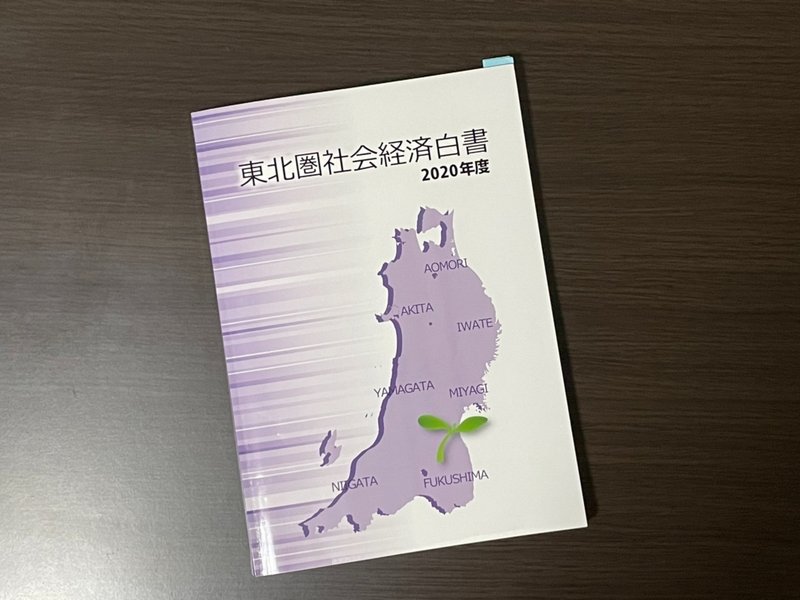
[概 要]
東北圏の社会経済の現状を定量的かつ定期的に把握することを目的に発行されている冊子です。公益財団法人 東北活性化研究センターが2013年から毎年発行していて、今年度は、「社会起業家」をテーマに据え、先進事例調査・アンケート調査などから、「社会起業家」を取り巻く課題と解決方策や行政&支援機関に向けた支援者に求められる施策提言がされています。
[pickup!]
東北圏の社会起業家へのアンケート結果(有効回答数:101件)から、社会起業家の実態をpickup!
<社会起業家の属性・特性に係る設問>
Q 設立者の設立当時の年齢
⇨「60代」「50代」が28.7%で最多。「40代」が14.9%。「30代」が13.9%。「20代以下」は5.9%。
Q 設立者の前職
⇨「会社員・公務員(管理職)」が25.7%で最多。以下、「自営業」20.8%、「会社役員」15.8%、「会社員・公務員(管理職以外)」12.9%。「学生」は2.0%。
Q 設立者の関連事業への従事経験
⇨「ある」が50.5%、「ない」が47.5%。
Q 設立者が設立に関心を持ったきっかけ(複数回答可)
⇨「社会への問題意識を持つきっかけがあった」が最多で64.4%。
<社会起業家が展開する事業の現状>
Q 主な事業の経営状況(複数回答可)
⇨「社会課題の解決に直結し、黒字・収益均衡」が最多で84.2%(85事業)。「社会課題の解決に直結するが赤字」が70.3%(71事業)。
Q 社会インパクト評価指標の保持
⇨「持っておらず、評価していない」が最多で45.5%。「どちらともいえない/わからない」が43.6%。「持っており、評価している」が8.9%。
[詳 細]
発行:公益財団法人 東北活性化研究センター(2021年3月発行)
URL:https://www.kasseiken.jp/kassecms/wp-content/uploads/2021/04/02fy-01-00.pdf
1-2. 社会起業家 #02 | SOCIAL ENTREPRENEURS IMPACT REPORT in TOHOKU

[概 要]
東北の社会起業家計32名を対象としたアンケートおよびインタビュー調査を行い、東北の社会起業家たちの取り組みやこれまでの事業を通じたインパクトに関してまとめた東北初の調査報告レポートです。
調査対象となった社会起業家は、一般社団法人 IMPACT Foundation Japanと仙台市が2017年から実施する社会起業家育成プログラム(0⇨1支援のプログラム)卒業生48者のうち22者(以下、「社会起業家育成プログラム卒業生」)と、一般社団法人 IMPACT Foundation Japanが連携・協業などの形で関係を持ってきた東北の社会起業家10者(以下、「連携・協業等、社会起業家」)という構成です。
[pickup!]
東北の社会起業家32者の活動実績をpickup!
Q 活動歴(開業してからの期間平均)
⇨「社会起業家育成プログラム卒業生」で4.5年。「連携・協業等、社会起業家」で8.9年。
Q 年間予算(1年間の活動予算)
⇨「社会起業家育成プログラム卒業生」で5.1億円。「連携・協業等、社会起業家」で3.9億円。
Q 総資金調達額(設立から現在までの総資金調達額)
⇨「社会起業家育成プログラム卒業生」では、「補助金・助成金」が9億円、「民間資本(投融資・クラウドファンディングなど)」が4.3億円、「自己資金(事業収入など)」が0.7億円。
⇨「連携・協業等、社会起業家」では、「補助金・助成金」が6.7億円、「民間資本(投融資・クラウドファンディングなど)」が1.7億円、「自己資金(事業収入など)」が9.9億円。
Q 事業に参画する仲間
*従業員、ボランティア、プロボノなどとして事業に関わる人の数。
⇨「社会起業家育成プログラム卒業生」で921人。「連携・協業等、社会起業家」で10,251人。
[詳 細]
発行:一般社団法人 IMPACT Foundation Japan(2022年3月発行)
URL:https://intilaq.jp/wp-content/uploads/2022/05/ImpactReport2022.pdf
1-3. 書籍からみる、「社会起業家」=まとめ=
「東北圏社会経済白書」と「SOCIAL ENTREPRENEURS IMPACT REPORT in TOHOKU」の2冊の書籍から東北の社会起業家の姿を読み解いてきました。
「東北圏社会経済白書」からは、社会起業家の人物像と社会起業家が取り組む事業の現状が見えてきました。社会起業家の人物像として、浮かび上がってきたのは下記のような姿です。
社会への問題意識を持つきっかけから、
起業を選択した50代・60代の元会社員・公務員(管理職)
*必ずしも、起業する事業のプロフェッショナルであるとは限らない。
この人物像から言えることは、最初から社会課題解決に取り組もうと思っていたというより、様々な社会経験をつむ中で、地域・社会の問題に触れる・直面する、きっかけがあり、それが契機となり、地域のため、社会のためと1歩踏み出してきたということです。
そして、彼らが取り組む事業の現状としては、多数の事業では収益性のある事業展開ができている反面、収益性の面で課題を抱える事業も相当数存在していること。また、社会課題の解決に向けて動いてきているものの、その社会課題をどれくらい解決できているかといった"ものさし"を持っている社会起業家はほとんどいないことが窺えました。
社会起業家が行うビジネスでは、一般的なビジネスと異なり、「受益者=お金の出し手」とは限りません。そうした中で、ビジネスモデルを構築していくことの難しさがあり、寄付やサポーター制度などの形で調達をしていくことが一つの形として考えられるわけですが、そのためには、取り組みがどのように社会課題を解決していくのかという社会インパクト評価の"ものさし"を作る必要があります。しかし、この評価の点でも単純な売り上げ・利益で測れないゆえの難しさがあるといえます。
このような難しさがありつつも、東北の社会起業家の取り組みは徐々に広がりを見せ始めてきているということが、「SOCIAL ENTREPRENEURS IMPACT REPORT in TOHOKU」から見えてきました。
それは、32者の社会起業家が、9億円もの年間予算を持ち、32.3億円もの金額を市場から調達をしているということです。そして、彼らの事業に関わる11,172人の仲間たちがいるということです。
東北では、震災以降、多くの社会起業家が誕生し各地で活躍をしていることから、より大きなインパクトが社会起業家の活動から生まれていることは自明であるといえるはずです。
社会課題解決は、しっかり持続性を持つ事業として成り立たせていくことができる可能性があり、社会課題解決に取り組む「社会起業家」が生まれ育つエコシステムが生まれつつあるのだと。
2. 書籍からみる、「政策起業家」
2-1. 政策起業家 #01 | 政策起業家が社会を変える -ソーシャルイノベーションの新たな担い手-

[概 要]
マイケル・ミントロム著の「政策起業家」論議に関する理論本。
政策起業家とは、ビジネスでは解決できない多様な社会課題を解決するための公共政策を実現させ、社会変革を促進させる人々のことである。本書は、約30年にわたり研究している著者が、世界各地の事例を踏まえて、政策起業家が採るべき戦略・活動しやすい環境・成果などを解説したものである。また、実際に岩手県陸前高田市を中心に政策起業家として活動している訳者の事例も、本書の理論に基づき紹介。今後の持続可能な社会を築くために政策決定プロセスを考える上で有用な1冊。
[pickup!]
公共政策領域において1980年代から世界で議論が始まってきた「政策起業家」。
著者は、その特性として、信念・社会感受性・信頼性・社交性・粘り強さを挙げた。また、その行動として、戦略的思考・問題のフレーミング・チームビルディング・ネットワークの活用と拡大・アドボカシーグループとの協働・実現可能性の明示・変革プロセスのスケールアップを挙げた。
ここでは、2000年代から議論が始まった日本における「政策起業家」をめぐる動向をpickup!
・「政策起業力」を「公共政策のあり方を適切な情報とデータに基づいて検証、分析し、新しいアイディアと政策を探究し、それを実現するため、多種多様な利害関心層を巻き込みながら社会を世界に及ぼす影響力」と定義。(船橋(2019))
・「新しい技術を社会に普及させることが求められている今の日本に必要なのは、テクノロジーのイノベーションではなく、社会の変え方のイノベーションではないか。」(馬場(2021))
・「ゼロを1にすることが社会起業、1から10への規模拡大の際に必要とされる力が政策起業力。」と位置付け。(馬場(2021))
[詳 細]
著者:マイケル・ミントロム
訳者:石田祐、三井俊介
発行:2022年3月
2-2. 政策起業家 #02 | 政策起業家 ー「普通のあなた」が社会のルールを変える方法
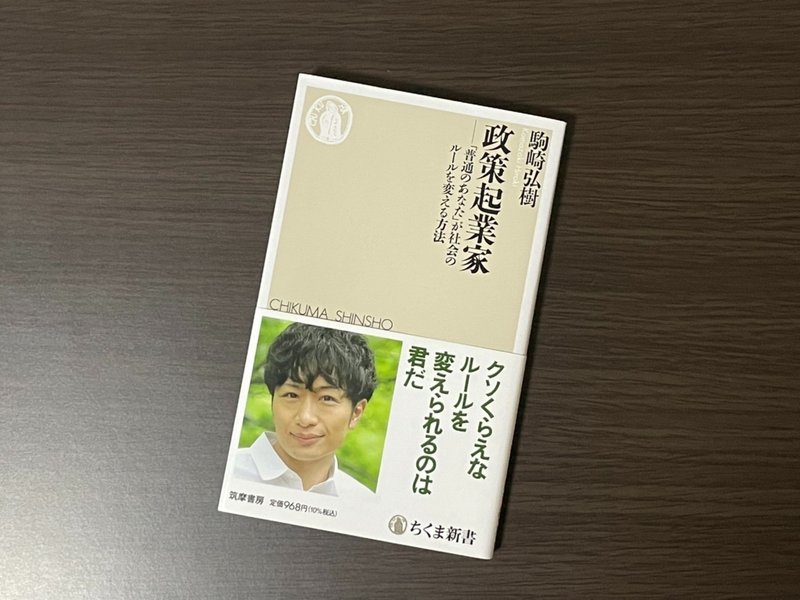
[概 要]
自身も政策起業家であるNPO法人フローレンス代表理事駒崎弘樹著の「政策起業家」としての実践本。
「政策起業家」とは、民の立場で社会のルールや制度を変え、時には新たな法律まで作ることができる人だ。人口減少の日本社会は既存のルールを変える必要があるが、今の官僚や政治家にはできていない。著者は「フローレンスの病児保育」「おうち保育園」「障害児保育園ヘレン」などを次々に立ち上げ社会を変えてきた。その悪戦苦闘ぶりをオープンにし、これまで政官に閉じていたルールメイキングを「普通の人」ができるようになる社会にしていきたい。
[pickup!]
著者の実践の中で見えてきた、政策起業家が行う社会変革(ルールメイキング)の流れをpickup!
Step1:現場にて、「問題(ミクロ)」を発見
Step2:「問題(ミクロ)」を「構造(マクロ)」へと昇華
Step3:「構造(マクロ)」と「打ち手」を持ち行政セクターへ接触&議論
Step4:「政策」として実装
Step5:結果の検証+改善
<参考:溺れる赤ん坊のメタファー>
社会運動に取り組む者が知っておくべき寓話がある。「溺れる赤ん坊のメタファー」である。
それはこんな話だ。
あなたは旅人だ。旅の途中、川に通りかかると、赤ん坊が溺れているのを発見する。あなたは急いで川に飛び込み、必死の思いで赤ん坊を助け出し、岸に戻る。
安心してうろろを振り返ると、なんと、赤ん坊がもう一人、川で溺れている。急いでその赤ん坊も助け出すと、さらに川の向こうで赤ん坊が溺れている。
そのうちあなたは、目の前で溺れている赤ん坊を助け出すことに忙しくなり、川の上流で、一人の男が赤ん坊を次々と川に投げ込んでいることには、まったく気づかない。
これは「問題」と「構造」の関係を示した寓話だ。問題はつねに、それを生み出す構造がある、そして、その構造に着手しなければ、真に社会問題を解決することはできないのだ。
[詳 細]
著者:駒崎弘樹
発行:2022年1月
2-3. 書籍からみる、「政策起業家」=まとめ=
「政策起業家が社会を変える -ソーシャルイノベーションの新たな担い手」と「政策起業家 ー「普通のあなた」が社会のルールを変える方法」の2冊の書籍から東北の政策起業家の姿を読み解いてきました。
「政策起業家が社会を変える -ソーシャルイノベーションの新たな担い手」からは、公共政策領域における議論の中で「政策起業家」という主体が定義づけされ、日本でも2000年代になり議論が進んできたという「政策起業家」に係る議論の潮流が窺えました。
ただ、ここでいえることは、「議論がなされていない≠政策起業家は存在しない」ということです。地方議会の開設に向けた活動等を行った福沢諭吉や国民健康保険制度成立に向けた活動等を行った賀川豊彦などまさに政策起業家といえる存在は過去にも多くいたというわけです。
そして、もう1点。「政策起業家」と定義される主体は、「社会起業家」と定義される主体のvisionによっては目指すべき立ち位置であると考えられます。すなわち、社会課題というものは特定地域の特定課題だけではなく、日本全国における課題である(+現行法制において障壁が存在している)というケースも多く存在します。小規模なモデルとして確立できたものを横展開し社会的インパクトを拡大していくための政策化。現行法制においての障壁をなくすための政策化。「社会起業家」⇨「政策起業家」というアプローチは1つの可能性としてあり得る話だと思います。
「政策起業家 ー「普通のあなた」が社会のルールを変える方法」からは、数々の実践の中から、政策起業家が行う社会変革(ルールメイキング)の流れが見えてきました。
Step1:現場にて、「問題(ミクロ)」を発見
Step2:「問題(ミクロ)」を「構造(マクロ)」へと昇華
Step3:「構造(マクロ)」と「打ち手」を持ち行政セクターへ接触&議論
Step4:「政策」として実装
Step5:結果の検証+改善
上記のStepをより具体的に記載していくと、下記のような流れとなります。
自身が当事者として、もしくは当事者に関わる中で、「◯◯さんが◯◯という問題を抱えている。」というミクロな視点での「問題」に出会う。
その「問題」を深めていくと「日本において◯◯という課題は1つの社会課題であり、それは◯◯という構造にて生じている。」とよりマクロな視点で「問題」を「構造」として捉える。
「構造」の中から課題解決に繋がるセンターピンを見出し、「打ち手」を検討する(ケースによっては小さく実践を始める社会起業家的アプローチをとる。)。
そして、「構造」と「打ち手」を持ち行政セクターに接触、議論を通じ政策として実装をしていく。
政策として実装された後も、結果の検証&改善を継続して行っていく。
政策を変えるのは、役場や政治家だけではなく、「社会課題解決のため有効な打ち手を横展開する」「社会課題解決のため障壁となる政策を改善する」この2点において当事者意識を持ち行動し、実際に社会変革を行っていく主体としての「政策起業家」が存在しており、ただ定義としてあるわけではなく実際に社会を動かす萌芽が出始めているのだと。
3. 書籍からみる、「社会起業家」と「政策起業家」
4冊の書籍から、「社会起業家」と「政策起業家」の存在を読み解いてきました。
ここから見えてきたことは、「社会起業家」と「政策起業家」は異なる主体であるように見えながらもAかつBの領域があることです。さらには、地域・社会の課題解決に向けてのアプローチは、必ずしも、行政・政治が担うものではなく、「普通のあなた」が、「社会起業家」と「政策起業家」として、もしくは彼らを支えるサポーターとして担う可能性が大いにあるのだということです。
*メインバナーは、<a href='https://jp.freepik.com/vectors/school'>Macrovector - jp.freepik.com によって作成された school ベクトル</a>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
