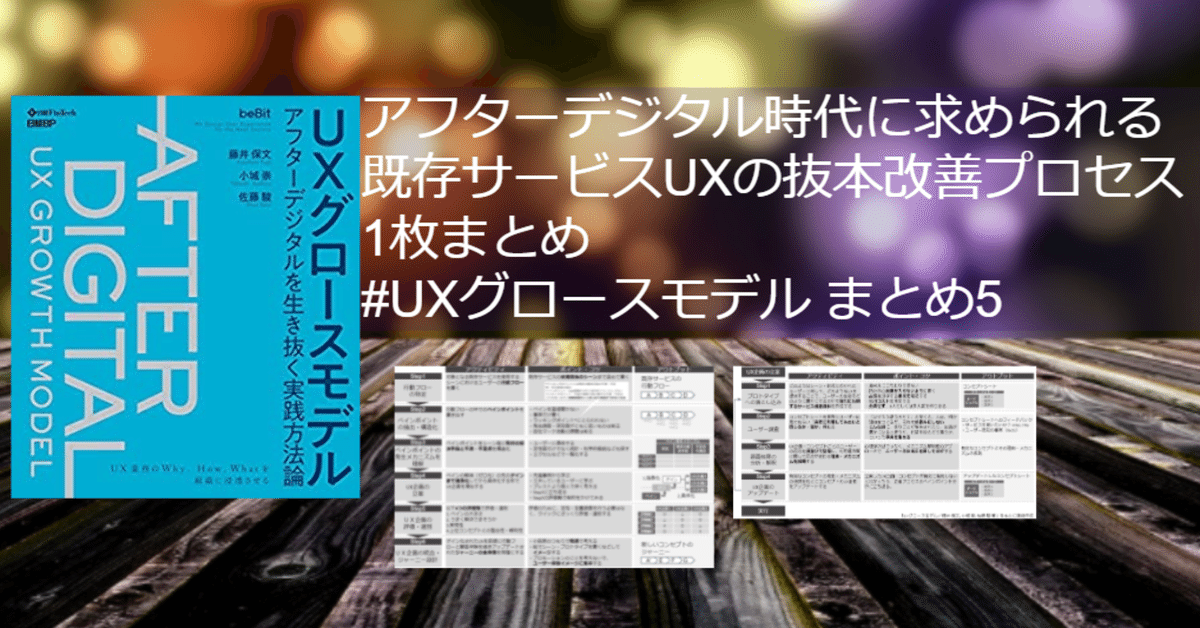
アフターデジタル時代に求められる既存サービスUXの抜本改善プロセス 1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ5
アフターデジタルの第3弾「UXグロースモデル アフターデジタルを生き抜く実践方法論」が2021年9月16日に発売となりました。本書では、UX(ユーザーエクスペリエンス)企画の秘伝である、方法論、プロセス、その裏にある考え方を詳説するといいます。今回は本書の「第4章 ボトムアップ型UXグロースの方法論1/2(既存サービスの抜本改善)」についての学びをまとめます。
本書の構成
「UXグロースモデル」の章立ては以下のようになっています。今回の記事は、★のところとなります。
はじめに
→UX型DXでのUXの定義とは #UXグロースモデル まとめ1
第1章 アフターデジタル時代に求められるバリュージャーニー型への転換
→1枚まとめ #UXグロースモデル まとめ2
第2章 UXグロースモデルの概要
→アフターデジタル時代に求められるUXグロースモデルの全体像まとめ3
第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)
アフターデジタル時代に求められるメカニズム解明型ユーザー理解 #UXグロースモデル 1枚まとめ4
★第4章 ボトムアップ型UXグロースの方法論1/2(既存サービスの抜本改善)
第5章 ボトムアップ型UXグロースの方法論2/2(既存サービスの高速改善)
第6章 トップダウン型UXグロースの方法論1/2(事業変革の推進)
第7章 トップダウン型UXグロースの方法論2/2(全社変革の推進)
第1章のまとめ
第1章:アフターデジタル時代に求められるバリュージャーニー型への転換顧客の成功をバリューチェーン横断で支援するプラットフォーマーと価値要素特化の機能提供者にプレーヤーが分かれる。競争力の源泉は顧客成功を継続支援する中でLTVを高めるビジネスモデルへ移行。その実現には使用価値を運用・成長・進化させるグロースチームの構築が経営に求められる。
第2章 UXグロースモデルの概要
UXグロースモデルとは中長期×経営目線のトップダウン型と、既存サービス改善のボトムアップ型のUXグロース活動の相互連携でバリュージャーニーを成長・進化させ企業変革を推進すること。2つの型では目指すゴール、ケイパビリティが異なるため組織・チームを分ける一方で、人材交流・ローテなど連携・循環を促すことで互いの創造性を尊重し高めあう文化を作ることが重要
第3章 人間心理の探求から、メカニズムの解明へ(ユーザー理解を再定義する)のまとめ
ユーザーの行動が、その人の性格や価値観などの深層心理から選択されるという心理探求型ユーザー理解のアプローチは、インサイト獲得の主観依存とUX企画化を複雑にする課題がある。UXの改善・進化にはユーザーが行動を起こすメカニズムを解明しようとする以下のアプローチが有効
メカニズム解明型のユーザー理解のアプローチ
1. ユーザーが目指す成功を確認する
2. 成功に至るまでの行動フローを特定する
3. 一連の行動フローにおけるペインポイントを抽出する
4. ペインポイントの発生メカニズムを解明する
第4章 ボトムアップ型UXグロースの方法論1/2(既存サービスの抜本改善)
第2章で、UXを進化・改善していくUXグロースモデルのアプローチには、トップダウン型とボトムアップ型があると述べられました。さらにこのボトムアップ型は、「高速改善UX企画チーム」と「抜本改善UX企画チーム」に分けるのが良いというのが本書の提案でした。

この第4章では、ボトムアップ型の抜本改善企画チームでおぼこなうUXグロースの方法論を学びます。本章の考え方が他のUXグロースにおいても基礎になるとのことです。
構成は以下の3つのパートに分かれています。
4章の構成
1. 既存サービスを抜本改善するUX企画立案の6ステップ
2. 既存サービスを抜本改善するUX企画の検証・緻密化の4ステップ
3. 抜本改善UX企画チームの運用
1.既存サービスを抜本改善するUX企画立案の6Step
ページ数はそんなにないのですが、まとめてみたら、アクティビティ、ポイント、アウトプット、ということで、プロセスの構造をとっていて、中身が意外と詰まってました。まず、プロセスは以下の6ステップです。

既存サービスを抜本改善するUX企画立案の6Stepの1枚まとめ
6ステップのプロセスを一枚にまとめると以下のようになります。

デザイン思考のアプローチで、カスタマージャーニー(UXマップという人もいますかね?)を書きながら新事業開発をされたことがある方には、なじみのある流れなのではないでしょうか?
個人的に、「あぁ、なるほどな!」と思ったポイントは2つです。
なるほどポイント1:ラッキングポイント

Step2のペインポイントの抽出のところで、ラッキングポイントにとらわれない、というTipsが紹介されています。現状の解決手段の不満・不足のことをラッキングポイントと呼称しています。こうやって、概念に名前を付けるのっていいですね。以下のような例が挙げられています。
例:住宅検索の場合
・ペインポイント:Web情報だけだと室内がイメージしづらい
・ラッキングポイント:写真や間取り図に関する不満・不足点
このペインポイントとラッキングポイントが玉石混交になっていて、ジャーニーマップの粒度感がぐちゃぐちゃでわけわからなくなって、フォーカスが定まらなくなって迷走した経験があるので、これは「なるほど!」感がありまくりでした。
なるほどポイント2:ゲインまで抽象化
バリュー・プロポジション・デザインを読んだことがある方は、Value Proposition Canvasを使って顧客価値について検討する際、Gainの書き方が難しい、と思った経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
私なんかは、Painの裏返しで、Gainを考えるというのは、結局、Painに引っ張られてその延長線上のアイデアしかでないので、悪手ととらえていました。なので、本書の提案する、Zeroまでもっていった上で、抽象化するというのは本当に有効なのかなぁ、とちょっと疑問を持っています。
おそらく、実際の運用上は、Step6の、あるべき全体のジャーニーを考えるフェーズで、Gainが想像できるようになるんじゃないかな、と思いました。
2. 既存サービスを抜本改善するUX企画の検証・緻密化の4Step
検証・緻密化の4ステップは以下のようになります。

4ステップのプロセスを一枚にまとめると以下のようになります。

なるほどポイント1:コンセプトシート

私は、FORTH Innovation Method(以下、FORTH)というイノベーション創出手法の認定ファシリテーターなのですが、その手法の中でも、ユーザーにコンセプトをクイックにぶつけることが重視されています。
そして、その際に、ユーザーの解釈が入りづらくするというのも重要視されています。FORTHでは、ビジュアルも入れないで、純粋にテキストのみのコンセプトシートが推奨されています。
なぜなら、通常、複数のコンセプトが検証されます。このとき作り手も複数になり、作り手によって、ビジュアルの良し悪しも入ってくると、顧客の反応に影響が生じてしまうからです。
なるほどポイント2:Factに忠実に

Step2のユーザー調査のところで、事実に着目することが書かれています。これが当たり前なのですが難しいところです。「なぜ」と聞いて、答えてくれたことは事実かもしれませんが、ユーザーが聞かれたからでっち上げた理由は、事実であって事実ではないというのが、むずかしさです。
本書の第4章のプロセスの中では、コンセプトシートを使ったクイックな検証を推奨していて、もしかしたら以降の章では、別の検証方法が紹介される中で出てくるのかもしれませんが、理想は、本当のユーザーの行動データが獲得できれば一番「事実」に近いです。
「NO FLOP!」という本が、まだないサービスを、ユーザーが本当に利用するのか、実際の行動データを獲得するためのアイデアがてんこ盛りで超おすすめです。
3. 抜本改善UX企画チームの運用

抜本的なUX企画チームは、抜本的というくらいなので、定常的に走らせるには、システム開発側の負荷が大きくなります。そのため、半年~1年くらいのサイクルで実施する方がよいケースもあるとします。
一方で、こういった抜本的UX改善ができる人材の育成は超重要なため、複数サービスの抜本的UX改善企画のタイミングをずらして、チームに定常的に抜本的UX改善の業務があるようにすることを提案しています。それが難しい場合は、第5章で紹介される、「高速改善UX企画チーム」の業務と合流するということになります。
おわりに
今回は、第3章までにはつけてきた、テキストベースでのまとめは割愛します。
DXについての記事は以下の「マガジン」にストックしてますので、併せて覗いてみてください。フォローや「スキ」を押してもらえると励みになります。また、まとめのスライドデータが欲しい方がいらっしゃいましたら、Twitter: shinojackieをフォローの上、DMいただけましたら幸いです。
ということで「形のあるアウトプットを出す、を習慣化する」を目標に更新していきます。よろしくお願いします。
しのジャッキーでした。
Twitter: shinojackie
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
