
好感デザインが当落を決める
(株)視覚デザイン研究所の所長・内田です。
常識では信じられませんが、脳は見た目(デザイン)で行動を決めています(B.リベット、1980年初期)。実際、好感された選挙ポスターは毎回80%以上が当選しています。視覚スケールを使うとデザインの好感度が測れ、使えるデザインができました。
脳・扁桃体。辺縁系の最奥にあり、意識下、本能といわれる感情(情動)を生む。
好感・扁桃体は3感(共感、美感、安心感)を統合して〈好感、嫌感〉を判定し行動を決める(クリューヴァー・ビューシー症候群)
視覚スケール・色や形は全てスケール形になっていて意識下の感情を伝える。ジャンプ率や版面率、色量など50種。1987年当室発表。
好感は測れる・新皮質の影響を避けた視覚スケール式アンケート法。3感の内容が読み取れるため、客観的デザインが成立した。

当選者のポスターはどれ?

上図は2022年7月10日に行われた参議院選挙、東京区のポスターです。この中の3点が当選者のポスターです。どれがそのポスターでしょうか。
初めて見ただけで分からないと思うかもしれません。
実際は好感度の高いポスターの人ほど当選しています。
人は行動する前に考えて決めると思われてきましたが、大半は考えないで好き嫌いで決めていることが脳の実験で分かりました。

第1部 好感が当選を決める
アンケートと点数表レシピを使ってポスターの好感度をA〜Eの5段階に分け、次にその好感度別に当選率を集計してみました。その結果、好感度Aの3点は全員が当選し、Bは25%、Cは11%でDEは0%でした。
脳が好感すると好感行動が起き、デザインの好感度と当選が直結していることが分かります。


結果
好感Aポスターは100%が当選
21年衆議院選挙の結果も比べてみましたが同じ傾向でした。



選挙ポスターの絶対必要な条件は①笑顔②力強さ③すっきり誠実 です。どれが欠けても投票したい気持ちになりません。
これはポスターデザインの条件ですが現実の政治家にも同じ条件が求められています。①決してえらぶらず②しかも私たちを導いてくれる強いリーダーシップを持ち③誠実でクリア。裏で怪しげなことをすると法律に違反していなくても脳が怒り出します。
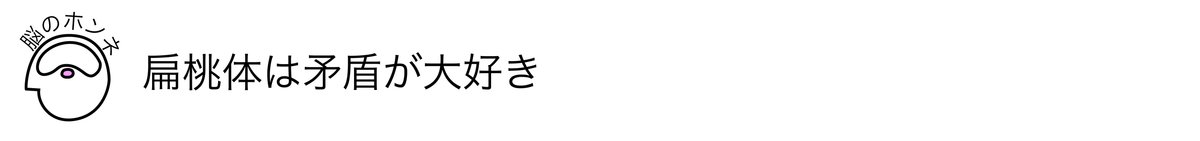
政治家には有権者の声に耳を傾ける親切な人が求められます。一方で力強さも求められ、欠けると頼りにならない人と嫌われます。
そこで、表情を力強くすると今度は威圧的な人と感じ不快になります。このため笑顔で親切さを表し氏名文字は太く大きくして力強さを表します。矛盾した条件でも画像と文字を使い分けて脳を好感させます。
私たちは、矛盾した主張を聞くと「矛盾しているではないか」と非難しますが、扁桃体は矛盾が大好きです。
第2部 好感Aデザインをつくる
好感Aデザインをつくる方法
好感D評価のポスターをA評価に変えてみましょう。
「好感のしくみ」が理解できれば好感Aデザインは迷うことなくつくれるようになります。
デザインの3要素、画像、文字、色を視覚スケールの最適値にします。
作例A
・画像を表情スケール6〜7にする
開放的で元気な笑顔が見る人の気持ちを安心させます。


・文字のジャンプ率を6〜7にする
力強い文字が候補者の力強さを感じさせ、見る人の共感が生まれます。

・色の強さを色量6〜7にする
明るく元気な配色を見て、積極的で前向きな気持ちになります。

完成
この3工程で好感Aのポスターができました。
これで当選率80%が見込めます。候補者の実際の選挙活動と重なって当選につながります。

作例B
・表情スケールを6〜7にする
女性候補者は男性に比べ少し優しめな笑顔6も適値ですが近年は少し強めな7に変わってきています。時代の反映でしょうか。


・文字のジャンプ率を6〜7にする
ジャンプ率に力強さが求められるのは男女で差がありません。

・色の強さを色量6〜7にする
新人らしさ、優しさはトーンを若干明るい色量6で表します。一方、実行力を訴えるには色量7にします。

完成
レシピの最適値に合わせて好感Aのポスターができました。デザインは脳のしくみと一致した客観3条件の揃った技術になりました。

第3部 好感を測る
視覚スケールで好感が測れます
好き嫌いの感情は本能ともいわれ、測れないとされていました。しかし下記のように測ると数値で読み取れることが分かります。
表情スケールで測る
顔を表情スケールに当てると、感情の強弱が整理でき数値化できます。個人差はありますが、多くの人はほぼ同じように感じています。

ジャンプ率スケールで測る
印刷物にジャンプ率スケールを当てて感情を読み取ります。静かに読みたい詩集は低いジャンプ率。熱狂したスポーツの結果をスポーツ紙の大ジャンプ率で見ると共感し、次も買いたくなります。
このように視覚スケールは感情を視覚化し、共感ゾーンをさぐり当てることができます。視覚スケールは感情を数値に変換するツールです。

アンケートで測る
好き嫌いは個人で異なりますが、多勢の好き嫌いを集計すると共通点があります。その共通した感情(共感)のお陰で私たちは安心な社会を築くことが出来るのです。感情は個人の感情と社会的な感情の組み合わせで生まれています。
アンケート結果から好感度を決める手順
結果を集計して好感度を5グループに大別します。


点数一覧表〈レシピ〉に集計する
アンケート結果が分かった各デザインに視覚スケールを当てるとそのデザインの形からどんな感情が生まれたのかが数値化して読み取れます。それを3感(共感、美観、安心感)に合わせて整理し、視覚スケールの一覧表に落とし込みます。更にアンケートを繰り返すと精度が高まり、一枚の点数一覧表(レシピ)が完成します。レシピが好感判定や好感デザインをつくる時の最終指示書になります。

3感とは…(共感、美観、安心感)
サルの扁桃体を切断した実験(クリューバー・ビューシー症候群)などから分かりました。
3感の全てが一致すると好感が生まれ行動が始まります。1感でも欠けると不快と感じ逃げ出します。
例えばサルも猫もヘビのような形を見ると逃げ出し、ヒトも同様です。
この時、ヘビそのものでなくヘビを連想させるだけで不快になります。つまり、私たちは実物ではなく抽象化、スケール化して感じています。
考える前に一瞬見ただけで行動し、本能ともいわれています。
表情を見た時に威圧を感じると多くの人は不安を抱き逃げ出したくなります。3感の安心感が欠けているからです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
準備が間に合わず前回の予告から予定を変更して申し訳ありません。
当室では、視覚スケールをより使いやすくする方法を開発中です。視覚スケールについて詳しい本や美術書も出版しています。
・デザイン書・美術書ストア

また研究の成果を生かして、子どもの感性を健康に育てるためのえほんを出版しています。
・えほんストア

視覚デザイン研究所のWEBサイトでは、選挙ポスターデザインと得票数の関係性や、良いデザインとベストセラーの関係性など、感性の数値化や視覚スケールでの実験を行っています。
また当室出版「レイアウト基礎講座」を再編集したレイアウト様式を決定づける8要素も無料公開しています。発行から年月を経ていますがレイアウトの基礎は不変ですので、ぜひご覧ください。
実験協力者募集
実験のテーマも募集中。読んでみたいテーマがありましたら教えてください。また、自信のある商品ができたら好感度Aデザインにして発売してみませんか?無償で協力させてください。
次回もお楽しみに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
