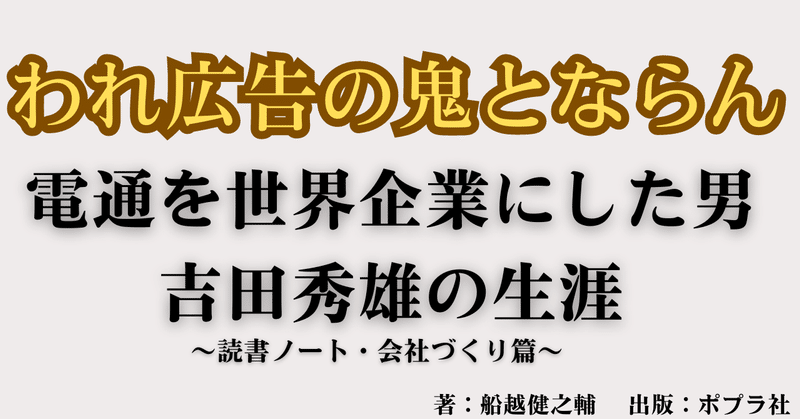
「われ広告の鬼とならん 電通を世界企業にした男・吉田秀雄の生涯」 (船越健之助)<読書ノート・会社づくり篇>
今日の大企業は、はじめから大企業だった訳ではありません。
大企業になっていった軌跡を紐解くと、それがそのまま壮大なドラマであったと感じます。
特に、戦後の灰の中から立ち上がって、大企業を作っていった物語は強烈で、戦後日本社会を作っていた人々の強靭な意志、生き抜く力強さを感じざるを得ません。
電通は国内最大、世界でも屈指の広告代理店ですが、その電通の中興の祖と呼ばれるのが四代目社長、広告の鬼、吉田秀雄氏です。
こちらの本はその吉田氏の生涯を詳細に記録したものです。
読んでいくと、吉田秀雄のその無尽蔵とも思える凄まじいエネルギー、巨大なスケール、どんなピンチでもブルドーザーの如く突き進む推進力に圧倒されるばかりでした。まさに鬼十則をそのまま体現したかのような人物です。
広告ビジネスに携わる人はもちろん、まったく別の仕事をしている人も含めて、力強く生きたい人にとって何かヒントになるかもしれません。
全体で500ページを超える分量ですので、いくつかの記事に分けて、読書ノートを作成したいと思います。
まず今回は、「会社づくり篇」と題して、人材集めと人材教育の様子に焦点を当ててみたいと思います。
※広告ビジネスの出発から発展の歴史の視点から構成した「広告ビジネスの歴史篇」はこちらでございます。
※吉田秀雄の無類のバイタリティに焦点を当てて構成した、「その働き方篇」はこちらでございます。
戦中から見据えた戦後
戦争中から、吉田は既に戦後を見据えて、希望を見出していました。部下の田村が、広告業はもう仕事がなくなると思い電通を辞めようと思っていると吉田に告げたところこんなコメントが返ってきました。
「きみは一体、この戦争がいつまで続くと思っているんだ。いま辞めていかん。戦争は間もなく終わるぞ。広告の仕事は忙しくなるから、いまにうつにミッチリ勉強しとけ。(後略)」
「戦争が間もなく終わる・・・。忙しくなる・・・」とはどういうことなのか、田村には理解できなかった。毎日のように空襲に遭いながら、アメリカに勝つことができるのであろうか。それでも敗戦になることなど、考えはまわらなかった。しかし吉田は、終戦を察知しているようであった。
p140
人材集め、人材発掘
吉田はまずは人材集めから精を出しました。終戦後350人だったのが、1949年には1,000人を超えるところまで増やしました。
しかも、広告に関してはずぶの素人も含めて集めたのです。
この人材たちを吉田は教育して立派な電通人を育てていったのです。
終戦後、三百五十人になっていた社員数は。昭和二十二年には六百五十五人に増え、二十三年には九百二人、二十四年にはついに一千人を超える社員数となったが、この凄まじさは何だったのだろう。(中略)
しかも社員といっても、新規卒業生とか、広告業経験者と言ったものではなかった。吉田の採用したのは、満鉄関係者、旧軍人、軍属といった、広告にはまったくの素人を次々に投入した。(中略)
戦後は社員急増で、しかも満鉄関係者が多いことで電通ビルは「第二満鉄ビル」と呼ばれていた。
第二満鉄ビルと呼ばれていた・・というところがなんとも昭和っぽいエピソードですね。。
公職追放者を採用。「旧友会」を作る
更に驚きなのが、吉田は次に公職から不適当な者として除外され、活動などを禁止された政治家、財界人、新聞人に声を掛けたのです。いわゆるGHQから公職追放されていた人物たちに目を付けたのです。
追放中なので解職と再就職禁止の処置があり、仕事に就くこともできないが、吉田はこの人たちをそのまま世間から隔離することに疑問を持ち、月一回集まってもらって食事をすることを考えた。食事をするくらいなのだから仕事ではない。昔の同窓会なのだ。
食事は米の配給制で主食は統制されているため、おおっぴらにはできない。昼に集まって、刺身、トンカツ、味噌汁などを電通隣の小料理屋一幸から取り寄せた。(中略)食糧難なのに、「電通にいけば、ただでビフテキが食べれる」と噂が立つほどであった。
うまい具合にルールの網目をくぐりぬけている感じや、「電通に行けばただでビフテキが食べれる」といった噂など、人々がたくましく生きようとしている昭和の空気感が伝わってきます。
早朝会議で社員教育、会社づくり
とにかく多様な人材を大量に確保した上で、集めた人材を吉田自ら徹底的に教育し、広告人を育てていきました。
朝食を済ませ、七時ニ十分頃に代々木大山の自宅を出て、八時に少し前に社に着く。他の首脳幹部も出社する。社員より三十分から六十分早い出社なのである。やがて全幹部が早朝出勤をするようになり、吉田が中心になって始めた早朝会議となった。当面する業務上のこと、広告の実務と理論の勉強会であった。吉田は社長と講師の二役を兼ねた。
(中略)
早朝会議のことを、吉田は「広告についてはずぶの素人を教育せねばならなかった」のだと言う。それだけに、吉田も実務と理論をアメリカから取り寄せ、翻訳させて学ばねばならなかった。
(中略)
吉田の考えは、会議を通じて幹部の教育をし、最高方針を徹底させ、社業全般に渡って計画性を高めることを狙った。人材確保した引揚者の中高年は、割合早く広告人として成長していった。そこにラジオ研究会も作られ、彼らの舞台があった。
まだ広告代理ビジネスが日本に確立されていなかった時代、吉田はマーケティング発祥の地であるアメリカから最先端の理論を取り入れて自らが勉強し、朝会議によって社員を教育していったようです。
みんなで一丸となって海外のビジネスを取り入れたり、会社を作っていこうとする雰囲気が、なんだか明治維新のようです。
言葉による社員教育、会社づくり
会社の進むべき方針、仕事に取り組むべき姿勢、そうした思想は言葉によってのみ、統制されると思います。
例えばアルバイトなどでも、スタッフが集まって心得みたいなものを復唱したりしていますよね。
吉田も、力強い言葉によって会社の統制を図りました。
吉田は幾つかの訓書をメモするようになった。日常職場で社員に語っている行動規範であるが、命令長は「武士の心構えに関する教え」の書である『葉隠』を連想させる戦闘訓であった。それは鬼十則と名付けられた。
阪急東宝グループの創業者・小林一三も、この鬼十則を知ると大変気に入って、吉田に「色紙かなにかに書いて、もらえないか?」と吉田に依頼したそうです。吉田から貰った鬼十則の写しを。小林は営業傘下の各会社に配布して、社内掲示をさせていたそうです。
その鬼十則の内容は以下のようなものです。
一、仕事は自ら創るべきで、与えられるべきでない。
一、仕事とは、先手先手と「働き掛け」て行くことで、受け身でやるものではない。
一、「大きな仕事」と取り組め。小さな仕事は己を小さくする。
(中略)
一、「周囲を引きずり回せ」、引きずるのと引きずられるのとでは、永い間に天地のひらきができる。
(中略)
一、「自信」を持て、自信がないから君の仕事には、迫力も粘りも、そして厚味すらがない。
一、頭は常に「全回転」、八方に気を配って、一分の隙もあってはならぬ。サービスとはそのようなものだ。
一、「摩擦を怖れるな」、摩擦は進歩の母、積極の肥料だ、でないと君は卑屈未練になる。
一部、過激な言葉もあり、たしかに今の時代にはそぐわない表現もあるかもしれません。
ただし、仕事に取り組む人にとって、力を与えてくれる部分があることもたしかだと思います。
なんでこれほどまでに胸に響くのか・・・ずっと疑問でしたが、とても面白いことが書いてありました。
吉田は漢詩が好きだったようなのです。
だから漢詩の歯切れの良さ、明解さが表れているとのことです。
この点は大変興味深かったです。
というのも、三島由紀夫がインタビューの中で、漢詩の素養が文体に影響を与えるという趣旨のことを述べていたのを私が最近読んだからです。
本旨とは逸れますが、言葉の美しさ、音の調子などの研究の観点から漢詩を勉強してみたいなと思いました。
新入社員を帝国ホテルのレストランへ連れて行く
新入社員の教育も都市伝説のようなザ・昭和のエピソードで度肝を抜かしました。吉田は秘書の小野に、新入社員を帝国ホテルのレストランへ連れて行かせました。
毎年、新入社員が入ってくると、小野は吉田の指示で帝国ホテルのレストランに連れて行く。お祝いということもあるが、吉田の考えは違った。「一流のもののところに出て、一流のものを食べさせろ。そしたら、一流のところに行っても驚かない。まわりにおどおどしていては、仕事は出来るものではない。お得意さんの広告部内でも仕事はするな。重役室に行って、仕事をしろ。気おくれしては、仕事はできない。そんなものはなれている、という気持ちでなければならない。何でもそうだが、日頃の訓練をしておかなければならない。」
食べ物に飢えている時代であったが、「帝国ホテルでまな板みたいなビフテキを食べさせてやれ」と、食べ物に苦労した自分を思い描くのか、肉類をご馳走した。
たしかにこれは理にかなっていると感じました。
広告代理業は時にお得意先の広告宣伝部/マーケティング部はもちろん、社長や役員を相手にプレゼン、交渉等のコミュニケーションをとることになるはずです。
また、お得意先の商材が富裕層向けの商品であることもあるかと思います。
つまり、自分よりはるかに格上/目上の大物との折衝が必要だったり、お金持ちの生活を想像できなければならないのだと思います。
私のような小者だったら、帝国ホテルなんて、入るだけでドキドキ、ワクワクしてしまいます。
しかしそんな調子では大物や一流人を相手にできません。
プレゼント攻撃 吉田流コミュニケーション
吉田は時には部下を叱りすぎてしまうこともあったようです。
しかし彼は人情家であり、決して部下をないがしろにしている訳では全くありませんでした。
叱りすぎたな、と思う部下には吉田は自分のスーツや靴、ゴルフバッグなどを次から次へとプレゼントしたようです。
何よりも楽しみなのは、昼間叱りすぎた部下への贈り物であった。
その贈り物は、代々木、銀座の一流テーラーで仕立てた背広が大半である。サイズは吉田の体系にあわせてあるところに、吉田の思想があった。もらった者は、サイズを自分に合わせて仕立て直さねばならない。この金額がとても高額であるという人もいた。まったく袖を通していないものもあったが、多くは吉田が一度袖を通して試着したものである。その数はおよそ二百着が、整理棚に下がっていた。(中略)
背広のほかは、納戸一階に靴が約百足、ゴルフ用具が約五十セット壁際に並べられていた。どれも部下に贈るものである。彼なりのコミュニケーションであった。しかし靴のサイズを当てるのは難しいが、これは吉田に秘訣があるのか、ぴたりと当てていた。たまにサイズが合わないと。次々に持っていくという執拗さがあった。(中略)一度袖を通した背広を贈るのは。武将の形見物のようである。強い生命のようなつながりがあることを意味していた。「お前と俺の信義」であった。
令和では考えられないような、上司と部下の付き合い方かもしれません。
その是非はあるかもしれませんが、こうした人情深い付き合い方は個人的には好きです。
おわりに
戦後の灰の中から立ち上がって、戦後日本を作り上げた人々のエネルギーは凄まじいものがあります。いまの時代にそぐわないものもあるかとは思いますが、それでも学べるものがあるかと思います。
別篇として、違う視点から本書に関する読書ノートをつけてみたいと思います。
その働き方篇はこちらでございます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

