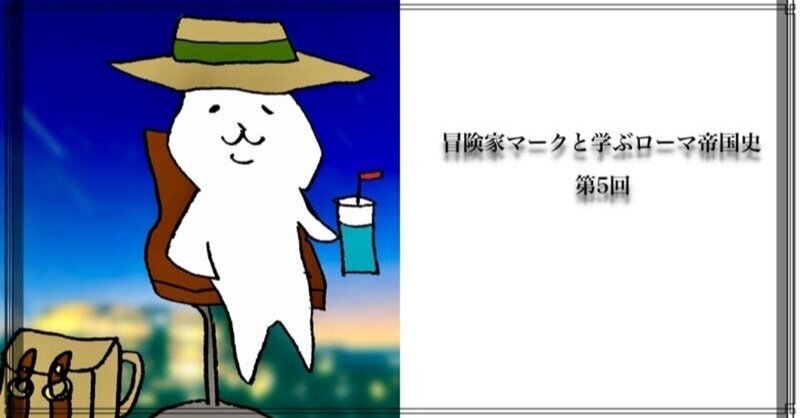
冒険家マークと学ぶローマ帝国史 第5回
さあ、今回でボクと学ぶローマ帝国史は、第5回目となる。前回はローマ・サビニ戦争の最中に登場したタルペイアというウェスタの巫女のお話だったね。ウェスタの巫女はローマではかなり優遇された身分で、劇場の最前列の席が用意されたり、引退後は年金で生涯生活には困らなかったり、周囲が羨む役職でもあったんだ。ただし、30年間の役職を全うするまでは、交際や結婚は一切許されないという制約もあったのだけれどね。そんな金銭的には全く困っていないタルペイアが、なぜローマを裏切りサビニに味方したのか?単に彼女が強欲だったという考えもできるが、実はタティウス王に恋していたという説もある。恋するがゆえに、ローマを裏切ってまでも敵方のサビニに味方したというのだ。そうであれば、とてもロマンチックではあるが、やはり最後は殺されてしまうことを考えると、何とも悲劇だね。

さて、それでは前回までのあらすじを見つつ、今回は続きのエピソードを紹介していくよ。ローマは偉大にして、永遠なり。そんな彼の軌跡を一緒に辿っていこう。
前回までのあらすじ
ローマ人によるサビニ人女性の誘拐事件。この事件を機にローマ・サビニ戦争が開始された。両者の戦力は互角といったところで、争いは長きに亘っていた。だが、ウェスタの巫女タルペイアの裏切りにより、ローマはサビニに城壁を突破される痛手を負った。タルペイアは作戦が成功したため、サビニの王ティトゥス・タティウスに報酬を求めた。だが、タティウス王と彼の部下はタルペイアに円盾を投げ、彼女を圧死させた。たとえ彼女が自分たちに味方し、有利になるように働いたとしても、裏切りを平気で行う邪な気持ちを持つ者は許さないという判断から下された結果だった。タルペイアの遺骸はとある丘に埋葬されたが、今ではそこがどこなのか、誰も知る由がない。タルペイアの一件の後も、ローマとサビニ間の争いは収まりを見せず、激しい抗争が繰り広げられていた。
タルペイアの一件の後も、ローマとサビニ間の争いは収まりを見せず、激しい抗争が繰り広げられていた。だが、誘拐されたサビニ人女性が入ることによって彼らの争いは突如終結した。彼女たちにとってこの戦争は、どちらにしても不幸を招くものだった。仮にローマが勝てば、彼女たちは自分たちの両親や兄弟を失い、仮にサビニが勝てば夫と子を失うことになったからである。そんな苦境に立たされた彼女たちの答えは、ローマとサビニの和平だった。こうして長き戦いの幕は、ローマに誘拐されたサビニの女性たちによって降ろされた。
その後、ローマとサビニは和平を結び、共存する方針となった。和平と共存の証として、ロムルスと共にサビニの王ティトゥス・タティウスがローマの王位を与えられ、共同統治を行う形となった。また、王位はローマ人とサビニ人が交互に継承していくこととなった。以下、ローマではロムルスを初代とし、全部で7人の王がその統治を行った。
和名:ロムルス
羅名:Romulus
在位:前753〜前717年
系統:ローマ人
解説:初代ローマ王。当初は弟レムスとローマを統治していたが、仲違いを起こして弟を殺害。単独統治開始後に、自ら王であることを宣言した。ローマ・サビニ戦争後は、ティトゥス・タティウスとの共同統治を開始する。最期は落雷によって行方不明または死亡したとされる。
和名:ヌマ・ポンピリウス
羅名:Numa Pompilius
在位:前717〜前673年
系統:サビニ人
解説:第2代ローマ王。ローマ一の賢王として知られる。統治中は一度も戦争を行わなかった。天より聖盾アンキリアを授かり、ユピテル神殿に奉納した。
聖盾アンキリア
冒険家マークが恵まれない子どもたちを救済するために回収を試みた秘宝。彼はアンキリアを英国の競売にかけて一攫千金を狙おうとしたが、ユピテルの怒りによる落雷とヌマ王の亡霊により諭され、回収を断念した。最終的にはジェシカが回収し、ゼロの座標に隠した。だが、彼女はアムラシュリング・オチデンタルの力で、いつでもアンキリアを呼び出すことができる。
詳細は下記。
マークの大冒険 古代ローマ編|アリウス・ロマエ ALIVS ROMAE
*マークの大冒険の聖盾アンキリアについての記述は実在の資料を元にしていますが、フィクションです。
和名:トゥッルス・ホスティリウス
羅名:Tullus Hostilius
在位:前673〜前641年
系統:ローマ人
解説:第3代ローマ王。父はローマ・サビニ戦争で活躍したローマの名将だった。ユピテルを召喚する儀式で不手際があり、落雷によって死亡したとされる。
和名:アンクス・マルキウス
羅名:Ancus Marcius
在位:前641〜前616年
系統:サビニ人
解説:第4代ローマ王。ヌマ・ポンピリウスの孫。賢王ヌマの孫ということもあり、期待されて王に指名された。ヌマ譲りの賢王で、ローマ初の水道橋を建設した。
和名:ルキウス・タルクィニウス・プリスクス
羅名:Lucius Tarqinius Priscus
別名:ルクモ
在位:前616〜前579年
系統:第5代ローマ王。コリント系ギリシア人(エトルリア人)
解説:父がコリント系ギリシア人で、純血のエトルリア人ではない。だが、先王アンクス・マルキウスは彼の才能を見抜いて自身の養子とし、王位を継承させた。
和名:セルウィウス・トゥッリウス
羅名:Servius Tullius
在位:前579〜前535年
系統:エトルリア人
解説:第6代ローマ王。奴隷階級出身。先王タルクィニウス・プリスクスを暗殺し、彼の娘を娶ることで王位を奪取した。出自が奴隷階級ゆえ民衆寄りの政治で平民からは支持されたが、貴族からは疎まれていた。
和名:ルキウス・タルクィニウス・スペルブス
羅名:Lucius Tarquinius Superbus
在位:前535〜前509年
系統:エトルリア人
解説:第7代ローマ王にして、王政ローマ最後の王。第5代ローマ王タルクィニウス・プリスクスの息子として誕生する。先王タルクィニウス・スペルブスを暗殺し、王位を強奪した。だが、初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルートゥスによってローマから追放される。これにより王政が終焉し、共和政が開始された。
戦争終結後、ローマとサビニは和平の証としてロムルスとサビニが共同統治を行う形を採ることとなった。この二王制は後のローマが執政官を2名置く原型になったとされるが、実際は逆で執政官が2名であることの理由付けと正当性を補強するために、ローマが当初は二王制だったという設定を作ったと解釈するのが定説である。尚、二王制という統治体制は既にエジプトやギリシアでも見られるもので、決して珍しいものでもなければ、ローマ起源でもない。
ローマの二王制が開始されるものの、共同統治5年目にタティウス王が儀式の際に暴徒によって殺害され、急死するという大事件が起こった。こうしてローマはまたロムルスによる単独統治となった。だが、その後ロムルスも落雷に当たって消息不明となる。彼が雷によって神格化され天に昇ったのか、死亡したのかは不明である。だが、実際のところは晩年は暴君化していたため、圧政に憤慨した元老院議員らによって暗殺され、遺骸をバラバラにされたという説もある。
ロムルスの死後、彼が後継者を指名せずに突如失踪したため、王位継承問題が生じた。そんな中、次の王はサビニ人から選んでほしいという声がサビニ側から上がった。彼らの声が汲み取られ、次の王にはヌマ・ポンピリウスというサビニ人の非常に有能な人物が選ばれた。彼は統治中に一度も戦争行わなかった王であり、ローマは束の間の平和を手にした。
ヌマの死後、次の王はローマ側から選出された。ローマとサビニで交互に王を選出するという取り決めが行われたのである。王位を継承したのは、軍人を父に持つトゥッルス・ホスティリウスというローマ人だった。そして、彼の死後はアンクス・マルキウスというサビニ人が王となった。彼はヌマ王の孫であり、祖父譲りの有能な統治者だった。アンクスには直系の男児がいたが、聡明な彼は血縁贔屓で後継者を指名することはなく、養子に取った血縁のないルキウス・タルクィニウス・プリスクスという人物を指名した。これは帝政期の五賢帝たちが採った王位継承政策と同様である。血縁よりも実力を重視することで、より良い統治に成功している。
「ルクモ」という別名でも呼ばれるルキウス・タルクィニウス・プリスクスはコリント系ギリシア人の父の下に生まれたが、その出自で苦労したことから自身をエトルリア人と主張していた。その後、ルクモは老衰で没する前にエトルリア人のセルウィウス・トゥッリウスという奴隷階級の人物に暗殺され、王位を簒奪されてしまった。だが、そんなセルウィウス・トゥッリウスも自分がしたことと同じように下克上され、ルキウス・タルクィニウス・スペルブスという同じエトルリア人に暗殺されて、その生涯を閉じた。
タルクィニウス王はエトルリアが得意とする土木工事を推奨し、灌漑事業を積極的に行った。だが、それによって酷使される民衆は王に対して次第に不満を抱くようになっていた。そんな中、タルクィニウスが王位から引きずり下ろされる決定的な出来事が起こった。彼の息子で三男のセクストゥス・タルクィニウスが貞節な人妻ルクレティアを陵辱したのである。ルクレティアは神に対して敬虔人物だったため、これを夫に対しての不貞にして神への冒涜と考え、自らの胸を突き刺して自害を図った。周囲はルクレティアの自殺を止めようとしたが、彼女は短剣を隠し持っており、突然の出来事で誰にも止めることができなかった。
ルクレティアの死に最も憤ったのは、彼女の近親にあたるルキウス・ユニウス・ブルートゥスだった。ブルートゥスは、ルクレティアの夫ルキウス・タルクィニウス・コッラティヌスと共に王族を追放するレジスタンス活動を介した。民衆を先導したブルートゥスらは王の屋敷に押しかけ、追放を命じた。こうしてローマから王という存在が消え去り、ブルートゥスはコッラティヌスと共に初代執政官(コンスル)に就任し、前509年ローマを共和国として統治する方針を打ち出した。
それでは、実際にルキウス・ユニウス・ブルートゥスが描かれたコインが残されているので見てみよう。

図柄表:リベルタス
図柄裏:初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルートゥス、護衛官、先導者
発行地:ローマ共和国ローマ市造幣所
発行年:前54年
発行者:マルクス・ユニウス・ブルートゥス
銘文表:LIBERTAS(自由)
銘文裏:BRVTVS(ブルートゥス)
額面:デナリウス
材質:銀
直径:19mm
重量:4.05g
分類:RC397, RRC433.1, RSCJunia31
前54年にマルクス・ユニウス・ブルートゥスが発行したデナリウス銀貨。カエサル暗殺メンバーの中核となったかのブルートゥスによって発行された一枚。彼は自身の先祖と自称していた初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルートゥスを貨幣の意匠に採用した。自らの血統の正当性をアピールするために、彼は末裔であることを自称していたが、実際のところ血縁関係はなさそうである。このローマの7人の王と同様、ルキウス・ユニウス・ブルートゥスも神話時代の人間であり、実在したかどうかも危ういからである。
この頃のブルートゥスはローマ政界の駆け出しであり、本貨は彼が貨幣発行三人委員を務めていた際に発行された。この役職はローマ政界にデビューしたばかりの青年たちが務める役職で、いわゆるキャリア組みの下積み時代の仕事だった。この頃、ブルートゥスはまだカエサルと敵対する前であり、二人の関係は互いに尊重し合う良好なものだった。だが、次第に二人は政治方針の違いで食い違うようになり、最後はカエサルがブルートゥス率いる暗殺メンバーに消されることとなる。

自由の女神リベルタスを描いている。ブルートゥスが好んだ神格であり、彼は自由を象徴する彼女の肖像を好んで用いた。リベルタス自身に特有の神話はないが、ローマの貨幣の上には頻繁に登場するメジャーな女神のひとつである。このように肖像画描かれることもあるが、全身像を写した姿でもよく表される。他の神格と容姿が被ることが多いため、誰が見ても彼女と分かるようにラテン文字で彼女の名が肖像の周囲に刻印されているケースが多い。

一番左端が先導者、2番目が護衛官(リクトル)、3番目が初代執政官ルキウス・ユニウス・ブルートゥス、4番目が同じく護衛官となる。執政官は先導者に案内され、二人のリクトルに前後を守られながら行進している。護衛官はその名の通り、執政官を守るガードマンであり、彼らの手にはファスケスが握られている。ファスケス(束桿)は斧に木の板を縄で巻き付けたものであり、権力の象徴物だった。木の板を解けば武器になるため、象徴物でありながら有事の際は実用性も兼ねていた。護衛官たちは執政官を襲う者が現れれば、ファスケスの縄をほどき、斧で敵対者に対抗した。
そんな共和政ローマだが、開始して間も無く執政官のコッラティヌスが、彼の氏族名が前王タルクィニウス王と同じという理由から暴君を思い起こされるとして解任。コッラティヌスはローマにも居られなくなり、ラティウムへと追放されるに至った。何とも報われない悲しい末路である。この動きには、彼の出世を妬むライバルたちの策略があったのだろう。コッラティヌスの後任には、プブリウス・ウァレリウス・プブリコラという人物が就いた。ローマで古くから有力氏族のひとつとして数えられている、ウァレリアヌス氏族の人物だった。
共和政が開始されたばかりの同年前後509年、亡命した元国王のタルクィニウスが故郷エトルリアで同盟を組んで傭兵を募り、ローマに報復を行った。この戦いをシルウァ・アルシアの戦いと呼ぶ。ブルートゥスは同僚執政官のプブリウス・ウァレリウス・プブリコラと共にタルクィニウス率いるエトルリア同盟軍を迎え撃ち、見事に勝利した。だが、最後にタルクィニウスの息子のアッルンス・タルクィニウス(Arruns Tarquinius)と刺し違え、命を落とした。こうして呆気なくも、共和政が開始された年に共和政の創始者が没することとなった。
ローマの歴史は、まさしく激動である。一寸先は闇。諸行無常。そして、明日は我が身。そんな言葉たちが相応しい常に変化が繰り返される壮絶な歴史だった。だが、だからこそ人々を惹き付ける面白さがあるのかもしれない。歴史そのものが既にドラマであり、2000年後に生きる私たちをも釘付けにしてやまないのである。
To Be Continued...
Shelk 詩瑠久🦋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
