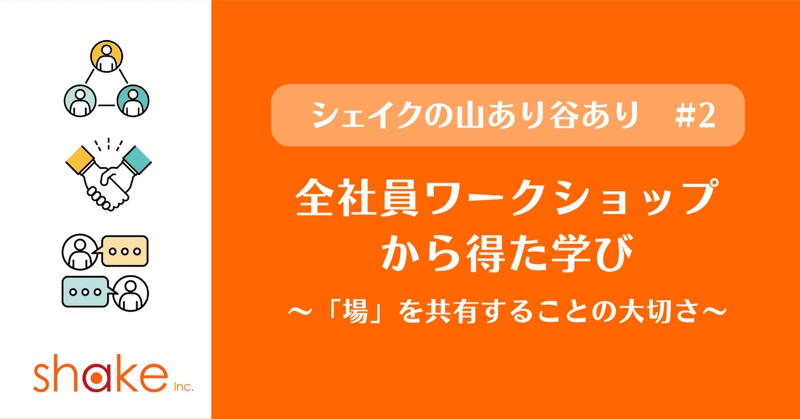
全社員ワークショップから得た学び~「場」を共有することの大切さ~
こんにちは。シェイクの北島です。
今年の4月、
シェイクがご一緒した新人社員研修において、
約8割の企業が対面で研修を実施しました。
テレワークが当たり前になり、
働き方が多様化した一方で、
新入社員研修といった節目の機会では
対面でのコミュニケーションを
重視する企業が大半です。
気軽に集まれるようになった今、
対面で集まることで得られる効果について、
シェイクの全社員を対面で集めた
半年前のワークショップを例に
考えたいと思います。
ワークショップのご紹介
2023年の年始早々、
シェイクでは全社員がオフィスに集まり
ワークショップを開催しました。
欠席はコロナ感染の1名のみ。
地方で働く社員も、
普段テレワークが多い社員も含め、
ほぼ全員が対面で集まったのは
実に3年ぶりでした。
ワークショップの内容は、
社員同士の相互理解を目的に、
「シェイク入社前の自分」と
「シェイク入社後の自分」を
「自分年表」としてアウトプットし、
質問を通じて相互理解をうながす、
というものでした。
※自分年表:
自分の人生を振り返り、
今の自分をつくった経験・出来事・言葉・
人のかかわりを年表の形で書き表したもの
私自身、どこまで自己開示すればよいのか、
戸惑いながらアウトプットしたため、
自分の人生が「A4用紙1枚」
にしかならなかったのですが、
中には10枚以上になった人もいました。


対面で社員全員が集まることを
楽しみにしている方もいれば、
自分年表を共有することへ消極的な方、
もちろん積極的な方もおり、
社員の状態は様々。
しかしながら、
始まってしまえば、なんのその。
シェイクの1年目と2年目社員が
想いをもって考えた企画ということもあってか、
ワークショップは温かく
和やかな雰囲気につつまれ、進んでいきました。
社員の反応を3パターンに分けてみた
ワークショップの終了直後、
参加した社員の率直な感想を集めました。
筆者の独断と偏見で
それらを分類してみると、
以下の3パターンが見えてきました。
①相互理解できて良かった!
・一緒に働く皆さんの考え方や
今を作った背景を知ることが出来て楽しかった。
・意外な過去や経歴を知り、
私の今までの経歴も知ってもらい、
「仲間感」が増した。
・皆さんの過去にも闇がかいまみえて、
人間苦しい時期があってもいいんだな
というのが率直な感想です。
・年代や経歴を超えて、考えを共有
できるのが楽しかったです。
②自己理解がすすんだ!
・目的は相互理解でしたが、
自分の今までの経験や価値観を
見直すきっかけにもなりました。
・現在と過去を比較して、
以前できていたことがブレーキになっていたり、
人とあまり本音で話せてないと感じるので
「殻を破る」ことを今後の課題としていきます。
・自分史は各時期によって、
そこに描かれる内容が変わると思いました。
前回とだいぶ変わったことを考えていると、
自分の成長や現状が見える気がします。
③コミュニケーションの質が高まった!
・自己開示すると、
心が軽くなる瞬間があることを知りました。
心が軽くなると、
相手のことを全身全霊で知ろうとする自分がいました。
全身全霊で知ろうとすると、
相手の話を聴くことにどれほど価値があるか分かりました。
・こんな感じでつながり感を深めながら、
みんなで支え合い、
高め合い頑張っていけると良いなと思いました。
・皆さんと、対面で話せたことが何だか
心地よい気持ちになりました。
上手く言葉にならないことも、
なんか伝わる感覚が良かったです。
「場」を共有することの効果とは
相互理解も自己理解も深まり、
コミュニケーションの質が高まる
ワークショップのポイントはなんだったのでしょうか?
ワークショップという「場」を
共有する中で私が感じ取ったのは、
時間が経過するとともに進む「自己開示」です。
空間を共にし、
自分のことを話すことが
ある意味で強制される場で、
言葉にできないことも、
分かろうとしてくれる相手がいて、
相手の反応を五感で感じながら、
自分のことをポツリポツリと話す過程を通じ、
「ちょっと話してみても良いかな」と、
ハードルがが少しずつ下がっていく
「あれ、私が自己開示しても、
相手との関係性は変わらないじゃん」
「だったら、隠さなくても良いかも」
と、思えてくる
この変化に私はとても価値があると思うのです。
組織で働く1人1人の社員は複雑で、
様々な葛藤や難しさを抱えています。
だからこそ、支え合い、
助け合うことができるのが組織、
にもかかわらず、
自分がどういう状態にあるのかを、
人は意図せず隠してしまう。
そうすると、
支えてくれる人、助けてくれる人、
受け止めてくれる人を見つけられない。
いつの間にか隠してしまうからこそ、
「自己開示」には
成功体験が必要なのかもしれません。
もちろん、
ワークショップのコンテンツが
「自分年表を語る」なので、
自然と自己開示がうながされる
仕掛けになっています。
しかしながら、
「場」を共有しているかしてないかでは、
自己開示の度合いに
大きな違いがあるように感じました。
冒頭、欠席が1名いたと書きましたが、
その方も「自分年表」を作っていました。
その場に参加はできないけど、
「自分年表」が書かれたファイルだけでも
共有しようと思ったそうですが、
テキストのみで共有することの怖さ、
文脈が伝わらないことへの恐れを感じ、
共有をやめた、とのこと。
私たちは、視覚や聴覚だけではなく、
様々な五感でコミュニケーションをしている
と、改めて感じました。
「場」をつくるために必要なこと
テレワークを継続するか、
対面とオンラインを使い分けるか、
対面に切り替えるか
組織ごとに、仕事ごとに、
最適解は異なると思います。
対面で開催した
今回の全社ワークショップでは、
テキストでは伝わらない、
自分の背景や文脈を
相手に共有することができました。
また、接点がない社員とも久しぶりに話し、
人脈づくりや関係構築につながったとも思います。
たくさんのメリットがある
対面の「場」ですが、
このような効果が得られた背景には
企画側に想いがあり、
それを社員へ丁寧に説明する
時間があったことが挙げられます。
企画側の若手社員が、
「なぜこの企画をやるのか」や
「対面へのこだわり」を
自分の言葉で語ってくれていたのが印象的でした。
対面で集まる際、
企画側の皆さんはどのくらい
「目的」と「ゴール」を言語化しているでしょうか?
対面で集まる目的やゴールを、
集まる社員へどのくらい説明しているでしょうか?
意図的に「場」を提供し、
参加した全員で「場」を作っていくためには
企画側の想いを言語化し、
説明するというプロセスが
欠かせなくなってきているように思います。
