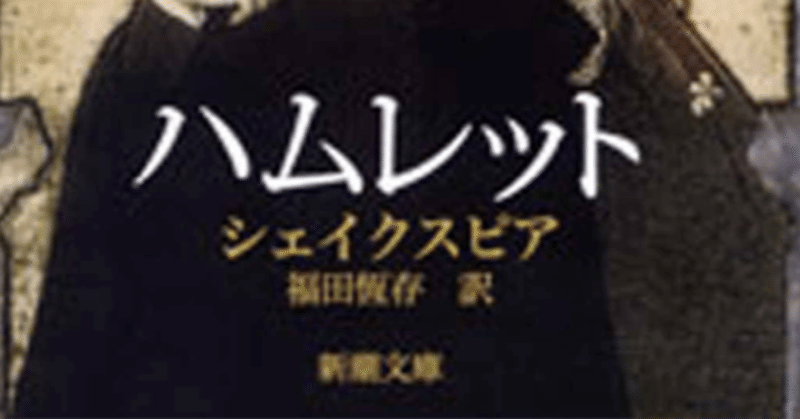
3/1,000冊目 ハムレットが頭蓋骨を手にしている理由→『ハムレット』 ウィリアム・シェイクスピア(著)
読んだ1,000冊

読んだ1,000冊の本を紹介していきます。
まどろっこしい!
ハムレットは、もう迷うし、冷たいし、混乱するし、躊躇します。それがおもしろいのですが、戯曲そのものは、シェイクスピアの『マクベス』や『オセロー』、『ロミオとジュリエット』などに比べるとまどろっこしくて読み進みにくいです。
『ハムレット』 ウィリアム・シェイクスピア(著)
シェイクスピアの作品の中では、読み進まない方の作品です。理由はまあまあたらたらしているんです。『マクベス』や『オセロー』はハラハラしながら読み進むのですが、『ハムレット』は、タラッタラした口上が進行を遅らせる場面が多々ある。それはまるで優柔不断なハムレットその人の気質のように。それでも名言は多々含まれており、それらに出会うたびに「おお、これはどこかで引用したい」と思います。それでも、「次どうなるのよ!?」というひっぱる力は、他の作品に比べて弱いように思います。
登場人物
ハムレット(Hamlet) デンマーク王国の後継者。
ガートルード(Gertrude) ハムレットの母親。クローディアスと再婚している。
クローディアス(Claudius) ハムレットの叔父。ハムレットの父の急死後にデンマーク王位についている。
先王ハムレットの亡霊(King Hamlet, the Ghost) 先代のデンマーク王。ハムレットの父。クローディアスの兄。
ポローニアス(Polonius) デンマーク王国の侍従長。王の右腕。
レアティーズ(Laertes) ポローニアスの息子。オフィーリアの兄。
オフィーリア(Ophelia) ハムレットの恋人。ポローニアスの娘。
ホレイショー(Horatio) ハムレットの親友。
ローゼンクランツ(Rosencrantz) ハムレットの学友。
ギルデンスターン( Guildenstern) ハムレットの学友。
フォーティンブラス(Fortinbras) ノルウェー王国の後継者。
オズリック(Osric) 廷臣。ハムレットとレアティーズの剣術試合で審判を務めた。
日本語版には、英語版の辛さはない
薄いし、英語でも読んでしまおう!と思って手を付けた『ハムレット』ですが、英語は古くてぜんぜん読み進みませんでした。
わたしが今回読んだのは、福田 恒存氏の翻訳ですが、とりあえずもう日本語で読んでおこ!って思うほど読みやすく感じました。あたりまえですが、英語で読むよりはずっと楽でした。
ハムレットがどうして頭蓋骨を手にしているのか?
デンマークの陶磁器ブランドである「ロイヤルコペンハーゲン」には、1898年のパリ万国博覧会以来継続して作り続けているフィギュリンという人形陶器があります。毎年その年のフィギュリンが発売されています。
2006年のフィギュリンが、ハムレットとオフィーリアのフィギュリンでした。そして可愛らしいハムレットのフィギュリンは右手に頭蓋骨を手にしています。この頭蓋骨は、亡き父のデンマーク王に使えていた道化の頭蓋骨でした。これを手にしながらハムレットは劇中で、アレクサンドロス大王や偉人たちちの死後の儚さについて語ります。日本語でいうところの「諸行無常」について触れる場面です。

またシェイクスピア自身の姿にも頭蓋骨を手にしているものもあります。

この頭蓋骨は、シェイクスピアの時代にヨーロッパで広まった「人生の儚さ」を作中に含ませるヴァニタス(ラテン語: vanitas)に通じるものでもあります。またシェイクスピアは、芸術の時代区分のひとつであるバロックにも属しています。バロックは、その直前に興ったルネサンスの反動であり、ルネサンスが永遠として頼めるものを模索したのに対して、バロックでは「移ろいゆくもの」をテーマとして捉えました。かるがゆえに、シェイクスピアは、作中で「移ろいゆく」栄枯や人心をよく扱っています。
またバロックの特徴のひとつである劇中劇(劇のなかでまた劇が行われること)もシェイクスピアの作品の特徴でもあります。
ハムレットの有名なセリフ
Frailty, thy name is woman.
これは、ハムレットが夫の死後すぐに義理の弟であるクローディアスと再婚した母・ガートルードに対する批難の台詞。坪内逍遥が「弱き者よ、汝の名は女」と訳しました。しかし、この訳文では弱き者とは、即ち保護すべき対象を指し、レディーファーストの意と誤解をしばしば招くことがあり、坪内も後に「弱き者」を「脆
もろ)き者」と再翻訳しています。なお、この台詞は当時の男性中心社会の中で、女性の貞操観念のなさ、社会通念への不明(当時のキリスト教社会では、義理の血縁との結婚は近親相姦となりタブーであった)などがどのように捉えられていたかを端的に表す言葉として捉えられています。
To be or not to be, that is the question.
劇中で最も有名な台詞。明治期に『ハムレット』が日本に紹介されて以来、この台詞は様々に訳されてきました。初期の日本語訳の代表的なものには、坪内逍遥の「世にある、世にあらぬ、それが疑問じゃ」(1926年)などがあり、また、これまでの訳では「生きるべきか死ぬべきか」という訳が多いが、この劇全体からすれば「(復讐を)すべきかすべきでないか」という意味に解釈できます。
Get thee to a nunnery!
これは、ハムレットがオフィーリアに向かって言った台詞です。この台詞にちては、大きく分けて二つの解釈があります。当時、尼寺では売春が行われており、隠語で淫売屋を表現する言葉でもありました。ハムレットは、オフィーリアに単に「世を捨てろ」と言っただけでなく、「売春婦にでもなれ」と罵ったとも解釈できます。しかし文字通りに、俗世間を離れ女子修道院に入ってほしいと願った、という解釈もあります。
まとめ
読み進みにくものの誰もが知るシェイクスピアの作品『ハムレット』をしっかり読んでおくのは、何かと糧になりそうな気がしました。また頭蓋骨とハムレットの関係を理解できたのも嬉しい。ついでは、舞台となったデンマークとイングランドの当時の歴史における関係を深めたいと思います。ノルウェーについても。
この本から得たもの
『ハムレット』の登場人物と展開をざっと知れる喜び
ポローニアスが好き。レイモンド・チャンドラーの『プレイバック』に出てくる老人を彷彿させる
17世紀という時代をよりよく知りたいという好奇心
ミレーのオフィーリアをより良く楽しめる知識

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
