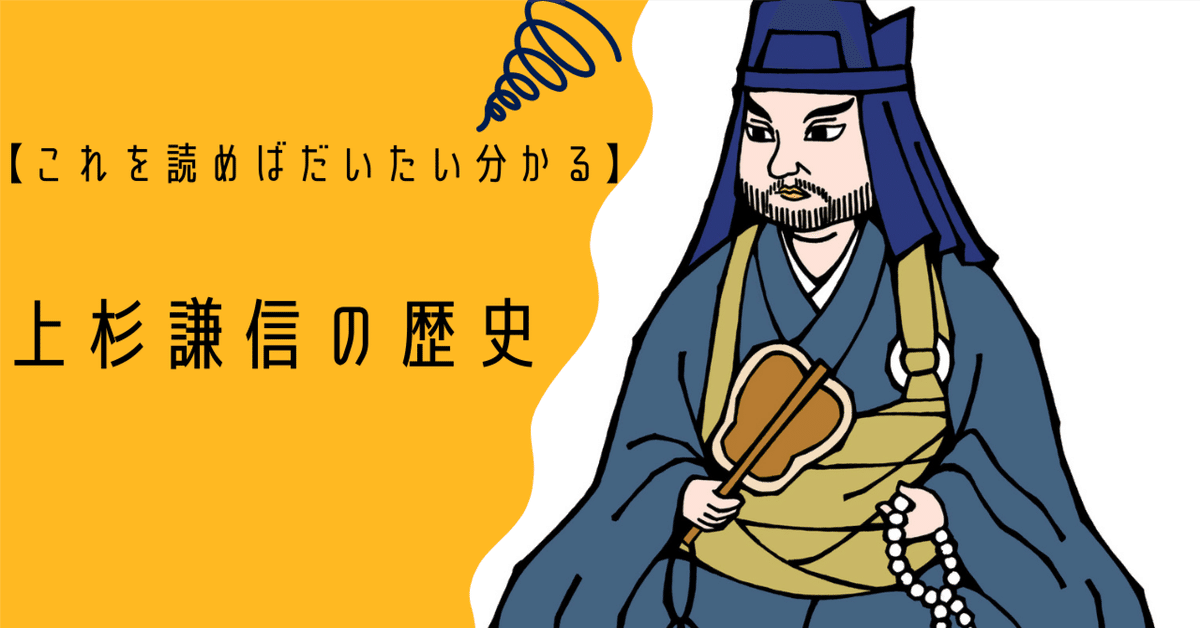
【これを読めばだいたい分かる】上杉謙信の歴史
上杉謙信は「軍神」とまで呼ばれた戦国時代の武将です。
生涯で70回以上の戦いに参加し、敗れたもはわずか2回ともいわれています。
そんな謙信の生涯はどのようなものだったのでしょうか?
今回は上杉謙信の生涯を追い、どのような人生だったのかに迫ります。
名言や有名なエピソードも取り上げ、謙信の人となりにも注目。
上杉謙信について知りたい方は是非ご覧ください。
生涯
上杉謙信はもともと、家督を継ぐような人物ではありませんでした。
それどころか、そもそも上杉家の人間ですらありません。
そんな生い立ちの彼が、戦国時代でも有名な武将になったのでしょう?
上杉謙信の生涯を追ってみます。
(※上杉謙信はたびたび名前が変わるため、基本的には謙信呼びで統一します)
謙信誕生:当時の情勢
上杉謙信は1530年、越後国(新潟県)の守護代・長尾為景(ながおためかげ)の四男として生まれました。
幼名は虎千代(とらちよ)。
当時の越後は内乱激しく、不安定な状況でした。
この内乱に、謙信の父も巻き込まれます。
1536年に父が隠居し、そん後すぐに病死。
この時謙信は、わずか7歳でした。
家督は兄・長尾晴景(ながおはるかげ)がつぎ、謙信はお寺に預けられます。
この時に謙信は、天室光育という僧侶から学問や武道を教わりました。
以降の謙信は仏を大事にするようになります。
時は流れ1543年。
14歳になった謙信は元服。
名を「長尾景虎」(ながおかげとら)とします。
初陣:栃尾城の戦い
謙信の初陣を15歳で経験します。
家督を継いだ兄が病弱なため、越後はいまだ内乱状態。
ある豪族が謀反を起こし、謙信が治めていた栃尾城に攻めてきたのです。
これが謙信の初陣となった「栃尾城の戦い」。
謙信は敵を見事に返り討ちにし初陣を勝利で治めます。
家督継承
「栃尾城の戦い」の後も反乱や戦を勝利していく謙信。
周囲も謙信に一目置き始めます。
しかし、兄・長尾晴景は面白くありません。
1548年、謙信が19歳になったころ。
謙信と晴景で戦となりかけますが、越後守護上杉定実(さだざね)の調停で事なきを得ます。
さらに兄晴景と「父子の義」を結び、謙信は長尾家の家督を継承します。
しかし1550年に上杉定実が死去し、上杉家は断絶。
謙信は室町幕府13代将軍「足利義輝」(あしかがよしてる)を頼り、実質的に国主大名としての地位を得ます。
(上司のような家が断絶したため、謙信の家が越後トップの家になったということです)
その後謙信は、22歳で越後統一を果たします。

北条家と敵対
このころ関東管領「上杉憲政」(うえすぎのりまさ)が、越後へ逃げてきます。(関東管領は、関東の偉い役職くらいの認識で大丈夫です)
関東で勢力を拡大する北条家に敗れたためです。
謙信は上杉憲政を保護したことで、北条家と敵対。
関東に出兵し上野国(現在の群馬県)から、北条家を撤退させることに成功します。
武田信玄と敵対:第一回川中島の戦い
問題は続きます。
今度は信濃(長野県)の守護「小笠原長時」が、謙信の元に逃げてきます。
勢力拡大する武田信玄に敗れたためです。
これにより信玄とも敵対。
1553年に信濃国に出陣し、「第一回川中島の戦い」がおこります。
信玄が直接対決を避けたこともあり、武田軍が信濃から撤退。
こののち謙信は、上洛を果たします。
関東出兵
京から越後に戻った謙信は、武田家との戦を続けます。
第二次・第三次川中島の戦いを経ますが、明確な勝敗はつきません。
1559年に謙信は、再び上洛。
足利義輝から管領並みの待遇を受けます。
事態が大きく動いたのは1560年。
桶狭間の戦いで今川家が破れ、弱体化します。
当時、武田家・北条家・今川家で「甲相駿三国同盟」が結ばれており、武田家・北条家と敵対する謙信にとってチャンスとなりました。
関東管領・上杉憲政の関東帰還の大義名分を掲げた謙信は、関東へ侵攻。
北条家に脅威を感じていた関東の諸大名を味方につけ、北条家の城を次々落とします。
ついには北条家の居城・小田原城を包囲。
この時の上杉・長尾連合の兵力は10万人に上ったと言われます。
しかし相手は難攻不落として有名な小田原城。
1ヶ月間包囲しますが、長期遠征の無理と武田家が侵攻する気配があるため撤退することになります。
ちなみにこの関東遠征時に謙信は、上杉憲政の要請で山内上杉家の家督と関東管領職を相続しています。
これにともない、「上杉政虎」(うえすぎまさとら)へ改名します。

第四次川中島の戦い
1561年、越後に戻った謙信はすぐさま信濃へ出陣。
これにより、もっとも有名な「第四次川中島の戦い」が起きます。
この戦いでは、上杉謙信と武田信玄の一騎打ちが起きたと伝わります。
両軍に犠牲がでる、激しい戦いだったようです。
上杉軍は武田家の軍師・山本勘助を打ち取るなど、戦果を挙げますが明確な勝敗付きません。
両軍、痛み分けとなります。
この間に北条家が奪われた土地を取り戻します。
謙信は再び北条家と対峙しますが、川中島の戦いでの損害もあり敗北。
同族から北条家に裏切るものもあらわれます。
このころ将軍・義輝から1字貰い「上杉輝虎」(うえすぎてるとら)へ改名します。
その後も何度も関東へ侵攻しますが、北条・武田同盟相手に苦戦。
1564年に「第五次川中島の戦い」も起きますが、引き分け。
さらには度重なる侵攻で、関東の諸大名も謙信から離反してしまいます。
北条と同盟
1568年越中(富山県)の一向一揆と椎名康胤が越後を脅かしたため、越中へ侵攻。
このころから越中への侵攻が増えていきます。
同じころ、武田信玄が同盟を破り今川家へ侵攻。
「甲相駿三国同盟」が崩壊します。
武田家をけん制するため、1569年に長年の敵である北条家と「越相同盟」(えつそうどうめい)を締結。
長きにわたる北条家との戦が終わりを迎えます。
そして1570年に謙信は出家。
法号「不識庵謙信」(ふしきあんけんしん)と称し、「上杉謙信」と名乗りだします。
関東での影響力低下
しかし北条家との同盟は長く続きません。
1571年、北条家当主が亡くなり代替わり。
次期当主の「北条氏政」は同盟を破棄します。
武田家と再び同盟を結び、再び謙信と敵対関係となります。
それだけでなく越中の一向一揆との戦いも過熱。
1572年に謙信は、富山城を攻略しています。
1576年までに、謙信は越中を平定。
しかし1572年、長年のライバル・武田信玄が病死します。
信玄が亡くなったことで武田家の脅威は低下。
この機を逃さず、謙信は北条家に対抗するため関東に出兵します。
しかしこの出兵は上手くいきませんでした。
「第二次利根川の対陣」では川の増水で対岸に渡れず撤退。
「第三次関宿合戦」では関東の諸大名が援軍を出さなかったため、上杉軍は攻撃できず味方の城が落城。
度重なる関東への出兵で、関東での謙信の影響力は低下していたのです。
VS織田信長
関東で苦戦していた謙信に転機が訪れます。
1576年、室町幕府将軍・足利義昭(よしあき)の要請を受け、武田家・北条家と和睦。
さらに一向一揆を主導していた本願寺とも和睦します。
将軍・義昭は織田信長と敵対しており、反信長体制の構築を目指していたのです。
謙信は織田家を倒し、上洛することが目標になります。
謙信はまず加賀一向一揆の救援に向かいます。
その際、兵たんの確保と背後の安全を確保するために能登を攻めます。
能登を治めていた能登畠山家は七尾城に籠城。
謙信は難攻不落の七尾城の攻略に手こずります。
謙信はおよそ1年かけて七尾城を攻略。
城内で疫病がまん延したことと、内通者が反乱を起こしたことが決め手でした。
手取川の戦い
謙信が七尾城を攻略した同年、七尾城から救援要請を受けていた信長が軍勢を派遣してきます。
一向一揆の支配する加賀を北上してきます。
これに対抗するため謙信も加賀を南下。
手取川付近で両軍が対峙します。
この時織田軍は、柴田勝家と羽柴秀吉の意見が対立していました。
この影響で秀吉は勝手に自分の軍を撤退させるなど、混乱した状態でした。
そのような状況で川を渡った織田軍に、謙信は襲い掛かります。
織田軍は形勢不利を察し、川を渡り撤退を開始。
謙信率いる上杉軍が追撃をかけ、大損害を与えます。
これが世にいう「手取川の戦い」です。

死亡
「手取川の戦い」で勝利した謙信は居城・春日山城に戻ります。
この時謙信は、次の関東への遠征計画を立てていたと言われます。
(北条家と再度、関係悪化していたため)
しかしこの遠征が実行されることはありませんでした。
1578年、上杉謙信はこの世を去ります。
享年49歳。
城内の厠(トイレ)で倒れて亡くなったと伝わり、死因は脳いっ血ではないかと言われています。
謙信の急死は、上杉家に大きな混乱をもたらします。
跡継ぎ争いが起こったのです。
上杉家内部で戦となり、最終的に養子の「上杉景勝」が家督を引き継ぎます。
その後の時代で上杉家は豊臣秀吉に恭順し、五大老にまで上り詰めることになります。
名言
上杉謙信は多くの名言を残しています。
代表的な3つをご紹介します。
運は天にあり 鎧は胸にあり 手柄は足あり
現代風に言えば「運命は天が決めるが、準備をすれば身を守ることができ、手柄は自分の働きしだい」です。
春日山城の壁に書かれていた文章です
我を毘沙門天(びしゃもんてん)と思え
謙信は自分を毘沙門天の化身であると信じていました。
毘沙門天とは仏教で北を守る存在です。
天皇がいる京から見て北に領地を持つ謙信は、自分を北を守る存在であると内外に認識させたのです。
幼いころから仏教が身近だった謙信には、こういった考えが自然だったのかも知れません。
戦の前には毘沙門堂で座禅やめい想をし、「毘」の旗を掲げ戦場に行きました。
生を必するものは死し、死を必するものは生く
「死を覚悟したものの方が生き残る」という意味です。
謙信は生涯で70回以上の戦を経験しています。
そんな彼が言うので、説得力のある言葉に思えます。
エピソード
他の戦国大名同様、謙信にも有名な逸話・エピソードが残されています。
今回は有名な「敵に塩を送る」エピソードと「生涯独身」に関するエピソードの、2つをご紹介します。
敵に塩を送る
ことわざにもなっている謙信の有名なエピソード。
内容は以下のようなものです。
謙信のライバルである武田信玄が、他の大名から塩の輸入を禁止されました。
信玄の領地に海はないため、塩不足に陥ります。
そこで謙信は弱った信玄につけこむのではなく、塩を送ったと言われています。
このエピソードを聞くと、「謙信が無料で信玄に塩をあげた」ように聞こえます。
しかし実際は「塩商人の往来を禁止せず定価で交易を行った」程度のものと言われています。
いずれにせよ、謙信らしい義に厚いエピソードです。
生涯独身:実は女性?
謙信は仏教を厚く信仰していたため、生涯独身でした。
それどころか、生涯で性交渉を一切していないとされています。
このことから謙信は同性愛者、または女性ではないかという説が存在します。
女性説を裏付けする根拠として以下のようなものがあります。
・毎月の腹痛
・恋愛小説が好き
・女性らしい綺麗な筆跡
しかしこの女性説は、今は真実ではないとされています。
謙信はやはり仏教の教えを重視していたため、その手の行為を行わなかったのでしょう。
別の説として「人質として自分の元に来た敵国の女性を愛していた」という説もあります。
「伊勢姫」という女性で、謙信は彼女を気に入り傍に置こうとします。
しかし家臣から「敵国の女性に恋をしてはいけない」といさめられ、諦めたのです。
その後伊勢姫が亡くなり、そのことを知った謙信は体調を崩すほどショックを受けたと言います。
伊勢姫が亡くなった後も彼女を愛し続けたため、謙信は生涯不犯を貫いたと言われています。
上杉謙信との居城:春日山城
上杉謙信と関係のある城と言えば、居城であった春日山城でしょう。
標高約180mにある山城で、現在も空堀・土塁・大井戸など山城の特徴が残ってます。
天守はありませんが、本丸跡からは日本海や頸城平野が見えます。
【アクセス】
えちごトキめき鉄道・妙高はねうまライン「春日山駅」より徒歩40分
頸城バス「春日山荘前」下車徒歩15分
北陸自動車道「上越IC」から15分
公式サイト:春日山城跡 - 上越市ホームページ
まとめ
上杉謙信は生涯で70回以上も戦に挑みました。
戦に明け暮れながらも、自分の信じる「義」を忘れませんでした。
そんな彼だからこそ、戦後時代でも有名な武将として現代に名を残したのかもしれません。
参考:上杉謙信とは? したことや性格、敵に塩を送った逸話や女性説の真偽など解説 | マイナビニュース
参考:知略に富み、義を重んじた戦国武将・上杉謙信公 | 【公式】上越観光Navi - 歴史と自然に出会うまち、新潟県上越市公式観光情報サイト
参考:戦国武将、上杉謙信とはどういう人物?敵に塩を贈ったってホント?性格や偉業を紹介|ベネッセ 教育情報サイト
【普段から使える戦国アイテム】をコンセプトにスマホ用品や日用雑貨を取り扱っています。
戦国グッズを集めていると家に飾るスペースがなくなったり、使いみちが無いから買わない、なんてことはないですか?
戦国雑貨 色艶では「普段から使える戦国アイテム」をコンセプトにオリジナルの戦国雑貨を販売しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
