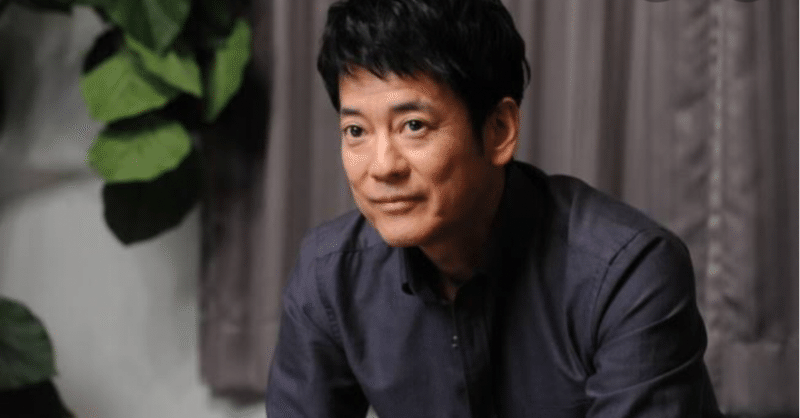
もしもゾンビが299
私は眉間に皺を寄せた。
「ヤンキー集団がやって来て、ガソリンを撒いて火を着けたんです。あっという間に燃え上がってホテルはなくなってしまいました」
ナカムラ達は驚き、呆れた顔をした。
「そんな馬鹿な事をする奴がいるのか」
本当に…。一体なんて事をしてくれたんだろう。炎に包まれたかつての住処を思い出し悲しくなった。
でも火事が起こらなくても、グリードの血がゾンビ化を招くと分かったらどっちみちコミュニティは崩壊していた。それともグリード達はいつまでも内密にしたのだろうか。
「グリードの…あの白い目の人の血が他人を…ゾンビ化を招くってご存知ですか?」
ナカムラは頷いた。
「ああ、知ってる。彼らと同行してた人が感染発症したそうだ。ここに来る前に。その後数人で暮らしていたけれど病人が出てやむなくここに来た。受け入れてくれるかと聞いたので勿論だと応えたよ」
受け入れたのか。ナカムラらしい。
「だけどそれを嫌だと言うのもいてね。血が怖いって、別のホテルに行った。彼らは充分気を配っているよ。俺達とは離れて暮らしてなるべく接触しないようにしてる」
ああ、それはとても孤独であろう。どんな気持ちで生きているのだろうか。人は他人と交わってこそ自分の価値を見出すものだ。
「じゃあ、彼らが自分自身もゾンビ化させるって知ってるか?」
ナカムラが見回した。
「え⁈」
私達は目を見開いた。
白い瞳のうちの2人は2週間程前に立て続けにゾンビになったと聞かされて心底驚いた。そうか。保菌者となった以上、その身はいつかゾンビ化を発症するのか。
クドウ達はその事実を知っているのか。もしそうなら耐え難い恐怖だ。いつか自分がゾンビになると、怯えながら生きるのだ。私なら益々心が病んでしまうだろう。
他人に害を為し、自らも陥れる。仲間が順に欠けていく…。ゾンビウィルスに勝ったわけじゃない。あの特別な人達はそんな過酷な運命と共に生きるのかと気の毒でならなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
