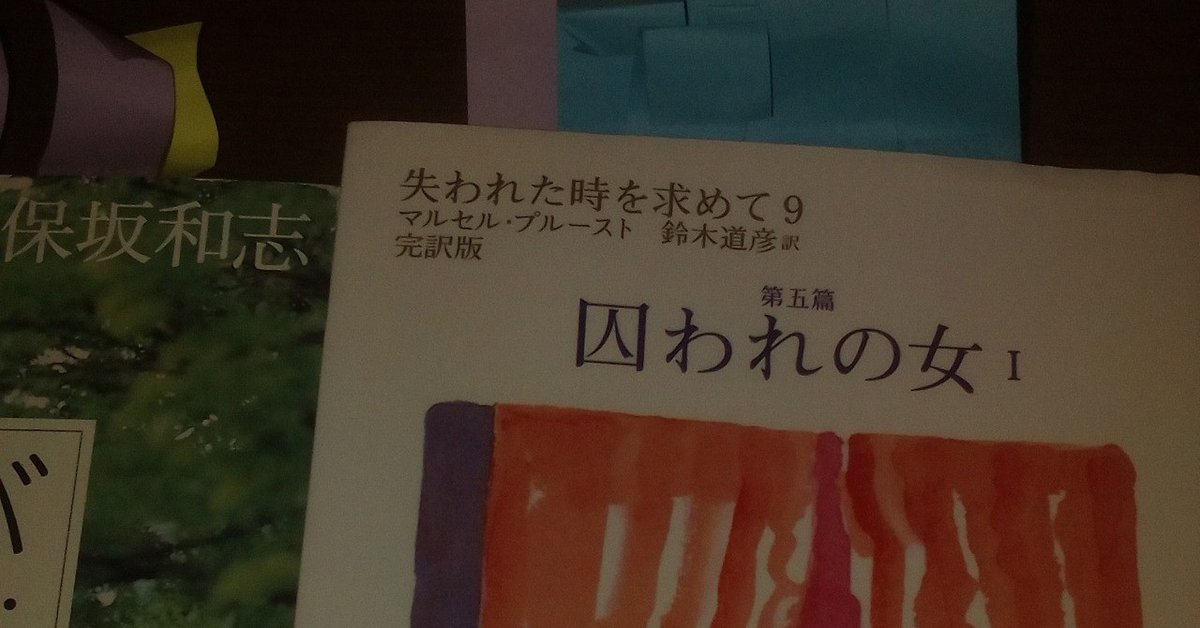
マルセル・プルースト『失われた時を求めて』その1(保坂和志『カンバセーション・ピース』からも)
第三回目はマルセル・プルースト。さて、どの情景を引用しようかと迷う。僕は読んでいるとき沢山付箋を貼って、気に入った箇所に線を引きまくったのだけど、今回その一つひとつを読み返してみて、ほんとに素晴らしい箇所ばかりだな、と。この小説も『遊覧日記』と同じように、というかこの小説こそ一度などではとても紹介しきれず、多分どんなに絞っても20回、30回とやること間違いなし。
問題は最初にどの場面を紹介すべきか? これは悩んだが、『囚われの女』から選んだ。訳は集英社文庫ヘリテージ、鈴木 道彦。
繰り返しになるけど、このnoteは小説自体の素晴らしさがぎゅっとつまった抜粋をお送りするのが目的なので、引用だけ読んでもらえれば本望。僕の文は蛇足でしかない(でも、これをつけないと引用にならなくて著作権侵害にならないように書いているだけ)。
が、『失われた時を求めて』を読んでいない人や、読みだしたものの『囚われの女』まで到達できずに挫折した人には意味が通らないと思うので、最低限の前情報を。主人公はアルベルチーヌという、好きで好きで堪らなかった女の子と同棲を始めたばかり。容易に想像できると思うが、毎日がバラ色なわけ。そんなバラ色の日々の朝、ベッドから起き上がる前に、街の活気が耳に入ってくる。気持ちがウキウキしてくる。そういう場面。220ページから。
ではどうぞ!
アルベルチーヌがヴェルデュラン家に行くかもしれないと言い、それから行かないと言いだしたあの晩の翌日、私は朝早く目をさまし、まだうとうとしながらも強い歓びをおぼえたので、冬のさなかに春の一日がはさみこまれているということを知った。外では、瀬戸物直しの角笛や椅子の修繕屋のトランペットから、晴れた日にはシチリアの牧人のような山羊飼いのフルートにいたるまで、種々さまざまな楽器のために巧みに書き分けられた民謡のテーマが、軽やかに朝の空気を編曲して「祝日のための序曲」を作りだしていた。聴覚というすばらしい感覚が外の通りを連れてきて、そのあらゆる線を再現し、そこを過ぎるすべての形を描きだし、その色を私たちに教えてくれる。パン屋や牛乳屋のシャッターは、昨夜は女性のもたらすあらゆる幸福の可能性を締めだしていたのに、今は若き女店員たちの夢に向かって透明な海を横切ってゆこうと、出航準備中の船の滑車のように軽々と巻き上げられてゆく。別の界隈に住んでいたら、このシャッターを上げる音が私のたった一つの楽しみになったことだろう。だがこの界隈ではほかにも多くのものが私の歓びを形作り、私はそのどれ一つも寝過ごして聞き逃したくはないのだった。
はい。素晴らしいですね。本当は、それで終わりたいところです。主人公がウトウトとしていると、瀬戸物直しの角笛、椅子の修繕屋のトランペット、また晴れた日には山羊飼いのフルートが聞こえる。さらにパン屋や牛乳屋のシャッターを巻き上げられていく音まで、いまの主人公には歓びとなっているんですね。
ここでワンポイント! プルーストの文章の特徴として、括復(かっぷく)的な情景が多用されること、また括復的な情景と単起的な情景が混ざり合うことを、フランスの文学理論家(ってなんなのかと思うが)のジェラール・ジュネットが指摘している。括復的な情景とは単起的な情景と対となる用語で、周期的に発生する出来事、習慣となっている出来事を一度に物語る情景のことをいう。例えば、『今日僕は歯磨きをする。明日僕は歯磨きをする。明後日僕は歯磨きをする……』と、実際に行うことを行う回数分書くのではなく、『僕は毎日歯磨きをする』と書く情景のことを括復的な情景と呼ぶ。そうではなく、前者のように行うことを行う回数分、素直に書く場合、その情景を単起的な情景と呼ぶ。
引用部は『あの晩の翌日の朝』のことだから、基本的にここ全体が単起的な情景のはずだ。だが、『晴れた日にはシチリアの牧人のような山羊飼いのフルートにいたるまで』という文で途端に雲行きが怪しくなる。えっ、単起だと思っていたのに括復なのか? 次の文の終わりも『その色を私たちに教えてくれる』となっていて、そのときそれを感じただけというのではなく、習慣的に、または真理としてそうであるという現在形だ。その次の文の終わりも『軽々と巻き上げられてゆく』で、こちらは習慣の現在形。その次は『楽しみになったことだろう』で推測で終わり、最後の文は、『なかった』とか『なかったのだった』ではなく、『ないのだった』でこれまた習慣という感じ。引用しきれなかったが、次のページまでいくと、『こうしたものを私がこれほど楽しく思うようになったのは、アルベルチーヌといっしょに暮らしはじめてからだった』という記述があり、いよいよ『あの晩の翌日の朝』とは関係なくなかったかと思い油断して読み進める。するとそこから読み進めること5ページ、227ページまで読むと、『フランソワーズが「ル・フィガロ」紙を持ってきた』というので、まだ『あの晩の翌日の朝』が続いてたんかぁーい! となるわけです。いやぁーかなわんわ。
さて、プルーストの引用といらない解説は終わったが、ついでに書きたいことがある。この場面、主人公が寝ていると周囲の音が聞こえてきて、その音から周囲の映像が浮かび上がってくるわけだが、ここを読んだとき、僕が思い出したのが、保坂和志の『カンバセーション・ピース』。主人公は、横浜球場にシーズン最終戦の応援にいくのを楽しみしていたのだけど、体調を崩してしまい、家で寝込んでいる。文庫版403ページからの場面(内容は全然ちがうけど)。枕もとで浩介と綾子と森中という、主人公の家で働いている(この小説では広い家の一部を職場として友人に貸しているという設定です)三人が野球の話をしているところから情景は始まる。そのうちみんな出て行って主人公は一人寝ているんだけど、周囲の音から他の人がどんな活動をしているのか想像する。主人公が寝ているは二階の一番奥の六畳で、みんながいつもいる主人公の部屋から離れている。404ページの終わりから引用する。
ではどうぞ!
それでとにかく熱が下がるまで、二階の一番奥の六畳に寝ていると、私がいなくても浩介はいつもと同じように私の部屋でブルースを弾いていて、私がそばにいないと途中で話しかけられたりすることがないために弾く方に集中するせいか、定期的に波が押し寄せるように激しいフレーズになっては、また穏やかというかかったるい感じのフレーズに戻るというのを繰り返していて、それを聞いているうちに私は三十分ぐらい眠っては目を覚ますというのを繰り返して、目を覚ますたびに上目づかいに見る秋の空が柔らかみのある光を放ちながら青く晴れていて、私が見ていても見ていなくても空はこうして晴れて広がっているというあたり前のことを感じるのだが、そのときに窓を少し開けている西側の道から若いお母さんらしい声が
「きれいなお空ねえ」
と言うのが聞こえてきて、私には唐突にそれが死んだ人に語りかけられた言葉のように感じられた。
その声と一緒に小さな子どものゴニョゴニョしゃべる声も聞こえてきたけれど、私が見ていても見ていなくても広がっているこの空が、ある人にとっては生涯の最後の秋に見る空であり、ある人にとってはもうこの空を見ることのない人に向かって語りかけるように見る空でもあるのだから、いま小さな子どもの手をひきながら歩いているお母さんが「きれいなお空ねえ」と何気なく言ったとしても、その言葉は本人の意図をこえて、この空を見る回数に限りある人間として、死んだ人たちへの語りかけになっているのではないかと感じたのだった。
長くなった。こんなに書くとは。でもいいとこだよね。この後も、いかにも保坂和志らしい、哲学的な思索が続いていく。こんな風な文章が続くのは保坂和志が主人公(だけど名前は高志だ。前に紹介した『デッドライン』では主人公は〇〇、『失われた時を求めて』では後半にマルセルという名前が残っているけど、前半は無理に主人公の名前が出てくるのを避けてる。だからどうということはないけど)だからだけど、この小説ではさらに、チャーちゃんという白血病で死んだ猫の死をどうやったら乗り越えられるのかというのが、テーマというか、小説の底に常に漂っているから。
主人公が寝てるところに聞こえてきた音という共通点で、二つの小説を引用してみました。でもまあ引用してみると全然違うね。まあ、好きな彼女と同棲できて幸せなマルセルと全然ちがうかんじになるのは当然だけど。
しっかし長くなった。ではまた!
この記事が参加している募集
よかったらサポートお願いしやす!
