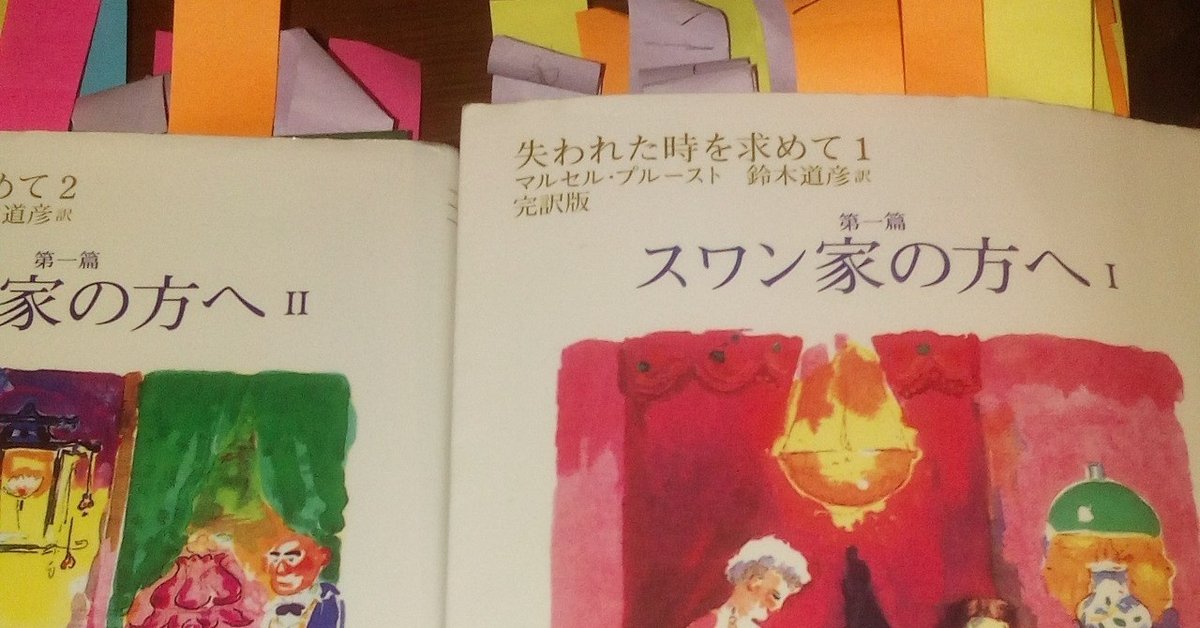
マルセル・プルースト『失われた時を求めて』その2(全体の構造)
今回から連続で『失われた時を求めて』を取り上げる。これは正直何回になるかわからない。最初に小説の概要というか、設計図を示して、あとは小説の内容をおいつつ情景を引用する、という感じにしようと思う。この小説は最初、はじまっては語り手が介入することを繰り返す。その部分を引用して、小説の構造を説明する。まずは有名な有名な冒頭から。集英社文庫、鈴木道彦訳の『スワン家の方へ』の29ページから。
長いあいだ、私は早く寝るのだった。ときには、蝋燭を消すとたちまち目がふさがり、「ああ、眠るんだな」と考える暇さえないこともあった。しかも三十分ほどすると、もうそろそろ眠らなければという思いで目がさめる。
冒頭で語り手が寝たり起きたりを繰り返しながら、これまで幼少期から自分が滞在した部屋を次々に思い出す場面から、小説は始まる。このはじまりは前回のその1でも取り上げた括復的な情景となっている。つまり語り手の習慣的な出来事の記述。これはいつの習慣か? この小説の始まりは小説全体のどの地点なのか? 答えは物語の最後の地点、すくなくとも最終章『見出された時』でタンソンヴィルのサン=ルー夫人の家に滞在した後だ。つまりこの膨大な物語のはじめからプルーストはもう小説のずっと後ろの方のことを頭にいれている。それは次の引用でわかる。36ページから。
それからまた別な姿勢の記憶がよみがえる。壁はちがった方向にこうたいしてゆき、私はサン=ルー夫人の田舎の家の、自分にあてられた寝室にいる。
ここでサン=ルーというのは、のちに主人公の友だちになる人物で、ゲルマント一族という、名家の一員だ。その夫人はジルベルトといって、主人公の初恋の相手だ。彼女とはコンブレー(フランス中部北部にあるイリエ=コンブレという田舎町がモデルらしい)という街にある、主人公の大伯母の家に滞在した際に出会う。主人公は完全に目が覚めてからコンブレーのことを思い出すのだが、そこに行く前に、主人公がまどろみながら思い出す部屋の描写がいいので一部引用する。37ページ中ほどから、どうぞ!
その部屋では、凍てつくような寒さの日になると、戸外から隔てられていると感じるのが喜びになり(海鳥が、穴の底の大地の熱に包まれたところに巣を構えるように)、また、ひと晩中暖炉に火の気を絶やされることもないので、暖かくけむい空気に包まれて眠ることになるが、ときどき燃えあがる燠火に照らしだされるその大きな空気のマントは、いわば形をなさない奥まった寝所か、部屋そのもののなかにうがたれた一種の暖かい洞窟、燃えたつ地帯で、しかも部屋の隅や、窓に近かったり暖炉と離れていたりして冷えきったところから、顔にひやりと風が吹きかかって、その熱の輪郭はゆれ動いている。――夏の部屋では、生温い夜に融けこみたいと思うのだが、半開きの鎧戸にもたれかかった月光が、その魔法の梯子をベッド足許にまで投げているので、眠るといっても戸外同様に、光の先端で微風にゆれているシジュウカラのように眠ることになる。
いいですね。「海鳥が、穴の底の大地の熱に包まれたところに巣を構えるように」「部屋そのもののなかにうがたれた一種の暖かい洞窟」「光の先端で微風にゆれているシジュウカラのように」などなど比喩が多用されるのは、いかにもプルーストという感じ。こうして色々な部屋のことを思い出してから目覚める主人公だが、まだベッドで横たわったままだ。こうした記述がしばらく続き、そのあと目覚めた後によく思い出すといって語り始めるのが、コンブレーだ。40ページから。
コンブレーでは、毎日夕暮れどきになると、ベッドにはいって母や祖母から離れたまま眠れずにじっとしていなければならない時間にはまだ大分間もあるというのに、寝室のことが頭にこびりついて私を悩ませるのであった。
ここから始まるコンブレーの物語(コンブレーⅠとでも呼ぼうか)は105ページまで続き、また語り手の時点に話が戻る。語り手はある冬の日に母にすすめられて紅茶とともに「プチット・マドレーヌ」を食べたことを思い出す。108ページの引用。
私は何気なく、お茶に浸してやわらかくなったひと切れのマドレーヌごと、ひと匙の紅茶をすくって口に持っていった。ところが、お菓子のかけらの混じったそのひと口のお茶が口の裏にふれたとたんに、私は自分の内部で異常なことが進行しつつあるのに気付いて、びくっとした。
紅茶とともに「プチット・マドレーヌ」を口にした途端、主人公の内部でなにかが起こる。このまま三ページ、主人公はこの感覚がなんなのか考え、ついにそれが、コンブレーで日曜の朝にレオニ叔母の部屋に行った際に、叔母が紅茶に浸してさしだしてくれたマドレーヌの味だったということを思い出す。このことで主人公の記憶が蘇ったことが報告され、115ページからコンブレーについての思い出(コンブレーⅡと呼ぼう)が語られる。
コンブレーⅡ以降の内容については、あとでふれることにして、まずはこの小説の構造をさささーっと説明する。コンブレーⅡは『スワン家の方へⅠ』の最後、つまり393ページまで続き、また語り手のもとに話が戻ってくる。『スワン家の方へⅡ』からは、主人公が生まれる前のスワンの恋の話(ここは後で語り手が聞いて書いているという設定だ)が突如始まり、『スワン家の方へⅡ』の417ページまで続くのだが、421ページからはまた語り手の側に話が戻ってくる。さわりを引用する。
眠れない夜、私がよく思い浮かべるいくつかの部屋のなかで、バルベック〈海のグランドホテル〉の部屋ほどあのコンブレーの部屋とかけはなれたものはなく、粉をまぶしたようにコンブレーの部屋を覆っていた空気が、ざらついた、花粉だらけの、食べられそうでしかも信心深い空気であるのに対して、この〈海のグランドホテル〉の壁にはエナメル塗料がかけられており、ちょうどプールの内側のつるつるした壁が青い水をたたえているように、澄んだ、空色の、潮気を含んだ空気をたたえていた。
はじまっては語り手が介入し、またはじまっては語り手が介入する『失われた時を求めて』だが、上記の引用のあと、半ページほどバルベックで滞在した部屋の様子が語られると、もう話は語り手に戻らない。小説は次のページ422ページから本当に始まる。
だがまたなによりも現実のバルベックとかけはなれていたのは、嵐の日に夢見たバルベックで、そんな日にフランソワーズが、私をシャンゼリゼに連れていく途中で、風が強くて頭の上に瓦が落ちてくるといけないからあまり建物とすれすれのところを歩かないようにと言い、溜息まじりに新聞で報道された災害や難破の話をするようなとき、私はよくバルベックを思い描いた。
フランソワーズというのは女中で、物語のはじめ、主人公がコンブレーで滞在するレオニ叔母の女中をしているが、その死後主人公の家の女中になる。バルベックというのは、三巻(集英社版)の途中からしばらく小説の舞台となる、海沿いの街で、フランスのカブールがモデルになっているらしい。ここから主人公の物語が基本的に時系列(二巻の終わり、土地の名・名の最後では今の地点(それがいつかは不明だが)からブローニュの森をふりかえているが、そこを起点にして回想したりはしない)で語られる。途中時間がとぶことはあっても、語り手に話が戻るようなことはない。
『失われた時を求めて』の一番大雑把な見取り図は以上となる。次の記事では、この小説を理解する鍵となる二つの方向(ゲルマントの方とメゼクリーズの方)について書く予定
ではまた!
頭がおかしい『失われた時を求めて』分析に興味がある方は、以下の三つの記事も是非!
この記事が参加している募集
よかったらサポートお願いしやす!
