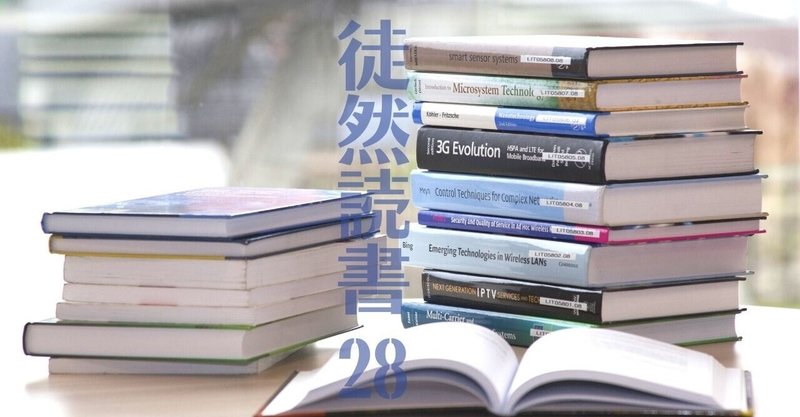
それ、数値化せずに感覚で語っていませんか?【徒然読書28】
計画を立ててもなかなか実行できない、効果がでない・・・そうした経験はありませんか?
その原因は「数値化」できていないことにあるのです。
私もよく上司に「数値で客観視するように」と言われていましたが、ようやくこの本を読んで意図が分かりました。
では、「数値化」とはどういうことなのか?
1.数値化とは?
数字=理論で冷静に判断するツール
感覚的に出来た!のではなく、100%の状態がこれで逆算すると今は70%です。といったように、数字を入れていく。
そうすると、目の前の風景がすこしすっきりするような気がします。
「どの数字を達成すれば評価されるのか?」を明確にすることも、日々の仕事の姿勢が変わると思います。
「この%は何分の何ですか?」の視点もなるほど、と思いました。
FACTFULLNESSにつながる捉え方ですね。
行動量が分母を表すようにするのです。
例えばこの塾には過去に東大合格者を50%出しています!とあっても、2人のうち1人合格した、と100人のうち50人が合格した、では大きな違いがありますね。
2.KPIの重要性と設定の仕方とは?
日々の行動に迷いがないレベルにまで、「KPIに分解できていること」
理想的なのは、この状態です。
常に「行動量」が減っていないかを数字の動きから見るようにします。
そのためには、目標とKPIにつながりをもたせることが必要です。
「5年後の姿」と「今日のKPI」はつながっている。
これを意識するだけでも、日々の生活の質が変わると思います。
会議でも、KPIを設定していれば、この会議で最低限決めないといけないことがわかり、内職も減るのでは?と感じました。
3.「真の変数」はどこに?
「変えられること」を変えようと努力し、「変えられないこと」は早々に見切りをつける。
この「変えられること」が変数であり、変数をつかむことができれば解決に大きな一歩を踏み出せます。
他人の成功談はあくまでも「仮説」であって、「変数」ではない。
そのまま使えば成功するモノではありません。
ですが、仮説という前提で知識をシェアすることは大事なことで、積極的にやっていくことと言っています。
とりあえず「真の変数」を1つ決めて、「やらないこと」を先に決める。
そして、もう一つ。「真の変数」は常に変化します。
以前は成功していても、今回も成功するとは限りません。
なので、常に「真の変数」を捨て続け、アップデートする努力が必要です。
4.長期的視点をもつためには?
「長期的に見て未来のトクを選ぶ」
「時間軸とセットでシミュレーションをする」
日々数値と向き合って入れば衰退と成長の兆しを見つけることができます。
まずは1日の行動と計画を見直す→長期的目標を設定する→目標を達成するための今日のKPIを決める
このサイクルを回し続けていれば、短期的利益に惑わされず、長期的視点で選択することができます。
少々脱線しますが、これも心に残りました。
自分には『何が足りないか』を明確にしてくれる上司のもとにつく。
数値化しても、自分のことをすべて分かるというわけではありません。
だからこそ、他者視点から客観的に評価してくれる上司のもとにつくことも大事だと思いました。
もちろん、良い関係を築いていること前提ですが・・・
いかがでしたでしょうか。
この本を読んで、スケジュール帳になるべく数値を入れるようにしました。
すると、何のためにこの時間を過ごしているのかが見えてきて、より1日が充実しているように感じました。
仕事でも、「100%の状態はこの状態で、今は60%です」「この作業に8時間かかりました」と報告するようにしたところ、進捗報告が楽になりました。
割り当てられるタスクも効率よく出来るようになってきたと思います。
ここまで読んでくださりありがとうございました!
スキやコメント、フォローをしてくださると大変嬉しいです(*^-^*)
