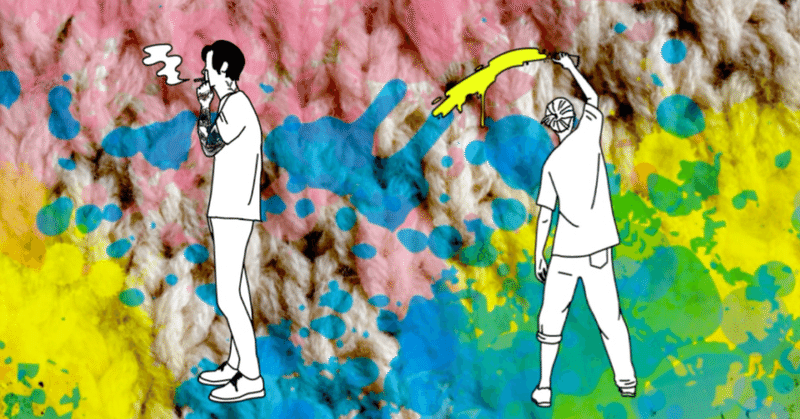
針を置いたらあの海へ 第1話
俺はただ、明日も俺のまま、
この身体と心のまま目を覚ましたい。
それだけだ。
<あらすじ>
16歳のニットの名手・レオと、28歳全身タトゥーの彫り師“たっちゃんさん”が織り成す、ニットとタトゥーを巡る賑やかな日常。
そしてその中に見え隠れする、2人の抱える苦しみの影。
バディ体制での創作活動を積み重ね、無二の絆を得た2人は、関門海峡へ旅に出る。
傷を負った大人と、傷の場所を知らない少年が、自分を肯定するまでの物語。
本編ラスト5行で、タイトルの意味が明かされる。
しょうしつ‐てん〔セウシツ‐〕【消失点】
遠近法や透視図法における、平行な直線群が集まる点。バニシングポイント。
高校中退を祝して美容室に行ったら、“たっちゃんさん”がいた。
半年前の高二の春、俺がリビングで朝のワイドショーを観ながら
「ダリィし学校行かね」
と言った時、母さんは
「お、とうとう決めたか」
と妙に愉快そうだった。
「あんた高校入ってからどんどん顔暗ーくなってたよ」
そう言って、高校サボり開幕記念ランチの店を探し始めた。
俺は俺で、高校サボり開幕記念に髪を伸ばそうと決意し、ネットで「セミロング メンズ」と検索してイメージトレーニングを始めた。
順調に出席日数を擦り減らし、先週俺はめでたく、学生証を返納した。女子からの校内ストーキングや、男子からの「レオってもしかしてさぁ……」と探る視線から、解放されたのだ。
そして今日、高校中退記念に、毛先を揃えるためにこの美容室に来た。半年経つと随分伸びるもので、長めのショートヘアは、肩につくくらいのウルフヘアになっていた。
さくさくというハサミの音とともに、白いケープに、母さんいわく「父親譲りの明るい栗色」の髪がはらはらと落ちていく。
写真の中の父親は、髪も肌も色素が薄くて、通った鼻筋はそばかすで彩られていた。レンズに目をやるでもなく、つまらなそうな表情をした、美しい男。
あのくしゃっとした短髪を思い返し、俺は今後も髪を切らんぞ、と決意を新たにした。
膝の上に、定期購読している雑誌「ニットの生活」を広げる。下関にある、小さな草木染の毛糸工房が取り上げられていた。
青色から黄色にグラデーションする毛糸が目に飛び込んだ。その鮮やかさは、俺にも分かる。こんな毛糸でセーターを編んだら……大分派手な人になりそうだ。手袋とか帽子とか靴下とか、差し色に使える小物を編んでみたい。俄然興味が湧いてきた。
行こうかな、下関。ライトに旅行を検討し始めた自分に驚く。十六歳にして少し早めのモラトリアム期に突入したことに、俺はすっかり浮かれていた。
会計を終えて美容室を出たら、吹きすさぶ木枯らし一号に面食らった。面食らっているその時、外のベンチに座っていた男が
「あ、レオ君やっほー。お迎えに来たよー」
と声を掛けてきた。
いや、お前誰だよ。
思わず言いそうになったが、彼の風体を見て堪えた。黒いセンターパートのショートヘアはいいとして、カーキのブルゾンからはみ出た首と手首と手の甲、そして指にまで黒のタトゥーが入っている。見えないけれど、腕も引き続きタトゥー入ってんだろこの感じは。
「髪、くせ毛?パーマみたいでいいねぇ。顔立ちちょっとおばーちゃんに似てるね!」
男はそう言いながら立ち上がり、俺の髪型をつむじの形込みで見た。割と細身だから、座っていたら予想がつかなかったけど、立ってみれば、見上げるような長身だった。
こんな人に「お迎えに来た」と言われてついていくほど、俺は平和ボケしていない。一旦美容師さんに助けを求めようと回れ右した。
「あ、ごめんねぇ言ってなかったね、レオ君のおばーちゃんから、レオお迎えに行ってあげてーって言われたんだよ。俺はね、おばーちゃんのカフェのお隣さん。たっちゃんって呼んでよ!」
呼ぶ訳がない。無視してドアノブを強く握ったら、
「ほら、おばーちゃんに電話掛けてるから……あ、おばーちゃん?レオ君ね、すーっごい警戒してる!全然目が合わないから、ちょっと喋って?」
はい、とスマホを渡された。知らない人の頬に当てられたスマホを、自分の頬に当てるのはかなり抵抗があったので、スピーカーに切り替える。
「あ、レオぉ?その人ね、たっちゃんだから」
ばあちゃん、よく考えてくれ。俺はこの人の通称しか知らない。子どもの頃あれだけ、「レオは可愛いから変な人に連れていかれそうで心配だわぁ」って言っていたじゃないか。この人は、変な人ではないのか。
「ごめん、それは聞いた」
「お隣の店の人でね、すっごく優しい子だから安心して!おばあちゃんのカフェまで案内するって言って、そっちに行ってくれたのよぉ」
確かにばあちゃんの声だが、ボイスチェンジャーを通して喋る別人かもしれないので、
「ばあちゃん、俺が中退する理由覚えてる?」
と聞いてみた。ばあちゃんは、あらぁアハハと笑って、
「ダルいから、でしょ」
と言った。正解、あなたは俺のばあちゃんだ。
一定の距離を置いて長身タトゥー男の後ろを歩く。
「レオ君、俺別に取って食ったりしないから安心して?結構モラリストよ。ところでさぁ、ダルいから中退ってなかなかパンクでいいね」
「はぁ、まあ」
パンクも何も。
勝手に注目してああだこうだ言われるのも、そもそも毎日課題やって予習復習やるのも、もっと言えば朝起きるのも、全部ダルかった。
あんたはダルくなかったの?なんて、聞いてもしょうがないことの為に、俺は口開けたりしない。それこそ、ダルい。
カフェに着いてばあちゃんに会うなり、小声で、努めて婉曲的にクレームを入れた。
「ばあちゃん、俺さ、もう Google マップ見たらばあちゃんの店まで行けるくらいオニイサンになったんだよね」
「あらあら、髪も背も伸びたし、立派になったのねぇ」
鷹揚にスルーされ、挙句
「たっちゃんと仲良くなれそうかしら?」
と言われた。
「あとひと押しで友達になれそう!」
頭上から、ポジティブな大声が降って来た。この先、めちゃくちゃ強くひと押しされるんだろうかと怖気付いた。
初めて来たばあちゃんのカフェは、大きな窓と白い壁のおかげで光に溢れていた。大テーブルの真ん中に、葉の着いた大きな枝が生けられた花瓶が置いてあった。
ドウダンツツジ、というらしい。頭上にはたくさんのドライフラワーが吊るしてあるのが、花が好きなばあちゃんの店らしいな、と思った。この空間でバイトできるのは悪くない、いや、すごくいい。
「店、おしゃれだね」
「たっちゃんがね、色々教えてくれたのよ。今はこういうのがウケるよーとか、ここの建築事務所いいよーとか。ねっ」
長身タトゥー男もアウターを脱ぎながら、ねっ、と応える。
忘れるはずの無いデカさなのに、一瞬その存在を忘れていた。
「……ばあちゃん、この方」
「あのね、佐藤タツミくんて言ってね、よくお茶に付き合ってくれるの。たっちゃんって呼んであげて」
改めて彼を上から下まで見た。首のストロークが長くて疲れる……と思ったところで、俺の目が釘付けになった。
「あの、佐藤さん」
「あ、たっちゃんね」
「佐藤さん。そのセーター」
「たっちゃん、ね」
「さと」
「たっちゃん。ね」
「……たっちゃん、さん。そのセーター。古着ですよね?」
「うん、そうだよ。高円寺にいい店あってさぁ」
「これ……」
俺は、たっちゃんさんの腕をつかんだ。
そしておもむろに、その濃紺のニットのにおいを嗅いだ。
「えっ、ちょ、おばーちゃん、レオくんこういう挨拶するタイプの子なの?」
「……やっぱそうだ」
少し立った襟元、腋部分のひし角のマチ、裾のスリット、たっちゃんさんの細身が際立つぴったりしたシルエット、そしてこの羊の脂の匂い。
「これ、ビンテージのガンジーニット……」
「え、何。ガンジーって、あの眼鏡坊主の」
「違います」
えーじゃーもうわかんないよーというたっちゃんさんの声を無視して話を続ける。
「イギリス海峡のガーンジー島で、漁師のために編まれた仕事着です。たっちゃんさん、ちょっとかがんで下さい」
えー、と戸惑いながらたっちゃんさんは素直に従う。
「ほら、首元も含め、前後のデザインが一緒でしょ?暗い夜でも、前後気にせず着られるようにこうなってるんです。あと腋のマチ。たっちゃんさん、腕動かすの楽だなって思いませんか?」
「あ、そうそう!細いつくりの割に、腕周り突っ張らなくていいんだよねぇ」
「まさに、作業用なので、腋下にマチを作ることで余裕をもたせてるんです。あと、動きやすいように裾にもスリットが入ってる」
気が付けば、たっちゃんさんを中腰にさせ、ニットの裾を引っ張っていた。
「たっちゃんさん、これ、部屋の中だと暑くないですか」
「……うん、そうなんだよねぇ。早く着たくて選んだけど、正直暑い」
「ですよね。羊の脂が残った糸を使ってて、結構なハイゲージ……編み目が細かくて、しかも袖口はぎゅっと締まって、全体的なシルエットもタイトだから、かなりあったかいと思います」
一気にしゃべって、俺は我に返った。そして気づいた。
捲った袖から伸びるたっちゃんさんの腕には、想像以上にごっついタトゥーが入っていた。左腕は大きな花と、前腕にぽっかりと白い空間。いや、それは陰影もほとんどない、シンプルな白い鳥だった。妙にかわいらしい左腕に対して、右腕はライオンの写実的な口元が見える。
こんな人を操り詰問するという、とんでもない蛮行を働いてしまった。俺は今度こそたっちゃんさんに「お迎え」されることを覚悟した。
でも、たっちゃんさんは目をキラキラさせていた。
「えーすごい、レオくんめちゃくちゃ詳しいね!俺何にも考えずにさぁ、いいじゃーんって買って、あったかーい楽ちーんって着てたのに」
想定外の朗らかさに気が抜ける。
「レオはね、編み物大好きなのよ」
「あぁなるほどねぇ、じゃあこのお店にぴったりだね」
お嬢様歴七十ウン年のばあちゃんはこの度、編み物友達の集会所として、ニットカフェなるものを開いた。お茶しつつおしゃべりを楽しみつつ、みんなで編み物をするらしい。俺も初心者〜中級者さんくらいなら、編み方を教えたり、失敗した時のカバーもできる。多分、ニートまっしぐらの俺に、ニート以上フリーター未満の生活を満喫させる為の店でもあるんだろう。
ばあちゃんの焼いたシナモンロールを食べながら、これからのことを軽く話した。
「注文取ったり、簡単な飲み物作ったりはお願いね。コーヒーはおばあちゃんがやるから、お紅茶とか、ジュースとか」
「あぁ、それくらいなら全然」
「てかさぁ、みんなレオくんと喋りたがると思うよ。おばちゃんおばーちゃんにモテるでしょ君。よ、看板息子」
「空いてる時間俺も編んでていいの」
「あ、無視されたー」
「ご自由にどうぞ。みんなと仲良くね。困ってる人いないか気にかけてあげて」
あんまり没頭しちゃダメそうだ。複雑な模様編みとかはここではやらないようにしよう。
「そういえばさぁ、レオくん、このニット売ってた古着屋紹介しよっか。古着屋っていうか、ほぼニット屋だったし、楽しいんじゃない?」
たっちゃんさんから初めて有益な情報がもたらされた。
「あ、お願いします。高円寺でしたっけ」
「そう高円寺のさぁ、うん、なんつったっけなぁ。あー。あ、あぁやばい、ど忘れした。店の場所……も何となく覚えてるけどぉ、そこまでの道が分かんない。店構えだけは覚えてんの!俺の脳内を念写して見せたいくらい」
前言撤回。
「もうさ、一緒に行こ。連れてってあげる。俺今日定休日で暇だし、今からでもいいよ?」
「いや、いいです自分で調べるし」
「無理じゃない?高円寺すっごい古着屋あるよ」
だからこそ店名だけでも覚えておいて欲しかったんだよっ、と言いたいのをグッと堪えた。
「レオ、行ってきたら?荷物うちに置いたら、やることもないじゃない。ついでに二人で晩御飯食べてきてもいいわよ。日持ちするものしか作ってないし、明日に回せるわ」
ばあちゃんとたっちゃんさんは本当に仲がいい。華麗な連係プレーで俺を追い詰めてくる。
「……じゃ、お願いします」
「はいはい、お任せあれ」
「……店覚えてないじゃないすか」
「あっ、レオくん反抗期?反抗期ってやつ?これ」
反抗期だと思っているのなら、騒ぐのが逆効果だと気付いていないのだろうか。この人と晩御飯まで一緒かと思うと、既に胃もたれがしてきた。
出がけにばあちゃんがこっそりと「お小遣い、持っていきなさい」と三万円持たせてくれた。甘い。実に甘い。ばあちゃんも、俺も。
たっちゃんさんと並んで歩くと、自分が中腰で歩いているかのように錯覚する。
電車の乗降口や中吊り広告を、のれんのようによけてさっさと歩く様に、長身歴十数年の貫録を感じた。
「レオくんなんでニットっていうか、編み物好きなの?」
「ばあちゃんと、あと母親の影響ですね。母親はニットデザイナーなんで」
「へぇ、サラブレッドじゃん。レオくんもそっち目指してんの?」
無視した。高校中退したばっかの奴に、進路なんか聞かないでくれ。
たっちゃんさんは特に気にする素振りもなく、週刊誌の中吊り広告の文言を見て
「レオくんはさぁ、『汚職事件』が『お食事券』じゃないっていつ気付いた?」
と聞いてきた。
高円寺に来るのは久しぶりだった。慣れないし結構道が入り組んでるから、店を知らないと狙った服にはたどり着けない。たっちゃんさん、本当に大丈夫なんだろうな。
「あー。……あー、記憶蘇ってきた。神よ、古着屋の場所を教え給え」
駅前で、目を瞑り、仁王立ちで呪文を唱える、タトゥーだらけの大男。すぐにでも置いて帰りたい。
「おっけ、思い出した!こっち!レオくん、俺を信じて」
「あ、はぁ、信じる要素今のとこ無いですけど」
「くぅー、辛辣ー。いいよ俺そういうの嫌いじゃない」
「店どっちですか」
こっち!と、小学生のような朗らかさで全身を躍動させて進んでいく。燃費悪そう。
たっちゃんさんは、迷いなく歩き、神の啓示の通り目当ての古着屋に辿り着いた。
店内に足を踏み入れると、店員さんが「いらっしゃいませ、あ、この前の」と言っていた。前回来たのはそうそう前ではないんだろう。「どうもどうも」じゃないんだよ。
静かな店内に日が射し込み、照らされるニットはさらに暖かそうに見える。たっちゃんさんの言った通り、本当に店中ニット、七十年代あたりのものもありそうなラインナップで、そわそわと目が泳ぐ。
「うわ、どうしよ、どこから見よう」
「わぁ、レオくんがテンション上がってる、貴重ー。連れてきてよかったぁ。目がキラキラしてて可愛いー」
たっちゃんさんにかまってる暇はないので、ひとまず端から見ていく。
入口すぐの棚は、平坦な編地の上に、3Dみたいに盛り上がったダイヤ柄とロープ柄の模様編みが詰め込まれた、アランニットのコーナーだった。意外とこういう、教科書みたいなアランニットは探しても売っていない。
その少し奥には、大きな襟付きの、ベージュっぽいアランカーディガン。この大きな襟にボタンとループを足して、襟を立ててハイネックのようにして着たら可愛いだろうな、と思った。鮮やかなナイロン地のショルダーパッチを片側に縫い付けても良さそう。
「良いのあったー?」
と聞かれたので、くだんのカーディガンを羽織って、ここにボタンを付けてショルダーパッチ付けて……と説明したら
「えっすっごいいいね。しかもカスタマイズするんだ、そういうのアリなんだ。似合いそう、絶対買いなよ」
めちゃくちゃ褒められて、たっちゃんさんとの買い物、悪くないかもと思った。
「ねぇこれもレオ似合いそうだよ」
勝手に呼び捨てにすんな、と思いながらたっちゃんさんを振り返ると、その手には、多色編みで、細かい模様がランダムなストライプのように積み重なった、見事なフェアアイルニットベストがあった。
受け取ると、フェアアイルの持ち味の、何度触っても驚嘆する見た目以上の軽さと緻密な編み目。模様の全貌は分からないけれど、これが間違いない品だということは分かる。タグを見ると、フェアアイルの老舗ブランドJAMIESON'S。まあ、そうだろうなとは思った。ますます欲しくなった。
「ねぇ、たっちゃんさん、これ」
「はいはい」
「ここ、何色?」
ベストの襟ぐり辺り、全体のベースとなる部分を指さしてそう聞いた。
「え、何色っていうんだろ、スミクロかな?ちょっと褪せた黒みたいな」
「じゃあ、ここは?」
「これは、ちょっと暗めの赤というか、ワインレッドみたいな」
少しの沈黙の後、たっちゃんさんが言った。
「レオ、色、苦手?」
「うん、黄色系と青系は分かるけど、他はあんまり区別付かない。全体が、多分みんなが言うところの茶色かグレー」
「生まれてから、ずっと?」
「うん、生まれつき」
だから俺には、技術はあったとしても、多色使いが最大の魅力のフェアアイルは編めない。一段一段はシンプルに二色を組み合わせるだけなのに、段ごとに色遣いを変え、気づけば複雑な模様を編み出す。その制作工程は、想像するだけで爽快だ。でも。
「レオ。ここ、上の方は青なの分かる?その中に、赤系の茶色でこの線が描かれてる。その下の段、地のスミクロっぽく見えるんだけど、すっごい暗い赤を使ってて、それがその下の赤色ベースの模様との橋渡しになってて、洒落てるんだよ」
急に、たっちゃんさんが流ちょうに解説し始めた。しかも、単に色名言われるだけよりずっと分かりやすく。
「全体は、赤系の模様と青系の模様の繰り返しなんだけど、赤と青の中間の紫がこことか、こことかに入ってて、対照的な色だけどうまく馴染んでる。ちなみに、こっちのベストは、ベースが薄めのグレーで、茶色とか、抹茶ぽい緑の模様。アースカラーって言うのかな。俺はこのスミクロの方が締まってて、レオに似合うと思うよ」
懇切丁寧に解説してくれているのを聴きながら、たっちゃんさんこんな長い文章喋れるんだぁ…と失礼極まりないことを考えていた。
「じゃあ、こっちにしようかな」
「試着、いいの?ていうか俺が見たいよ、着てるとこ」
「ご試着どうぞ、試着室こちらです」
インナーのTシャツの上から重ね着してみる。
「いいじゃんいいじゃん。普通のシャツでもいけそう」
「……これに、フラップ付きのキャップとか合わせようかな。俺、こういうトラディショナルなやつ着る時、ハズさないと『よそ行き坊ちゃん』になるから」
「はは、自己分析的確!レオ面白いねぇ」
ちょっと笑った後、たっちゃんさんが言った。
「このベスト、俺買ってあげようか」
「えっ、いいですよそんな、理由ないし」
「いいのいいの、連れてきたのも見つけたのも俺だよ?買わせてよ。そしてもっと俺に優しく接して?」
俺を金払わないと笑わない奴みたいに言わないで。
「いやでも、ホントに、ばあちゃんに小遣いも貰ってるし」
「それはとっときなよ。ちょっとお兄さんぽいことさせてよー、俺兄弟いないしそう言うのやってみたいのよ」
これ以上いやでも……を繰り返すと、何か変な感じになりそうだから、潔くお言葉に甘えることにした。アランカーディガンは自分で買った。
青少年の健全な育成に対して意識が高いたっちゃんさんの
「さっさと食べてさっさと帰って、おばーちゃんを安心させましょうね」
という提言に従い、17時半だけど近くのカレー屋で晩御飯を食べることにした。
「ベスト、ありがとうございました」
「急にかしこまるね。全然、いいよぉ」
「あと、デザインの説明も。すげぇ分かりやすかった」
お役に立ててよかったでーす、と言ってたっちゃんさんはお冷をがぶ飲みした。
「ここ俺、出します」
「え、やめて。俺いくつだと思ってんの?ティーンにおごってもらうほど非常識じゃないよ」
本当にいくつなのか教えてほしい。見た目は年齢不詳、中身は無邪気で、捉えどころがない。
「いくつですか」
「当ててみてぇ」
ニッコリ笑って返された。俺は、質問に質問で返されるのが大嫌いだ。一回目だからギリ許す。
「二十五ぐらいですか」
「惜しい」
いくつに見える?の会話に2ラリー以上かけんなよ。二度目はない、と思って黙り込んだ。
「……えっさみしい、聞いてよ。二十八だよ、レオのひとまわり上だよね、たぶん」
「そうですね」
お冷をひと口飲んでテーブルに置いた。
「……あっ、やばいこれ俺が喋んないと仲良くなれないやつだ。俺、達人の達に海で達海。苗字は佐藤。超ふつう。レオは?」
「市原レオです。市原悦子の市原に、レオはカタカナ」
「市原悦子さんレオの世代でも分かるんだぁ、大女優ー」
沈黙。俺は慣れてるけど、たっちゃんさんたぶんこういうの苦手だろうなと思いつつ、沈黙。でも、意外とたっちゃんさんは平気そうで、テーブルの隅にある、球体の占いマシーンをいじったりしていた。
「ねえ、さっきのベストさ、あれどういうやつなの。俺のこのセーターみたいに、解説してよ」
「あー……あれは、フェアアイルって言って、スコットランドのシェットランド諸島の中の、小さい島で編まれてるニットですね。ああいう、カラフルな細かい模様が特徴なんですけど、それ以外にも、使っている毛糸がちょっと変わってて。シェットランドの羊の毛って、柔らかくてしっかり絡みやすいから、ああやって何色も使って細かい編み目で編んで、最後に洗いをかけると、フェルトみたいになって模様が馴染むんです」
「確かに、編み目一体化してたかも。ちょっと見せて」
袋からさっき買った、いや買ってもらったベストを取り出す。
「ほんとだぁ、フェルトみたいだわ」
「古着だから尚更、フェルト化進んでますね。あと、もう一つ大きい特徴があって」
V字の襟元と袖ぐりを指さす。
「ここ、最初は閉じて編むんです。大きな袋みたいに」
「えっ、じゃあどうやって穴開けるの?」
「切ります」
「えっ」
「一度編んだものを、ハサミで切るんです。もちろん、そのために『スティーク』っていう切りしろ部分がありますけど」
「切って、解けたりしないの?!」
「編地がよく絡んでるから、切っても解けないんです。袋みたいに繋げて編むから、脇にとじはぎ……えっと、縫い目みたいなものがなくて、保温性も高いし」
「っはー!よくできてるねぇ」
本当に、よくできていると思う。その地の気候や羊の毛質がうまく生かされている。こんなに目の細かい、柄も細かいニットを編み上げた後、大胆にハサミを入れるなんて発想をした人は、余程肝が据わっていたんだろう。
「レオはこれ、編んだことあるの?」
「俺は……編めない」
黙り込もうかと思ったけど、さすがに失礼だから、ちゃんと答える。
「普通の人でも、これだけの色数使うと、こんがらがると思います。俺なら、なおさら」
そこまで話したところで、料理が運ばれてきた。カレーが付いたりしないように、さっとベストを片付ける。たっちゃんさんは「おいしーね、めっちゃお腹すいてたからほんとおいしー」と言いながら、俺は無言で食べる。
半分くらい食べたころ、たっちゃんさんがメニューを見ながら、ラッシー飲む?と聞くのに続けてこう聞いてきた。
「レオ、さっきの編みたいんでしょ。なんだっけ、名前忘れた」
「フェアアイル」
「そう、それ。編みたいでしょ」
「や、だから」
「一緒に編もうか」
「え?」
「手は貸せないよ、目だけ。毛糸選ぶとか、次この色だよとか、ここまで間違えずに編めてるよとか。何が必要かは、俺編み物したことないし分かんないからさ、そこはレオが指示してよ」
うそ。考えたこともなかった。
誰かと一緒に編む?目を借りる?にしたって、編み目の段数は三桁に達するだろうし、そのいちいちに「この色だよ」なんて教えてもらうのは現実的じゃない。でも少なくとも、色選びに関しては、とても信頼のおける人だということは分かっている。
「編みたい。編みたいけど、どういう方法にすればいいかが」
「まぁ、そこはゆっくり考えようよ。声かけてくれたら俺はいつでも乗るよ、なんかすごく楽しそうだし」
全く、変な人だ。愛想悪い俺のために、こんな見るからに面倒くさそうなことを、楽しんでやろうとしている。この親切で変な人のことを俺はよく知らない、と気づいた。
「あの、たっちゃんさんは、何してる人なんですか」
「あ、俺の店見てなかったか。うちタトゥースタジオなの。彫師さんだよ。刺青彫る人」
編針と違って、ずいぶんと鋭利だけど、俺と同じく、針を持つ男だった
第1話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n9f79b10dce8d
第2話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n656a7baae358
第3話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n0caf87e0d234
第4話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n65d2d34e144c
第5話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n51ad680fcd23
第6話
https://note.com/scrapandbuildai/n/ne06fe62db7a9
第7話
https://note.com/scrapandbuildai/n/na60bc5388cdd
第8話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n533984bffd5d
第9話
https://note.com/scrapandbuildai/n/n9775a74d3f28
エピローグ
https://note.com/scrapandbuildai/n/n5e1ea23137e6
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

