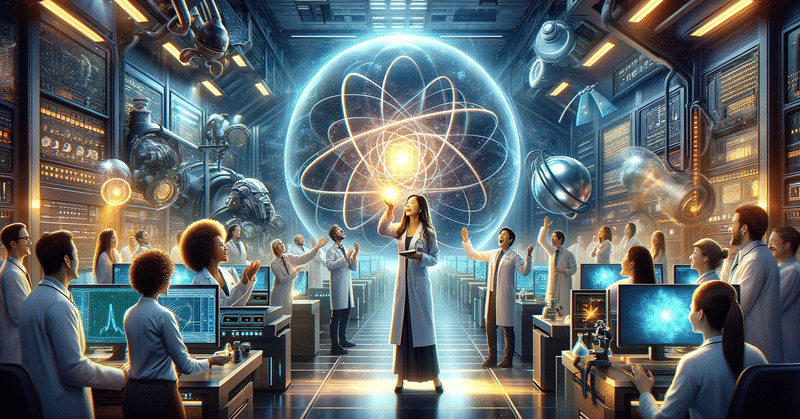
#2.リアルな近未来を描いた「万物理論」(グレッグ・イーガン)
物理学を志したもの、またはSFに興味がある人なら一度は思い描くのが「万物理論」または「究極理論」です。
呼び方はそれぞれですが、要はすべての物理現象を説明する理論です。
そしてそれを題名にしたのがグレッグ・イーガンの「万物理論」です。
オリジナルのタイトルは「Distress(敢えて直訳すると「苦悩や災難」)」で、おそらく直訳だと分かりにくいので、出版社が改名したものと推測しています。
初出は1995年ですが、2023年時点から見ても色あせない重層的な未来ネタが詰まっているので、ぜひ気になった方はポチってみてください。
以降は、ネタバレも含むのでご留意ください。
あらすじ
時代は2055年。アインシュタイン没後100周年記念会議で3人の科学者がそれぞれの万物理論が発表されることに。
それに賛同・反対する組織や会場となった特殊な人工国(無政府)での衝突が絡み合って、最後は万物理論が発表された世界観へ到達する。
みどころ
まずはなんといっても気になるのが、「万物理論」の中身ですね。
現実世界でも万物理論は研究されており、今のところよく聞くのが「超ひも理論」と「ループ量子重力理論」です。
現代の物理学は、我々が直接感じられる重力・電磁気力に加えて原子や宇宙の精緻な研究を可能にした、
・ミクロ(原子サイズ以下)で有効な量子力学
・マクロ(天体のように重いか早い)で有効な一般相対性理論
が二大理論があります。
いずれもアインシュタインが重要な役割を握っており、その没後100年を記念するのは誰もがうなづける設定です。
この2つの理論をなんとか統合しようとしているのが今の「万物理論」への一般的なアプローチと思ってください。
ざっくりですが、図示すると下記のようなイメージです。

物語に戻ります。
3名の科学者による候補理論があり、名称と方針だけ書いてみます。
ヴァイオレット・モサラ:
物語の中核となる女性。無限の位相空間を基にして10次元の空間を設定した理論を展開
ヘンリー・バッゾ:
プレ宇宙から有限な空間を形成するためにいくつかの位相(孤立位相)の測度が打ち消しあうアイデア
ヤスオ・ニシデ:
Originalではヤスコだが京大所属の日本人研究者を意識した設定。病気を理由に会議不参加となったため内容は不明だが、モサラによるとバッゾと同じ発想らしい。
リアルの物理・数学をどこまで従っているのかは正直わからないです。
今の宇宙論を覗いてみると、インフレーションというエネルギー爆発から今でも膨張している、という流れが主流です。(厳密にはまだインフレーションの直接証拠は得られてませんが)
謎なのは、宇宙・星・生物が存在するには、宇宙空間の曲率含めた物理定数(身近だと重力の大きさや太陽からの距離)があまりにも都合がよすぎる値であることです。
ちょっとでも今とずれてたら我々は生存不可能になってしまいます。
それを打破するときに使われる理論の1つが「マルチバース宇宙」、つまりインフレーションは1つでなくポコポコ泡のように多数沸き起こり、そこから都合のよい宇宙がたまたまできて我々がこのように存在・宇宙を観測しているのだ、というものです。
バッゾとニシダは、この偶然を必然に変える理論を作ろうとしている、というのが、万物理論に挑む共通指針らしいです。(これはモサラの意見で、バッゾはその計算過程でミスを犯したとも指摘)
一方モサラのアプローチは、そういったポコポコ宇宙像は持ち出さず、今存在している我々の宇宙が全て(偶然ではない!)と前提を置いて、そこでのマクロからミクロへとつながる橋を「位相」という概念(おそらくはトポロジー的な発想?)を拡張して数学的に紐づけようとしているようです。
これは上述の「ループ量子重力理論」がやや似ているかもしれません。
空間を細切れにしていくと、究極的には「ループ」という数学的構造物の繋がり度合いによって、空間や物質だけでなく時間すらも形成したかもしれない、というものです。
このように、モサラはマルチバース宇宙などのご都合主義を捨て去ったわけですが、皮肉にも物語の鍵となるのがその視点です。
とある変わった思想を持つ団体がストーリー全体を支配します。
それはAnthroCosmology(以下AC)と呼ばれる考えを支持する団体で、直訳すれば「人間宇宙論」という造語です。
ざっくりいうと、人間が理解することで宇宙は存在する、というものです。
これだけ聞くとページを閉じる、または×ボタンを静かに押しそうですが、作品ではリアリティを出すために、ジョン・ホイーラーという実在した物理学者を援用します。
お茶の間では「ブラックホール」という用語を広めた方として有名ですが、「人間原理」を唱えた人でもあります。
※注意:初めて提唱した人として扱われ、作品内でもそのようになってますが、正直創始者かどうかまでは裏付けはとれませんでした。
経緯はともあれ、これをさらに狂信的に発展させたのがACです。つまり、人間が理解して説明可能になったことが世界そのものであるという、魔法の世界です。
ただ、悲劇なことに、これを両極端に解釈した派閥が生まれてしまいます。
1.素晴らしい世界が到来すると信じる派閥(主流派こちら)
2.人類や宇宙すら壊滅してしまうと信じる派閥
ここをどこまで受け入れるかが読者の分かれ道かもしれません。
改めて、マサラの理論によると、森羅万象あらゆるものは最下層でリンクしており、その混合度合いで整理されます。
2にあたるACの反主流派は、マサラが万物理論を完成して世の中を理解し説明することで、それ以外のすべての存在が危うくなる、だったら殺してしまえ、というとんでもない論理を持ち出し最新生物兵器で実行してしまいます。
ところが、マサラは万一に備えて死後その理論を公開する仕掛けを施しており、主人公をはじめとして誰もが万物理論を知ることとなります。
果たして世の中はACの激派の予言通り(マサラ以外)滅在するのか?
その結末はぜひ手に取ってごらんください。
と、万物理論に絞って書きましたが、それよりも現代の社会・個人の在り方への課題提起が目立つ作品でした。
おそらく初めからぶっ飛ぶと思います。
いきなり死後間もない体を強制蘇生して最後の記憶を可視化する(そして失敗してしまう)、という荒業からスタートし、否が応でも個人の死に対する尊厳を考えさせられます。
今更ですが、主人公は映像ジャーナリストという職業で、アインシュタイン会議の映像制作のため現地へ取材をかける設定です。
ところが身体は半分サイボーグで、内蔵された映像記録・AIアシスタント機能を備えています。
そして作品内では、男性・女性でもない第三の性として汎性(原題はasex)という概念も登場させ、性別という意味も考えてしまう、まさに現代の旬なテーマを内包しています。
社会制度でいえば、アインシュタイン会場は太平洋に人工的に作った政府のない国家で、そこではバイオ系特許が治外法権、つまりパクり放題です。
作品全体としては、その人工国(ステートレスと呼ばれます)に住む人々は、世界中から制裁を受けていながらある程度ポジティブに書かれています。マサラも南アフリカからこの地に移住することを望みます。
ここはやや深読みかもしれませんが、国家という単位で特許という知的資産を囲うことの問題点を引き出したかったのかな?と感じました。
万物理論も実はその枠組みを踏襲しており、我々が普段使う「理解」という言葉の危うさを、万物理論による世界のアップデート、というキワモノを出してまで演出しようとすら感じました。
全体に横たわるのは、時代の価値観にとらわれたまさに「Distress」で、作者がタイトルとして選んだのも納得がいきます。
見ようによっては、物理を道具にして、社会や人類の現状の価値観への問いが主役にもとらえられます。
と、若干最後に万物理論という名のちゃぶ台をひっくり返した気もしますが、1つ1つのサブ設定だけでも密度が濃いので、これを1冊に仕立て上げたイーガン、恐るべしです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
