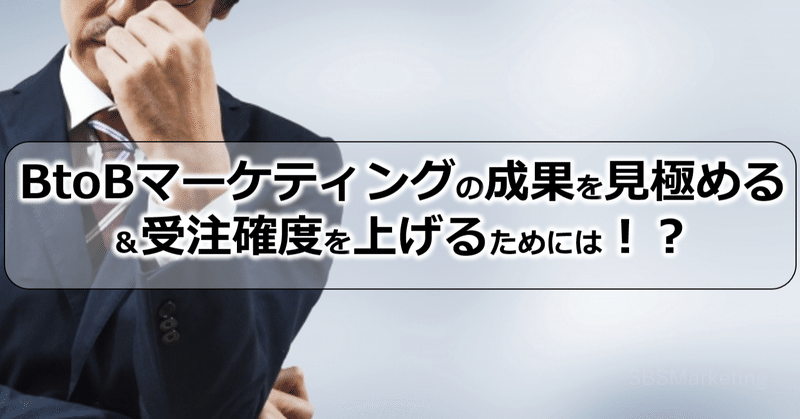
BtoBマーケティングの成果を見極める&受注確度を上げるためには!?
こんにちは。BtoBマーケターです。
私はこれまで中小規模のBtoB事業会社に複数在籍し、マーケティング業務に従事してきました。
その実務経験の中で、疑問に思い直面したこと、試行錯誤したことやその解決策、「BtoBマーケティングあるある」を、noteでまとめていきたいと思います。
今回は、【BtoBマーケティングの成果を見極める&受注確度を上げるためには!?】のテーマでまとめます。
◆BtoBにはBtoBの『購買特性』があります。
さまざまな種類の施策(販売促進・プロモーション)を実施するBtoBマーケティング。
実施後に「この施策の成果はどうだったか」を効果測定すると思いますが、
社内の賞与や昇給に関わる評価で「全く成果が出ていない」と『見誤られる』ケースが発生しがちです。
その原因は、マーケターの活動や資質によるものではなく、多くは『BtoBならではの購買特性』を考慮していないことで起こります。
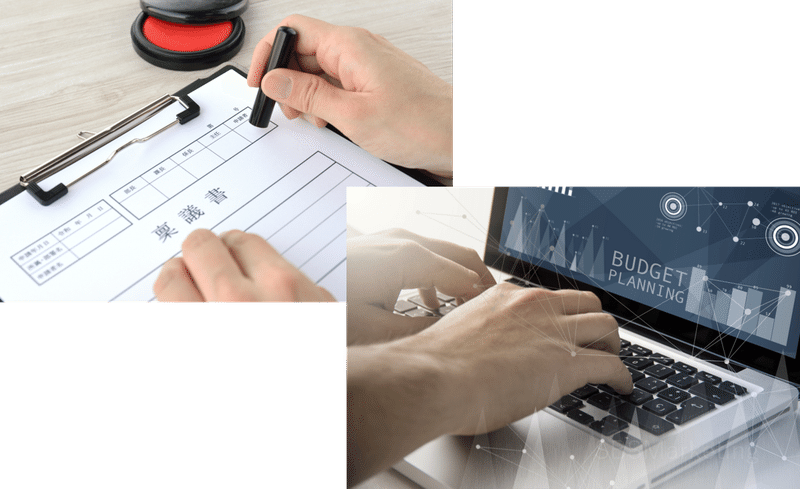
◆BtoBならではの購買特性=稟議文化&期初策定予算の縛り
マーケティング施策の中で、見込み客(リード)獲得目的で実施するのは、オンライン or オフライン広告の出稿、展示会へのブース出展、セミナーの開催、オウンドメディアの運用などが挙げられます。
なのですが、『BtoBならではの購買特性』により、これらの施策で獲得した見込み客(リード)が仮に購買意欲が高かったとしても「今期」に受注となりません。
この『BtoBならではの購買特性』は2つあります。
まず1つ目は、BtoBでは個人のお財布ではなく『企業のお財布』で商品やサービスを契約・導入することになるため、稟議申請をする現場担当者やその上長、情報システム担当や経営層といった社内の複数の意思決定者が関わるため、承認までに時間がかかります。
企業によっては、申請から承認まで数か月かかることもあります。
2つ目としては、事前にその商品やサービスを導入検討していない限り、期初に決める予算策定に盛り込まれてはいないため、契約・導入するのは次年度の予算策定以降、ということになってしまうという点です。
この場合、今年度に諸々を詰め、来年度以降に本格検討、というケースになるのがほとんどです。
つまり、複数名の意思決定者が関わる稟議申請~承認ルールによるタイムラグと期初に決める策定予算の縛りにより、(高額であればあるほど)早くて相手企業の次年度、もしくは予算調整などによって契約・導入までに数年単位で時間がかかることが多いため、今期中に受注するということには到底ならないわけです。
ただし例外があります。それは『緊急性』を要する商品・サービスの場合です。
「この商品(サービス)が無いと業務が滞ってしまう」といったような必要不可欠なモノであれば急いで別枠で予算が組まれ、稟議承認も別次元のスピードで進むことになります。
ですが、緊急性のある商品やサービスを取り扱っている企業ばかりではないので、該当するケースはそれほどないかと思います(煽って緊急性をチラつかせる手もあるかと思いますが注意が必要です)。
この2つの『BtoBならではの購買特性』があるため、①稟議が承認されやすい提案、②相手企業の予算策定の時期を見定める、といった活動が必要となります。
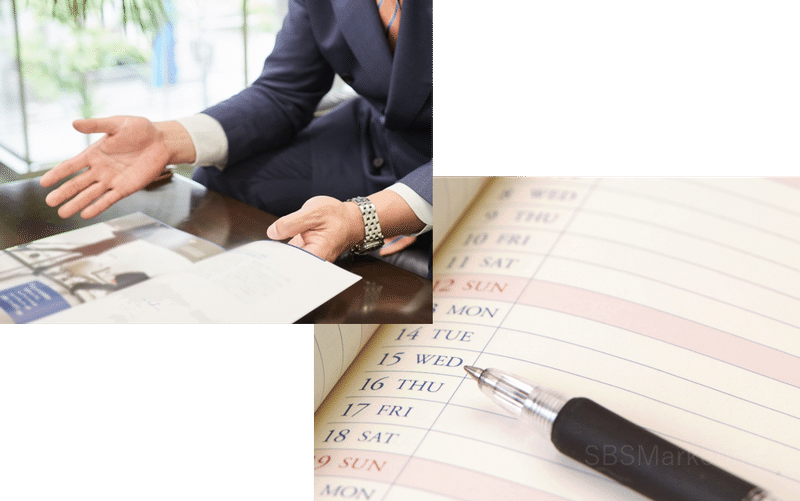
◆『BtoBならではの購買特性』を踏まえた受注確度アップ方法
①稟議が承認されやすい提案という観点では、稟議承認に関わる相手企業内の意思決定者が誰なのか・何名程度いるのかを情報として得ておくことが理想ですが、社内のことですので中々開示してくれないかもしれません。
もし把握できるようであれば、「現場担当者向け」「担当の上長向け」「情報システム部門担当向け」「経営層向け」の提案書、もしくはそれぞれに向けた導入メリットを提案書内に盛り込むことで、稟議承認に弾みがつく可能性が高まるはずです。
また、②相手企業の予算策定の時期を見定めるという点も、社内のことですので中々開示してくれないかもしれませんが、情報を把握することで、自社側の準備や見込み時期が立つので大きなメリットになります。
今期がNGだとしても来期の予算策定案に盛り込んでもらって、来期以降の検討確度をより明確にできるはずです。
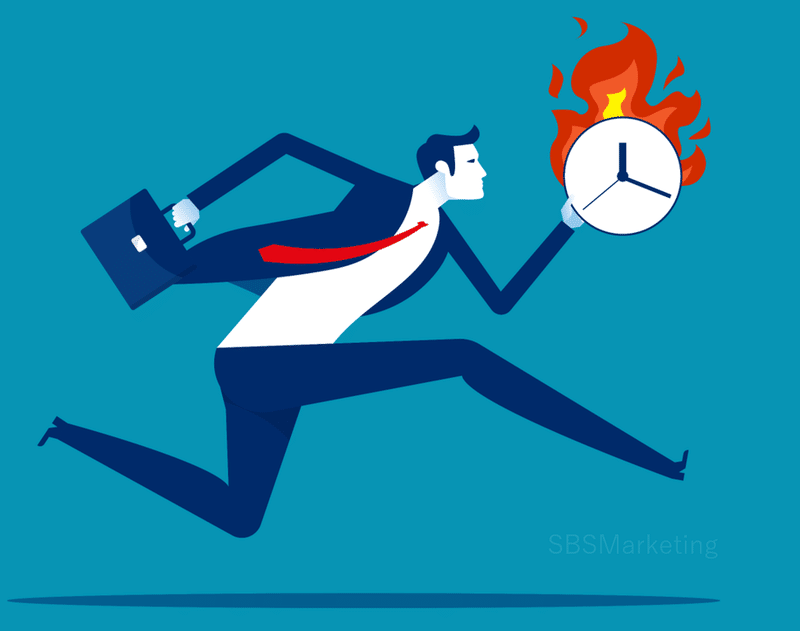
◆自社商品やサービスの『リードタイム』を把握しましょう
冒頭の「マーケティング施策の全く成果が出ていないと見誤られる」に戻りますが、BtoB領域では、これらの特性により契約・導入までに数年単位で時間がかかってしまいます。
なので、ビジネス特性を考慮した上で施策の成果や社内の評価をしていれば『見誤る』ことはなくなるはずです。
ですが、「BtoBなのでリード化してから受注までには数年単位の時間がかかって当たり前ですよ」とマーケティング側が伝えても、ある種の『言い訳』に聞こえてしまうこともあります。
そこで(理論武装というわけではないですが)マーケティングとしても、自社の商品・サービスの『リードタイム』を把握しておくべきです。
『リードタイム』というのは、物流業界において、商品の発注~納品までの生産や輸送などにかかる時間のことを指します。
この考えを転用して、見込み客(リード)の獲得から商談、受注までの期間を『リードタイム』と呼ばれています。
正直なところ、「この業種企業のリードタイムは〇年」「この業種企業は△年」と明確に区切ることはできません。稟議承認フローや予算策定時期・予算の融通性(例:トップダウン型経営)など企業それぞれが抱える変数によって異なるからです。
なので、リードタイムはあくまで『目安』として考えることが必要です。
とはいえ、「この商品(サービス)のリードタイムはおおよそ□年」という目安が在るのと無いのとでは雲泥の差です。
事業会社に在籍していた際、リードタイムを目安としても社内で把握していなかった時期があり、「いつ頃受注できるのかわからない」中でマーケもセールスも活動していたので、暗中模索な気持ちで進めていた経験があります。。
※また当たり前ですが、リードタイムはマーケティングだけでなく、案件をクロージングするセールスも経営陣も把握しておくべきことです。

◆リードタイムの算出方法と精度を高める方法
リードタイムの算出方法は、これまでの受注実績をベースにするのが良いと思いますが、欲を言うと、「〇〇サービスの特定業種」、「〇〇サービスの特定のリード流入経路」ごとに平均期間を算出できると、マーケティングの活動と受注時期の目安が紐づきますし、セールスや経営陣も一定の確度を持って先を見据えた活動を行うことが可能になると思います。
次にリードタイムの情報精度を高める方法ですが、下記が挙げられます。
・インサイドセールス部隊が接触する
:案件をクロージングする(フィールド)セールスは多忙になりがちです。
そのため、1見込み客ごとに相手企業の受注に向けた情報を得るためのフォローをすることは難しくなるので、インサイドセールス部隊がその時点での検討状況、対象の相手企業の稟議ルールや予算についてヒアリングすることで、より受注に向けた流れが明確になります。
・システムやツールを導入する
:相手企業・リードに関する情報や案件の進捗状況を管理・共有するためにCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理システム)を導入したり、メール配信による関係性強化、トラッキング機能によるWeb来訪などのデジタル情報を得られるMAツール(Marketing Automation:マーケティング活動自動化ツール)を導入することでより受注への道筋がクリアになり、アプローチ効率もアップしやすくなります。

◆まとめ
少し長くなってしまいましたので総括しますと、事業会社では「今期の評価は今期の成果」で見ることが多い傾向があります。
ですが、BtoBの場合は実施した施策の成果は来期以降に出ることが多いため、BtoBの購買特定を考慮した評価などの設計をする必要があります。
そして、受注に向けての活動としては、相手企業・リードと接点を持って稟議ルールや予算策定などの情報を得つつ、検討確度が上がるための関係性の強化をじっくり行い、受注までのハードルを取り除くような提案をタイミングを見計らって実行する。
また自社としては、見込み客化から受注までの平均期間である『リードタイム』を社内の各部門で把握・共有し、インサイドセールスなどによるフォローで受注に至るまでの関連情報を獲得、CRMによる案件情報の管理や、MAツールによるデジタル情報の獲得をすることが大切になります。
BtoBマーケターより。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
