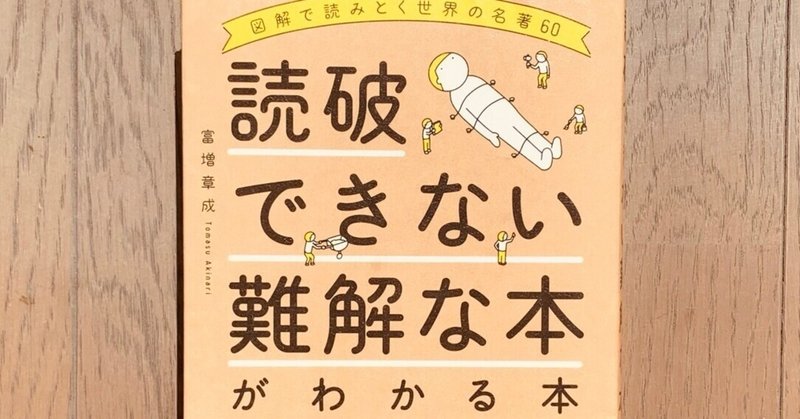
【読書録】『読破できない難解な本がわかる本』富増章成
今日ご紹介するのは、富増章成(とます・あきなり)氏の、『読破できない難解な本がわかる本』(2019年3月、ダイヤモンド社)。副題は、『図解で読みとく世界の名著60』。
その名のとおり、難解で読破困難な古典など60冊の名著を、1冊につき見開き2ページ×2=4ページで易しく解説してしてくれる。本のダイジェスト本だ。
全体を通じて、シンプルな語り口や、ポップなイラストで、難しい名著のざっくりとしたエッセンスを分かりやすく紹介してくれる。
また、「ひとめでわかる名著の関連図」において、60冊の本の相関関係を、見開き2ページのチャートでコンパクトに図解してくれている。ビジュアルなチャートなので、頭に入りやすい。
著者の富増章成氏は、予備校講師。河合塾やその他大手予備校で「日本史」「倫理」「現代社会」などを担当されているとのこと。歴史、哲学、宗教などを、読者に身近な視点で解きほぐすことで定評があるらしい。中央大学文学部哲学科を卒業後、上智大学神学部にて学ばれたとのこと。
名著を学んでこられたアカデミックなバックグラウンドと、受験生たちに難解な概念をわかりやすく解説する職業上の説明力。この2つを併せ持つ著者だからこそ書ける本だ。
まず、「はじめに」に書かれていた、次のメッセージに、とても嬉しくなった。これを読めただけでも、この本を手に取った甲斐があった。
…「名著」の多くは、とても難解で、それでいて分厚いものが多いです。しかし、名著が難解なのには、実は理由があります。分厚い古典的「名著」は、その時代背景と常識を前提として書かれているので、多くの場合、現代の私たちにとっては説明不足なのです。また、その学問世界の専門用語を「知ってるんでしょ?」という前提のもとに書かれていますから、こっちはわかるわけがない。
「名著」は、下手をすると一冊をしっかりと理解するのに20年以上かかります(それでも、さらに疑問は増えていきます)。普通に生きて普通に暮らしている私たちには、そんな時間はありません。つまり、「名著」とは基本的に「読破することができない本」なのです。(p3)
「本書の使い方」というくだりでも、迷える子羊たちへの優しいアドバイスが書かれている。
それから、ちょっとしたアドバイスです。本書のようなダイジェスト版を読んだあと、すぐに原点へとジャンプするまえに深呼吸しましょう。
「ショーペンハウアーは人生の苦しみについて書いているのか。もっと知りたい。じゃあ、原典の『意志と表象としての世界』を読むぞー!」というのは、あまりおすすめできません。紹介されている難解な「名著」に興味が出たら、新書などの解説書に進むのです。そうやって、ダイジェスト版からより専門的な概説書へ、余裕があれば、原典に向かうという段階を踏みましょう。くれぐれもジャンプしすぎないように。
名著とは、読破できない本である、と、ズバリと言ってくれている。これは、大学(特に文系学部)で、研究の一環として古典を解読する苦労を経験したことのある人にとっては、救いの言葉だろう。
20年以上前、私も、大学で、古典を原書で少しずつ読む授業を受けたことがある。膨大な時間を使って少しづつ読むのだが、なかなか頭に入らず、ちんぷんかんぷんで、はっきり言って苦痛だった。
そのような苦労が全く無駄であったとまでは思わない。また、そういう苦労がイヤだという学生は、レベルが低いと見なされ、大学で学ぶに値しない、と言われるかもしれない。
しかし、もし私が、その当時に、こういうダイジェスト本に出会っていたら、名著を読むのが苦痛ではなくなっていただろう。むしろ、知的好奇心の刺激になり、もっともっと研究意欲が湧いていたのではないかと思う。
本書で取り上げられているのは、以下の60冊だ。
第1章 古代からの叡智を知ることができる本(9冊)
プラトン『ソクラテスの弁明』
アリストテレス『形而上学』
『旧約聖書』『新約聖書』
キケロ『老境について』
『論語』『孟子』
『老子』『荘子』
『朱子語類』
『真理の言葉(ダンマパダ)』
『般若心経』
第2章 考えに考えて人生を変える本(8冊)
フランシス・ベーコン『ノブル・オルガヌム』
ルネ・デカルト『方法序説』
ジョージ・バークリ『人知原理論』
バルフ・デ・スピノザ『エチカ』
エマニュエル・カント『実践理性批判』
アルトゥール・ショーペンハウアー『意思と表象としての世界』
エドムント・フッサール『現象学の理念』
ゲオルグ・フリードリヒ・ヘーゲル『歴史哲学講義』
第3章 悩める人生について考えることができる本(9冊)
ゼーレン・キルケゴール『死に至る病』
フリードリヒ・ニーチェ『ツァラトゥストラはこう言った』
ウィリアム・ジェイムズ『プラグマティズム』
カール・ヤスパース『哲学』
エマニュエル・レヴィナス『全体性と無限』
マルチン・ハイデガー『存在と時間』
ジャン=ポール・サルトル『存在と無』
ブーレーズ・パスカル『パンセ』
アラン『幸福論』
第4章 現代の政治思想とその起源がわかる本(10冊)
マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう』
トマス・ホッブズ『リヴァイアサン』
ニッコロ・マキャベリ『君主論』
ホルクハイマー&アドルノ『啓蒙の弁証法』
エーリッヒ・フロム『自由からの逃走』
ハンナ・アーレント『全体主義の起源』
ジェレミー・ベンサム『道徳および立法の諸原理序説』
ジャン=ジャック・ルソー『社会契約論』
ジョン・ロールズ『正義論』
カール・フォン・クラウゼヴィッツ『戦争論』
第5章 仕事と生き方がよくわかる本(7冊)
アダム・スミス『国富論』
マックス・ウェーバー『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
ジョン・スチュアート・ミル『自由論』
トマス・ロバート・マルサス『人口論』
カール・マルクス『資本論』
ジョン・メイナード・ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論』
トマ・ピケティ『21世紀の資本』
第6章 人の「心」と「言葉」について考えてみる本(6冊)
ジグムント・フロイト『精神分析入門』
カール・グスタフ・ユング『元型論』
アルフレッド・アドラー『人生の意味の心理学』
ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』
フェルディナン・ド・ソシュール『一般言語学講義』
ミッシェル・フーコー『狂気の歴史』
第7章 現代社会を別の角度から考えてみる本(6冊)
マーシャル・マクルーハン『グーテンベルクの銀河系』
ジャン=フランソワ・リオタール『ポストモダンの条件』
ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』
ヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代の芸術』
トーマス・クーン『科学革命の構造』
ジル・ドゥルーズ&フェリックス・ガタリ『アンチ・オイディプス』
第8章 日本の思想をふりかえって自分を知る本(5冊)
空海『三教指帰(さんごうしいき)』
唯円(親鸞の弟子)『歎異抄(たんにしょう)』
道元『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』
新渡戸稲造『武士道』
西田幾多郎『善の研究』
以上のとおり、誰もが名前くらい聞いたことのある名著が、多く含まれている。
これから名著を学んでいく、学生さんたちへ。興味があったけれども、難しそうで敬遠していたものや、課題などでいずれ読まなければいけないものが、この中にあれば、ラッキーだ。是非、著者による、「目から鱗」の解説を読んでみてほしい。
そして、私のように、名著に苦手意識のある、大人の皆さんへ。リベンジのチャンス到来だ。人生100年時代となった今こそ、こういう本のサポートを得ながら、名著の世界観を自分のものとする、知の旅へ出かけてみるのはいかがだろうか。
この本が、少しでも多くの方にとって、楽しく名著を学ぶきっかけになれば嬉しい。
ご参考になれば幸いです!
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
