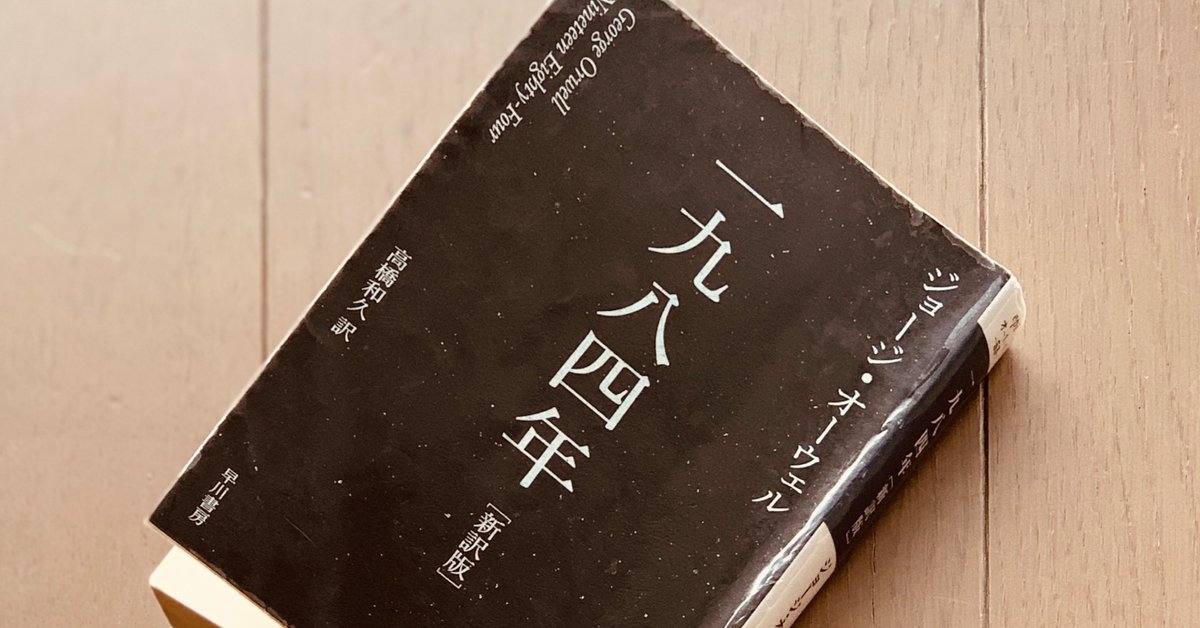
【読書録】『一九八四年』ジョージ・オーウェル
1949年刊行。イギリス人ジョージ・オーウェルによる、ディストピア小説、『一九八四年』。冷戦下の英米でベストセラーとなった、大変ショッキングな作品。
「全体主義」や「管理主義」という文脈で引用されることも多い。2015年の公開の、ジェームズ・ボンドシリーズの映画『007 スペクター』でも、監視社会についての会話で、彼の名前が言及されていた。
(※以下、ネタバレご注意ください。)
国民の生活が当局により、常時監視されている。国民が自由な思考を持つことが厳しく禁じられ、違反者は世間から存在を抹消され、拷問にかけられる。歴史が現体制に都合よく改ざんされ、国民の記憶を消し去る。公用語から語彙を消してゆき、国民の思考力を奪う。戦争を続けることにより、困窮状態を維持して、政府の管理体制を継続させる。
「思考警察」「思考犯罪」「二分間憎悪」「反セックス青年同盟」「ニュースピーク」「イングソック」「二重思考(ダブルシンク)」「二足す二は五」「真理省・平和省・愛情省・潤沢省」「戦争は平和である・自由は服従である・無知は力である」・・・・・・
これらのような、ショッキングな概念をこれでもかというほど取り入れ、管理主義的な世界観を恐ろしくリアルに描いている。その想像力の豊かさには脱帽である。
第3部は拷問のシーンなどが多く、読み進めるのがつらかったが、第1部から第2部にかけては、国家による管理主義がどれほど恐ろしくなりえるかということが強烈に伝わってきた。
そのフィクションの世界を恐ろしいと感じながら、現実の世の中でも、政府やマスコミなどによる世論操作などには十分気を付けておく必要があると思った。
また、さんざん恐怖をあおっておきながら、労働者階級の一般市民が世界を変えることもできる、という希望のメッセージが織り込まれていたのも興味深かった。
「ニュースピークの諸原理」という附録と、トマス・ピンチョンの解説も、それぞれ読み応えがあった。
とにかく考えさせられる小説だった。これを読んでおいてよかったし、また時々読み返すべき作品だと思った。
最近、個人のデータがIT技術やAIによって容易に管理されたり、解析されたりするようになってきているが、さらにこの傾向は続くだろう。そうすると、この作品に描かれている監視社会が現実のものとなることも、もしかしたらあり得るかもしれない…。そう思うと、ちょっと怖い。
ご参考になれば幸いです。
この記事が参加している募集
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
