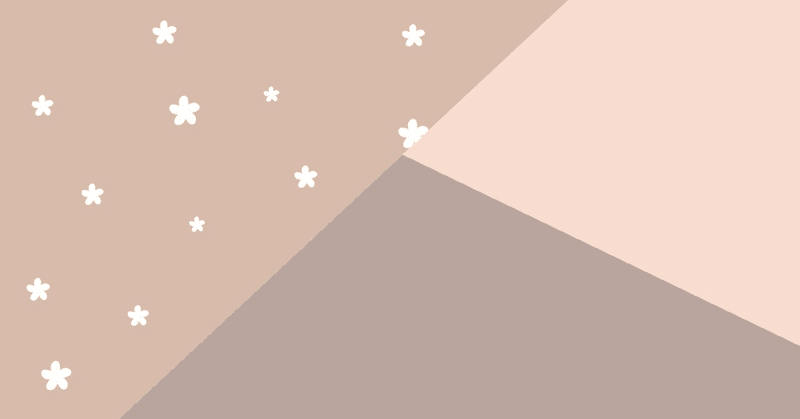
【短編小説】ぬるいプリン
落とした気分を拾ってもらって、冷めた身体を温めてもらって、私はどんどん彼にのめり込んでゆく。
この遣る瀬無い感覚にすら、恋は私を酔わせてゆく。
エレベーターの中は、いつも無言だ。
さっきコンビニで買ったプリンが入った袋が、微かに揺れている。その音が耳に障るくらいの静けさ。
だけど手を繋いでいるのだから、間を持たせる言葉は必要ないのだ。
部屋に入ると彼は、いつも通り先にお風呂を譲ってくれた。だけど彼は知らない。身体の隅々まで完璧に綺麗にした私が、広いベッドに薄着でたった一人で、彼を待つ時間が苦手だということを。
彼がいなきゃ寂しくて仕方がないダメな私を、ほかほかに温かい私を、甘ったるいボディーソープの匂いがまだ残っているうちに、ベッドに辿り着いたその瞬間に抱きしめて欲しいのに。
しかし寂しさごと布団に包まった束の間の憂鬱も、彼によっていとも簡単に晴れてしまう。
布団の中の新しい温もりと、わたしと同じ安い匂い。
「寂しかったの?」
「うん」
「僕のこと待ってたの?」
「うん」
首筋に湿った温もりを感じる。
音を立てた小さなキスが、肩へと降りてくる。
私の前に回された彼の手が、薄いルームウェアの紐を解くのを感じた。
私はゆっくりと、夜に溶けてゆく。彼とふたりで。
恋をすると気が緩み過ぎてダメになってしまう類いの人間が一定数いるのだとしたら、私はもれなくその一人だ、なんて頭の片隅で思った。
ホテルの部屋の決め手はいつも「広いテーブルがあるか」だった。同じ部屋で抱き合い、大学の課題もする。そのアンバランスな付き合いが私達の普通だった。なにせ二人とも実家暮らしで、落ち着いて二人でいられる場所は限られている。ホテルは二人にとって、「1日借りられる便利な部屋」なのだ。
彼は同じ授業を受けていて、偶然隣の席になって知り合った。授業中の些細なやり取りを繰り返し、それからは自然と今日も隣の席を選んで貰えるかと、期待しながら過ごすようになっていった。
「来週のテスト勉強、一緒にやらない?」
そんな声がかかった、とある放課後。
カフェで勉強していたはずが会話は弾み、気づいたら終電間際になっていた。別れ際が名残惜しくて入ったホテルの、暖房の効きすぎた暖かい部屋で、彼は私のことが好きなのだと言った。
私も、と答えた。なんの迷いもなく。
「今、何考えてんの」
授業用のプレゼンを作成している彼が、パソコンから手を離さずに言う。さっきおやつのコンビニプリンを食べ終えたばかりだ。昨日冷蔵庫に入れ忘れてお風呂に入ってしまった。ぬるいプリンはあまりにも甘かった。
「告白された日のこと」
「私、今では君がいなきゃ寂しくなっちゃうの」
「僕がいつでも会いに行くよ」
二人きりだから、学校のある明日からはほんの少し遠ざかっている。そんな気がするだけだけど。
多分、勉強に疲れたらまた抱かれるんだろうな、と思った。それまでもう少し頑張ろうかな。存分に恋に溶けている分、タスクはなんとかこなさなきゃいけない。
「ねえ、僕そろそろ休憩したい」
キスで呆気なく崩れるさっきの覚悟。
プリンの残香が、鼻先をくすぐった。
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
