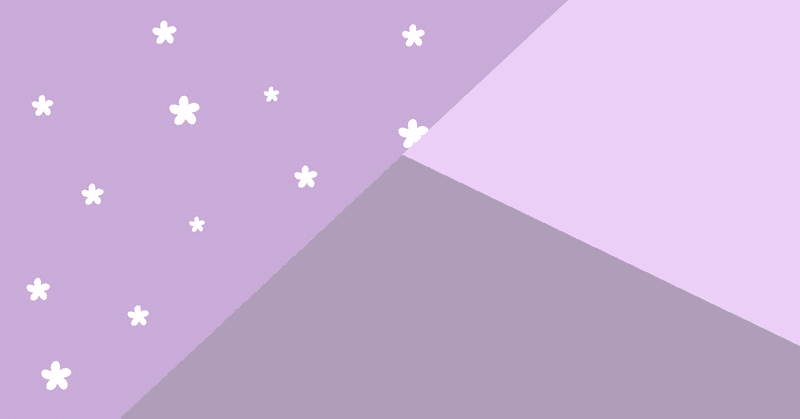
【短編小説】冷たい人形
「お願い、ドアは閉めて」
彼女がこれを言うのは多分100回目だし、僕がほんの数センチだけ残して寝室のドアを閉めるのも多分100回目だ。怖がりな彼女は隙間があると落ち着かないのだと言う。理由は誰かが簡単に入って来れそう、というものだ。実際寝室のドアに鍵はついていないのだから、少しくらい開いていても 誰 か が入って来るとしても大した違いはないと僕は思う。けれどもあの数センチを埋めるだけで彼女が安心して眠れるのなら、200回目を言われても、面倒くさがりな僕でも癪には触らないはずだ。200回も忘れる僕も僕だけど。
僕の家に彼女が越して来て4ヶ月ほどが経つ。不眠気味だった僕の空っぽの夜が、彼女の寝顔でぴったりと埋まるようになった。視界には穏やかな彼女の寝顔、機械のように規則正しい寝息と、それに伴って上下する胸。寝ている彼女は僕を苦しくさせる。ある時には幸福感で。しかしほとんどは孤独感で。だって僕には到底信じられないのだ。朝は半ば踊りながら楽しそうに洗濯物を干す(機嫌がいいと鼻歌まで歌うのだ)彼女が、夜にはまるで人形のように動かなくなってしまう。もしも、この白い肌の柔らかさがゴムだったなら。手入れされた真っ直ぐな髪が糸だったなら。おはようの声を二度と聞けなかったなら。そのとき僕はきっと、その隣に横たわるもう一体の冷たい人形になるだろう。
やがて長い夜には終わりがくる。
僕を包み込んでいた静けさのシャボン玉みたいなものが、突然弾けるようにして消える。朝の光が感じられ、人形の寝息以外の音が耳に触れる。猫のキヌアが起こしに来るのだ。彼女のお腹の上の布団を何度も踏んで。それでも起きないと、キヌアはミャアミャアと鳴いて前足で彼女の鼻をグイと押す。そうして寝室に朝がやって来る。
塩揉みをした薄切りのキュウリとハムをパンに乗せ、マヨネーズと黒コショウを振る。それとヨーグルトにはちみつをかけたものが僕たちの朝食となった。彼女はパンを半分しか食べられないので、残りは僕が食べる。
「これ美味しいわ。今日もご飯ありがとう」
彼女は毎朝必ずありがとうと言う。僕はお粗末様です、と毎朝返す。本当は朝に弱い彼女が少しでも元気に一日を始められる献立選びに日々悩んでいるのだけど、彼女がこれを知ることは多分無いだろう。
彼女が仕事に行くと、僕は家での仕事を始める昼まで睡眠をとる。彼女が無事に目を覚まさないと不安で眠れない僕の、少ない睡眠の時間だ。彼女の匂いが残ったベッドの、”彼女側”で寝る。そこにキヌアがやって来るので、ふくふくに丸い温もりを抱く。
僕はもはや彼女と出会う前、一体どうやって生きていたのだろう。いやむしろ、彼女と出会う前の方が生きている心地がしていたのかもしれない。今となっては彼女の生活サイクルに振り回され、彼女ひとりの為に生きている。
人形になってしまったのは僕の方かもしれない。皮肉なことに彼女が仕事に出て行った瞬間から人間らしい欲望を感じられるのだから。
昼間、僕は起きるとファストフード店で昼食をとりつつ作業を進めた。帰り道にスーパーに寄り、夕飯の食材を買う。家で仕事ができるので、わざわざ外出する予定を作らない限りは外に出る機会がない。だから、散歩と仕事を兼ねているファストフード店での時間は大切なものだ。一人で上手に生きられているような気がして。そして今日は薬局へ行くという、大事な予定をもう一つ作った。人形はもう、見たくない。
夜、僕は昼間に買った薬を一つ、飲んだ。
人形と過ごす時間には終止符が必要だ。
ブニブニした何かに鼻を潰されて目が覚めた。瞼を開けるとキヌアと目が合う。カーテンから漏れる光が眩しい。しかし、ベッドの彼女側は冷たい。
混乱したままリビングへ行くと、コーヒーの深い香りが鼻をくすぐった。テーブルには焼き目の濃いトースト、マーマレード、ヨーグルトにバナナが置いてある。
「おはよう。あんなに気持ち良さそうな寝顔初めて見たわ」
よく眠れたのね、とソファでキヌアを撫でる彼女がいる。
ああ、眠れたのだな。そう思った。そう思えて幸せだと思った。ちょっといい?僕は彼女を抱き寄せた。温かな両腕が僕を包んだ。
ああ僕もちゃんと夜を生き抜いたんだな。
よかった。君が人形じゃなくて。
サポートいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
