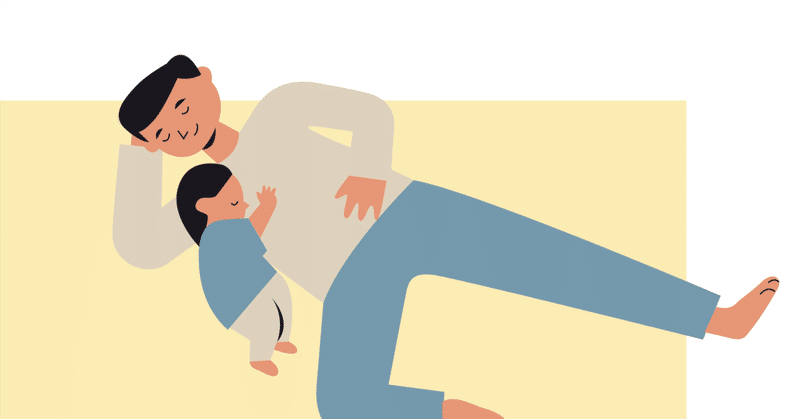
初のワンオペ育児(約2日間の行動振り返り)
10月に取得した1ヶ月の育休期間を過ぎ、11月から通常業務に復帰しています。
人手が足りない部署なので、「育休」と言いながらもほぼ毎日何かしらの連絡が来たり、打ち合わせに参加したりと所謂「タダ働き」がありましたが。。子どもと「あーうー」とか「ブブブ」といった会話が日中メインであった自分としては、仕事の連絡が来るのはちょっとした息抜きになっていました。
(そんなに仕事大好き人間では無いはず・・・)
仕事と育児をしながら過ごす日々が戻ってきたところで、先日はじめての「連日ワンオペ育児」に臨みました。僕が出張や実家の用事による外泊で、妻にワンオペをお願いしてしまう機会は何度かありましたが、その逆は初。
今回はその行動を振り返ろうと思います。期間はタイトルに書いていますが、約2日間(1日目の昼前から2日目の晩まで)です。子どもは明日で生後5ヶ月を迎えます。
【1日目 - 一番の不安は「入浴」】
時は11月24日(金)。前日の祝日(勤労感謝の日)と翌日の土曜日に挟まれた週末で、有給を取得して準備。妻は10時台に出発していきました。
この日の子どもは↓のような行動履歴でした。
7時35分:起床
8時45分:1回目のミルク(180ml)
10時20分:午前のお寝んね
11時55分:起床(1時間35分のお寝んね)
12時35分:2回目のミルク(210ml)
14時30分:午後のお寝んね
16時35分:起床(2時間5分のお寝んね)
17時00分:3回目のミルク(220ml)
19時10分:お風呂
20時05分:4回目のミルク(180ml)
22時15分:5回目のミルク(90ml)
22時20分:就寝(翌日までぐっすり)
ミルク:5回(計880ml)
睡眠時間:13時間
この日は「ミルクを飲むたびにウンチをする」1日でして、おそらく過去最多の1日6ウンチでした。2~3日に1回しか出ない子もいると聞く中で、うちの子は快便すぎやしないか?と不安に。便の色や形状に異常は無さそうなものの、お尻が荒れないかが心配どころです・・・。
不安に思っていたワンオペ入浴は、↓の流れで対応してみました。
①脱衣所にバウンサーを置き、子どもをそこに寝かせて浴室を掃除。
(ちょいちょい扉を開けて姿を見せたり、浴室から声を聞かせたり)
②お湯はり後、リビングと近くの洋室のエアコンを稼働。
廊下を少しでも温かい状態にしておく。
③脱衣所に「自分の着替えとバスタオル」、「子どもを包むバスタオル」を
用意。まずは自分が脱衣し、入室。急いで身体を洗いきる。
(この時も扉の外にいる子どもの声を傾聴しながら、度々声を聞かせる)
④洗体後、サッとバスタオルで身体を拭いて一旦退室。
子どもを脱衣させ、バウンサーにバスタオルを敷き、一緒に再入室。
子どもの身体を洗いきったら、一緒に湯船に浸かって身体を温める。
⑤退室後、バスタオルが敷かれたバウンサーに子どもを乗せて、包む。
リビングへ運ぶ前に自分の身体を急いで拭き切り、
上半身インナー1枚、下半身はタオル(いわゆるノーパン状態)で
子どもをバウンサーから抱き上げ、リビングに移動。
⑥保湿クリームや塗り薬を施し、ベビーベッドに一旦寝かせる。
風呂上がりのミルク欲求に備えてお湯を沸かしつつ、浴室まわりの
後片付けと自身の風呂上がりケアを施す。
初日は脱衣所がびちゃびちゃになりました。自分の身体を拭いて子どもを抱えるまでの時間は、ついつい焦ってしまいますね。2日目は追加でバスマットを敷いておいたり、前日の経験があったりで多少は改善できたものの、今まで「2人1組で行っていた子どもの入浴」が、1人だとこうも高難易度に感じるとは。と思いました。
晩ご飯も落ち着いて食べにくく(すぐに抱っこを要求してくる)、後半は流し込むようにして完食。寝る前のグズリが最近一番手を焼くので、何とか22時台に寝かしつけたところで一緒に寝ました。自分が寝る直前にグズられるのは精神的にもダメージでかいので、早めの就寝です。
ちなみに、この日は18時台に仕事でヘルプの連絡が来まして、1時間ほどフォロー対応していました。子どもを抱っこしながら、有給時に仕事。業界的なものもありますが、「この人に聞かないと何とかできない」という状況は子どもの有無に限らず、組織的に改善していかないといけないですね。
【2日目 - 妻の帰宅を待ちわびながら過ごす】
2日目の履歴は↓です。
6時20分:起床
6時45分:1回目のミルク(170ml)
7時45分:二度寝(子どもだけ)
8時25分:起床(40分のお寝んね)
10時10分:2回目のミルク(150ml)
10時45分:午前のお寝んね
13時15分:起床(2時間30分のお寝んね)
13時35分:3回目のミルク(220ml)
15時20分:午後のお寝んね
17時00分:起床(1時間40分のお寝んね)
17時20分:4回目のミルク(160ml)
19時10分:お風呂
19時45分:5回目のミルク(150ml)
22時25分:就寝(翌日までぐっすり)
ミルク:5回(計850ml)
睡眠時間:12時間45分
約8時間の睡眠を経て、ちょうど朝陽が昇っていってるところで子どものグズり声を聞き、起床。せっかく早起きしたものの、子どもから目を離すわけにはいきません。朝の情報番組を見ながら、午前をゆっくり過ごしました。
昨日はお散歩に行ってなかったので、今日は午後にでも外出しようかなと思っていたところ、午後もあっさりとお寝んね。自宅でヴィッセル神戸の試合や大相撲を見て過ごしていました。この日はとても寒いと予報で聞いていたこともあり、無理に外出させて風邪を引かすようでは本末転倒。見事なインドア生活でした。
そして、妻が21時台に帰宅。子どもも安心したのか、しばらくウニャウニャした後に眠ってくれました。長いようで短い2日間でした。
【総括】
かなりザックリとした振り返りではありますが、初めての連日ワンオペ育児を体験して思ったことを下記に纏めてみます。
《振り返り① 普段から育児をしていて良かった》
何を当たり前な。と思われるかもしれませんが、これは大前提ですね。
普段どういったことをしているのか。必要なものや注意すべきことは何かを把握し、自身で実行している経験は欠かせません。
「子どもが泣いているけれど、何が理由で泣いているのか分からない」という状態は、子どもにとっても、お父さんにとっても辛い時間です。
普段から子どもの泣き方を見ておくことで、何を欲しているのか僅かな違いですが、推察できるようになってきます。また、普段からログを付けておくことで凡そのルーティンが見えてくるので、そこから予測することも軽減させるポイントだと思います。
また、普段は母乳とミルクの混合ですが、この2日間は基本的にミルクのみでした。これが却って、1日の傾向と翌日の予測が立てやすかったです。母乳の方が子どもも落ち着いて眠りについてくれやすいものの、「結局どのくらいの量を飲んだのかが、数値として可視化しにくい」のが個人的な悩み。
それを可視化できる要素で管理することによって、以降の行動予定を変更・調整しやすいようにしておけたのは助かったなと思いました。
《振り返り② 子どもがパパを好いていて良かった》
これは個人的に大事な点かなと思いました。同じことをしても「ママが良い」「ママで無いと嫌だ」と泣く子どももいると思います。
嬉しいことに、我が子は僕がいる方をいつも目で追ったり、抱っこするとすぐ落ち着いたりする子です。在宅で仕事をしている時も、休憩の合間に顔を見せては抱きしめているくらい我が子が好きですし、子どもも僕の姿を見るとすごく嬉しそうに笑い、身体を大きく動かしてその喜びを表現してくれます。
なので、基本的には同じ空間のすぐ近くにいてあげているだけで、機嫌良く過ごしてくれていました。が、抱っこをせがむことも多いので、自分がテレビを見ている時とかは、ずっとお膝に乗せて一緒に過ごすようにしていました。子どもが落ち着く過ごし方を優先して行うことが、今回の機会では大事だなと感じました。
《振り返り③ 1人で数日も育児をするのは大変》
改めて身に染みたのはこれでした。今回は2日間だけでしたが、1週間、1ヶ月、1年も毎日1人でルーティンを回していくのはしんどいと思います。
子どもを育てるための時間(育休)も、休業中の保障(給付金)も大事ですが、それ以上に「サポートし合える相手」や「助けを求めることができる先」の存在が大きく感じられました。
僕の幼少期を振り返ると、祖父母はいずれも家から少し遠い地域に住んでいて、育児のために家に来てくれるようなことは、殆どありませんでした。父も出張で家を空けることがしばしば。
その時、母の支えになっていたのはジグソーパズルと、ご近所さんでした。
同じマンションの同じ階だけでも、同い年や1つか2つ歳の離れたお子さんを持つご家庭がいくつもあったようで、日中はお母さん同士が集まって息抜きをしながら、皆で子どもを見ていたと聞いています。
なので、親に怒られて家から出された時や、仕事が長引いて帰りが遅くなるような時は、別の家のお母さんが預かって面倒を見るようなことをしていました。これも時代ならではという感じですが、今の時代にもあると良いコミュニケーションなのかなと思っています。しかし、ここに「お父さん」という存在が殆ど入っていないために、昔ながらという印象に留まっています。令和の時代には、この育児に関するご近所付き合いの在り方を、アップデートさせていかなければならないのだろうなと思います。
《ワンオペ育児をしていて思った、「生」との向き合い》
最後に、「なぜ僕は、大グズりする子どもをグッタリした気分であやしているのだろう・・・」と、1日目の夜にふと思いました。
あれだけ待ちわびた、我が子の誕生。少しずつ大きく、できることも増えて成長していく姿に喜びながらも、「なぜそんなに泣く?」「なぜそんなことで泣かないといけないの?」と、正直我が子にイライラすることも少なくありません。泣く以外のコミュニケーションも早く覚えて、体力を無駄に使わないよう生きなさいよ。とウンザリする日もあります。
けれど、ヒトの子にも多少の差異はあれど、成長スピードというものがあります。自立できるようになるまで、ヒトという生き物は他の生き物よりも、とても時間がかかります。「なぜヒトの成長スピードは、こうもゆっくりなのか」と思ったりしました。生後2~3ヶ月で歩き、半年で喋れるようにならないものかと。
とは言え、ヒトの成長に時間がかかるのは、やはり何かしらの理由があってのことだろうし、このスピードが今後数年でいきなり変わることも、可能性としてはかなり低いと思います(人生何があるか分からないので、あり得ないという表現はあえて避けます)。だからこそ、生き急がせるようなことや望みは御法度だよなと思ったりもします。ただ、赤ちゃんの笑顔や一つ一つの行動は愛おしくて堪らないことは、これからも不変だと思います。
(日々スマホのアルバムに増えていく、我が子の写真を眺めては思う)
我が子の他にも、世の中には日々たくさんの赤ちゃんが誕生し、一方で、多くの方が亡くなっていきます。亡くなる人は老人だけではありません。
ヒトが生きる理由ってなんだろうなとたまに考えますが、生物としての視点で考えると、「子孫を残していくこと」が回答の一つになると思います。
「子孫の残して生き方」を自分なりにどうしていこうか。ということを考える機会にもなった、今回のワンオペ育児でした。この話を書こうと思った時に、偶然ヨッピーさんのX投稿を見かけました。
僕は普段から「男性も育休は最低1ヵ月取るべき」っていう主張をしているのでその辺についてツラツラ書きます!
— ヨッピー (@yoppymodel) November 23, 2023
【何故育休を取らなければいけないか】
1.新生児期のワンオペ育児はほぼ虐待… https://t.co/JNKo3ao1c1 pic.twitter.com/JePw9q11D3
企業は、これから母になる人だけでなく、父になる人へのフォローも忘れてはいけないですね。
(労働力への対価をどれだけ整備できるか。既に成人している子を持ち、自身は育児に殆ど関与していなかった中堅層オジサン達のアップデートなど)
