
地方映画史研究のための方法論(9)装置理論と映画館②——ジガ・ヴェルトフ集団『イタリアにおける闘争』
ゴダール映画と地方映画史研究
特別講座「徴は至る所に——ゴダールの陰謀論」@jig theater

jig theaterで行われている特集上映「追悼 ジャン=リュック・ゴダール映画祭」の関連企画として、2023年6月18日(日)に特別講座「徴は至る所に——ゴダールの陰謀論」を行なった。当日の様子はインスタライブで配信され、7月9日(日)の会期終了まで視聴することができる。
「地方映画史研究のための方法論」
ゴダールのレクチャーは6月頭に急遽決まったことだったが、『ユリイカ2023年1月臨時増刊号 総特集=ジャン=リュック・ゴダール』の原稿執筆のためにゴダール作品を集中的に見返していたのと、ちょうどこの連載(地方映画史研究のための方法論)でもジガ・ヴェルトフ集団を取り上げるために準備をしていたため、いい具合にそれぞれを連動させて進めることができたと思う。
「地方映画史研究のための方法論」は、2021年にスタートした「見る場所を見る——鳥取の映画文化リサーチプロジェクト」の調査・研究に協力してくれる学生たちに、地方映画史を考える上で押さえておくべき理論や方法論を共有しておきたいと考えて書き始めた。杵島和泉さんと行なっている研究会・読書会でレジュメをまとめ、それに加筆修正や微調整を加えて、このnoteに掲載している。
前回は、映画研究における「装置」理論を理解する上での前提となるルイ・アルチュセールの「国家のイデオロギー装置」論を概説した。今回は、アルチュセールのイデオロギー論を映画化してみせたジガ・ヴェルトフ集団の『イタリアにおける闘争』と、映画制作のありかたや上映のありかたの根本的な見直しを図る運動——「映画を政治的に作る」ことの実践——について見ていきたい。
ジガ・ヴェルトフ集団

コリン・マッケイブ『ゴダール伝』みすず書房、2007年、p.231
ジャン=リュック・ゴダール
ジャン=リュック・ゴダール(Jean-Luc Godard、1930-2022)はフランスの映画監督。映画批評家として『ラ・ガゼット・デュ・シネマ』誌や『カイエ・デュ・シネマ』誌で執筆活動を行なった後、1960年に初の長編映画『勝手にしやがれ』を監督。1961年の長編第2作『小さな兵隊』で主演を務めたアンナ・カリーナと結婚し、二人のコンビで『女は女である』(1961)、『はなればなれに』(1964)、『気狂いピエロ』(1965)など数々の作品を発表。世界的な人気を博した。
だが『気狂いピエロ』公開と同年(1965年)にアンナ・カリーナと離婚すると、1967年に『中国女』に主演したアンヌ・ヴィアゼムスキーと結婚。『中国女』はパリ大学の学生たちが夏季休暇中に毛沢東思想を学び、過激化していく様子を描いたフィルムで、翌年のフランスの五月革命を予見したとも言われた。ゴダールはこの頃から政治的な映画制作に没頭するようになり、『ウイークエンド』(1967)を最後に商業映画との決別を宣言する。
ジャン=ピエール・ゴラン
1967年、『中国女』を制作中だったゴダールは、映画批評家イヴォンヌ・バビーが催した晩餐会で、ジャン=ピエール・ゴラン(Jean-Pierre Gorin、1943-)と出会う。ゴランは高等師範学校への入学を目指してルイ・ル・グラン高校の準備学校に通った時期があり、そこでルイ・アルチュセールのマルクス主義や構造主義など当時の新しい思考法を身につけた。ゴダールと出会ったのは、『ル・モンド』誌で書評の仕事を始めたばかりの頃。共産主義青年同盟「マルクス・レーニン派」に属する若き新左翼の活動家で、また映画にも造詣の深かったゴランは、ゴダールの強い興味を惹き、両者は同時代の哲学や理論、映画について対話を重ねるようになった。
ジガ・ヴェルトフ集団
1968年、ゴダールはゴランに次の映画『東風』(1969)共同制作を持ちかけ、それをきっかけに「ジガ・ヴェルトフ集団」(Groupe Dziga Vertov)を結成。ソ連の映画作家ジガ・ヴェルトフ(1896-1954)からグループ名をとり、集団的・匿名的な映画製作、マルクス主義的な政治思想、商業的・資本主義的な流通回路に乗せないオルタナティブな上映形態の模索など、ラディカルな政治性を志向した映画運動を展開した。
1969年にはジャン=アンリ・ロジェ(Jean-Henri Roger、1949-2012)が加わり、『ブリティッシュ・サウンズ』(1969)や『プラウダ(真実)』(1969)の制作に参加。その後もジガ・ヴェルトフ集団は『イタリアにおける闘争』(1969)、『勝利まで』(1970)、『ウラジミールとローザ 』(1971)などの制作に取り組むが、公開を拒否されたり、完成にまで至らないこともあった。1972年にイヴ・モンタンとジェーン・フォンダを起用して初の商業映画『万事快調』(1972)を公開した後、出演したジェーンを批判する短編『ジェーンへの手紙』(1972)を制作。その直後にジガ・ヴェルトフ集団は解散する。
「なにをなすべきか?」(1970)
ゴダールは1970年 1 月に「なにをなすべきか?」と題したジガ・ヴェルトフ集団のマニフェストを発表。「政治映画をつくるべきか」それとも「映画を政治的につくるべきか」を問うている(『ゴダール・マニフェスト——イタリアにおける闘争/カラビニエ』所収、深見耕一郎 編、フランス映画社+創造社、1970年、p.2)。
「政治映画」とは、現実の政治状況を題材として、世界のありようを描写・説明することを目的とした映画であり、作品の制作前から配給を行おうとする、従来の商業的・資本主義的な流通回路を前提とした映画のことである。それはまだブルジョワ・イデオロギーから抜け出し得ていない、観念論的・形而上学的な世界観を前提とした古い思想であると指摘される。
対して「映画を政治的に作る」とは、「具体的な状況を具体的に分析」(p.3)することで、能動的に世界を変革しようとすることである。その実践は「映画の編集を、撮影前に行い、撮影中に行い、撮影後になお行なうこと」、さらには「映画の配給を行なおうとする前に、まずそれを製作すること」(p.4)によって行われる。すなわち、製作側が自ら配給ルートを決めて上映活動を展開するということであり、こちらはプロレタリア階級の立場に立った、マルクス主義的・弁証法的世界観に立った新しい思想であるとされる。
ジガ・ヴェルトフ集団は、ただ「政治映画」を撮るだけではなく、その映画の生産過程や流通過程を批判的に分析し、解体していくのだと宣言する。闘争と革命こそが第一の目的であり、「映画をつくることは第二義的な活動であって、革命のなかの小さな「ねじくぎ」」(p.5)であると知らねばならない。
『イタリアにおける闘争』
『イタリアにおける闘争』(1969)
『イタリアにおける闘争』はイタリア国営放送(RAI)からの依頼で1969年12月に制作されたが、結局放映されることはなかった。当時のイタリアでは各地で激しい労働争議が行われていたが、ゴダールとゴランはその様子を記録しに行くのではなく、多くの場面をパリのゴダールの自宅で撮影。他にはフランス・リール近郊の織物工場や、ミラノ郊外の映像が数カット登場するのみであった。

同作の理論的な支柱になっているのは、前回取り上げたルイ・アルチュセールの「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」である。クリスティアーナ・トゥリオ=アルタンが演じる女子大生パオラ・タヴィアーニが、マルクス主義者として革命運動に身を投じる中で、自らの日常生活にも入り込んで作動する国家のイデオロギー諸装置の存在に気づくという物語が描かれる。なお、「イデオロギーと国家のイデオロギー装置」の刊行は1970年6月なので『イタリアにおける闘争』の公開と前後するが、映画作中に直接的な文言の引用も登場するため、アルチュセール本人から直接原稿を得たものと思われる。
以下では、『ゴダール・マニフェスト』(深見耕一郎 編、フランス映画社+創造社、1970年)所収のシナリオを土台としながら、映画本編と適宜照らし合わせつつ、ゴダールとゴランがアルチュセールのイデオロギー論をいかに映画化してみせたのかをまとめている(シナリオと本編の異同については、今回は考慮していない)。
第1部——パオラの日常生活
第一部の冒頭では、女子学生パオラ・タヴィアーニが観客に向かって語りかける。曰く、認識論の歴史上、世界には二つの発展法則があった。一つは形而上学=観念論であり、もう一つは弁証法=マルクス主義である。そしてパオラは、マルクス主義者としてその革命運動に身を投じている。

続いて、パオラの日常生活が、「闘争」「大学」「社会」「家庭」などの部門ごとに映し出される。それぞれの場面の随所には「黒画面」が挿入され、そこにあるべき何かが隠されているような、あるいは日常生活が断片化されているような印象を与える。
「闘争(戦闘的行動)」では、パオラが革命闘争のためのビラを制作したり、共産党の集会について電話で話したり、三つの新聞・雑誌の政治的立場を読み比べたりする姿が映し出される。パオラはビラを書くシーンに重ねられたナレーションで、各国の人民闘争を分析して自らの闘争に活かすことがブルジョワジーの国家装置(警察や軍隊)を攻撃するために有効であり、またそれゆえにブルジョワジーはそれを恐怖し、取り締まろうとするのだと指摘する。
「大学」では、パオラの後ろ姿だけが映し出され、そこに講義を行う教授の声と、学生たちの「くたばれ観念論!」という野次の声が重なる。
「科学」では、パオラの青年労働者に家庭教師をしている。青年は、そこで教わったことを自らの労働や闘争に実践的に適用する方法を尋ねるが、パオラは「あなたの言うとおりだけど、そんなに単純ではない」と言葉を濁す。
「社会」では、パオラが婦人服店を訪れてセーターやブラウスを試着する。気に入った服の価格の高さに驚くが、女性店員に「手のかかっている品物ですから」と説明され、購入を決める。店員がレジスターに金額を打ち込む。パオラは店員が持っている本について話をしようとするが、店員は店主に「個人的な話は禁止だ」と怒られる。

「家庭」では、食卓の上のスープ皿が映し出される。パオラは父親に、集会に参加して食事に遅れたことを責められる。「おまえは革命とやらを待ちながら、いつも家へ来てたっぷり食べ、ぐっすり眠っていく。私と母さんを食いものにしているんだ。」

「健康」では、パオラが母親のために薬を用意する手元が映し出される。母親は、パオラと父親が口論するのを見るたびに胸がつまる想いがすると述べる。
「住宅問題」では、パオラが早朝に洗面所で化粧をしている。トイレに入りたい弟と口論になり、パオラが「洗面所が足りなきゃ、働いてもっと大きなアパートを買えばいい」と言うと、弟は「自分の利益をまず守ろうとするのは共産主義者ではない」と揶揄的に反論する。
「性格の問題」では、パオラがベッドの脇の資料を確認しながら、誰かが勝手に自分の持ち物に触れ、位置を変えたことを非難する。
「セックス」では、少し開いたドアの映像に、パオラと彼女の夫の会話音声が重ねられる。夫は金の無さを嘆き、パオラは来月はもっと倹約すると言う。
「身分証明」では、街で「支配者に対する闘争を!」と呼びかけながら機関紙を売るパオラが警官から職質を受け、身分証明書の提示を求められる。またパオラは、試験官から番号で呼ばれたり、劇場の入口で学生証を求められたりする。
第2部——「現実」ではなく「反映」
第2部では、第1部で見てきたパオラの日常生活の分析が行われる。パオラは、そこに映っているのは自分自身の「全体」ではなく「断片」であり、また「現実」ではなく「反映」であると述べる。
ここで言われる「反映」については、イギリスで制作した映画『ブリティッシュ・サウンズ』(1969)および同年に発表された論考「最初の《イギリスの音》」(『ゴダール全評論・全発言Ⅱ』所収、筑摩書房、1998年)で説明されている。曰く、「ブルジョワジーは自らの世界についての映像をつくりあげ、それを現実の反映と呼んでいる」(p.80)。要するに「反映」とは、現実をありのままに映し出したイメージではなく、ブルジョワ・イデオロギーによって歪められたイメージが、あたかも「現実」であるかのように映し出されているということだ。
作中では「大学」や「家庭」などこれまでに登場した場面が鏡越しに反転したイメージとして示され、「反映」が視覚的に表現されている。

続くナレーションでは、「大学」「家庭」など個々の部門は「幻想」によって結合されて組織された全体を成しており、その全体の中枢が「社会」であると説明される。ここで言われる「幻想」とは、ルイ・アルチュセールが「諸個人が彼らの現実的諸条件に対してもつ想像上の(幻想としての)関係の表象」として述べたもの、すなわち、イデオロギーのことだ。
イデオロギーは人々の意識に呼びかけて「実際行為(プラチック)」を組織し、日々休みなく生産諸関係の再生産を行うように促す。第1部に登場した黒画面は、パオラの日常生活がブルジョワ・イデオロギーによって歪められた「反映」のイメージであり、あるべき「現実」が覆い隠されていることを表しているのだ。
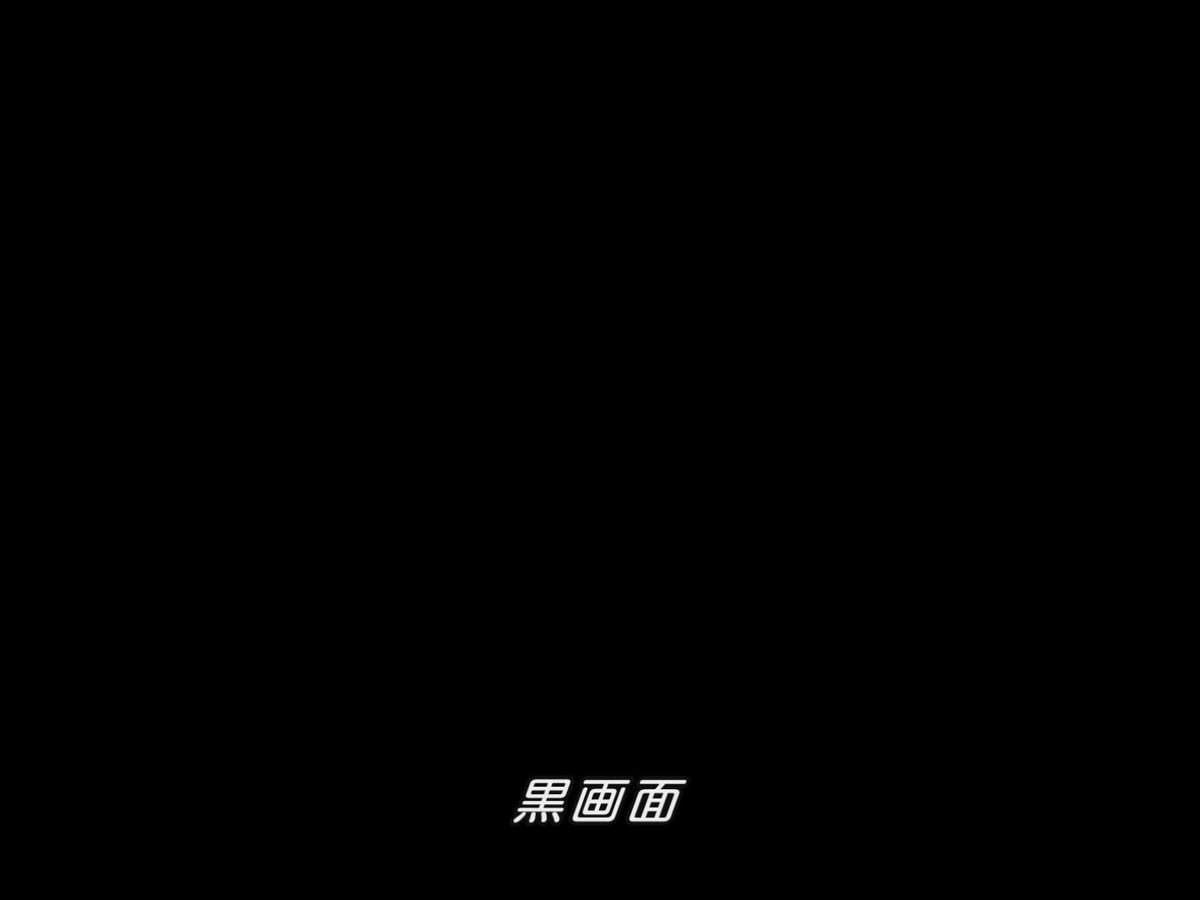
パオラは1部の冒頭で、観念論とマルクス主義という二つの世界観があると述べたが、両者が対立関係にあることについては語っておらず、マルクス主義者を名乗りながら実際にはまだ観念論者に留まっていたと反省を口にする。
そしてパオラは、「人間の社会的存在が人間の思想を決定する」というマルクス主義的な命題を掲げ、自分自身の日常生活や社会的な関係の問い直しを始める。積極的かつ具体的な行動に出ることで、世界の変革を目指すマルクス主義の思想を体現しようとするのである。
だがその試みは、なかなか思い通りには進まない。パオラは「社会」の婦人服店で出会った女性店員に本を薦めようとするが、「言葉でいうのはカンタンだわ。だって、あなた労働してないんだもの」と拒絶の言葉を浴びせられる。「科学」の青年労働者からの「学んだことをどう実践に結びつければ良いのか」という問いにも、いまだにうまく答えることができない。
「セックス」の部門で映し出されたのと同じ部屋で、パオラは夫との関係や普段の行動を反省する。セックスをセックスそれ自体として、他と切り離してはいけない。何もすることがないからと言って昼間からセックスができるのは、まさに働かなくても良いブルジョワ階級の特権ではないか。そう考えたパオラは、家庭というブルジョワ概念と戦い、「革命的夫婦」であろうと夫に提案するが、「実際には僕らは階級社会に生きてるんだし、ブルジョワジーが権力を握っている。むずかしいよ」と返される。
さらにパオラは、「科学」の青年労働者の問いに応えるためには自分自身が労働者と同じ経験をしなければならないと考え、実際に工場に働きに行く。だがそこでも、パオラは不慣れな仕事で足を引っ張り、他の労働者と連帯するどころか却って遊離してしまう。

第3部——黒画面を埋めていく
これまでの試行錯誤と悪戦苦闘を経て、パオラは新たな認識に至る。それは、「反映」という概念はブルジョワ・イデオロギーから生まれたものでもなければ、それ特有のものでもなく、すべてのイデオロギーのメカニズムそのものだということだ。
だとすれば、すべての「反映」を否定して「現実」へ向かおうとするよりも、それがどのようなイデオロギーから生まれた「反映」なのかを検討すべきだろう。より具体的には、客観的矛盾——例えばパオラが世界の変革を目指しながら、同時にブルジョワ的生活を送ってしまっていること——自体を否定し、覆い隠してしまう「反映」と、それを包み隠さず表してみせる「反映」、また別の言い方をすれば、世界が現状のままであることを望むブルジョワ・イデオロギーと、世界の変革を望む革命的イデオロギーとの闘争を問題とせねばならない。
このように考えると、『イタリアにおける闘争』における黒画面の位置付けも変化する。1部と2部では、黒画面はあるべき「現実」を覆い隠すものとしてあった。だが3部では、黒画面は別の映像を代入するための空箱のようなものとなる。
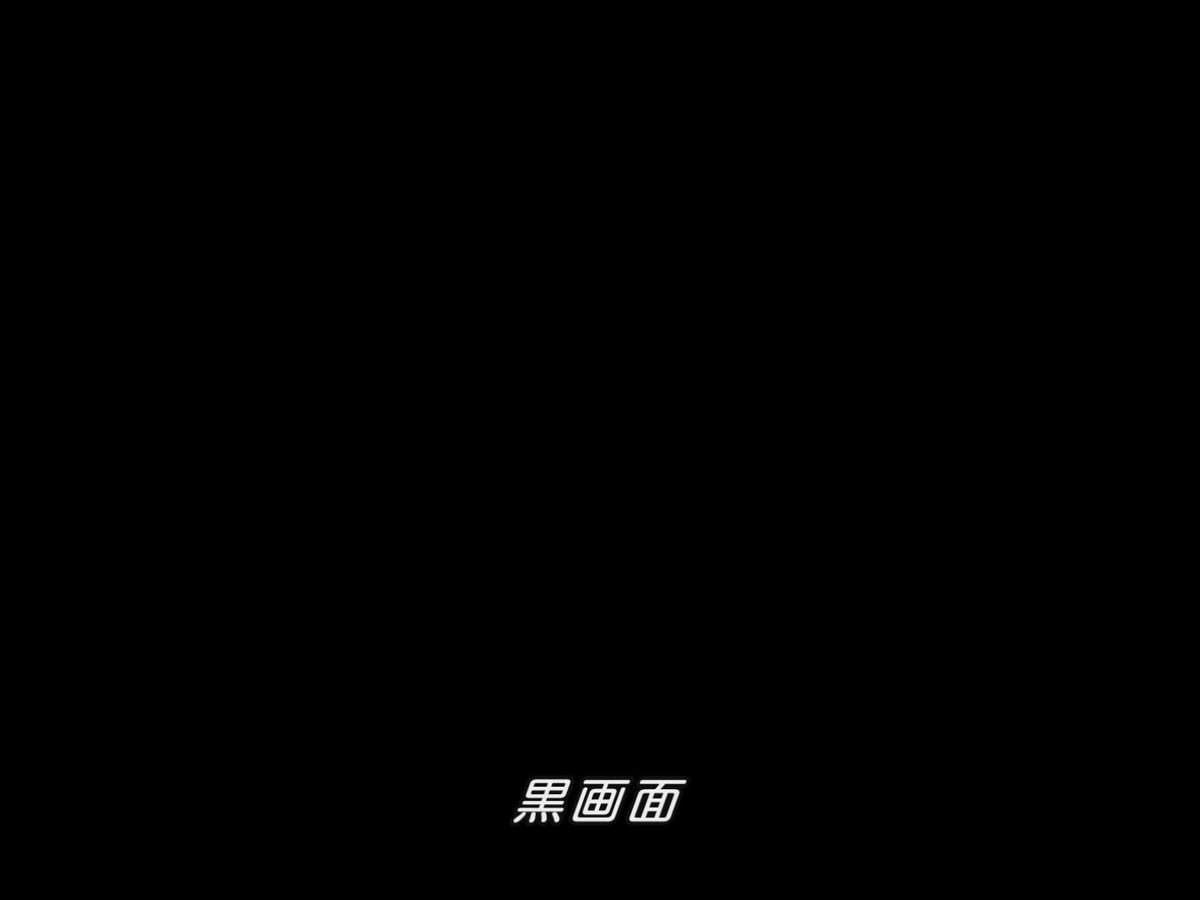
さしあたり、パオラは「生産関係」——生産の過程に関わる人々の社会的関係——を意味する工場のショットを2つ用意し、その間に黒画面とパオラが話をする音声を挟み込む。これは、現在の資本主義的な生産関係を自分自身との関係から考えるためだと説明される。

パオラは上記の観点から、第1部の映像を再検討する。まずは「社会」の婦人服店で試着するショットの前後にあった黒画面が、それぞれ生産関係を意味する工場のショットに置き換えられる。

さらに「家庭」におけるスープ皿のショットの前後にあった黒画面も、それぞれ工場のショットに置き換えられる。こうしたモンタージュにより、パオラの日常生活における「実際行為(プラチック)」がブルジョワ・イデオロギーの求める生産諸関係の再生産の過程に組み込まれていることが示されるのである。

またパオラは「大学」の例を挙げ、講義を行う教授の声は「あとで私を試験に呼び出す声」であり、「全体として大学当局の声」であり、つまりは「国家の大学部門の声」「国家の教育装置・イデオロギー装置の声」(p.42)であると指摘する。学生たちはその「呼びかけ」に応じるかたちで試験に呼び出され、名前を呼ばれ、身分を確かめられ、国家のイデオロギー装置に従属する。
そしてパオラもまた「科学」の青年労働者の家庭教師として、敵(大学教員)に教わった話を同士(労働者)に教え、資本主義的生産関係の耐えざる再生産に加担するのだ。

第2部でパオラが自分自身の日常生活や社会的な関係の問い直しを始めたことは、様々な困難や苦難が伴ったが、その行動が思考に変化をもたらし、国家のイデオロギー諸装置の作動に気づくことができるようになった。
生活に変革をもたらすということは、思想と行動、理論と実践の間にある様々な矛盾を激化させることであり、生活の中に階級闘争を持ち込むことである。
第4部——今日のテレビで何を語るべきか
第4部では、パオラがイタリアの国営テレビに出演する俳優として観客に語りかけ、自らの労働と闘争がいかにあるべきか、今日のテレビで何を語るべきかを問う。
国営である以上、テレビ放送は国家のものである。権力を握る政党が変わっても、日々国家の代表者がテレビを通じてイタリア人民に向けて「呼びかけ」を行う。そうした日常的な暴力に争い、革命を起こしてすべてを破壊し変革するためには、今までと考え方を変えなければならない。
まずはイタリアのテレビで「今までと違う方法で、2分でも3分でも話すこと」(p.47)。それは第1部のパオラのように革命について語り始めることであり、「政治映画」を撮ることである。

だがそれでは、自分自身の「革命的」な言動や映画と、それらを成立させている土台にあるブルジョワ・イデオロギーとの間の矛盾が解決できていない(テレビ局はそうした意見にも一見寛容な素振りを見せ、ある程度は自由に語ることを認めるだろう)。その先に進むためには、第2部のパオラのように、自らの生きる具体的な状況を具体的に分析し、能動的に世界を変革しようとすることが必要だ(「人間の社会的存在が人間の思想を決定する」)。
そして第3部で、分析と変革のための具体的な指針が示された。現実かイデオロギーかという二項対立で考えるのではなく、誤ったイデオロギーと正しいイデオロギーの対立を問題とすること。すなわち、世界が現状のままであることを望むブルジョワ・イデオロギーと、世界の変革を望む革命的イデオロギーとの闘争を問題とし、思想と行動、理論と実践の間にある様々な矛盾を激化させ、生活の中に階級闘争を持ち込むこと。
そしてジガ・ヴェルトフ集団は、活動家の学生パオラを主人公とする物語映画=「政治物語」を撮ることで満足するのではなく、『イタリアにおける闘争』という作品自体の成立条件をも批判の俎上に上げ、さらにはそれをイタリアの国営放送で放映することによって、まさに「映画を政治的に作る」ことを実践しようとしたのである。
日本におけるジガ・ヴェルトフ集団と『イタリアにおける闘争』の受容
1970年7月、『東風』の日本公開
松田政男によれば、日本においてゴダール映画は『気狂いピエロ』(1965)の次に『中国女』(1967)、そして『ウィークエンド』(1967)の順に公開され、その間に制作された『メイド・イン・USA』(1967)や『彼女について私が知っている二、三の事柄』(1967)の公開が遅れたため、なぜゴダールが従来の映画の文法を破壊するような映画を撮り始めたのかが分かりづらくなっていた。そんな折、1970年7 月にフィルムアート社がジガ・ヴェルトフ集団の『東風』を日本で初公開し、その作風の変貌ぶりに多くの批評家たちが大混乱に陥ったという(松田政男「「ゴダール・マニフェスト」の頃——同時代者のモノローグ風に」『文藝別冊 ゴダール——新たなる全貌』河出書房新社、20002年、p.130)。
映画評論家の山田宏一が「『東風』では、ゴダールは自作の『中国女』の自己批判をおこなって、これを廃棄するしまつである。もうまったくとりつくしまがないのだ。ゴダール・ファンを自認するひとたちは、みんなガックリとくるにちがいない」(山田宏一「東風吹かば」『映画芸術』1970年8月号)と嘆いたのをはじめとして、60年代のゴダール作品に思い入れを持っていた者たちから失望の声が上がる中、松田政男は『キネマ旬報』1970年8月下旬号に『東風』を高く評価する批評を書いている。さらに1970年10月10日に松田が中心となって創刊した第二次『映画批評』(新泉社)では、津村喬による本格的なゴダール論「東風は西風を圧倒する」が巻頭論文に選ばれた。このようにして、「政治の時代」に突入したゴダールとジガ・ヴェルトフ集団の映画運動を受け止め、積極的に応答していこうとする機運が日本でも高まっていくのである。
上映プログラム「ゴダール・マニフェスト」
『映画批評』創刊号の表紙裏面には、創造社とフランス映画社主催による上映プログラム「ゴダール・マニフェスト」の広告が掲載されている。このプログラムは柴田俊と川喜田和子の尽力で実現したもので、一連の上映作品を通じて60年代後半のゴダールの変貌とジガ・ヴェルトフ集団での活動を辿り、新たなゴダール像を提示しようとする画期的な取り組みであった(松田政男「「ゴダール・マニフェスト」の頃」p.130)。

「ゴダール・マニフェストは4期に分かれており、第1期が1970年10月3日~16日(於 新宿・京王名画座)、上映作品は『勝手にしやがれ』(1960)と『彼女について私が知っている二、三の事柄』。第2期が1970年11月7日~17日(於 大手町・日経小ホール、新宿・四谷公会堂)、上映作品は『カラビニエ』(1963)と『イタリアにおける闘争』。第3期が1971年1月15日〜2月1日(於 新宿・京王名画座)、上映作品は『女は女である』(1961)と『メイド・イン・USA』。第4期が1971年11月3日〜12月14日(於 新宿・蠍座)、上映作品は『プラウダ(真実)』と『ブリティッシュ・サウンズ』。この直前の10月12日〜10月22日には、「ゴダール6+3」と題した上映も行われた(於 新宿・京王名画座)。これは『勝手にしやがれ』や『気狂いピエロ』などゴダールの代表作に加えて、『シャルロットとジュール』(1960)や『立派な詐欺師』(1964)、『カメラ・アイ』(オムニバス映画『ベトナムから遠く離れて』より、1967)という短編3本を紹介するプログラムであった。
映画を「見る場所」の模索
テレビ放映を拒否された『イタリアにおける闘争』をはじめとして、ジガ・ヴェルトフ集団の作品は資本主義的な流通回路を否定するがゆえに、フランス本国でさえ見る機会が極端に限られていた。堀潤之が指摘するように、日本においてそれらの作品が一定期間だけでも映画館(新宿の京王名画座と蠍座)で商業的に公開されたのは、世界的に見ても特筆すべきことであったと言えよう(堀潤之「映画は音楽のように——日本におけるジャン=リュック・ゴダール作品の受容についてのささやかな覚書」『東西学術研究所紀要』45号、2012年、p.165)。
また第2期の上映は、大手町の日経小ホールと新宿の四谷公会堂で行われた。こうした「見る場所」の設定からは、「ゴダール・マニフェスト」が映画館での上映を前提とせず、オルタナティブな上映の場や上映形態を模索しようとしていたことが窺える。所詮は「貸し館」でしかない公会堂を選んでも、ブルジョワ的な上映形態からは抜け出せないのではないかという批判もあったが(グループ・アノニム「〈日本におけるゴダール映画〉への批判」(『シネマ71』NO.8 1971年6月号)、そのような対立意見も含めて、各々がゴダールの「映画を政治的に作る」という言葉を受け止め、自らの戦線に立って、その実践を試みていた。
映画=運動と集団創造——「映画を政治的に作る」ことの実践
1970年の日本では、大島渚の創造社や若松孝二・足立正生らの若松プロダクションといった「独立プロダクション」が精力的な映画製作を行っており、小川紳介が率いる小川プロダクションも三里塚に移住して「暮らしながら撮る」という独自の映画制作と上映活動を展開していた。
松田政男は、「ゴダール・マニフェスト」がこうした国内の様々な映画=運動の結節点になると共に、そうした運動が「世界的同時性」を持つものであることを確認する機会として機能したことを指摘している(松田政男「「ゴダール・マニフェスト」の頃」p.130)。
例えば「ゴダール・マニフェスト」の上映に際しては、ゴダール側からの要請でいくつかの作品の日本語吹替版が用意されることになったが、『イタリアにおける闘争』では足立正生とカメラマンの長谷川元吉、『プラウダ(真実)』では日本全学連国際部長としてプラハに赴任していた石井保男、『ブリティッシュ・サウンズ』では創造社の松方正とNDU(日本ドキュメンタリストユニオン)の主要メンバー布川徹郎の妻・中島葵が「声の出演」を務めている。これは、当時の日本で映画=運動に取り組んでいた人々が所属団体や立場を超えて結集し、まさにジガ・ヴェルトフ集団的な「集団創造」が行われた、ささやかな一例であると言えるだろう。
日本語吹替版の制作からは、映画を芸術作品として扱い、その唯一性や真正性を保証することに力を注ぐのではなく、あくまで闘争と革命こそが第一の目的であり、映画はそのための小さな「ねじくぎ」あるいは「アジビラ」の如きものとして扱うべきだという志向が読み取れる。
またこうした映画制作・上映の姿勢を批判的に継承し、より先鋭化させたフィルムとして、足立正生と若松孝二による『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』(1971)を挙げることができる。

『赤軍-PFLP・世界戦争宣言』は、足立と若松がカンヌ国際映画祭からの帰路でレバノンのベイルートに立ち寄り、パレスチナ解放のために闘うアラブゲリラの日常生活を撮影した映像と、黒画面上に表示された字幕から成る。「プロパガンダの最良の形態は武装闘争である」というスローガンを掲げ、武装闘争の様子を伝える「ニュース映画」であると共に、世界革命のための「プロパガンダ映画」として制作された。また同作は、ジガ・ヴェルトフ集団の映画と同様に商業的な流通経路に乗せての上映を否定。通称「赤バス」に乗り込んで各地の大学や工場に巡業し、映画の上映と議論をセットで行なうスタイルが選ばれた。
誌面上での活発な議論——黒画面論争
松田政男は第2期の劇場用パンフレット『ゴダール・マニフェスト——イタリアにおける闘争/カラビニエ』(深見耕一郎 編、フランス映画社+創造社、1970年)の制作にも関わり、「『イタリアにおける闘争』覚え書」という論考を寄せている。なおこのパンフレットには、他にゴダールによるマニフェスト「なにをなすべきか?」、佐藤忠男「『カラビニエ』について」、「68年5月以降のゴダールの映画(資料)」、『イタリアにおける闘争』シナリオ(翻訳・監修:北原敦)、『カラビニエ』採録(構成:柴田駿)が掲載されていた。

深見耕一郎 編、フランス映画社+創造社、1970年
「ゴダール・マニフェスト」のパンフレットが刊行されたのはこの号のみだったが、その後は松田らが創刊した第二次『映画批評』が代替的な役割を果たし、上映に合わせて作品の台本や採録、ゴランやゴダールのインタビューなどを掲載。さらに津村喬を初めとする批評家たちが作品論や作家論を書き、誌面上で活発な議論が行われた。『映画批評』に限らず、『季刊フィルム』や『シネマ』、『映画芸術』など各紙がゴダールを取り上げ、他誌の論者との横断的な論争が起こることも珍しくなかった。
とりわけ白熱した論点の一つは、『イタリアにおける闘争』の「黒画面」を巡る解釈である。例えば足立正生は写真家・中平卓馬との対談の中で、黒画面は映画の「解体」の実践にはなり得ず、解体の「象徴」としてしか機能していないと批判する(「「作品」の解体と崩壊」『日本読書新聞』、1970年12月14日、1970年12月21日、日本読書新聞社)。
これに対して津村喬は、黒画面は「映画の解体」を観客個々人が実践するための手本であり、作品を見て学んだことを各々が自身の日常で実践することこそが重要なのと反論した(津村喬「《真実》を読むための五つの困難」『映画批評』1971年7月号、新泉社)。
これらの映画=運動的な解釈に対して、文学者・批評家の蓮實重彥は黒画面の独立した意味を論じるのではなく、『イタリアにおける闘争』という作品全体の構造の中で黒画面が果たす役割を記述し、さらには他のゴダールの映画にもまたがる色彩の構造を読み解いていく。蓮實は徹底して具体的な画面に即した解釈を行うことで、ゴダールの政治性・運動性を脱色した解釈を示した。
三者の論争は主に『映画批評』と『シネマ』誌上で行われ、特に津村と蓮實は長期間に渡って互いに反論と批判を加えながら、自身のゴダール論を深化・洗練させていく。『映画批評』1971年3月号(津村喬「鏡の国のゴダール——イタリアへの旅あるいは〈黒画面〉試論」)で津村が蓮實を批判したことに端を発した議論は、結局『映画批評』の終刊号となる1973年9月号まで続くことになった(蓮實重彦「ゴダールにおける隠蔽と顕示」)。
(なお「黒画面」論争については、『ユリイカ2023年1月臨時増刊号 総特集=ジャン=リュック・ゴダール』に寄稿した「黒板としてのスクリーン——ジガ・ヴェルトフ集団のオンデマンド授業動画映画」でも少し違った角度から論じている。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
