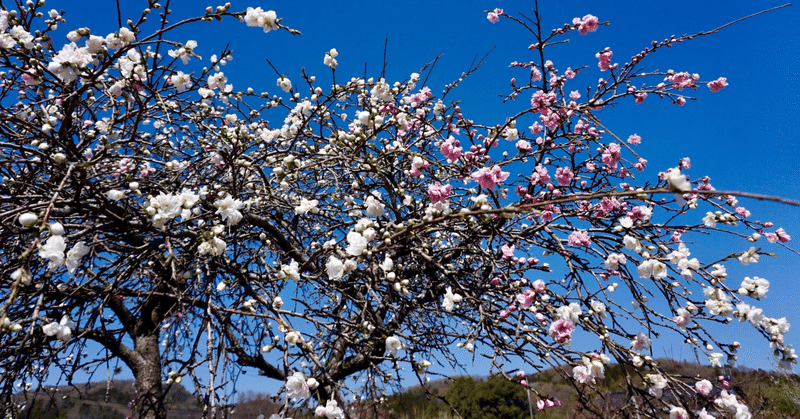
ドラマで描かれなかった平家の動き
2022年3月20日(日)NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』第11話「許されざる嘘」が放送されました。
この話で描かれた歴史的事実は以下の通りです。
西暦1180年(治承四年)
11月17日 侍所設置。和田義盛(演:横田栄司)が別当(長官)に就任。
12月12日 頼朝、大倉御所に入る。御家人制度の成立。
12月12日 平家により園城寺(三井寺/義円の育ったところ)が炎上。
12月28日 平家により興福寺、東大寺が炎上(南都焼討)。
西暦1181 年(治承五年)
閏2月4日 平清盛 病死。
2月15日 三浦義澄に預けられていた伊東祐親が自害。
3月10日 墨俣川の合戦。義円討死。
ドラマの描き方では、
園城寺が焼き討ちにされたのは以仁王を匿ったため
興福寺、東大寺が焼きうちにされたのは平家にはむかったため
と長澤まさみのナレーションと三善康信の一人語りですませられました。
ですが、さすがにここは歴史的事実も踏まえてきちんとお伝えしなければならないと思いまして、ここでは平家のやったことや動きについて記事化することにします。
園城寺は仏教武闘派勢力その1
話は西暦1179年(治承三年)11月に平清盛(演:松平健)が起こしたクーデター(治承三年の政変)まで遡ります。
清盛はこの時、後白河院政を武力を以って停止させ、後白河法皇(演:西田敏行)を鳥羽殿に幽閉しました。
さらに、翌年2月に高倉天皇が皇位を自分の息子である言仁親王に譲位させて安徳天皇として即位させ、高倉天皇を上皇にして「治天の君」に据えました。
高倉天皇は清盛の義理の甥にあたります。そして安徳天皇は、高倉天皇の皇子である上に清盛の孫にもあたる(安徳天皇の母親は建礼門院徳子)ため、このクーデターで清盛は朝廷と院を完全に支配したことになります。
これに黙っていなかったのが、後白河法皇を支持してきた園城寺や興福寺といった仏教武闘派勢力です。
園城寺と興福寺は延暦寺を巻き込んで法皇を鳥羽殿から救出しようとしましたが、この時は平宗盛(演:小泉孝太郎)によって阻止されています。
以仁王を匿った園城寺
そういう鬱憤が溜まっていた中、1180年(治承四年)5月15日、以仁王(演:木村昴)の平家への謀反が発覚。逃げまどう以仁王を園城寺が匿いましたが、その上、源頼政(源三位/演:品川徹)まで園城寺に駆け込むと、寺の大衆の中で不協和音が生じはじめました。
園城寺は後白河法皇のシンパである以上、法皇の子である以仁王を匿うことに異論はありませんが、頼政まで匿う義理はありません。さらにこの二者を匿ったことで平家に園城寺を攻める口実を与えてしまいました。
園城寺は興福寺、延暦寺と連携して後白河シンパを形成してきましたが、平時忠(清盛義弟/検非違使)の工作によって延暦寺が平家に帰順してしまいます。
延暦寺の平家帰順は以仁王と頼政が京へ攻撃をかける入り口を塞がれたことになり、園城寺に籠る理由がなくなったため、興福寺へ移動することにしました。しかし、5月26日、頼政はその途中の平等院鳳凰堂で、以仁王は興福寺に向かう途中でそれぞれで討たれてしまいました。
翌27日、以仁王の討死が知らされる前に、院庁にて議定(公卿の会議)が開かれることになりました。議題は平家に対する謀反に加担した園城寺・興福寺に対する措置についてです。
この席上で左大臣(藤原経宗)は
園城寺の事は責任者を出頭させ、それから決定しよう。興福寺のことは、まず使者を遣わして謀叛の意志があるのかどうか、また以仁王を匿っているのかどうかを問いただしそれによって官軍を遣わせば良い。
と方針を決定しました。
しかし、それは官軍の武力による園城寺、興福寺の殲滅を願う清盛をブチギレさせるのに十分でした。
清盛は京都の寺社勢力が今後政務に関われないように、都をまだ完成していない福原(兵庫県神戸市)に移すことを決定します。
近江・美濃源氏の反乱と園城寺
それから約半年後の西暦1180年(治承四年)11月17日、美濃源氏・源光長(摂津源氏・源頼政と同系統)が反平家の兵を挙げました。
さらに3日後には、美濃源氏に呼応して、隣国の近江国(滋賀県)で近江源氏(甲斐源氏と同系で佐々木氏とは別系統)の山本義経と柏木義兼の兄弟が挙兵します。
美濃・近江源氏の勢力は琵琶湖周辺を押さえて、勢多川を遮断。北陸の平家の補給路を断つとそのまま京都に進軍します。
その勢力を迎え入れたのが園城寺でした。
美濃・近江源氏の兵力を加えた園城寺・興福寺コンビは再び平家に歯向かう態度を示し、延暦寺を恫喝して自分たちの味方に加えます。
仏教武闘派勢力三羽烏の再結成です。
そして再び清盛はブチギレます。
「またか….またあいつらか…..」
同年11月23日、清盛は都を平安京に戻すことを決定し、26日、高倉上皇に奏上して園城寺と興福寺への追討の院宣を出させます。
12月1日、平家継(平家家令・平家貞の子)が出陣し、翌2日、平知盛(清盛四男)、平資盛(清盛孫)が出陣しました。
家継、知盛、資盛の連合軍は知盛は家継と合流し、12月5日、近江国柏原(滋賀県米原市柏原)で近江・美濃源氏の源氏連合軍と合戦に突入。兵力で大きく上回る源氏連合軍を壊滅させました。
敗れた山本義経は園城寺に逃げ、それを追った知盛、資盛の平家連合軍は園城寺を包囲します。
12月10日、平重衡が清盛の命令書を携えて平家連合軍と合流しました。清盛の命令書には
「園城寺を攻撃せよ。焼き討ちにしても構わん」
というものでした。
12月11日、連合軍は四方から園城寺に攻撃を開始。これよって園城寺の建物は半分近くを戦火で失いました。
これがドラマで描かれた「園城寺の焼き討ち」のおおまかな歴史事実になります。
興福寺は仏教武闘派勢力その2
園城寺勢力を壊滅させた清盛の次のターゲットは、園城寺と連携して事に当たっていた興福寺でした。
『玉葉』によれば12月22日の段階で
聞くところによれば来たる25日、官軍を南都に派遣し、悪徒を捕縛、房舎を焼き払って殲滅させるそうだ。まずは大和・河内等の武士を以て、道中を守護させ。その後、官軍を向かわせるとのこと。
となっており、その通り25日の条で
今日、蔵人頭平重衡、大将軍として南都の悪徒を追討するために派遣された。28日に南都と攻戦し、一両日宇治に回るとのこと
となっているので、清盛が重衡を将軍として南都征伐を命じたのは間違いないです。その軍勢は『平家物語』では4万とされていますが、別の史料には数千とあり、実態がつかめていません。
この軍勢には平通盛(清盛甥)が副将として従軍していました。
対する興福寺側は、興福寺の北方にある般若寺(奈良県奈良市般若寺町)を本拠とし、ここから奈良坂(奈良から京都府木津川市に出る坂道で通称:般若寺坂)方面に堀と土塁を築き、およそ7000余りの僧兵でこれを迎撃する体制をとりました。
般若寺と奈良坂の防備が完璧であることを知った重衡は、通盛を別働隊の大将にして、兵を二手に分け、木津方面に進軍し、力技で奈良坂を押し出そうとしましたが、興福寺側の反撃は鬼のように凄まじく、27日の戦いは引き分けに終わりました。
翌日28日の戦いは、興福寺側の疲労と消耗は大きく、さらに数の上では4倍以上の平家軍を防ぎきれるものではありませんでした。よって、平家方に押された興福寺側は、本拠地である般若寺を明け渡さざるを得ませんでした。
重衡らは敵の本拠である般若寺に入って、ここを自らの本陣とし、僧兵たちは興福寺に立てこもりました。
その日の夜、重衡は兵に興福寺周辺に火をかけることを命じました。清盛の命令にあった「房舎を焼き払う」ことを実行したのです。
しかし今年の冬は雨が少なく、空気も乾燥しきっていました。そこに火が付けられ、さらにこの日は夜から風が強かったため、たちまち興福寺周辺を飲み込む大火災に発展してしまったのです。
火の広がりは現在の奈良市の大部分に広がり、興福寺の北方にある東大寺にまで及んでしまいます。
この火災で興福寺は東金堂、三重塔、講堂、北円堂、南円堂他38の施設が焼け落ち、東大寺も主要な建築物および金堂(大仏殿)が盧遮那仏もろとも焼け落ちました。
人的被害は僧侶、住人など数千人が焼死するという状況でした。
南都炎上は重衡の本意か否か
歴史事実の「南都焼討」の事実は前述の通りですが、最初からここまでの焼き討ちを重衡が考えていたのかどうかはわかりません。
というのも興福寺は藤原氏の氏寺であり、これを焼き討ちにすることは摂関家を敵に回すことに他なりません。
当時の清盛の勢いであれば「摂関家など何程のことやあらん」と思うかもしれません。現にこの頃の藤氏長者は藤原基通(従一位/摂政・内大臣)で、基通の妻は平完子(清盛六女)という関係から、当時の摂関家は完全に平氏に抑えられていたと言ってもいいでしょう。
しかし、この当時は奥州に奥州藤原氏という摂関家とは別の藤原氏勢力が存在していました。
源氏の謀反が連発しているこの時期、奥州藤原氏は頼朝を背後から狙える絶対的なポジションに位置しており、平家にとっては味方にしておくべき存在で、決して敵に回してはいけない存在でした。
それらをすべてわかった上で、重衡が南都の寺院を意図的に炎上させたとは私には思えないのです。
清盛が園城寺と興福寺を敵視した理由
年が明けて、西暦1181年(治承五年)正月、清盛は東大寺および興福寺の寺社領をすべて没収し、寺の別当(長官)と僧綱(管理責任者)らを更迭し、両寺院の再建を認めないことを発表しました。
これら一連の清盛の行動は園城寺、興福寺とさらに東大寺をも支配下においたことで、後白河法皇のシンパである仏教武闘派勢力を一掃し、南都宗派の抑え込みにも成功したことになります。
しかし、なぜ、清盛はここまでしなければならなかったのでしょうか?
これらを総合的に考えると、やはり親後白河法皇勢力の排除にあるのではないかと考えています。
本題からズレているので触れていませんが、高倉上皇は院政開始からまもなく病床についています。この状況で高倉上皇が亡くなった場合、自動的に後白河院政が復活します。
そうなった場合、平家にとってこれほど御しにくい存在はありませんでした。そして後白河院政の復活は、そのまま仏教武闘派勢力の復活につながります。
治承三年の政変以前ならいざ知らず、東国に源頼朝(演:大泉洋)、甲信越に武田信義(演:武田信義)、北陸に木曾義仲(演:青木崇高)、そしてこの時は九州、伊予でも反乱が勃発しており、その勢力と仏教武闘派勢力が結びつけば、平家そのもの政務・軍事力が奪われていくのは必定です。
そのため、なんとしても高倉上皇が存命のうちに、これらの親後白河勢力を排除しておく必要性があったのではないかと私は思います。
「政権返上」 の表現は正しくない
ドラマで清盛の死が描かれ、酒盛りをやっているシーンでナレーションはこう言っています。
「清盛の死を受け、宗盛は後白河法皇に政権を返上する」
これだけは表現として絶対に正しくないので、きちんと説明してこの記事を締めたいと思います。
高倉上皇の死=『自動的に後白河院政の復活』
平家は「保元・平治の乱」で源氏勢力と京都から駆逐し、平家に反する公卿を失脚させました。
その上、一族縁者を公卿に引き立てて、朝廷勢力を平家一門で固め、朝廷を支配していきました。
さらに清盛は後白河法皇に義理の妹の滋子(建春門院)を嫁がせて高倉天皇を産ませ、その高倉天皇に自分の娘である徳子(建礼門院)を嫁がせて安徳天皇を産ませました。これで清盛は天皇家の外戚になったわけです。
しかし、この時代、政治の中心は院(上皇・法皇)であり、天皇はその見習いみたいな存在でした。院が「治天の君」と呼ばれるのはこのためです。
平家が天皇家や摂関家に入り込むことを警戒した後白河法皇は、朝廷の権力工作(摂関の任命)や土地工作(荘園相続の介入)などを行なって平家を牽制しましたが、冒頭の通り、1179年に清盛にクーデターを起こされて院政を停止させられます。
法皇に代わって院政を行ったのは新たに上皇となった高倉上皇でした。しかし高倉上皇は前述の南都焼討の14日後(1181年1月14日)に病死します。
「治天の君」が薨去された場合、再び「治天の君」に返り咲けるのは院の直系の血縁者のみとなっています。
順番で言えば安徳天皇ですが、三歳の幼子に上皇が務まるわけがありません。また安徳天皇は幼子で結婚しておらず、皇子も存在しません。よって、この時、唯一の上皇だった「後白河院政」が自動的に復活することになります。
後白河院政復活前と復活後の清盛の策略
後白河法皇の中宮(正室)は前述の通り滋子ですが、この時はすでに亡くなっています。つまり法皇と平家との縁は切れています(それが治承三年のクーデターの遠因でもあったので)。
後白河院政復活となれば、法皇が平家に牙を剥くのは明らかでした。そのため、清盛は高倉上皇が危篤になると、極めて破廉恥な行動を起こしています。それは
「高倉上皇の中宮(正室)の平徳子(清盛娘)を、後白河法皇の後宮(後妻)に迎える」
というものでした。
要するに危篤状態の上皇の奥さんを離縁させて、今はまだ幽閉中だけど次の「治天の君」となる後白河法皇と再婚させようというものです。
これによって後白河法皇と平家は縁つづきとなり、平家は国政に関与し続け、権力の源泉を保持することが可能となります。
目的のためには手段を選ばない、なんとも恐ろしい考えですが、この策は平家周辺の関係各者からフルボッコにあっています。
すると清盛は自分の娘(七女)である御子姫君を法皇に輿入れさせました。しかし、法皇も清盛の意図を見抜いているため、一切手をつけなかったと言われています。
清盛の策は功を奏さず、高倉上皇の死去と共に後白河院政が復活します。
つまり清盛が死のうが生きようが、「治天の君」の地位は、高倉上皇が亡くなった段階で後白河法皇に自動的に移っているので、「(平家が法皇に)政権を返上する」という表現は間違っています。
ちなみに後白河院政復活後の清盛は即座に次の手を打っています。
1181年正月19日
「高倉上皇の遺詔」として嫡男・宗盛を畿内惣官職に任命。
※畿内一帯にまたがる軍事指揮権を宗盛に与えるというもの。
※畿内の兵馬の指揮権は平氏が掌握できる。
同年翌2月7日
丹波国(兵庫県北東部、大阪府北部)に「諸荘園惣下司職(国内の荘園の統括官)」を設置し、平盛俊(清盛側近・平盛国の嫡男)を任命。
※京に最も近い丹波国から自由かつ無制限に兵糧を調達可能。
これによって京周辺における兵馬と食糧を完全に平家のものにし、後白河法皇の好きにはさせないように釘を刺しています。
しかし、清盛はこの月の22日より病を得て床につきます。
そして翌月(閏月)2月4日、清盛は法皇に以下の申し入れを行っています。
「私が死んだ後は、政務のことはすべて宗盛に申しつけてください。何事も宗盛に仰せつけられ相談し、共に手をとって政務を行ってください。それが私の最後の望みです」
これに対し、法皇は「今はその時ではあるまい」とはぐらかしましたが、
「天下の事、すべて前幕下(近衛大将のこと、すなわち前右大将・宗盛)に委ねるのが最上であります。法皇様であってもこれに異論はなりませんぬよう」
とさらに強く申し入れました。
しかし、清盛はその答えを知る事なく、その日の閏2月4日病死します。
ドラマの劇中で言っていた通り、宗盛は源氏の戦いを止めることなく、追討の院宣を以って、東国への軍勢を出陣させます。総大将は平重衡。軍勢の数およそ数万騎。
その延長線上に「墨俣川の戦い」があるのですが、これは次のエントリーで触れたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
