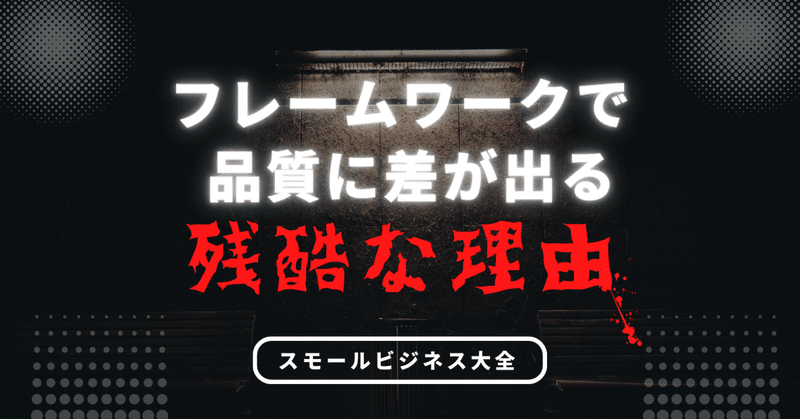
フレームワークでアウトプットに差が出る残酷な理由と改善方法
世の中には、賢明な先人たちが創り出してくれたフレームワークというものがありますよね。
例えば、マーケティング戦略を決めるためのWho・What・How、競争優位性を分析するためのPoX分析など。
ニッチ戦略やコストリーダーシップ戦略、差別化戦略なども「こうすれば競争優位性が築けるよ」と教える枠組みを作っているのでフレームワークと呼べるかもしれません。
これらは「この枠組みに沿って考えたら一定以上のアウトプットを保証してあげるよ」という性質を持っているはずです。
しかし、現実を見てみましょう。
起業志望者100人を集めて、「あなたが考えている事業のマーケティング戦略をWho・What・Howのフレームワークを使って考えてください」と指示したとすると、大体次のような結果になります。
15人はそもそも考えずに脱落→残り85人
85人中、一発で実用レベルのアウトプットができるのが5人→残り80人
80人中、フィードバックを貰って修正できるのが40人→残りの40人は諦めて脱落
※各種数値はこれまでの経験でざっくり置いたものです。
フィードバックを貰って修正するのが40人としていますが、マンツーマン型など強制的にやらせる環境を整えれば80人全員が修正する状況を作ることも可能です。
フレームワークに問題があるのか?否!
一発目で実用に耐えうるアウトプットができるのはたったの5%。
フィードバックを貰って修正できるのが40%、合計45%の人しか満足の行くアウトプットは出せないのです。
「これは……もはやフレームワークに問題があるのでは?」と思われるかもしれませんが、それは違います。
問題があるのは「フレームワークを提示するまでの条件づくり」です。
今回の指示「あなたが考えている事業のマーケティング戦略をWho・What・Howのフレームワークを使って考えてください」だけだと、Whoはどのくらいの粒度で、Whatとは何を表しているのか?など諸々の事が不明瞭すぎますよね。
この指示で合格点のアウトプットが出せる5%の人が凄いだけ。
指示を出す前に、Who・What・Howフレームワークの意味と役割を教え、正例・負例を理解させておけば一発目から合格点を叩き出す人は10倍以上に増えます(5%→50%くらい)。
正例:「こういうアウトプットを出してね」という良い見本。
負例:「こういうアウトプットはダメだよ」という悪い見本。
フレームワークの意味・役割、期待するアウトプットの正例・負例を教えるだけで、ただフレームワークを提示して、フィードバックをしたとき以上の人数が一発で合格点のアウトプットを叩き出せるのです(感覚ですけど)。
当然、意味・役割、正例・負例を教えた人に細かいフィードバックを与えれば更に多くの人数が実用レベルのアウトプットを作ることができるようになります。
フレームワークを提示するまでの環境を整えるだけでかなりの効果が期待できる。このことは覚えておきましょう。
フィードバックを貰わないと合格点が出せない人の特徴
ここまで、「意味と役割、正例・負例を教えれば半分の人は一発で合格点が出せる」と述べましたが、一発目で合格点を出せる人と、フィードバックを貰わないと合格点を出せない人の違いとは何なのでしょうか?
私自身、この謎に長年向き合ってきたのです。そして、この差異が思考のクセに由来するものだと最近になってようやく気付きました。
フィードバックを貰わなければ合格点が出せない人は、「自分がその事業を進めるという実感に乏しい」のです。いわゆる当事者意識ってやつに欠けているんですね。
学校教育など様々な場面で”それっぽい答え”を出すことが癖づいている人は、どのようなフレームワークを与えたとしても一見すると”それっぽい答え”を出せてしまいます。
しかしそこには「顧客へ刺さる商品、売れる商品を作るためのプロセスである」という認識が欠けているのです。
Whoというのはあなたの商品を必要とするターゲットのこと。
商品の提供する価値を大きくとらえたときにリーチできるターゲット(戦略的ターゲット)と、あなたの商品をめちゃくちゃ魅力的に感じるターゲット(優先的ターゲット)の二つ考えてくださいーー
~~意味・目的、正例・負例の説明~~
このようにフレームワークの意味・目的、正例・負例を伝えられたとしても「このタスクは売れる商品を作るためのプロセスである」という認識に欠けていれば良いアウトプットは出せません。
学校の課題を解くのに慣れ過ぎた人はフレームワークをあたかも宿題かのようにとらえて、「それっぽいアウトプット」を作り上げる傾向にあります。
意味ないですよ。
改善する方法はないのか?
あります。例えば、会社で上司から逐次フィードバックを貰って「当事者意識」が当たり前に身につく環境で働くなどすれば徐々に改善されていきます。
逆に言うと、定期的にフィードバックを貰い、「あ、このアウトプットはダメな思考のクセが出てる」ということに気付けるようにならなければ、改善するのは難しいかもしれません。
第三者にフィードバックを貰う環境が作れない。という人はアウトプットを出す前に"品質評価のための質問"を用意しておくとよいでしょう。
品質評価のための質問というと、ややこしいですが要するに「アウトプットが意味のあるレベルに到達してるか?」を確認するための質問です。
例えば
このアウトプットは、売れる商品を作るための成果物として求める品質に到達しているか?
このアウトプットを基にタスクを進めていけば売れる商品ができると思うか?
自分が顧客だとして、本当にこのアウトプットからできた商品をお金を払って購入したいと思うだろうか?
友人や見込み顧客がこのアウトプットを基に作られた商品を見てなんと言うだろうか?
など、
使用するフレームワークに合わせた質問を考える必要がありますが、自分に厳しい上司が居ると想定して質問を考えておきましょう。
アウトプットの品質はフレームワーク由来のものに限らず、日々の生活・習慣に由来する部分が大きいです。そして悲しいことにアウトプットの品質が低い人ほど自分のアウトプットが低いことに気付いていません……。
良い質問を事前に考えていたとしても「このレベルで本当に良いのか?」を判断するのが自分である以上、必ずアウトプットの質を高められると言い切るのは難しいですが、一定の効果はあります。
アウトプットを一日から三日ほど寝かせておいて、第三者になったつもりで評価すると、更に効果を高めることができます。
とはいえ、完全に客観的な目線で見るのは本当に難しいです。アウトプットの品質(思考の癖)を、一朝一夕で改善できるとは思わない方が良いでしょう
そして、品質を改善する”簡単な”方法はありません。
例えば、ダイエット、最初に想定したようにやり切れた経験はありますか?
宿題、計画通りに終わらせることができましたか?
寝坊、しようと思ってないのにしてないですか?
運動、やる気が続いたのは何日ですか?
つまり、今のあなたが改善したい。と思っていても明日のあなたはそう思わないのです。明日のあなたが思ったとしても3日後のあなたはそう思いません。
1ヶ月後、1年後のあなたは「思考のクセを矯正しよう」と思ったことすら忘れてるはずです。そんなもんです。絶望ですね。
最後にちょこっと希望が持てる話
ここまであまりにも残酷で無慈悲な話ばっかりだったので、最後にちょこっと希望が持てる話をします。
世の中には「習慣を変えたい」と思うひとたちが割と沢山いて「身に付いた習慣をどのように変えるのが最も成功率が高いのか?」と研究する人たちは結構いるんですよね。
だから、当然論文は沢山ありますし、それを一般向けにした書籍も沢山出ています。
その中から「これだ!」と思う一冊だけを選んで、書いてあることを忠実に実行してみたら人生が変わります。まぁ、その一冊に何を選ぶか?が重要なんですけどね。
以下、購読者限定部分では「私が一冊を選ぶならこれにする」という書籍の紹介と、フレームワークを効果的に使うためのチェックリストを載せてます。
初月無料で二か月目以降も980円と手ごろな価格です。70記事弱の購読者限定記事(無料だけど購読者限定領域があるnote)も読み放題なのでかなりお得です。
有料記事についてはこれまで購読していた月のものしか読めませんが、それでも十分に読みごたえがあると思いますので、興味がある方は定期購読をおすすめします。
習慣を変えるために私が選ぶ一冊
購読者限定コミュニティの【03_面白かった情報シェア】にも投稿してありますが、習慣を変えるための本を一冊だけ選ぶなら
ここから先は
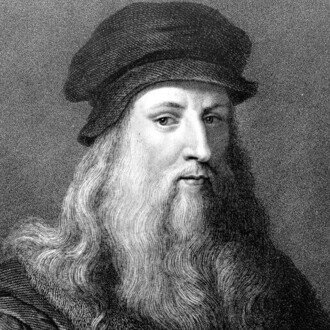
スモールビジネス大全
【低リスクで副業的にビジネスを立ち上げ自由に使えるお金を増やしたい方へ】 - 海外スモールビジネスの実例(ケーススタディ) - リスクを最…
サポートしたつもりで身近な人にプレゼントして上げてください.
