
『水底の橋』『ほの暗い永久から出でて』を読んで
こんにちは桜です。今日は、かねてから興味がありようやく読めた2作品について拙文ながら感想を書きました。どうぞ宜しくお願いします。
上橋菜穂子さん『水底の橋』同じく上橋菜穂子さんと医師の津田篤太郎さんによる『ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話』
『鹿の王』その後
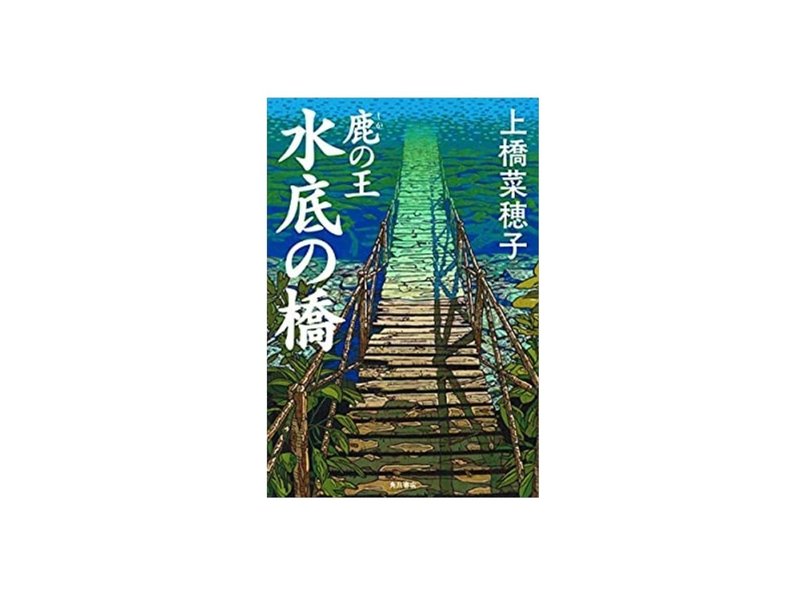
数年前、本屋大賞受賞の『鹿の王』の壮大なストーリーを夢中で読みました。感染症×上橋さんの作品はその世界観が唯一無二のものだと圧倒されたのを覚えています。
そして2020年夏、リビングに常に娘達のいる夏休み。決して時間に余裕があるとは言えない状況でも、コロナ禍の今何とかして読みたいそう強く感じていたのが 続編『水底の橋』です。
こちらは『鹿の王』その後のお話で、外伝的な意味合いがありました。今作は、ホッサルとミラルのストーリーです。
現実の世界でも数多ある民族によりその死生観は異なりますが、この物語では清心教医術とオタワル医術がお互いの立場にしたがってそれぞれのカタチで医術を施していました。美しい景色が目に浮かび、医療や政治が見事に描かれた作品で一気に読みました。
立場は違えど“人を救いたい、なんとかしたい”想いがある。
これは現代の医療関係者の皆様と等しい心の底にある想いなのではないかと感じました。“人を助けたい”その気持ちに感謝する日々です。最近はSNSで医療を優しく教えて下さる方もあり、勉強させていただいています。
作者上橋菜穂子さんは、『水底の橋』を書く前にご家族を亡くされ、ご自身も年を重ねる中で人の命について熟慮されたとインタビュー記事※で拝見しました。
以前#自己紹介noteで触れましたが、私は昨年病により手術をうけたため、予定より何年も早く突然更年期が訪れることになりました。医療は自分事になると急に近い分野になるものですね。
だからこそ、上橋さん自身の状態にも共感し「ある病気の治癒はひとつの経過でしかなくて、やがて、身体が命を支えられない日が訪れて人は逝くのだ」という考えに深く頷くこととなりました。
大きな時間の流れに坑うことはできないけれど、あわよくばそれまでは楽しく過ごしていたい。経過中助けてくれるのは健康管理をする自分自身とホッサルとミラルのような医療に携わる方々なのかもしれません。
おおよそ80年の人生だとすると、ある意味半分を過ぎればもう終わり支度が少しずつ始まっているのでしょう。今『水底の橋』を読めて良かった。ここから先をどう生きていくのかが今の私の新しいテーマになりました。
対話『ほの暗い永久から出でて』

そこで、もう一つの本『ほの暗い永久から出でて 生と死を巡る対話』上橋菜穂子さん と津田篤太郎さんによる本を手にしたのです。
これはお二人の手紙のやりとりが織り成す形の本でした。西洋医学と東洋医学の両方を取り入れた診療を実践している聖路加国際病院の津田先生と上橋さん。お二人共に、とにかく医療のみらず広く全てにおいて造形が深すぎる。想像の何倍も情報量がありました。会話のような手紙の応答が、一つ一つとにかく深いため、ゆっくり何度も読み返したいそんな本になりました。
なんのために生まれ、なんのために生き、なんのために死ぬのか。
この本の中で、生物のシステムは命を支えながら病や感染症に立ち向かったり、その驚くべき能力でやがて個体の命をおわらせようとしていると記されていました。また様々な見解も知ることができました。
私など知らないことばかりでまだまだ勉強不足ですが、おばさんになった今読むとなんだか人間そのものを少し俯瞰で見ることができました。
お話が多岐にわたる為、いろんなことに想いを馳せましたが、この本の中で上橋先生がおっしゃるように、ならば残りの時間を輝かせたいと私も思うようになるそんな一冊でした。
***
ちなみに…単行本で読ませていただいた『水底の橋』も『ほの暗い永久から出でて』も文庫化され写真の表紙が新たに変わりました。2冊ともに新型コロナウイルスに関する文章が追記されましたので文庫版オススメです。
お読みいただきありがとうございました。
桜
リンク失礼致します。
※出典参考資料ダヴィンチニュースインタビュー(2019.4)↓
いただいたサポートは娘達への図書カードに使わせていただきます。
