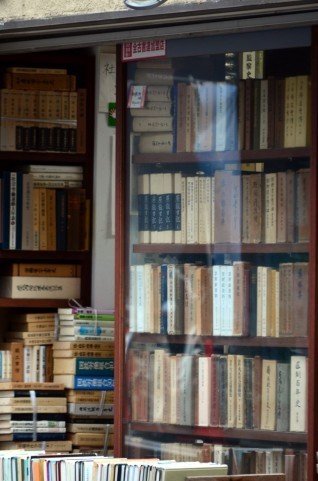
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2019年5月の記事一覧
縄文から弥生への記憶なのか
つまり、6つの別伝が終わった後、再び日本書紀の本文が始まります。
次に神有り、埿土煑尊埿土・沙土煑尊、次に神有り、大戸之道尊・大苫邊尊。次に神有り、面足尊・惶根尊。次に神有り、伊弉諾尊・伊弉冉尊。
こうして、有名なイザナギ・イザナミが登場してくるわけです。
ところで、日本書紀冒頭部の第二別伝では、「葦牙の抽け出たるが如し」と葦の芽のようなものがあったとしています。
この葦の芽について、他の




