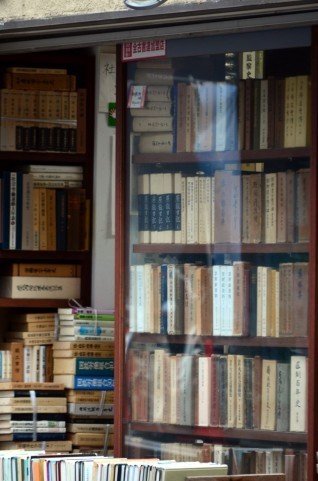
聖書や日本書紀、平家物語などを読みながら、「日本」について外国人に説明するにはどうしたらいいかとか、農村部の論理と都会人の論理がどう違うかと言ったことについてのヒントを考えていま…
- 運営しているクリエイター
2019年1月の記事一覧
混沌の次に古い奈落とエロス
原初にカオスが生じた。胸幅広いガイア(大地)、雪を頂くオリュンポスの頂きに宮居する八百万の神々の常久に揺るぎない御座なる大地と、路広の大地の奥底にある曖々たるタルタロス、さらに不死の神々のうちでも並びなく美しいエロスが生じたもうた。この神は四肢の力を萎えさせ、神々と人間ども、よろずの者の胸うちの思慮と考え深い心をうちひしぐ(ヘシオドス 神統記 岩波文庫版)
ヘシオドスの神統記では、原初にカオス=
贈与は物々交換でなく、信用を前提にしていると言うこと。
マルセル・モーセの贈与論は、非常に示唆に富んでいます。
面白いと思ったのは、贈与経済と言うのは、物々交換ではないと言うこと、信用を前提にしていると言うこと、銅器が「名前」を持っていると言うお話です。
三番目の件は、また後で書くとして、僕もそういう言い方をしてきたことがありますが、通俗的な「貨幣」についての説明と言うのは、
ある人がお米を持っている、別な人が布を持っている、
でまあ、お米と布

