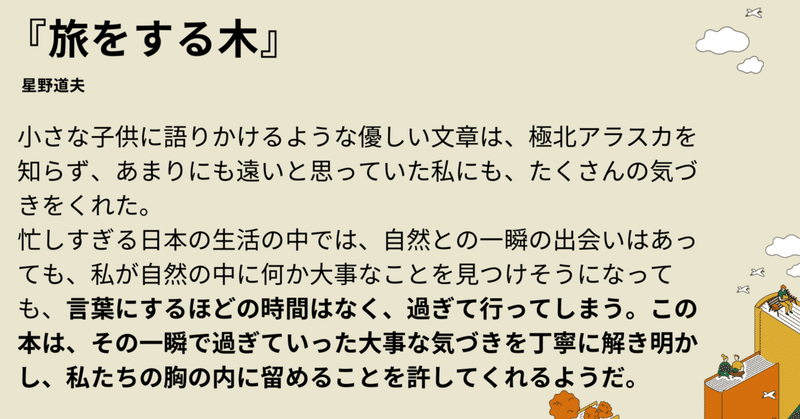
その木も旅をしているのかもしれない〜『旅をする木』/読書感想文
いつも行く公園の入り口に、
大きなアキニレの木が立っている。
季節は秋。
実は褐色に色づき、葉は黄金色に変わり、クリーム色と水色を薄く伸ばしたような空に、さわさわとそよぐ。歩くと地面はカサカサと音を立て、落ち葉の匂いがする。
このアキニレの木は、私の知る限り、旅をしない。
いつも公園の入り口の同じ場所に立ち続け、四季折々の姿を見せてくれている。
では、星野道夫さんの著書『旅をする木』に書かれているのは、どんな木なのだろう。
本の中で、筆者はアラスカの自然を物語のように書き上げた本"Animals of the North (北国の動物たち)" の第一章"旅をする木"について紹介している。
アラスカの中でも特に北の土地、ツンドラと呼ばれる凍った地面には、木が生えないのだそうだ。ツンドラに横たわっているトウヒの木は、もとは南方の内陸のトウヒの種子だった。鳥がついばんだ実が落ちて、種子は川沿いで大木となった。長い歳月の中、川の侵食によって大木は流され、極北のツンドラにたどり着く。木が生えない土地でランドマークのような存在になった木は、キツネがテリトリーとしたり、エスキモーが罠をしかける場となる。最後には、エスキモーの家の薪ストーブの中で、旅を終えるのだった。
こんな壮大な旅があるのか。
木はそこに生えているものであって、旅をすることなんてないと思っていた。
けれど、そうではなかった。
目の前にあるアキニレを、もう一度見る。このアキニレにも、アラスカのトウヒと同じように、野鳥がやってきて実をついばんでいる。この野鳥が海の近くに種子を落とせば、木は育ち、潮流に乗り、アラスカに渡ることだってあるのかもしれない。
大きな自然や時の流れを想像する時間は、なんと豊かなのだろう。
この本は、そんなアラスカの自然や人との関わりからの気づきに溢れている。写真家であった筆者のあたたかなファインダーを通して、アラスカの自然や人、さらにその先にある人生を一緒に見せて頂いている気持ちになる。
この本を読む前は、アラスカは、今私のいる日本の首都圏という場所から、途方もなく遠かった。
遠すぎて別世界のように感じていたし、ちゃんと興味を持って最後まで読み切れるのかな、と不安に思っていたくらいだ。
けれど、杞憂だった。
一編一編を大事に読み進めながら、
「これは私のこの先の人生で、
何度も読み返したい本だ。」
とじんわりと感じた。
読む前には、先の不安もあったが、淡い希望もあった。
未だ続く閉塞的な日常から離れ、遠いアラスカという地を旅するように、描かれた自然に触れることができればなぁ…と。こちらは、その通りになった。
文章もしみじみと良い。自然や動物に詳しくなくても、分かりやすい言葉で書かれている。小さな子供に語りかけるような、優しさに溢れている。
アラスカは確かに遠い。
けれど、その遠さを感じさせないほど、文章には不思議と納得感があった。
よく考えれば、私も日々自然の中を生きているのだと思い至る。
現代を生きる私たちが、
「自然の中にいる!」なんて、
きちんと実感するのは、キャンプに出かけたり、山にハイキングに行ったりする時くらいになってしまったかもしれない。けれど、それでも自然の一部を借りて、動物が巣を作るように家を建て、その中で日々生活していることに違いない。
だから、どんなに便利な生活を送っていても、
人は自然に惹かれるし、自然から学ぶことはきっと山ほどあるのだろう。
それはアラスカだろうと、日本だろうと同じなのではないか。
けれど、忙しすぎる日本の生活の中では、
自然が何か大事なことを見せてくれたとしても、
私が何か大事なことを見つけたとしても、
それは言葉にできるほどの時間はなく、一瞬で過ぎていってしまう。
アラスカの自然を書いたこの本は、その一瞬で過ぎていった大事ななにかを丁寧に解き明かし、ふたたび私たちの胸の内に止めることを許してくれているようである。
たとえば、アラスカの秋。
冬籠もりのために木の実を食べるクマ、枯れ草をくわえたナキウサギ、南方へ去って行くカリブーやカナダヅルを見つける。原野を染める輝くように美しい秋を前にして、筆者はこう語る。
無窮の彼方へ流れゆく時を、めぐる季節で確かに感じることができる。自然とは、何と粋なはからいをするのだろうと思います。一年に一度、名残しく過ぎてゆくものに、この世で何度めぐり合えるのか。その回数を数えるほど、人の一生の短さを知ることはないのかもしれません。
“北国の秋”より引用
あぁ、その感覚なら知っている。
アラスカのように大きく迫ってくる自然ではないけれど、私も忙しい毎日の中で、移ろう季節を感じることはある。
窓を開けて、金木犀が香った、とか。アキニレの降るような落ち葉が美しい、とか。そんな些細なことで、秋が本格的にやってくることに心が弾んだり、季節が去って行くことを寂しく感じたりすることがある。
けれど、それはやはり、ほんの一瞬のこと。
なかなかそこから人生を振り返って深く掘り下げるほどにはいたらない。日本での生活は目まぐるしいし、自然以外に目に入ってくるものが、あまりにも多すぎる。
そんな生活の中で、この本は思い出させてくれる。
一年に一度、名残しく過ぎてゆくものに、この世で何度めぐり合えるのか。その回数を数えるほど、人の一生の短さを知ることはないのかもしれません。
あぁ、私は過ぎて行く時間の中でわすれてしまっていたけれど、もっと自然とじっくり向き合いたかったし、こういうことを感じていたかったのだと気づく。
この本に書かれた33編はどれも、遠いアラスカを見つめながら、私を人生の大事なところに立ち返らせてくれる。何度も読み返すことで、その大事なことを自分の中に留めておけたらと、強く思う。
この本を読んで起こった私の変化は、以下の文章と少し似ている。
筆者にとって旅する先だったアラスカが、定住を決めたアラスカに変わる場面である。
それまでのアラスカの自然は、どこかで切符を買い、壮大な映画を見に来ていたような遠い自然だったのかもしれない。でも、今は少し違う。たとえば、自分自身の短い一生と原野で出合うオオカミの生命が、どこかで触れ合っている。
“アラスカに暮らす”より引用
この本を読んで、私にとってのアラスカも、映画のように遠い異世界のことではなくて、同じ時間を生きている、同じ地球上の出来事なのだと感じはじめている。
遠いアラスカの大きな自然と、
すぐそばにある小さな自然との交わりを見つけることができたからだし、
この本を開くことで、いつでもアラスカの自然に会いにいけると知れたからでもある。
けれどやはり、トウヒの木でもアキニレの木でもなく、
私自身が旅をして、
いつかこの目で確かめてみたいとも思う。
本当に同じ地球にあることを確かめて、
その大きな自然に向き合った時、
私自身は一体、何を思うだろうか。
本を開いて、その日を想像することも、
また、楽しいのである。
読んでくださり、ありがとうございます! いただいたサポートは、次の創作のパワーにしたいと思います。
