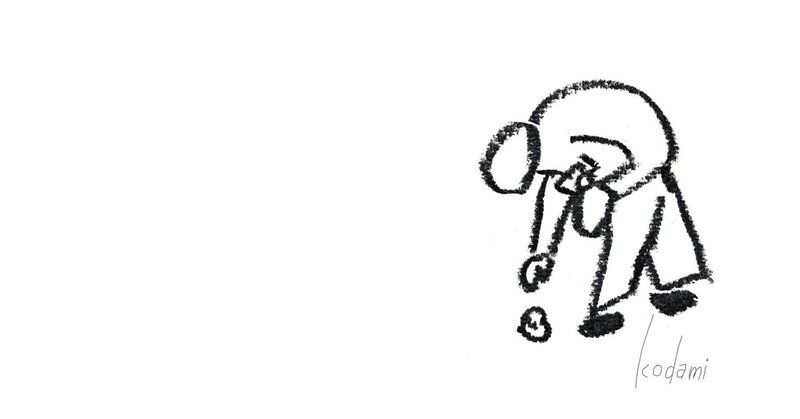
遊びながら変えていくルール / 『手の倫理』から考える
子どもとの遊びは決まりがない。
ルールがある遊びであったとしても自由に変えていいし、お互いに良いなと思ったことを取り入れて新しい遊びになる。
例えばごっこ遊びをしていても、自由に関係のないキャラクターやストーリーを組み合わせて遊んでいくことが多い。
また、ルールというものに慣れ親しんでいる大人である自分としては、時おり面倒くさく感じる場面もあるけれど、遊んでいく中でルールや遊び自体がなめらかな流れで変化していくことも楽しい。
「~~遊び」と「~~遊び」・・・をして遊んだ
ということではなく、細分化されたそれぞれの「~~遊び」をひっくるめた名前のつけられない「遊び」を共有することを楽しんでいるのかもしれない。
もちろんルールがあることも楽しいのだけれど、自由な遊びの中にある不安定さがワクワクやドキドキを生み出しているのだろうと思う。
不安定とは何なのか
『手の倫理』で書かれている「触れるコミュニケーション」に生じる不安定さと共通しているのではないかと合わせて考えてみる。
ほどきつつ拾い合う関係
一方的な「触る」ではなく「触れる」コミュニケーションとは、
「ほどきつつ拾い合う関係」と『手の倫理』では表現している。
トレーナーは私の腕の伸びぐあいや筋肉の張りを感受しながら、「腕を引っ張る」力の強さを調節しているのであって、そういう意味では、私の「腕が伸びる」が能動的で、トレーナーの「腕を引っ張る」が受動的ともみなしうるのだ。このように、相互に情報を拾い合い、影響を与え合う関係が、ある程度成立している。
家族や、気心の知れた関係性の深い相手とコミュニケーションをとる際、やりとりが不安定であることに気づきにくい。もちろん違和感ややりづらさを感じたりすることもあるけれど、はっきり認識出来ていない。
ふれる側が抱える不確実性は、ふれたことによる相手のリアクションが読めないという不確実性です。つまりリアクションの不確実性を超えることが、ふれる側にとっての信頼になる。
これに対して、ふれられる側の不確実性とは、ふれようとしている相手のアクションが読めないという不確実性です。つまり、アクションの不確実性を超えることが、ふれられる側にとっての信頼になります。
接触とは、この異なる二種類の不確実性が出会う出来事です。
「ほどきつつ拾い合う関係」
「不確実性」
要するにコミュニケーションは自分と相手の両方が、探りながらお互いに進めていくことなのだろう。
そんなこと「当たり前だろう」と自分でも突っ込みたくなるけれど、いかに自分が今まで「触れる」ではなく、「触れる」雰囲気の「触る」中心でコミュニケーションをとっていたのかと気づかされる。
共話と対話
「触る」と「触れる」の概念に似ている考えが、『未来をつくる言葉』という本にも書かれている。
共話
話者同士が互いのフレーズの完成を助け合いながら進める会話様式
対話 : (ターンテイク)片方が話を終えてから、他方が話を始める。AとBの差異が強調され、互いの主体性は交わらない。
共話 : (あいづち)片方が話を終える前に、他方が話を重ね始める。AとBは協働して文を作り、互いの主体性が交わる。
対話では個々の主体の差異が明確になるが、共話のなかでは主体がコミュニケーションの場に溶け込んでいく。
どちらかが良いということではなく、どちらも必要
「触れる」と「触る」
「共話」と「対話」
2つの概念を見てみると、どうしても自分の中では共に作っていく「触れる」「共話」に魅力を感じてしまう。自分がうまく出来ていないからなのかもしれないけれど、子どもとのコミュニケーションでは特にである。
「共話」は一見いつものコミュニケーションでやっているのかもしれないが、「対話」の特徴である主体意識を多く含んだ「共話」になってしまっていないかと不安な気持ちもある。
ただ、やはり必ずしもどちらかのコミュニケーションの方が良いということではないのだろう。一方的な雰囲気を感じる「触る」「対話」であっても最適な場面があるのだろうし、良いと思う態度でばかりコミュニケーションをとっていくと広がりがなく、どこかで行き詰まってしまう可能性がありそうだ。
その両極にも「良い」「悪い」という軸の違いがあるはずで、
①「良い触れる」「良い共話」
②「悪い触れる」「悪い共話」
③「良い触る」「良い対話」
④「悪い触る」「悪い対話」
のようにいろんなパターンがあるからこそ、自由に行き来をしながらグラデーションのように細分化されたコミュニケーションがとれるのだろうと思う。
共創には対等という態度が大切
①~④のパターンを使いこなすことは難しいけれど、自分にとって足りていないと感じている『良い「触れる」「共話」』をまずは少しずつでも取り入れていきたい。
互いに探り合いながらコミュニケーションを進めていくということは、いろいろな立場の違いはあっても、共に作っていく共創関係なのだから、態度としては対等であることを意識しないといけないのだと感じている。
対等という関係を忘れた先に、いつしか共創の格好はしていても一方的なコミュニケーションというものに変化してしまうのではないか。
対等という態度が大切
ただ、また自分の場合そこばかり意識し過ぎてしまうと偏りが生まれてしまうこともあるのだろうなと思う。
わかりやすい親子関係で例えると、明らかに知識、経験、思考回路、思考スピードなどなど全てにおいて違うのに、対等関係にばかり囚われていると自分が感じる基準で判断してしまい、自分が納得できる反応ではなかった時に、不満を感じてしまうなどというようなことがありそうだ。
コミュニケーションは気を抜くと「触る」「対話」のコミュニケーションに引っ張られる引力のようなものがあるのかもしれない。
自分に「触る」コミュニケーションが根付いているから引力を感じているだけで、全く反対の人ももちろんいるのだろうとは思うのだが。
対等ではあるのだけれど、他人なのだからお互いの立場や状況、いろいろな差異があるのが当たり前。
だからこそ、マインドを常に対等に保つ為には、シンプルに差異を補うという気持ちが大切なのだと思う。
補うというのは要するに「拾う」こと。
まずは自分が「拾う姿勢」で交わることこそが、相手からも拾われる
「ほどきつつ拾い合う関係」に近づく為に大切なことなのだろう。
拾うための足がかり
「触る」や「対話」というものは、過去や未来にとらわれている一方的なコミュニケーションとも言えるのではないだろうか。
過去を見て思い込み、判断し、決めつけている。
未来を見て思い通りにしたいという思惑が生まれている。
過去や未来を一切とっぱらって、今現在のみに集中すれば変な思い込みや思惑が入り込む隙きがなく、対等なマインドで共創できるのだと思う。
大人と子どもの違いは、
大人は過去、現在、未来すべてを見ているが、子どもは現在のみを見ている。と良く言われている。
だとすれば、共創するコミュニケーションは子どもをお手本にするのが一番良いのかもしれない。
それに、遊びながらルールが変わる自由な遊びそのものが、実は自分が理想とするコミュニケーションの形なのだと気づくことが大切で、守らなければいけない体験なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
