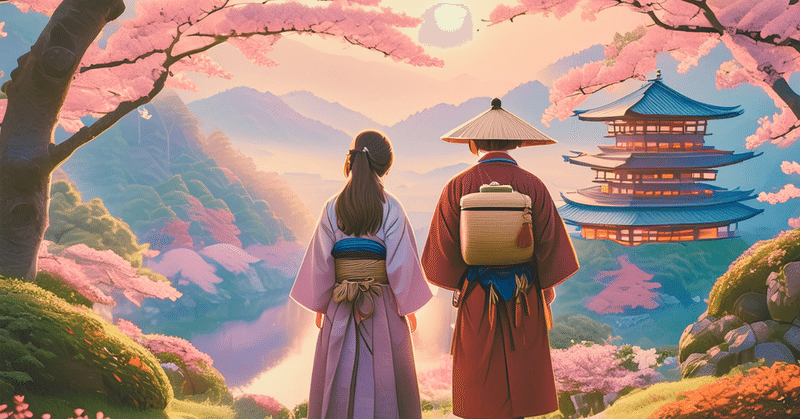
あくびの隨に 22話
前回
猛る炎の渦に飲み込まれる数良を、逸流は呆然と見送る。
「そんな……どうして、あんな無茶を」
「母の面影を渇望したか」
逸流の横に立ちながら、稲は数良の心情を言表す。
「肉親への情念は理性とは異なる。たとえそれが無意味と頭の片隅で理解していようが、湧き上がる執着心を捨て去ることなどできはせん」
淡々とする稲は、嘆く逸流をどこか意味あり気に見つめる。
その視線を受け止めて逸流は悟った。彼女はこれから、自分が言おうとする言葉を予感し、それを明言する機会を与えてくれたのだ。
「稲……僕は、あの子を助けたい」
「それがぬしの選んだ道なれば、私はひたすらその傍らに在ろう」
理解の範疇に押し留めるように、稲は逸流の在り方を認めた。
人々から少し離れた位置に移動し、稲は片手を空に掲げる。
月のいずる晩は横薙ぎの風に煽られていた。しかし光を遮ることはできず、月光を通じて舞い降りるものは、しかと地上に顕現せしめる。
「繚乱季装が伍の光――〝鳳葉〟」
地に突き刺さった陰影。それは今回、二つあった。
まったく意匠の同じ二振りの手斧。常識外れに幅の広い斧刃と比べ、非常に短い握り。左右片手で持つためにあるそれは、どこか羽を模すような造りである。
「斧の誓約は振り下ろしであるが、家屋を破壊してしまっては元も子もあるまい?」
稲は呪封符札を逸流に渡しながら、助言めいた台詞を残した。
逸流は身体に誓約を宿して両手に鳳葉を握る。その重量は、持ち上げるのも一苦労するほどの塊だった。これではたとえ誓約がなくても、まともに振り下ろすこともできない。
斧を地面に引きずりながら、逸流は火事の大本である建物の前に向かう。
周囲の人々は大火に気を取られて、逸流を気にかける暇もないようだ。見咎められることなく、炎に恐怖する者たちの間を抜けて屋敷の前に佇む。
「建物を壊したら、数良が巻き添えになる……けど、他にどうやって火を消せば」
逸流は思わず稲を見そうになるが、これは自分がやると決めたことだ。
彼女に救いを求めるのはお門違いであり、そもそもこれまで稲は一度も繚乱季装の使い方を教えて来なかった。
己の考え一つで切り抜けなければ、人を救う行為は偽善にすら成れないのだ。
「……そうだ、風は?」
はたと逸流は、横殴りの風を受けて発想した。
斧を振り上げた風圧で、火を消そうと考えたのである。
しかしすぐにそれが愚策と気づいた。風は火を煽って他に被害をもたらすもの。無暗に力を振りかざせば、街は今以上の災禍に見舞われる。
火を消すには水をかけるのが最善だが、この辺りに池のようなものはない。井戸では量が足りず、他に使えるものと言えば土ぐらいだ。炎は酸素を糧に燃えているので、それを取り込めない状況を作ってしまえば自ずと鎮火する。けれど、結局地面に力をぶつければ二次被害の方が甚大になるし、そもそも斧を振り下ろすことには誓約がかかっている。
それこそあとは、建物自体を消し飛ばすしか――
「……腐土の権現が飛んでやがる」
そのとき逸流は、昼間の数良の方便を思い出した。
ぱっと上空を見て、一縷の望みが湧いて来る。
「やるしかないか」
逸流は柄を固く握り、そこに季力を込めていく。
炎を失くすためには周囲が無酸素状態になれば良いが、いくら突風を巻き起こしたところでそれは不可能だ。ならば火元そのものを消してしまえば、燃えるものがなくなった火が残ることはない。
横薙ぎに力を放出すれば、隣家を巻き添えにすることは必至。
だが振り上げてしまえばどうだろうか。瓦礫を巻き込んで上空に舞った炎は、山岳に位置するこの街の特性上、湿気を多く含んだ風に乗る。そこで火が消えてしまえば、たとえ残骸が落ちてきたとしても火事は無くなる。もう大火が広がることはないのだ。
「……でも、できるのか」
力を振るうと決めて逡巡、逸流は建物に入った数良が気にかかった。
家屋が吹き上がれば、間違いなく数良も巻き込まれる。一緒に上空へと飛ばされれば、地面に落下して即死は免れない。
逡巡する逸流は、じわっと、握り締めた鳳葉の柄が熱く滾っていることに気づいた。
この感覚は繚乱季装を使う度に感じるものであり、逸流にその絶対的な力を示してくれる足掛かりとなっている。
逸流の自信など要らない。
この武器を、これを託した稲を、逸流はただそのひと振りのために信じるだけだ。
「……いや、違う」
行動に移そうとした直前、逸流は感じた。
持っている鳳葉は二振り。一度でも力を使えば、逸流の全身から季力が失われて、二度と振るうことはできないだろう。
しかしその羽ばたきが、同時である必要はないのだ。
「数良、無事でいてくれ!」
逸流は右手に力を込めて、それを一気に振り上げた。
ぶわっ――と地面から立ち昇る突風。
豪、と渦巻く上昇気流。
唸る斧撃は光を纏い、破砕の威力を天に打ち上げる。
しかし被害を与えないために、優しき想いが籠った一撃はそれに応えて、家屋ばかりを破壊した。
隣家に登っていた火消したちは、突然の強風を受けて屋根へとしがみついた。炎を伴って丸々一棟が宙に舞い、自分たちが消火するはずだった火事そのものが、花火のように夜空へと場所を移したのだ。
上空に視線を向けた逸流は、建物の残骸の中に二つの人影を見出す。
鳳葉の気流にのった数良と取り残された遊女が、重力を無視してそこに浮かび上がっていた。だが、このままでは彼女たちは落とされる。
「もう一つ……っ!」
地上から再び、逸流は鳳葉を振り上げた。
今度は左手から放たれる閃光は、業火たなびく瓦礫群を瞬時に飲み込んだ。
腐土の権現を塵に還すように、輝きを受けた残骸は微塵となって山の気流に流される。
されど、数良たちの身体を覆うは揺蕩う風。
降り注ぐ灰と消し炭の残り滓に混じり、二人は天女のようにゆっくりと、地上の残骸の中心に舞い降りてくる。
火事の跡地には、まだ微かに炎の燻りが残っていたが、それは風前の灯。 夜風に掻き消えるほど儚い火種は、今ここで完全に潰えた。
「数良!」
逸流は斧を手放し、更地と化した空間に走った。
今し方、自らに起きた奇跡に愕然としつつも、数良はすぐさま遊女を気にかける。
煤だらけで横たわる女性は、多く煙を吸っていた。それでも僅かな呼吸を頼りに、意識を失った彼女を見て数良は胸を撫で下ろす。
「……」
しかしすぐに数良は項垂れる。
全身の節々に負った火傷の跡が、とても痛々しかった。
「なぁ、馬鹿みてぇだろ。おっ母なんているわきゃねぇ。火が強すぎて、帰る道なんざなかった。さっきの奇跡みてぇな風が吹かなきゃ、自分もこの女も、間違いなく死んでた。自分は、どうしてこんなとぼけた真似しちまったんだろうな」
理屈では語りきれない己の言動に、数良は困惑しているようだ。
逸流は彼女に、その意味を教える。
「それが数良の本質だからだよ。僕と稲を救ってくれたときみたいに」
「だとすりゃ、自分もおのれみてぇなとんまだった、って。そういうわけか?」
「人助けは悪いことじゃない。たしかに、救う力のない人間が何を言っても無意味で終わるかもしれないけど……それでも僕は、自分もそんな人間でありたいと思ってる」
「けっ。やっぱ、おのれは底抜けのお人好しで……優しい、にぃにだよ」
数良はすっくと立ち上がり、正面から逸流と向き合った。
すぐに立ち直る気骨の強さは数良の長所だろう。そうでなければ、到底この色に溺れた街で生き抜くことはできないのだから。
「――追い着いたぞ、そこの不届き者ども!」
そんな中、唐突に上がる怒号に逸流たちは振り返った。
見ると、通りの群衆を払い除けて先ほどの同心風が、部下を引き連れていた。
彼らは物々しい雰囲気を纏いながら、逸流たちを見て血気盛んに告げる。
「この火付け、お前らの手であることは一目瞭然! よもや言い逃れはあるまいな!」
「ふざけたこと、抜かしやがって……」
数良は唇を噛んで、同心を睨みつける。
再び逃亡を繰り広げなければならないのかと逸流も思ったが、その矢先に訪れる眠気。
逸流が膝をつくと、数良は慌てて声をかけてくる。
「にぃに! まさか煙にやられたのか!」
「ち、違う……けど、もう……」
目の前がちかちかと白くなり、逸流は意識が飛びかける。
「案ずるな、こやつの身体に問題はない」
事情を知る稲は数良に言い聞かせながら、ある言葉を彼女に向けた。
「数良よ。そなたの心、すでに寄せておるな。なれば問う。仮にこやつが大事を成そうとしたそのとき、この礎となる心構えは持ち合わせているか?」
「え……な、何のこったよ。いきなりそんなこと言われたって……」
稲の不可解な台詞に数良が動揺する中、役人の足が逸流たちに近づいてくる。
それを見て、数良は倒れそうになる逸流に目を向けた。
到底走ることのできないその身体では、呆気なく役人に捉えられて死罪を言い渡される。
彼女にとって、それはきっと己の身を削られるよりも辛いことだった。
「……なぁ、ねぇね。逸流はさ、とんでもねぇことやらかしそうだなって、何となく自分は思うんだけどよ。それって自分が単に、絵空事描いてるだけなのかな?」
「それは分からん。されどこれだけは言えよう。たとえそなたが叶う見込みもなき、淡き泡沫を抱いていようが、こやつは決してそれを笑わぬだろう」
稲の弁に迷いはなく、それを受けた数良は一つの答えを見つけたようだ。
「ったく……そんだけ聞けりゃ、上等さ」
数良は口端を緩めて、逸流と稲の姿をしかと瞳の中に収めた。
「何をごちゃごちゃと言っておる! 大人しくお縄につけ!」
先陣切って、三人に近づいてきた体格の良い同心。
そこに数良は両手を上げて、降参の格好をしながら首を横に振った。
「参った、お手上げさ。おうよ、ここに火ぃつけたんは、自分一人さ」
「か、数良……何を、言って……」
数良は嘘の告白に、逸流は驚いて口を挟もうとする。
しかしこれを遮るように、数良はわざと大声で男に続けた。
「うっせぇ、のうたりんはすっこんでろ! へっ、そこの奴らは、街で会っただけの間抜けどもさ。ちょいと利用してやったが、こうなりゃもう足手纏いよ。自分とはなんも関係ねぇ馬鹿どもの相手なんざ、天下のお役人様がする暇なんざねぇんだろ?」
「それはこちらで決めることだ」
数良の渾身のはったりは、眼前の男には通用しなかった。
「弁明ならば、あとでたっぷり聞いてやる。さあお前ら、そこの奴らともども、この餓鬼をひっ捕らえ――」
男が後方の仲間たちに指示を下した直後。
「うすのろが、いっちょ前に命令してんじゃねぇよ!」
がっ、と蹴り上げられた数良のつま先。
いつか見た惨劇が、眼前の男の股間へと引き起こされる。
当然、急所を潰されて耐えられる男などいるはずもなく、同心風は目玉を飛び出しながら股ぐらを抑え込んだ。
「ご、は、ぐぅ……」
「ざまぇねぇぜ。おらおら、無関係の奴ら巻き込むぐれぇなら、実行犯の餓鬼一人ぐれぇ捕まえたらどうだ? おのれらみてぇな無能集団に、自分が捕まるわけねぇけどよ!」
『……っ』
剣呑とした空気が、役人の男たちに伝播する。
彼らの標的は数良に固定された。人を舐めた態度を取る小娘一匹に、好き放題に言われたままでは男としての名折れである。
「ほぅら、こっちだ鈍足ども! おのれらの足じゃ、かたつむりにも勝てやしねぇぜ!」
数良は煽るだけ煽って、ひたこら夜の闇に消えていく。
役人たちはすぐさまこれを追いかけて、股を蹴飛ばされた男も両脇から部下に担がれ、そのあとに続いた。
その様子を薄れていく意識の中で逸流は見届けた。
自分たちのために囮を買って出た彼女に対し、申し訳なさと、絶大な恩を感じながら。
「ぬしは休め。ゆくは次なる道が待つのだから」
そして稲の響きに瞼は揺らぎ、直にあくびを噛み殺した。
【続】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

