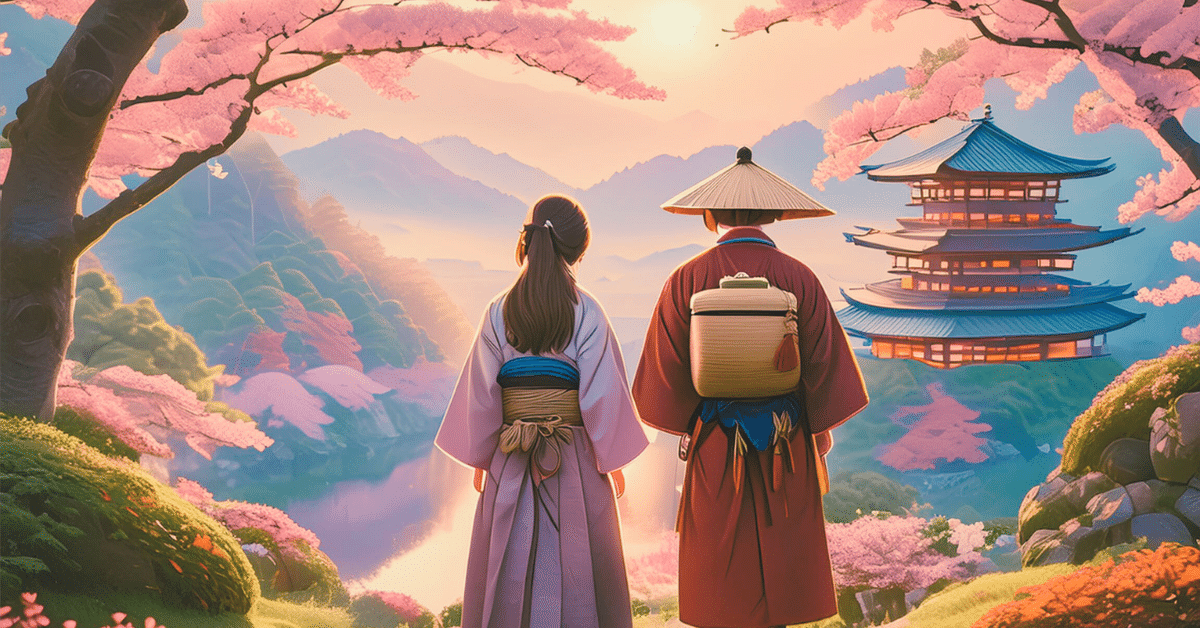
あくびの隨に 21話
前回
長屋を出て正面の通り。
微かに肌寒さを覚える夜。人通りのない道の中心で、提灯片手に数良はぼんやり佇んでいる。臭いの出どころでも探すように、くんくん鼻を鳴らしていた。
「何が臭うんだ?」
逸流の鼻孔は、数良の認識する臭いをまったく感じていない。
しかし数良は眉を潜めて、その所在を探っている。
「煙草の煙に混じって、い草が燃えてんだよ。どっかの馬鹿が寝落ちしやがったんだ」
「火事か。それはちと、まずいことになるやもしれん」
稲はその危険性をいち早く理解していた。
「この街は標高が高い。風が吹けば、瞬く間に燃え広がってしまうぞ」
「そっか。学校で習ったけど、火付けは大罪。昔は消防車なんてないから、その被害が街中に及ぶかもしれないんだっけ」
「何でも良いから、逸流と稲も火元探してくれよな。何年か前も、火事が起きたときはてんやわんやの大騒ぎだったんだ」
数良の焦りを受けて、逸流たちは出火元を探そうとするが――
「――おい、そこの三人」
そのとき、こちらの明かりを見咎めたように男の声が響く。
そこには提灯片手に歩いて来る同心がいた。肩幅が広く、強面をした屈強な男性。
数良はその姿に気づくなり、大きく目を見開いた。
「まずっ、あいつは袖の下で動かねぇ堅物だぞ!」
「今は非常時だし、話したら分かってくれるんじゃないか?」
「あほんだら! おのれは知らねぇのか! って、知らねぇか」
数良は一瞬頭に血を上らせつつも、はたと我に返って手短に説明する。
「ありゃあ、非でも是にする知恵遅れだ。問答無用でしょっ引かれてった奴なんて、手足の指合わせても足りやしねぇわ」
「だったら、どうするんだ?」
逸流が聞くと、数良は二人に目配せする。
右足が地面を擦りながら、僅かに前に出されるのを見てその意図を察した。
「逃げるが勝ちに決まってんだろ!」
「や、やっぱり」
「面倒がよく舞い込むものだ」
三人は男がやってくる前に、全速力で駆け出していた。
数良が先導して、街中を駆けずり回った三人。
さすがに土地勘のある彼女のおかげで、昼間のように遅れを取ることはなかった。途中で空き家に押し入ったり、屋根の上を登らされたりしたが、無事に撒くことに成功する。
しかし、いつしか夜風が総身を吹き抜け、芯から削るように冷気を飛ばした。
それどころか空を見上げれば、星の光を覆い隠すように、天を赤く染める景色が三人の視界に飛び込んできた。
「ちくしょう、あのどあほのせいで!」
舌打ちしながら数良は、逸流たちと現場に急行する。
大通りは、すでに人でごった返していた。艶やかな着物姿の女たちや、腰に刀をぶら下げた侍。半裸に布を巻いただけの女、ふんどし姿の男なども入り乱れて、その場は混乱を極めていた。
どうやら遊郭が丸々一棟、轟々と音を立てて真っ赤な色に染まっている。
半鐘が鳴らされ、纏を担いだ火消したちの姿もちらほら見えた。
大きな桶に水を汲んで梯子に登るも、あれでは焼け石に水。実際彼らにできるのは、火元や隣家を崩してそれ以上燃え広がらないようにするだけだ。
けれど猛火の果敢さに気圧されているのか、現場の意思疎通が取れていない。屋根に登って水を流す者の隣で、その足元を鋸で切るような真似をし、さすまたを火元の家に突き入れようとしながら、危うく転落しそうになる者までいる始末。
「ちっ、へなちょこばっかじゃねぇかよ……けどそれよりも、この並び」
何かに気づいたように、数良が火元からその隣家を辿るように眺めていく。
「……ふっざけんなよ、くそったれが!」
「数良、どうしたんだ?」
唐突な数良の激怒に、逸流は困惑する。
「どうしたもこうしたもあっかよ! このままじゃ、自分とこの長屋が燃えちまうんだ!」
数良に言われて、逸流は通りを見た。
そこは先ほど同心に声をかけられた場所。おそらく町内を一周して、元の場所に戻ってきたのだ。
数良は感情剥き出しにして火消したちに叫ぶ。
「さっさと消しやがれよ! おのれらのへまに、自分たちを巻き込むんじゃねぇぞ!」
罵声を浴びせたところで、火消したちの動きが洗練されるわけではない。
それでも訴えずにはいられない数良は、逸流の横でぽつりと想いを漏らす。
「何でだよ……あそこが無くなったら、自分はどこで待ってりゃ良いんだ……」
おもむろに、数良は髪に付けていた簪に手を当てた。
「いつか、おっ母が迎えに来るかもしんねぇのに……あの場所が無くなっちまったら、本当に二度と会えなくなっちまう……」
母との再会を信じ続けた少女の本当の姿。
どれほど強がりを装ったところで、彼女はまだ子供。何よりも母に会いたいと願うその気持ちを、燃え盛る大火が無常に焼き尽くさんとする。
「――おぉい! まだ中に誰か残ってるみてぇだぞ!」
不意に、屋根に登っていた火消しの一人が大声で呼びかけた。
「ありゃ女郎か! くそっ、この火の手じゃ無理だ!」
「……何だって。中にいんのか?」
火消しのもたらす情報に、数良は目が覚めたように面を上げた。
「まさか、おっ母――」
数良は近くで消化を行っていた男から、水桶をひったくる。
「あっ、何しやがんでえ!」
男の叱責など耳に入らない様子で、数良は頭から水を被った。そして目の前で倒壊しながら燃える屋敷の中へと、遮二無二走って行く。
「数良! 駄目だ!」
逸流は慌てて呼び止めるが、数良の耳には何者の声も届いてはいなかった。
【続】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
