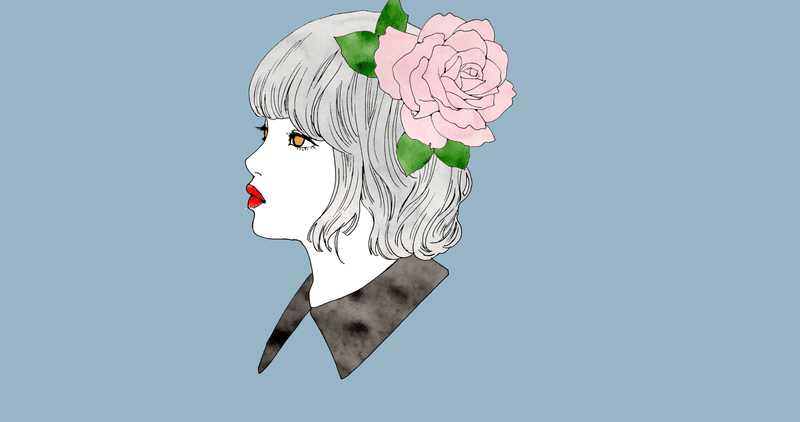
大人になれない僕たちは 第9話 プリンセス症候群
母親の化粧品を勝手に使って怒られたのは、多分、4歳くらいの頃だ。人はこんなに怒ることができるものなんだと、その時の母を見て、私は初めて知った。
映画で見た主人公のように、きれいになりたい。私はそう思って、母の化粧品に手を出した。母の怒りは、幼い私が化粧をしてしまったからではない。高価な口紅を折ってしまったことだ。母は、何歳になっても綺麗であることにこだわっていた。
「綺麗にしなさい」
小さな頃から、そう口うるさく言われてきた。母は、出かける日になると必ず、私を人形のように扱った。隣に並ぶ自分が、人の目にどう映るのかだけを気にして。
綺麗であること、それが私の目標になった。
高校を卒業すると、美容師の専門学校に入った。母が希望したからではない。美容師になれば、ずっと自分を可愛くすることができる。そうすれば、きっと母に大切にしてもらえる。そう思った。母は、私の選択をとても喜んだ。
卒業後、就職してすぐに、美容師は、何よりも他人を綺麗にする仕事だと理解する。目的を果たせない私は、半年もせず、その仕事を辞めることにした。
この先、私はどうしたらいいのか。そう母に相談した。"あなたの好きにしなさい"、母はそれ意外、何も言わなかった。その時すでに、私は母の所有物リストから外されていた。母の興味はもう、私にはない。私は、この時、目標も目的も失ってしまった。
それからしばらく、仕事を転々とした。どれも上手くいかず、私は抜け殻のように色んなところを彷徨った。誰かがきっと、私を助けてくれる。そんな物語を空想しながら。
今は、派遣会社から勧められるがまま、ドラマ制作のADをしている。スタイリストの補助もできるらしいと言われていたせいなのか、その仕事を上手くこなすことが出来ない私は、ここでもすぐに浮いた存在となった。今日もまた、ミスをした。
「岬さん。それ、プリンセス症候群だね」
屋上で、茜さんは言った。茜さんは、先ほどの会議で自分が手掛けたドラマの企画がひとつ潰されたばかりだ。心無いことを言う人たちを相手に最後まで一人戦って、見事に玉砕した。
「多分、自分をずっと特別だと思っているのよ。それ、わかるなぁ」
不器用だけど真っ直ぐな茜さんは、どこか人間らしい。私は、そんな茜さんが好きだった。
「小さい頃にさ、だいたい人気のある物語って、ステキな王子様が迎えに来るじゃない?それで最後は、ハッピーエンドになる。子どもたちに夢を与える物語ってさ、私はある意味、とても残酷だなって思ってる」
茜さんは、私のミスを叱らない。私のせいで、今日も現場が散々だったというのに。目的も目標もない私は、多分、ここにいる必要のない人間だ。
「だってそうでしょう。頑張れば、王子様が迎えに来るって信じてる。でも、いつかそれが幻想だって気づく時がくるでしょ。大抵さ、それに気がついた時には、受け止めることができないところまできちゃってるのよ。そんなの受け止めたらもう、自分が自分じゃなくなっちゃうよね」
茜さんは、私を慰めているようだ。この人は、やっぱり不器用な人だ。
「王子様なんて、来ない。私も分かってはいるんだけどね。ハッピーエンドが待ってるって思わないとやってられない時ってあるのよ。そういう時は、決まってシンデレラとか見ちゃってさ」
私は、吹き出してしまった。
「え、何なに?」
「シンデレラとか見てるんですか」
「そうよ。そんなもんなのよ、人間なんて。残酷だって幻想だって分かってても、結局、自分だけのストーリーの中で生きてる生き物なんだよ。悔しいけど、それも私」
茜さんは、私の背中を擦りながら、泣いていた。企画が潰され、きっと悔しかったのだろう。茜さんは、自分に言い聞かせるように、こんな日もあっていい、と言った。
屋上から見下ろすと、路上では、バラエティの制作班がリハーサルをしている。手を振るのは、私と同じ時期に入ってきた金城朱樹だった。親は大手広告代理店の偉い人らしい。彼は、自分の可愛さを存分に発揮するように笑い、私に手を振った。彼はいつでもポジティブで、夢見がちだ。
「あいつも、私達と一緒ね」
茜さんは笑った。
「それ、治るんですか」
「治す必要なんてない。夢をみなきゃ人は前を向けないから」
夢を見ても悪くない。茜さんは、今までの私を肯定してくれたような気がした。迷ったけれど、間違いではなかった。迷いながらいけばいい。そう言われたような気がした。
「もう少しだけ、ここにいようかな」
私は、ポツリとそう呟いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
