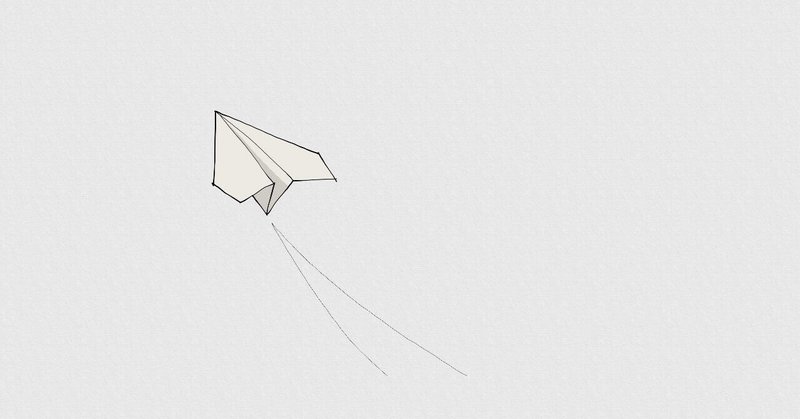
大人になれない僕たちは 第4話 紙飛行機は宙を舞う
「つまり、僕の企画はボツになったと」
茜さんは、申し訳なさそうに自分に向かって頭を下げた。
高校1年生で新人脚本賞、佳作。史上最年少で手にした賞の効力は、あっという間に消え去っていた。その後は、のらりくらりと、結局、そこら辺の若者と変わらない毎日を過ごしている。あの時、大賞を取っていたらもう少し変わっていたのかもしれない。
今の肩書きは、劇団サークルに所属する大学生。活動にのめり込み、気が付けば、今年も浪人が決まっていた。
「あなたの作品をドラマにしたい」
そう声をかけてきたのは、一昨年の小劇団の打ち上げの席だった。どこから聞きつけたのか、二次会に駆けつけた茜さんはテレビ制作部の名刺を差し出し、熱心に僕の作品について語りだした。無名な自分の作品がドラマになる。夢が夢でなくなった日、部屋に戻ると、僕は一人で喜びを噛みしめた。
「本当、ごめんなさい。でも、いつか必ず…」
そんな言葉は聞きあきた。賞をとったあとも、何度も企画書を送った。すごい、面白い、制作者は定型文のような褒め言葉を並べた後、決まってこう言う。
「また、何かあったら連絡します」
未成年だからという理由で、地方に住んでいるからという理由で、僕の作品は日の目をみることなく埋もれていった。
でも、茜さんは違った。何度も直しに付き合って、企画がボツになっても声をかけ続けてくれた。今度こそデビュー出来ると、企画が通った日は夜中にわざわざ電話をくれた。
「次の作品は誰が書くんですか」
「…中川美知子先生が。それで杉本君にも脚本家のチームに入ってくれないかなって。エンドロールには、名前は出ないんだけど。もちろん、ちゃんとお金も支払う」
中川美智子は、恋愛ドラマの大御所だ。その大御所が、オリジナルではなく、原作の作品を手掛けるとは、ため息をつくしかなかった。書き手は腐るほどいる。コロナ禍の今、大御所たちもいつ仕事にありつけるか分からないと、小さなオファーでも進んで引き受けるようになっていた。そんな時代、無名の新人にそうそうチャンスは回ってこない。アシスタントに入れるだけでも奇跡に近い。それは分かっていた。
「ごめん。やっぱり嫌だよね。オリジナルでデビューだって言ってたのに。原作ありきの、しかも、またアシスタントだなんて。プライドが許さないよね」
そこまではっきりと言われると、むしろせいせいした。茜さんは、きっと正直な人なのだろう。
「やります」
家に帰ると、書きかけの原稿をカバンから取り出した。今日、茜さんに見せるはずだった原稿だ。背に腹は代えられない。学生で稼げる額は知れている。上京して一人暮らしを続ける自分の生活は楽ではなかった。バイトも自宅待機が増える中、目の前の金は手が出るほど欲しかった。
原稿を投げつけてみるか。そう思って振り上げる。年齢も地方に住んでいる理由も、今はもう通用しない。ただ、自分の作品が受け入れられなかった。ただそれだけだ。
紙飛行機にでもして、飛ばしてやろうか。机に広げた原稿用紙を手に、一枚一枚折りはじめてみる。よく飛ぶ作り方はどうだっただろう。少年時代の記憶を呼び起こし、一つ試しに飛ばしてみることにした。
飛び立った紙飛行機は低空飛行のまま、みごとに床に向かって墜落した。まるで自分の人生のようで、なんだか笑えてきた。
寝転んで、今度は天井に向けて飛ばしてみる。紙飛行機は、円を半分まで描くと真っ逆さまに落ちていく。これでもかと改良しては、飛ばし続ける。残り三枚となった時、紙飛行機は部屋をきれいに回ってゆっくりと着地した。
もう一度、それに手を伸ばす。勢いよく放った紙飛行機は、スッと飛んでいき、まるで自分の想いを乗せたかのようにゆっくりと宙を舞った。
どこか遠くへ。僕の行き先は何処だろう。もう一度飛ばした紙飛行機は、ゆらゆらと揺れていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
