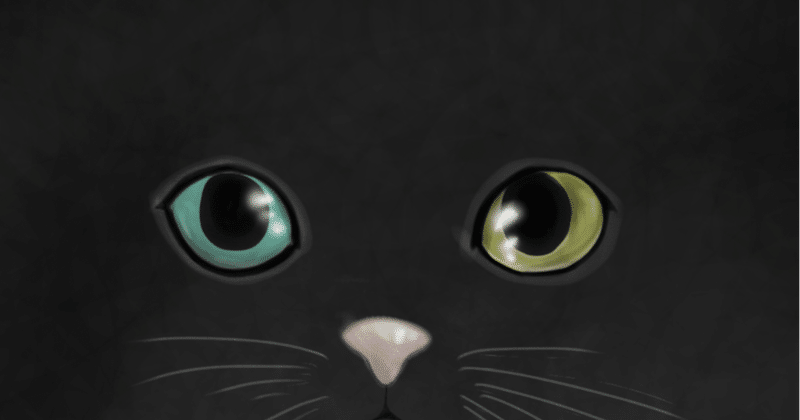
過去作、再掲したったん
最近「自分の過去作を読んでいただくにはどうしたらいいか?」という話題をよく見かけます。やはりさかのぼって読んでいただくのは難しいですよね。
初期の頃はフォロワーさまも少なくて、読んでいただく機会の少なかった作品たち。それでも愛した作品に変わりはないんですよね。
そこで私もたまに初期の作品を再掲してみようかな、と思いまして♡
今日はショートストーリー「郷愁と感傷の物語」を再掲します。加筆修正していません。よろしくお願いします。
【郷愁と感傷の物語】
私は郊外のある駅にいた。
ホームには私と、もうひとり女性がいた。
女性は臙脂色の大きなトランクを足元に置いていた。
女性はふいにしゃがむと、トランクを開けて中の荷物を取り出し始めた。
兎の剥製。
抜け替わって落ちた鹿の角。
世界一広い砂漠の砂。
瓶に入ったタイピストの指。
廃墟となった遊園地。
移動サーカス団のテント。
孤島に浮かぶ教会の蜃気楼。
漆黒の森。
たしかにトランクは大きなものであるが、これだけのものを収納できるとは、なんて有能で素晴らしいトランクだろう。私は感心した。
駅のホームはたちまち女性のトランクから取り出された荷物たちに埋め尽くされた。
ホームの半分は漆黒の森に支配されどこまでも深い闇になった。ベンチには蔓植物がするすると巻き付き、森の奥からは動物たちの気配がする。花が咲き、色とりどりの蝶たちが舞い、鳥が鳴く。
しだいに女性自身も埋もれ始めた。膝あたりまでは地中海の潮騒に沈み、肩には栗鼠や鳥たちが乗り、それでも女性はトランクから荷物を出し続けるため、旅人の口笛やチシャ猫の口が半分はみ出し、ピアノの旋律までもトランクから出ようと溢れていた。
私はホームに立ち尽くしその光景を眺めていた。
目の前までせまった砂漠の砂を興味本位で触ってみると、焼けるように熱くて慌てて手をひっこめた。
女性はきっとこのトランクを抱え、世界中を旅してきたに違いない。
そしてその思い出をトランクに詰め込んできたのだ。
砂を、花を、虫を、鳥を、虹を、風を、森を、海を。
ひとつひとつ丁寧にトランクにしまってきたのだ。
旅の帰路の途中、駅で思わず、思い出たちを取り出してしまったのだ。
そして、奥ゆかしいノスタルジーとともにあっという間にホームを飲み込んでしまった。
ひとりの駅員がホームの端から歩いてくる。
漆黒の森を抜け、鹿の角を跨ぎ、真っ赤な柘榴の実を避け、地中海の潮騒をゆるゆると進み、ようやく女性のもとに辿り着いた。
すでに女性は水平線に沈む夕日とそのとき聞いた夕刻のお告げに飲み込まれ、存在のほとんどが旅の思い出に侵食されていた。
駅員は夕刻のお告げをゆっくりと掻き分け女性の耳を探り出す。
「お客様、お手荷物はトランクへおしまいください」
女性はハッと我に返ったように駅員を見つめかえし
「ごめんなさい。つい思い出に浸ってしまって」
と赤面しながら荷物をトランクにしまいはじめた。
すっかり荷物をしまい終えるとホームはいつもの間延びした平和を取り戻していた。
女性は駅員に会釈をすると、いつのまにか到着していた電車に乗り込んだ。
私は先程少し触れた焼けるように熱い砂の感触が消えず、いつまでもひりひりと痛かった。
その日からというもの、私の指先の痛みは消えることなく、ホームで見た女性の思い出たちが私の生活にも侵食し始めた。
仕事をしていてもデスクの下で紺碧のアドリア海が私の足を濡らし、同僚の頭の上で虹蛇がうねっているため会話に集中できなかった。
生活に支障を来すので、私はあの女性を探しにまた駅へ行った。
女性はホームにいて、臙脂色のトランクを足元に置いていた。
そして私を見るなり「この前はごめんなさい」と話しかけてきた。
「あなたの思い出が私の生活を侵食しています」
「そのようですね」
近付いて見つめる女性の瞳の中には、アルベロベッロのトゥルッリが並び、その先にエンジェルフォールのしぶきが霧になって飛んでいた。
「本当にごめんなさいね」
女性が私の肩にそっと指を触れた途端、砂時計の砂のように私の一部はさらさらと崩れ早秋の風に吹かれて飛んで行ってしまった。
「あぁ」気付いたときには遅かった。
私は少しずつ消失し、元々私だった存在は郷愁と感傷に満ちた思い出の物語に飲み込まれてしまった。
女性は元々私だったものをそっと掬い、臙脂色のトランクに丁寧にしまった。
《おわり》
おもしろいと思っていただけましたら、サポートしていただけると、ますますやる気が出ます!
