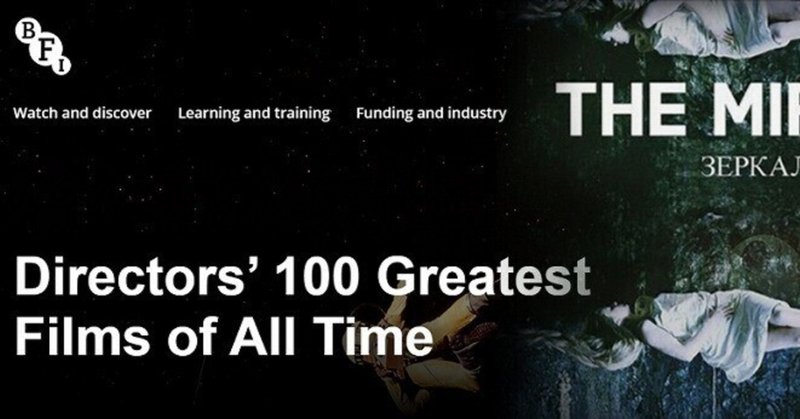
アンドレイ・タルコフスキーの「鏡」が第8位! ~ 世界の映画監督480人の選ぶ映画100 :英国映画協会BFI
名作映画ランキング・ベスト100
ネットで検索をかけると、英国映画協会( British Film Institute、BFI)が10年ごとに実施、その最新である2022年度版、世界各国の映画監督480人の投票による名作映画ランキング・ベスト100が目に入りました。
それによると第1位は、スタンリー・キューブリック監督の「2001年宇宙の旅」。ちなみに10年前の2012年は、何と、小津安二郎の「東京物語」だったのです!
10位~1位は以下の通り ( 9位・6位・4位は同点作品 )
9:
クローズ・アップ (1989 監督 アッバス・キアロスタミ)
花様年華 (2000 監督 ウォン・カーウァイ)
仮面/ペルソナ (1966 監督 イングマール・ベルイマン)
8:
鏡 (1975 監督 アンドレイ・タルコフスキー)
6:
8½ (1963 監督 フェデリコ・フェリーニ)
めまい (1958 監督 アルフレッド・ヒッチコック)
4:
ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080 (1975 監督 シャンタル・アケルマン)
東京物語 (1953 監督 小津安二郎)
3:
ゴッドファーザー (1972 監督 フランシス・フォード・コッポラ)
2:
市民ケーン (1941 監督 オーソン・ウェルズ)
1:
2001年宇宙の旅 (1968 監督 スタンリー・キューブリック)
なるほど、映画史にその名を残す巨匠たちの代表作ばかりです。第8位には「鏡」アンドレイ・タルコフスキーが入っており、前回は9位でしたので
ワンランクUPです!
そもそも、引き続き「鏡」が上位に入っていること自体、大変な驚きです。1975年公開当時は何の賞も取らず、話題性もなく、興行収入も低かったであろう、旧ソビエト連邦時代のタルコフスキー作品がベスト10入りしているのですから。
ネット上には、2000年以降の映画、批評家、興行収入など、さまざまな枠組みでのランキングが公表されていますが、私が最も愛する「鏡」をランキングしているこのサイトには最も注目と信頼ができますし、また、投票した映画監督たちは、観客でも批評家でも映画配給業者でもない、表現者としての立場から「鏡」を選んだであろうことはきわめて重要な点だと思います。
ちなみに、20位~10位は以下の通り
20:
自転車泥棒 (1948 監督 ヴィットリオ・デ・シーカ)
羅生門 (1950 監督 黒澤明)
19:
こわれゆく女 (1974 監督 ジョン・カサヴェテス)
18:
地獄の黙示録 (1979 監督 フランシス・フォード・コッポラ)
14:
ストーカー (1979 監督 アンドレイ・タルコフスキー)
勝手にしやがれ (1960 監督 ジャン=リュック・ゴダール)
七人の侍 (1954 監督 黒澤明)
美しき仕事 (1998 監督 クレール・ドニ)
12:
バリー・リンドン (1975 監督 スタンリー・キューブリック)
タクシードライバー (1976 監督 マーティン・スコセッシ)
嬉しいことに、前回は30位だったタルコフスキー「ストーカー」が14位にUPしており、26位にはロシア史大作「アンドレイ・ルブリョフ」、残念ながら、亡命後のイタリアでの「ノスタルジア」や遺作「サクリファイス」は100位以内にはありません。
ちなみに、世界のクロサワは、14位「7人の侍」、20位「羅生門」です。
私にとって「映画」とは・・
やはり、小学生からずっとテレビで見続けていた「・・映画劇場」で見た映画こそが、私にとっての「映画」です。それは、何よりもまず、「銀幕のスター」の存在が不可欠で、次に、心ときめく映画音楽や痛快無比、奇想天外な物語が必須で、恋愛、怪奇趣味、SF、戦争、史劇などあらゆるジャンルの映画を楽しんだ10代でした。
東京での20代は、ミニシアターでのみ上映される「アート系映画」なるものも観るようになりました。福岡に戻った30代以降は、もっぱら、レンタルショップで借りて見ることが多かったのですが、現在はもはや、ほとんどテレビ放映の映画を鑑賞するだけです。
そういう私に・・・
果たして、タルコフスキー「鏡」以降に、それに匹敵するような映画はあるのか?・・と自問自答した場合、当たり前のことですが、過去に見た数少ない映画の中からしか選べません。
では、どういう映画を候補として選ぶべきか・・・
と、考えた場合、最も重要視されるのは、映像です。映画「鏡」は、俳優、脚本、音楽その他いろいろな要素が絡んではいても、最後はタルコフスキー監督の紡ぎだした映像の魔術に、見る者は心を奪われてしまったわけです。
ですから、そのような「映像の魔術」が感じられる映画がその後にあるのだろうか、探ることとなります。
ところで、映画製作の現場・・
いわば最前線激戦地は、おそらく、編集室でしょう。そこに籠って、撮影した膨大なフィルム( 今はデジタル主流 )をカットしてはつなぐ編集を重ねながら、一本の作品にまとめていくわけです。「鏡」は、まさに、そんな編集作業を通じ、大変な労力と時間を費やして創出されたと思います。
余談:先にお断りします
今から挙げる作品は期せずして、欧米資本によるメジャー大作中心になってしまいました。
いずれは、日本映画で「映像の魔術」作品を取り上げるつもりです。いますぐに思いつくだけでも、「飢餓海峡」「怪談」「赤いハンカチ」「告白的女優論」「田園に死す」「蟲師」「ナイトヘッド」「CURE」などいろいろありそうです・・。
では古い年代から、あくまで私が見た少ない数の映画の中から、「映像の魔術」を感じられた映画を紹介します:
1975年:「鏡」
アンドレイ・タルコフスキー監督
そして、それ以後は;
1977年:戦争のはらわた
Cross of Iron
サム・ペキンパー監督
20代半ば、東京の名画座で初めて見ました。ラストのクライマックスで、立ち見もいた超満員の会場は一瞬シーンとなり、誰かが小声でつぶやきました、「 凄すぎる ! 」。

戦争という極限状況での人間が描かれており、アクション物でも反戦映画でもないと思います。スローモーションと無音の間を生かした、細かいカット割りの連続による、ペキンパー独自の映像編集の「リズム」にこそ、この映画の真価があると考えています。

*その後の作品 Getaway でも同じで、映像に迫真と緊張を高める呼吸のようなリズムがあるのです。
1979年:地獄の黙示録
Apocalypse Now
F・フォード・コッポラ監督
前作の「ゴッドファーザー」の世界的な大ヒットで名声と莫大な興行収入を得たコッポラの野心作で、私も公開時の劇場で見ました。

当時としては最新最大のスクリーンに凝った画像と音楽の狂宴のごときベトナム戦争が演出されていて、映画を超えたイベントかと錯覚するほどの興奮がありました。

*1982年の同監督作品 One from the heart では、がらりと趣向を変えて、スタジオ内に完璧なまでに造形した電飾の夜の歓楽街で、平凡な男と女の痴話喧嘩を自由奔放な演出で描き切っていましたが、一番印象に残ったのは、歌と曲を担当したトム・ウェイツの個性的な声と音楽でした。
1982年:ブレードランナー
Blade Runner
リドリー・スコット監督
これも20代に客が数名しかいない劇場で見ました。当時は全くヒットしなかったのです。ミニチュアを活かしたCG撮影など視覚的に目を見張る興奮がありましたが、後にカルトムービーとなったのは、生と死という永遠のテーマがしっかり描かれた脚本、適材適所の俳優陣、ヴァンゲリスの素晴らしい電子音楽、そして、スコット監督のアート感覚にあふれる画面造形力があったからだと思います。

*スコット監督の優れた画面造形力は、後の Graduater や Black hawk daown でも発揮されています。

1991年:ふたりのベロニカ
クシシュトフ・キェシロフスキ監督
タルコフスキーが逝去して、彼に勝る映画はもう出てこないかも・・と諦めかけていた当時、旧友が見たらと薦めてくれたのが、この映画でした。
ポーランド映画を見ること自体、「地下水道」・「灰とダイヤモンド」のアンジェイ・ワイダ監督以来、久しぶりでした。

DVDで観ました。光の反射を巧みに使ったガラス細工のような輝きの繊細な映像美、最後まで謎のベールで被われているような物語、不思議な魅力の漂う登場人物たち、そんな映画の醸し出す雰囲気を精緻な音のつづれ織りにしたようなズビグニエフ・プレイスネルの音楽。
キェシロフスキ監督の知性と感性によって、映像、音楽、俳優、脚本すべての要素が絶妙に融合されて奇跡的な化学変化を起こした、・・とでも言うべき「秘密の宝箱」を私は所有できたのです( Blue-ray Disc で)。

*その後、彼は、トリコロール三部作で多くの映画賞を獲得しますが、1996年に心臓発作を起こし54歳で亡くなります。早すぎた死です。
2000年:花様年華
( 英語版:In the mood for love )
ウォン・カーウァイ監督
テレビ放映で一度見ただけの香港映画です。画面が極端に狭いのは、画角の狭いレンズで撮影したからでしょうか。ですがそのことが逆にこの映画に
独特のリズムに統一された映像世界を表出させています。音楽の入れ方も映像と人物の動きに連動するように独特のテンポです。

少ない登場人物による日常生活の断片がひたすら流れるだけ、何か奇跡や事件が起こるわけでもないのに、記憶に余韻が残り続ける・・・今まで経験したことのない、そんな映画です。

*同監督の「恋する惑星」も印象的な演出でしたが、カンフーの師を描いた「グランド・マスター」では全く違う趣向の映像でしたので、この監督は多芸多才なやり手の監督と感じます。ところで、私にとっての香港映画といえば、古くはブルース・リー、そして、ジョン・ウー監督「男たちの挽歌シリーズ」がまず思い浮かびます。
2010年:告白 中島哲也監督
この映画を印象深く思うのは、奇抜な着想の脚本と自由自在な遊び心あふれる映像表現があったからです。以前に見て、とても感動していた映画「嫌われ松子の一生」の監督だったと知ると、なるほど、と納得しました。

この監督は、CM業界でも才能を発揮してきた方であり、ヴィジュアルセンスが際立って光っています。そのセンスが物語の流れとうまく融合すれば、
見事な感動が生じるでしょうが、表層的な華美さで終わる危険(例えば蜷川実花監督など・・)もあるでしょう。
そんな微妙なバランスの中、中島監督は、商業映画としても、映像表現の冒険としても見事に面白い作品を創出されたのです。

2010年:インセプション
Inception
クリストファー・ノーラン監督
筋書きとしては、他人の頭の中に潜り込んで、潜在意識から情報を抜き出す産業スパイの話で、全くの絵空事ですが、映画そのものは、最新SFX技術とCG処理を多用した、壮大かつ精緻な映像体験アトラクションとでも言うべきでしょうか。ただ、脚本のベースに、主人公コブ(レオナルド・ディカプリオ演じる)と妻や子供との関係が謎解きのように盛り込まれているので、人間ドラマとしても興味を持つことになります。
冒頭の、崩落してゆく建造物や、中盤での想像上の都市が360度回転して万華鏡のごとく様相を変えていくシーンなど、単に視覚的な興奮を超えた、つまり、芸術的な=アート的な感動があるのです。

2013年:ライフ・オブ・パイ
Life of Pie
アン・リー監督
この作品でリー監督は2度目のアカデミー監督賞受賞。過去の作品「グリーン・デスティニー」が印象深かったですが、その後も多くの作品が国際的に高く評価され続けている監督です。
この映画の醍醐味は、なによりもその映像表現です。海、空、島、生物など地上のあらゆる自然と人類の棲息するこの地球という大きな視点から幻想的なまでに美しく驚異的な映像が拡がります。一方、脚本も実に巧みで、小さな存在でしかない人間の愛おしさも演出されています。

興行的にも作品の質の高さでも大成功を収めた映画ということになりますが、考えてみれば、映画とはもともと、どんなに名作でも娯楽的要素があったなと思います。たとえば、昭和のある時期、D・リーン監督の名作「アラビアのロレンス」を学校行事として鑑賞する公立中学校もあったのですから。ただ、タルコフスキー「鏡」を娯楽作品とはどうしても言えないですが、この「ライフ・・」なら芸術的な娯楽、あるいは、娯楽的な芸術作品と呼べるでしょう。

最後に、まとめ
以上に紹介した作品以外にも、候補作はいくつもあったのですが、いろんな条件付きで最終的に残ったのがこの8作品でした。どの作品も、再度の鑑賞に耐え得る出来のものばかりです。
「鏡」は、旧ソビエト連邦の国家統制による限られた予算をどうにか確保して、当局の厳しい検閲を回避しつつ、何とか完成にこぎつけた、タルコフスキーの不遇時代の作品であり、作品価値に見合った名誉ある賞はなく、公開の機会もきわめて限られ、ソビエト国内では賛否両論の問題作品だったらしいです。
それに比べ、私がここに挙げたその後の作品群は、「戦争のはらわた」の興行的不成功は例外として、他はすべて世間的な評価と成功を得ています。
だからと言って、そのことは、作品の「芸術的価値」を貶める要素ではありません。
しかしながら、「鏡」に比肩しうる作品があるのか、と問われれば、私は明言します;
キェシロフスキ監督の「二人のベロニカ」および「トリコロール3部作」のみが、「鏡」に比肩しうる作品である、と。
なぜか、その理由は;
たとえば、ベートーベンの「交響曲第9番合唱つき」の凄さと人気やベートーベン先生の偉大さもよくわかるけど、ちょっと派手で大仰すぎると感じたりもするのです。でも、ショパンの「別れの曲」やバッハの「主よ、われは汝の名を呼ぶ」なら、一人ひっそりと聴けて、自らの思いに応えてくれて
愛おしむことのできる作品と思える、そういうことと同じ理由だと思うのです。
