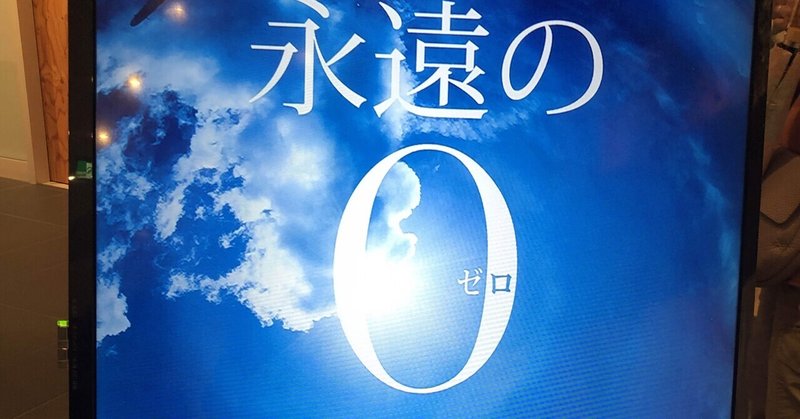
【映画】楽しみ方は様々でいいよねと思った映画『永遠の0』
ここのところ、また新しいマイルールが増えました。
《新マイルール》
春馬君の出演映画を初めて観る時はスクリーンで!
特に、意識してるわけじゃないのに、何故か脳が、心が、そう欲するのです。
だから、従ってるまでなのですが。
そんなわけで、今回は『永遠の0』を観てきました。
なんだか、心がズシンと重くなる映画でした。
映画館を出て、目の前に平和な秋葉原の街が広がっているのに、なかなか現実に戻ってこれないくらいの不快な重さです。
それはなんだろう?と考えながらレビューを書いてみたいと思います。
戦争体験を聞いたことがありますか
私の両親は、昭和一桁の生まれなので、よく子供の頃から親戚が集まったりすると、戦争の話を聞きながら育ちました。
父方の祖父は、軍で働いていて南方の島で戦死、父は空襲の中を逃げて九死に一生を得た人です。
母方の祖父も元軍人。母は、戦中に大陸から命からがら引き上げてきた後、軍需工場で、特攻隊が乗るための飛行機の部品製造に携わっていたそうです。母の2人の兄は特攻隊予備軍でした。
出撃前に終戦を迎えましたが。
戦中の話だけでなく、戦後の混乱期の話も含めて戦争体験を聞くのが当たり前の環境で育ったので、実体験はなくとも、それなりに戦争を肌で感じる事ができている最後の世代なのかもしれません。
例えば、父が50歳の誕生日を迎えた時、母は心から安堵して、「もうこれで兵隊に取られる心配がない」と大真面目に言いました。
母は、戦後40年近くたってもなお、自分の夫が兵隊に取られるかもしれないと恐れ、平和が続く事を願っていたのです。
こういう心持ちは、やはり体験者のリアルだなと思います。
特攻隊予備軍で、訓練を受けているうちに終戦を迎えた母の兄(私の叔父)のお通夜の日の事も忘れられません。
叔父のお通夜のセレモニーが終わった後、親戚一同のだれもが知らない中年の男性が2人、遺影の前で持参した日本酒を飲みながら無言で、夜通し泣いていました。
叔母が言うには「特攻のお仲間なんじゃないか」と。
叔父にとって、特攻隊の生き残りである事は、非常に複雑な問題だったようで、多くを語らなかったと聞いています。その一方で、特攻時代のお仲間とはずっと交流があったようで、亡くなった後も、命日にお墓参りに行くと、お墓が綺麗に掃除され、お花が手向けられていました。親戚一同、誰にも心当たりのない事で、おそらくは、あの遺影の前で飲んでいた方達なのではないか、と推察していました。毎年続いていたのに、ある時からそのお花が上がらなくなり、天国でみんな揃ったのかな、と思ったのが、平成も半ばの頃。ようやく叔父の戦争が終わったのだなと思ったものでした。
そんなわけで、私にとっての戦争は、歴史の教科書の中の出来事よりは、いくらか生々しく、生活の中にいろんな影を落とす存在でありました。
母が「空襲警報を思い出すから」と嫌うので、サイレンの音は私も大嫌いだし、戦争中の様子が描かれる映画やドラマも大嫌いなのも、母の刷り込みの影響だと思います。
しかしながら、今それを子供の世代に伝えて行こうとすると、私の「戦争体験」は、あくまでも両親や親戚を通してでしかなく、又聞き。
実体験を持つ親世代からの熱量は、とても持ち得ないので、まったく説得力のないフィクションのストーリーになってしまいます。
ならば。
いっそ、フィクションでもいいじゃないか。
ドラマや映画を通じてでもいいから、あの時代の事に触れて欲しい。
そう思いながら、そんな親心に足る映画なのか見極めるつもりもあって、映画館に足を運びました。
『永遠の0』はどんな作品か
『永遠の0』は、元大日本帝国海軍の航空兵であった祖父の生き様を、現代の若者が詳らかにしていくお話です。
その現代の若者を春馬君が演じます。
春馬君お得意の「最初はやる気のない今時の若者が、ストーリー展開が進むにつれて、いろんな事を学び成長していく物語」です。『陽はまた昇る』や、『僕のいた時間』とも通じる世界観の役柄かと思います。
この作品は、百田尚樹氏による同名のベストセラー小説が原作ですが、残念ながら戦争モノは嫌いなので、原作を読んではいません。
映画を見た後で、書評をいくつか読んでみましたが、賛否両輪。
非常に評価の分かれる小説でした。
私が映画を見ながら、なんともしっくり来なかったポイントを指摘する書評も散見され、映画のプロットの重要な部分は、比較的原作に忠実なのかな、と思います。
と同時に、原作のプロットがそもそも無理があるというか、あくまでもフィクションなんだな、という推測も成り立ちます。
そのあたりについて、フィクションとして納得してしまえば、エンターテイメントとしてはありな作品かなと思います。
エンターテイメントとして「あり」、な1番のポイントは、語り部として出てくるベテラン俳優さんが豪華!これに尽きると思います。
語り部としてのシーンは、それぞれ短いワンシーンなのに、ものすごい存在感の方ばかり。
余計な説明はされない元航空兵の現代の姿は様々で、ある人は古いアパートの一室で、ある人は病床で、ある人はどう見てもカタギじゃなく。。。しかし、今の立場に関しては一切の説明もないのに、一瞬にして、その人の戦後がなんとなく思い描けるシーンの連続。
ベテラン俳優さんたちの一瞬の熱演は、なによりの見どころかなと思います。
また、キャスティングの面白さは、他にもあります。
春馬君演じる健太郎青年によって、その生き様を明らかにされていく祖父、宮部久蔵を岡田准一さんが演じています。
物語の設定として、健太郎が久蔵の生き様を調べている年齢と、久蔵が亡くなった年齢が同い年の26歳という設定になっているのですが、健太郎を演じた春馬君はこの時23歳(公開時)、久蔵を演じた岡田さんは33歳(公開時)。
これ、上手いキャスティングだなぁと感心しました。
司法浪人で、ふらふらしている健太郎は、とても頼りない半人前にしか見えないし、妻子がいて部下を持つ軍人の久蔵は、もう一人前の大人。
同じ26歳でも、時代や生きてきた時間、背負っている物の重さで、人はこんなに違う、というのを表すのに、実年齢が10歳も離れた俳優さんをキャスティングするセンス!これはさすがです。
さらに、久蔵の教え子で、久蔵から命を救われ、戦争から戻って久蔵の家族を支える事になる大石賢一郎の若い時を、染谷将太さんが演じています。
年齢的には春馬君と同世代の俳優さんです。
つまり、亡くなった時の久蔵と同い年の健太郎は、先生と生徒くらいの精神年齢の差があった、という描かれ方になっているわけです。
そのあたりの表現をキャスティングの妙で見せているあたりが、面白い作品だと思います。
また、この時代のVFXの技術を駆使した、飛行シーンも見どころです。私は、スクリーンだと酔ってしまうので、途中気分が悪くなったりしつつ、半分くらいは目をつぶって堪能しました(笑)。ただ、リアリティという点で言うと、よくできたシューティングゲームみたいで、良くも悪くもフィクションのエンターテイメントだなと。
古い映画だけど、『トップガン』の飛行シーンなんかは、もっとアナログながら、リアリティがあったように思います。
とは言え、監督さんのバックグラウンド的にも、当時こういう映画を撮らせたら右に出る人はいなかったのだろうし、VFX過渡期の映画だなと思いつつ観ると、映画史的にも色々興味深い作品です。VFX好きの方には面白い作品なのではないかなと思います。
モヤっとするポイントがある映画です
ストーリー上、1番肝になる役は、言うまでもなく久蔵です。
岡田さんがほんっっっとによく演じていらっしゃいます。
近年の岡田さんは「去っていく後ろ姿で演技ができる俳優さん」だなぁと思いながら、いくつかの作品でお見かけしましたが、この作品でも、後ろ姿が何度あった事か。
そして、そのどれもが意味のある表現になっている。上手いのです。
この頃からそうだったのか、と改めて感心します。
それだけに。
久蔵のキャラクター設定が、ちょいちょい破綻しているのが残念でなりません。
例えば、飛行技術はあるのに、乱戦になると高度をあげて高みの見物、というエピソードは、「妻子の元に帰りたいから命を大切にしている」という臆病な一面として何度も出てくるのですが、高度を上げるだけで高みの見物ができるものなんでしょうか。
また、軍人として、仲間が撃たれて落ちてゆく様子を、高みから見物していられるなんて、あり得るんでしょうか。
仲間が撃ち落とされているのは、高見の見物していたのに、教え子を特攻に送る事で心を病むほどのダメージを受けるというのは、どういう心境なのでしょう。
そのあたりが丁寧に描かれていたら、モヤっとする事もなかったのか、それとも、そもそも無理のあるプロットなのか。。。
また、久蔵は、真珠湾攻撃の後、「真珠湾で空母を攻撃できなかったから、作戦は失敗だ」と言ってみたり、ミッドウェーだったか、ラバウルだったかでも、攻撃ポイントまで遠すぎる事を理由に、作戦の合理性がないと指摘するシーンがあります。
つまり、空からの攻撃の意味、長所も短所もよく理解し、戦略に長け、冷静で頭のいいキャラクターとして描かれています。
にもかかわらず、帝国軍人としての人生を、軍人らしく全うしてしまう。
久蔵が試みた、数少ない抵抗は、教え子をなかなか試験に通さず、前線に送るのを少しばかり遅くする事くらい。
なんとも、頭の悪いやり方ではありませんか。
あえて言うなら、戦略家としての側面を描く意味はあまりなかったように思います。
ただ、家族を愛し、部下を愛したハートの温かい人物、と言うだけで充分だったのではないか、と。
そんなこんなで、久蔵の描き方には、モヤっとする事が多々ありました。物語の上で、久蔵だけは、矛盾がないように、しっかり描いて欲しかったなぁと、岡田さんが好演されてるだけに、ちょっと勿体なかったなぁと。
春馬君周りで、触れておきたいモヤっとは、ラストシーンで、春馬君演じる健太郎が、祖父の事を調べて、自分のルーツを知り、司法試験には受からないものの、ひとつのことを成し遂げた経験をした事で、どうなったのか、の描かれ方。
健太郎の頭の上を、久蔵の戦闘機が飛んで行って目が合う。
その後、健太郎が感極まっている様子が映し出されるのですが、作中において、単なるストーリーテラーの健太郎に、あのシーンは必要なのかしら?と。
途中で、健太郎が、調査そのものに興味を持っていく様子は丁寧に描かれているのですが、そのプロセスを通して、何を学び、どう成長していっているのか、は描かれていないのです。
悩める半人前健太郎の人生に、久蔵の存在がなにを与えてくれたのかは、まったくわからぬままの、ラストシーンなのです。
久蔵の戦闘機が、健太郎のイマジネーションの中に現れるのはいい。
ほんの少し、2人の触れ合いを描くだけで、あのシーンは成立するはずだし、三浦春馬の演技力を信じるなら、感情を表に出すような芝居でなくても、なんらかの成長をそこに描く事ができるのではないかと思うのです。なのに、かえって色んなことをわかりにくくしてしまっているように思えて、モヤっとしてしまう。うーん、残念。
最後に、久蔵が松乃に残す言葉、「たとえ死んでも戻ってきます」という一言。これが、最大のモヤモヤポイントです。
あれほど、生きることにこだわり、妻子の元に帰る事を望んでいた久蔵なのに、一回帰って顔を見ただけで、満足してしまったのでしょうか。自分が戦死する前提の言葉を口にするなんて縁起でもない事です。
で、この一言が、後に、松乃の窮地を大石など、久蔵と戦地で関わりのあった人達が支えるというストーリーの根拠になっているわけですが、これはもう『ゴースト』のようなファンタジーの世界。
その一言がなくても、大石と松乃の関係は充分丁寧に描かれていたのに、この一言を拠り所にするために、急にチープになる気がします。
というわけで、大筋は感動的なお話のはずなのに、モヤっとポイントの地雷は思いの外多い作品だなぁという印象。
力のある役者さんが揃っているだけに、プロットの綻びは、ほんとに勿体ないとしか言いようがなく、残念でなりませんでした。
役者にとって人の歴史を知るということ
書籍『日本製』の中でも、この作品について触れている春馬君。
折に触れ、この作品に関わったことで、考えた事、感じた事などについて、インタビューなどでも話しているのを目にした方も多いと思います。
きっと色々な意味で、思い入れのある作品だったのではないかなと思います。
そう思いながら、この作品を観ると、また違った風景が見えてきます。
映画の中の健太郎青年は、祖父久蔵について知る事について、最初は「気になりつつも、まあ、めんどくせぇ事」だと思っていました。
そもそも、つい最近までその存在を知らなかった人です。
知らなくても、26年生きて来られた。
知らなくても、おそらくこの先も生きていくのに支障はない。
そんな存在の祖父について調べ始めると、最初は悪評ばかりを聞いて、ますます心が折れる。
それでも続けて行くと、やがていい話も出てきます。家族を愛し、仲間をリスペクトし、教え子を守ろうとするいい面も見えてきて、さらに知りたくなる。
そうやって、能動的に知ろうとする事の大切さを、健太郎という役が伝えています。
春馬君もまた、この作品を通して、能動的に人の歴史に触れるという事を知ったのではないかと思います。
祖父久蔵の歴史を辿る健太郎という役を通じて、また、役者の世界の名だたる大先輩たちとの共演を通じて。
子役から青年期を演じる場合は、その人の背景といってもあまり濃厚に描かれる事はあまりありません。
けれども、年齢が上がれば上がるほど、役が大人になるわけで、その人の人となりを研究しながら演じるようになっていくのが普通です。
その人がどんな人生を送っているのか、なにを背負っているのか。
役者さんにとって、「その人物を知る」という力は、必須のスキルです。
ここからたった数年で、ローラにしろ、五代さんにしろ、ジェシーにしろ、なんなら田中君や佐藤だって、私たちは、役の作り込みのレベルの高さに、毎回予想をはるかに超えて、楽しませてもらっています。
能動的に人を知ろうとする姿勢がなければ、あの魅力的なキャラクターは生まれてこなかっただろうなと思うと、『永遠の0』の健太郎が役者三浦春馬に与えた影響は大きかったんじゃないかと思うのです。
春馬君にとっての戦争という物語
春馬君は、この作品の役作りで、自身の親族の戦争体験の話を聞いたというのはよく知られたエピソードです。
健太郎も春馬君も、いや、好奇心旺盛が服を着て歩いている春馬君を持ってしても、なにかのきっかけがなければ、単なる歴史の教科書に書いてある出来事になってしまうのが、戦争の歴史というものです。
しかし、私自身も含め、自分には実体験がなくとも、身近な人を辿れば、今ならまだ自分のルーツ上に存在する戦争に触れる事はできるかと思います。
春馬君は、まさにこの役を通じて、そんな体験をしています。
自分でない誰かの人生を生きるのが仕事の役者として、戦争中に生きた祖父の足跡を辿った春馬君が、後に、『太陽の子』で、まさに戦争中に生きた青年を演じる事になったのは、面白い巡り合わせだなと思います。
『永遠の0』から始まった春馬君の戦争体験は、『日本製』での広島訪問と、『太陽の子』で、ついに完結するのかなと。
8月に、またスクリーンで、あの難しい時代を精一杯生きる青年に、春馬君を通して会えるのを楽しみにしたいと思います。
おわりに
以前から何度も書いてますが、私は人が死ぬお話は苦手です。
戦争ものも、好んで観る事はあまりしません。
どんなに人間愛の物語と美化されても、戦争を題材にした作品は、エンターテイメントとして、心から楽しむ事がなかなかできないのは、私の育った環境のせいかもしれません。
その意味では、この作品は間違いなく「春馬君が出ていなかったら見なかった作品」です。
作品全体としては、あの時代を描く作品にありがちなヒロイズムで、感動させようというのが見えてしまい、戦争ものによくあるマンネリ感が否めませんでした。
ただ、明らかにフィクションだけど、現代の感覚から見ると、久蔵みたいな人もいたかもしれない、となんとなく思えてしまうリアリティとのバランス感覚は絶妙。
とにもかくにも、芸達者な役者さんと、細部にこだわった演出のおかげかなと思います。
春馬君の衣装、ごちゃごちゃとおかれている小道具たち、それぞれのシーンで、ひとつひとつこだわって選んだのだろうなと想像できる箇所がたくさんありました。
作り手の愛を感じる作品という意味では、とても温かみを感じる事ができました。
すでに書いたように、久蔵の描かれ方に、ツッコミどころがあったとしてもなお、久蔵はやはり魅力的な人物でした。
作品として、観に行ってよかったか、と言われたらよかった。けれど、人に勧めるのはなかなか難しいなぁ、というのが正直な感想です。
春馬君のファンの方なら、春馬君の受けの芝居を楽しむ目的で行くのもいいかもしれません。
個性豊かな役者の大先輩たちとの共演が、こんなにひとつの作品に凝縮されているのは、春馬君にとっては、ものすごい贅沢な事だったはずなので、その贅沢さをファン目線で堪能するのは、面白い楽しみ方かなと思います。
とは言え、戦争モノです。鑑賞後の心には、鉛の塊がドスンと置かれたような重苦しさはどうにもなりませんでした。
どうにもならない時は‥

春馬君も好きだった日本酒で(笑
(この銘柄が好きだったかどうかは知りません。たまたま選んだだけです。)
明るいうちからなんて贅沢な時間の使い方なんでしょう!
が、一杯ではただの呼び水。この後、友人の店へ場所を移して、マンボウタイムアウトまで、だらだらと飲んで気持ちをリセットしました。
え?飲みたかっただけだろ?って?
ええ、まあ、否定はしませんけども、でも、なにか気持ちをリセットするモノが必要だったのも事実で。
ああ、だから健太郎は最後に叫んだのか。
私は叫ぶ代わりに、飲んじゃったよ。てへ。
そんなわけで、ご覧になる方は、現実社会に戻ってくる心のリハビリプランも、あらかじめ考えておくのをお勧めします。
ああ、春馬君のおかげで、今週もいい週末だった!
ありがとう。春馬君。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
