
【思考法】やる気はいらない。やれてしまえばいい。
『吹いている風がまったく同じでも、ある船は東へ行き、ある船は西へ行く。
進路を決めるのは風ではない、帆の向きである。
人生の航海でその行く末を決めるのは、なぎでもなければ、嵐でもない、心の持ち方である。』
エラ・ウィーラー・ウィルコックス(1850~1919)
まえがき
皆さんは、なぜ仕事をしているのですか?
ほとんどの方は何かしら仕事をしていると思いますが、日曜日も後半になってくると『明日仕事行きたくねぇ』という声をよく耳にします。
では行かなければいいじゃないか?
行かなくたって違法でもないし、クビになるのもあなたの自由なのだから。
でも行きますよね。それはなぜか?
言うまでもなく、
仕事をしないと稼げないから。
稼げないと食べられないから。
食べられないと生きていけないから。
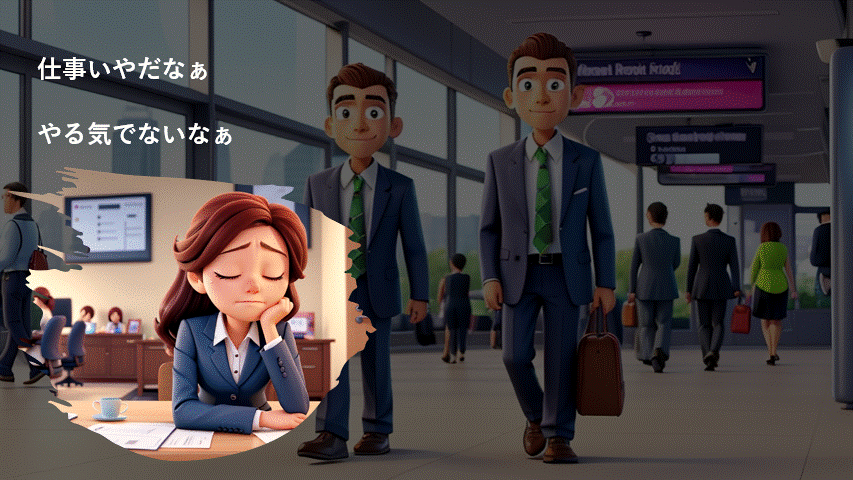
わざわざこんな当たり前過ぎる話をしたのには意味があります。
ここで言いたいのは
”やりたくなくても、人に言われずとも、人は行動できる”
ということです。
今回はこの心理の正体を知り活用することで、人生の様々なタスクに対し”主体的”に行動できるようになる理由と、他の心理効果と組み合わせてより効果アップをはかる実践編をご紹介します。
ギャップモチベーション
人間の行動には様々な心理が関与しています。
その中でも効果的なものの一つがギャップモチベーションです。
ギャップモチベーションとは、理想(目標)と現状との間に生じているギャップへの違和感や問題意識から自分の中で自然に芽生えるモチベーションです。
こういったものを内発的動機づけと呼びます。

内発的動機づけの最大の強みは目標設定における明確さと意味づけがしっかりしていることです。
先の例で言えば、
『理想:生きる』という大目的を果たすために『現状:食べるという行為』が必要であり、
『理想:食べる』という中目的を果たすために『現状:稼げている状態』が必要であり、
『理想:稼ぐ』という小目的を果たすために
『現状:仕事に行く』をせざるを得ない。
そのことをあなた本人が理解しているから、
誰に言われなくても勝手に仕事に行くんです。
この対象は私生活も学業もビジネスも問いません。
目標が明確でしっかり意味づけされ、ギャップを本人が問題だと認識すればどんなものでも行動にうつせる。
これは立派なモチベーションです。
日本における『やる気』
ここまでの話に違和感を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
おそらくそれは先の例に、『やる気が全く感じられなかったから』ではないですか?
嫌々やれているだけで、そんなものモチベーションではないと。

ということでここで一度、日本における『やる気の定義』の話をしましょう。
MAACoが思うにこの国に広く普及している”やる気”とは、積極的な"意欲"を伴うものでしょう。
よしやるぞと自分を奮い立たせ、"アドレナリンが出ている状態"かもしれません。
この状態を『ハイモチベーション』といいます。
残念ながらこのハイモチベーションは、アドレナリンの特性と人間に備わる『恒常性』の働きにより長続きしません。
恒常性とは体温や感情などに大きな動きがあっても、元の安定状態に戻ろうとする生物の性質のことです。
例えば映画を見て感動しても、1週間涙が止まらないなんてことは起きません。
昂った感情は必ず元に戻ります。
これが三日坊主で終わる原因の一つであり、言い方を変えれば
『行動するためのモチベーションの選択を間違えている』のです。
内発的動機づけと外発的動機づけ
ハイモチベーションの効果を無理やり延ばそうとすれば、自然と褒罰、評価、報酬などが生まれ始めます。
こういった外部からの圧力によって生まれるモチベーションを外発的動機づけと呼びます。
そして外発的動機づけが行動原理となってしまった人間は、厳しく言うと”無能の道”を突き進みます。
この理由は過去の記事で詳しく話しているので触りだけとしますが、外発的動機づけで動く人間の行動目的は褒められることや報酬を得ることだけに偏重しがちなのです。
褒められるからやる、褒められないならやらない。
そういう人間が育つ。
内発的動機づけで主体的に動く人間と、外発的動機づけで他人からの評価、賞罰ばかり気にして動く人間では、取組み前の仮説の質、行動の質、最終的には人間としての自立度合いがまるで違います。
これは本来の大目的と、賞罰や報酬という中目的以下の優先順位がすげ替えられているので当たり前です。
外発的動機づけは本来の目的を見失いやすく、自立を妨げやすいのです。

影響力の強い他の心理効果
ギャップモチベーションをより活用する為に他の心理効果と関連した例もご紹介します。
その為には『保有効果』、『一貫性の法則』という2つの心理効果を先に知っておいてもらう必要があります。
保有効果
自らが保有したものに対し、本来の価値以上の価値を見出す心理です。
例えば新車で買った自動車を10年後手放すとき、それはなんの繋がりもない他者から見ればただの古い中古車ですが、あなたにとっては思い出の詰まった大切な車でしょう。
この心理を保有効果と呼びます。そしてこの保有効果は、モノだけではなくプロジェクトなどコトへも及びます。
一貫性の法則
一度決定した態度や行動を貫こうとする心理です。
人は一貫性のある人を評価しやすく自分もそうでありたいと望む為、過去の発言や態度、行動に筋を通したくなります。
この心理を一貫性の法則と呼びます。
これらはときにモチベーションを後押ししてくれます。
実用編
ステップ①
例えば何かの売上拡大プロジェクトを任されたとしましょう。
目標と現状を照らし合わせ、まずはギャップを探します。
売上が足りないのはなぜか?量で上げるのか?単価で上げるのか?各リソースの配分は適量か?イメージ戦略との整合性は?
など、定性・定量それぞれにおいてなるべく細分化して言語化します。
少し本題から外れますが、この『定性・定量それぞれを細分化して言語化』はとても重要です。
なぜならどれだけ多くのギャップに気づけるかどうかと、見つけたギャップの改善に価値があるかどうかはここで決まるからです。
↓問題・課題発掘における良書です。読んでみてください。↓
ステップ②
本題に戻ります。
次に、言語化したギャップに優先順位付けします。
定性ならプロジェクトの特性と”あなたの信念”が結びつくもの。
定量なら最も生産量の高いものを選択するといいと思います。
ここであなたの信念が出てくるのは行動目的を内発的動機に紐づけるためです。
問題だという意識と、あなたの信念や正義が組み合わさらないと,
ギャップを埋めたいという強いモチベーションは生まれません。
こうでありたい、こうしたい。
という明確なイメージ:”未来記憶”があって初めて、ギャップモチベーションはその力を発揮するのです。
この段階で”内発的動機づけ>外発的動機づけ”の構図が完了している方は、もうギャップモチベーションの効力は出始めているハズです。
効力を感じられない方は、まだ”他者からの評価や賞罰”を気にしているなど、外発的動機づけの中にいる。
そういった方はこう考えてみてください。
『あなたが今取り組んでいるプロジェクトの評価者は、途中で価値観が真逆の上司に変わります。今どんなやり方を選んでも、半分は必ず悪評価になります。』

あなたが誰に対しても一貫して通せるものはあなたの信念だけです。
ステップ③
それがすんだら優先順位の高いものから対策を練ってみてください。
まずは『生きる』⇄『食べる』⇄『稼ぐ』⇄『仕事』の例のように、プロジェクトの幹の部分から作成し、最終的には枝葉の部分となる具体案まで。
このとき頭の中だけでなく企画書やプレゼン資料など、プロジェクトメンバーや上司が内容確認できる状況を必ず作っておいてください。

この時点で問題、ギャップ、課題、行動する意味を誰よりも理解、腹落ちしているのは誰でしょう。そう、あなたです。
このプロジェクトで問題発掘から対策立案までを一貫しておこなったあなたには、一貫性の法則により筋を通したい心理と、保有効果によりそれを自ら生み出した愛着が芽生え始めます。
そして行動に移した後は、その効果がより強くなっていきます。
しかもその想いは、責任感としても働きます。
全員が見れる形で資料も残っているので、一貫性の法則がより強く働き言い訳もしません。
ステップ④
ここまできたら、もう『やる気』なんてものは必要ありません。
ギャップを埋めたい。筋を通したい。わたしが生み出した。
という三本矢で、あなたは勝手にやれてしまうでしょう
強力なモチベーションの正体は”やる気”ではなく”動機”だったんですね。

まとめと注意点
いかがでしたでしょうか?
やる気を出すのは大変で、出しても長続きせず、すぐに本来の目的から離れていってしまう。これは本能には逆らえない人の性です。
逆に言うと、本能の行き先にタスクをおいてあげれば人は勝手にやるということであり、ギャップモチベーションは他の心理と連携したそれでしょう。
今回は実用編として、一貫性の法則、保有効果とともに、ギャップモチベーションを最大限活用するガイドをご紹介しました。
ただしこの2つの心理効果は意図せずとも発現してしまうこともある為注意が必要であり、その対策として知っておいたほうが良かったとも言えます。
一貫性の法則も保有効果も、悪い言い方をすると”執着”なのです。
自身の考えたプランが間違いだったとき、”意地”を張って路線変更できない。
または見込んだ程の成果がなかったとき、”目的から外れた意味づけをして価値創出”をはかる。
こういったことは簡単に起きるし、それすらも理性で抑えられないのが人の性。心理バイアスというものです。
おすすめの対策としては、プロジェクトの撤退水準や路線変更水準まで事前に具体的に決めておくことです。
期間や売上などなんでもいいので、納期やノルマなどの条件を自ら課せておくことで、一貫性の法則に則って撤退できます。
この考え方はif-thenプランニングの回で話しているので興味のある方はぜひご覧ください。
おまけ
戦争のモチベーション
余談ですが、戦争は国家間ではなく宗教や思想、正義などのイデオロギー間が最も多いそうです。
命をかけた殺し合いができる程のモチベーション。
これを末端の兵士が持ち続けることができるということ自体が、それぞれの正義と、それが脅かされている現状とのギャップに対するモチベーションであり、やる気とは違う本能的な行動原理が存在する証拠と言えるでしょう。
ジョブ・キャリア・コーリング
今回ギャップモチベーションについて書きながら思い出したことがあります。
仕事に対する価値観はジョブ・キャリア・コーリングという3つに分類できるというもので、どれに属するかと幸福度は相関がある。
即ち仕事への価値観、取り組み方次第で幸不幸の度合いが違うという、いまの時代に経営者が発言したらポジショントーク、ブラック企業と言われかねないセンシティブな理論ですが、これも納得すると仕事観が変わりモチベーションに繋がります。
いずれ話してみたいと思います。
Rethink MAACo
#思考法 #哲学 #思考法 #処世術 #ギャップモチベーション #やる気 #内発的動機づけ #外発的動機づけ #一貫性の法則 #保有効果 #本能 #ジョブキャリアコーリング #Rethink#MAACo
[The text below is an English translation generated by chatGPT.
I am not responsible for the accuracy of the information provided by this translation.]
The following article is available for a fee, but you can read it all for free. Only the original data (pptx file) of the images used in this article are available for sale.
"Though the winds blow ever the same, one ship may head east, another west. The direction is not set by the wind but by the set of the sails. In the voyage of life, it is not the winds or storms that determine our destiny but the way we set our sails." - Ella Wheeler Wilcox (1850-1919)
Preface
Why do people work? Most people are engaged in some form of work, but as Sunday draws to a close, we often hear voices saying, "I don't want to go to work tomorrow."
So why go if you don't have to? It's not illegal to skip, and getting fired is within your rights.
But people still go, don't they? Obviously, it's because you need to work to earn. You need to earn to eat. And you need to eat to survive.
There's a reason I'm stating such an obvious thing.
What I want to convey is that "even if you don't want to, even without being told, people can act."
In this article, we'll explore the essence of this psychology and how to utilize it to act "proactively" towards various tasks in life. We'll also delve into an advanced section that combines it with other psychological techniques for enhanced effectiveness.
Gap Motivation
Human behavior is influenced by various psychological factors, and one of the most effective is gap motivation.
Gap motivation arises naturally within oneself from the discomfort or awareness of the gap between ideals (goals) and the current reality. Such motivation is termed intrinsic motivation.
The greatest strength of intrinsic motivation lies in its clarity and meaning in goal setting.
For example, in the earlier example, to achieve the overarching goal of "living," the action of "eating" is necessary as per the current situation, and to achieve the intermediate goal of "eating," the state of "earning" is necessary, and to achieve the goal of "earning," one must inevitably "go to work."
Because you understand this personally, you go to work without anyone telling you to.
This applies to personal life, academia, and business alike. With clear goal setting and understanding of the gap between the current situation, one can act if they perceive the gap as a problem. This is a significant motivation.
Motivation in Japan
Some of you may feel a discrepancy in the discussion so far. Perhaps it's because there was "no sense of motivation at all" in the earlier example? Just doing it reluctantly isn't motivation, right?
So let's briefly discuss the definition of "motivation" in Japan.
In MAACo's view, the widely prevalent "motivation" in this country would involve an active "will." It might be the state of "having adrenaline," getting oneself pumped up. This state is termed "high motivation."
Unfortunately, this high motivation does not last long due to the nature of adrenaline and the operation of "homeostasis" inherent in humans. Homeostasis is the tendency of organisms to return to their stable state, despite significant fluctuations in factors such as body temperature or emotions.
For example, even if you're deeply moved by a movie, you won't be crying uncontrollably for a week. Elevated emotions always return to their original state.
This is one of the reasons why things often end up being started but not continued, or in other words, "choosing the wrong motivation for action."
You Shouldn’t Rely on Motivation
In an attempt to prolong the effects of high motivation, pressure from rewards, evaluations, or punishments naturally arises. Motivation generated by such external pressures is termed extrinsic motivation.
And individuals who are driven by extrinsic motivation can be said to be on the path of "incompetence."
The reason for this, which has been discussed in detail in previous articles, is that individuals driven by extrinsic motivation tend to focus only on receiving praise or rewards.
They work because they’re praised; if not praised, they won't work. That's the kind of individuals they become. The quality of hypotheses before undertaking a task, the quality of actions, and ultimately, the degree of independence as a human being are all vastly different between those who act proactively with intrinsic motivation and those who focus only on evaluations or rewards from others.
This is because the original purpose and the priorities lower than the intermediate goals such as rewards or evaluations are reversed. Extrinsic motivation tends to obscure the original purpose, hinder autonomy, and impede independence.
Other Influential Psychological Effects
To further enhance the utilization of gap motivation, let me provide examples of its connection with other psychological effects. However, to understand these connections, you need to be familiar with two psychological effects: "endowment effect" and "principle of consistency."
Endowment Effect
This is the psychological phenomenon where individuals ascribe a higher value to things they own than their objectively determined market value. For instance, while a ten-year-old car you bought new might be seen by others as just an old used car, to you, it's a cherished vehicle filled with memories. This phenomenon extends not only to physical objects but also to projects or endeavors.
Principle of Consistency
This is the psychological tendency to maintain a set attitude or behavior once adopted. People prefer consistency and seek to align their past statements, attitudes, and actions. This principle is known as the principle of consistency.
These psychological effects can sometimes provide a boost to motivation.
Practical Steps
Step 1
Let's say you've been tasked with a project to expand sales. Compare the goals and the current situation, then identify the gaps.
Why is sales lacking? Is it a matter of quantity? Or is it about increasing unit price? Are the resources allocated appropriately? Is there alignment with the branding strategy? It's essential to articulate and break down both qualitative and quantitative aspects as much as possible.
Slightly deviating from the main topic, articulating and breaking down "qualitative and quantitative aspects" is crucial. The number of gaps you notice and whether the identified gaps are worth addressing determine the value at this stage. Here's a recommended read for identifying issues and challenges. Give it a read. (Insert link)
Step 2
Returning to the main topic, prioritize the articulated gaps. In qualitative terms, choose those that align with the project's characteristics and "your beliefs." For quantitative aspects, select the most productive ones.
Your beliefs come into play here to link the action purpose to intrinsic motivation. Without the combination of problem awareness and your beliefs or justice, strong motivation to fill the gap won't arise. You need clear images like "future memories" to unleash the power of gap motivation.
For those who have already completed the structure of "intrinsic motivation > extrinsic motivation," the efficacy of gap motivation should already be evident.
For those who don't feel its efficacy yet, they may still be concerned about "evaluations or punishments" from others, indicating they are still within extrinsic motivation. In such cases, consider this: "The evaluator of the project you're currently working on may suddenly change to a superior with completely opposite values. Whichever approach you choose, half of it will inevitably receive negative feedback."
The only thing you can stick to regardless of who evaluates you is your beliefs.
Step 3
Once you've done that, start devising strategies for the prioritized gaps. Begin with the core aspects of the project, then gradually
move to concrete proposals, just like in the example of "living" <-> "eating" <-> "earning" <-> "working." Make sure to create a situation where project members or superiors can review the content, such as a proposal or presentation material, not just in your mind.
At this point, who understands the problem, gap, challenge, and significance of action better than anyone else? Yes, it's you.
For those who have consistently addressed the problems from discovery to countermeasures in this project, a sense of adhering to principles and an attachment created by oneself through the endowment effect will begin to grow. Once you take action, this effect will become even stronger. Moreover, this sentiment will also act as a sense of responsibility. Since materials that everyone can see are left behind, there's no escaping responsibility.
Step 4
By now, you no longer need "motivation." You want to fill the gap. You want to stick to your principles. You want to do what you created. With these three arrows, you'll naturally get things done.
Conclusion and Points to Note
How was it? It's challenging to muster motivation, and even if you do, it doesn't last long, and you quickly drift away from the original purpose. This is human nature; people can't go against instinct. On the contrary, if you put tasks in the direction of instinct, people will do them automatically. Gap motivation is likely to be one of these, closely connected with other psychological aspects.
In this practical section, we introduced a guide to maximize gap motivation along with the principle of consistency and endowment effect. However, since these two psychological effects can sometimes manifest unintentionally, caution is necessary. Knowing them as a countermeasure would have been better.
Both the principle of consistency and the endowment effect can be seen as "attachment" in a negative light. When the strategy turns out to be wrong, being unable to change course due to "stubbornness," or creating value by giving meaning to something that has deviated from its original purpose when expected results are not achieved—these things happen easily, and even rationality can't suppress them. This is called psychological bias.
A recommended countermeasure is to set specific withdrawal or course change levels for the project in advance. By imposing conditions such as deadlines or quotas, you can adhere to the principle of consistency and withdraw.
Extra
Motivation for War
As a side note, it seems that wars are mostly fought not between nations but between ideologies such as religion, belief, or justice. Motivation strong enough for people to risk their lives in battle. The fact that individual soldiers can maintain this motivation is evidence of their motivation towards the gap between their respective beliefs and the current state being threatened, rather than mere motivation. This shows that there are instinctive behavioral principles different from mere motivation.
Job, Career, and Calling
As I was writing about gap motivation, I recalled something. Views on work can be classified into three categories: job, career, and calling. Happiness correlates with which category one belongs to. In other words, depending on one's values and approach to work, the degree of happiness varies. If business leaders were to mention this nowadays, it might be seen as position talk or sensitive theory that could lead to accusations of being a black company. Nonetheless, understanding this can change one's perspective on work and lead to motivation. I'd like to discuss this further someday.
Rethink MAACo
いつか誰かのためになる。 そんな好循環を夢見て活動しています。 お力添えをよろしくお願いしますm(_ _)m
